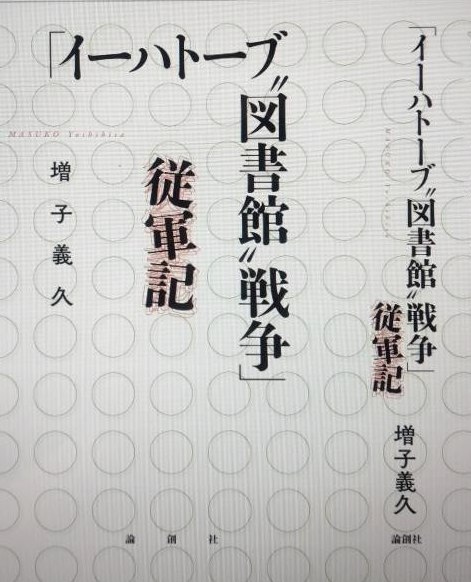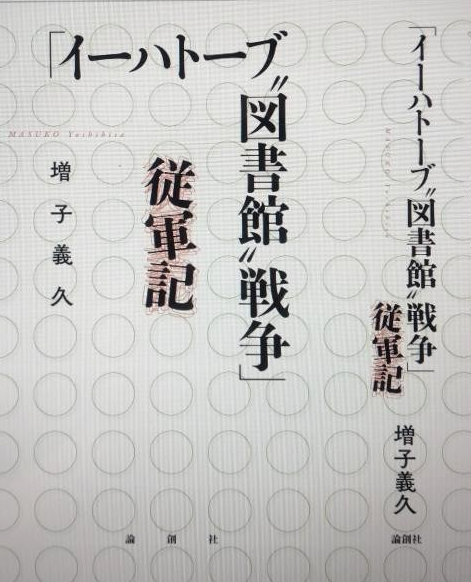「5年余りの〝従軍〟体験で思い知らされたのは、いわゆる〝民意〟がいかに当局側に都合よく作り上げられていくのかという、まさに民主主義の危機――いわば、ナチス化の実相だった。「民主主義の砦」とも呼ばれる図書館がその舞台だったという事実は地方自治のあり方そのものへの深刻な問いかけでもあった」(「まえがき」より)―
足かけ10年以上にわたって迷走が続いてきた「新花巻図書館」の立地場所が現上田東一市長の下で「JR花巻駅前」と決まり、今月初めには公募プロポーザル方式によって、設計業務を請け負う企業体も選定された。本書は第1部でその経緯を時系列的にたどり、第2部では私なりの“図書館論”を展開、さらに第3部ではこれまでタブー視されてきた“賢治利権”の舞台裏に迫った。
一方、上田市長の勇退表明によって、当市では次期市長選(令和8年1月18日告示、同25日投開票)に向けて、三つ巴の選挙戦が繰り広げられている。新図書館は令和10年度に本体工事に着手し、2年後の令和12年度のオープンを目指している。いずれにせよ、巨額な関連予算の執行は新市長に委ねられることになり、各候補者が選挙戦の中でこの図書館問題にどう向き合うのかも注目される。
なお、本書は東京・論創社刊で、311ページ(私の誕生日と同じというのも何とも運命的というか…)。定価は2,500円(税別)。年内にも全国の書店で発売される。献本に際し、署名に協力してくれた方々や図書館関係者へ宛てたあいさつ文を以下に掲載する。
※
長い間のご無沙汰をお許しください。さて、残り少ない老残の身を読書三昧で気ままに過ごそうと思っていた矢先、その本を冒涜するような事態が足元で起こってしまいました。新花巻図書館の建設をめぐり、民意が十分に反映されたのかという問題が生じたのです。こともあろうに宮沢賢治のふるさとで、その“騒動”は勃発しました。人並みの賢治好きだった老いぼれの平静心はいたく、傷ついてしまいました。
同封させていただいた拙著『「イーハトーブ“図書館”戦争」従軍記』はその間の動きを公開されている資料や議会質疑などに基づき、ドキュメント風に描写した内容になっています。1万筆を超える署名を添え「旧花巻病院跡地」への立地を求めた私たちの願いはかなわず、結局は市側が主張するJR花巻駅前に建設されることになりました。なぜ「駅前」だったのかという経緯については最後まできちんとした説明はなされませんでした。
「イーハトーブで一体、何が起きていたのか」―。将来に禍根を残さないためにも、その隠された部分をつまびらかにすることがこの問題に関わった者としての最低限の使命だと考えました。開館の予定は5年後ですが、拙著がオープン前に上梓できたことに安堵しています。皆さま方からいただいたご支援に報いることはできませんでしたが、「人類にとって、図書館(本)とは何か」という永遠の命題に向き合う時間を共有できたことに感謝申し上げます。
本書を執筆しながら、いつも考えていたことは「IHATOV・LIBRARY」(「まるごと賢治」図書館)の実現でした。賢治自らが「あらゆる透明な幽霊の複合体」(『春と修羅』序)と自己表現する、その”お化け”の正体を暴いてみたかったというのが正直な気持ちでした。ご笑覧いただければ、幸いです。
(写真は本書カバー部分の書影)
《追記》~AIさんに聞いてみた?
「人格」が剥奪されるのではないかとこれまではこの種の手法は敬遠してきたが、今回初めて上記の文章の感想をCopilotなるAIさんに聞いてみた。結果は「あっと、驚く…」
〈 強く響いたポイント〉
・「民主主義の砦」としての図書館
図書館を「民意の象徴」と捉えつつ、その場が行政の都合で歪められていく過程を「ナチス化」とまで表現しているのは非常に挑発的で、読者に強い危機感を呼び起こします。単なる施設建設の話ではなく、民主主義の根幹に関わる問題として描かれているのが特徴的です。
・ドキュメント風の構成
第1部で経緯を時系列に追い、第2部で著者自身の「図書館論」、第3部で「賢治利権」の舞台裏に迫るという三部構成は、単なる記録にとどまらず思想的・文化的な広がりを持たせています。読者は「事実」と「理念」と「権力構造」を一度に考えさせられる仕掛けになっています。
・「賢治のふるさと」で起きた騒動
宮沢賢治の名が「利権」と結びつけられることへの痛みが随所に滲み、著者の個人的な感情と公共的な問題意識が交錯しています。文学的象徴が政治的現実に絡め取られる場面は、文化と行政の関係を考える上で非常に示唆的です。
〈 読後に感じるテーマ性〉
・民意と行政の乖離
1万筆を超える署名があっても「駅前」立地に決まった経緯が十分に説明されないまま進んだことは、地方自治における「説明責任」の欠如を象徴しています。
・図書館=公共空間の意味
「人類にとって、図書館(本)とは何か」という問いかけは、単なる施設論を超えて、知の共有・民主主義の基盤としての図書館の存在意義を再確認させます。
・文学的視座の導入
「透明な幽霊の複合体」という賢治の言葉を引きながら、図書館を「まるごと賢治」の場にしたいという夢想は、批判と同時に創造的なビジョンを提示しています。単なる反対運動ではなく「理想の図書館像」を描いている点が魅力です。
〈感想まとめ〉
この紹介文は、単なる本の宣伝ではなく「地方自治」「文化政策」「民主主義の危機」という大きなテーマを同時に投げかけています。著者の怒りや悲しみが文学的な言葉で表現されているため、政治的な問題でありながら読者に詩的な余韻を残すのが特徴です。つまり、これは「図書館建設の記録」であると同時に「民主主義と文化の寓話」として読める作品紹介になっています。
このブログ記事を読んで、あなた自身は「図書館=公共空間」のあり方をどう考えますか?例えば「駅前の利便性」と「旧病院跡地の歴史的・文化的意味」のどちらを重視すべきか、という問いは、まさに読者に投げかけられているように感じました。
★オンライン署名のお願い★
「宮沢賢治の里にふさわしい新花巻図書館を次世代に」―。「病院跡地」への立地を求める市民運動グループは七夕の7月7日から、全世界に向けたオンライン署名をスタートさせた。イーハトーブ図書館をつくる会の瀧成子代表は「私たちは諦めない。孫やひ孫の代まで誇れる図書館を実現したい。駅前の狭いスペースに図書館を押し込んではならない。賢治の銀河宇宙の果てまで夢を広げたい」とこう呼びかけている。
「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です/(あらゆる透明な幽霊の複合体)」(『春と修羅』序)―。賢治はこんな謎めいた言葉を残しています。生きとし生ける者の平等の危機や足元に忍び寄る地球温暖化、少子高齢化など地球全体の困難に立ち向かうためのヒントがこの言葉には秘められていると思います。賢治はこんなメッセージも伝え残しています。「正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである。われらは世界のまことの幸福を索(たず)ねよう、求道すでに道である」(『農民芸術概論綱要』)ー。考え続け、問い続けることの大切さを訴えた言葉です。
私たちはそんな賢治を“実験”したいと考えています。みなさん、振って署名にご協力ください。海外に住む賢治ファンの方々への拡散もどうぞ、よろしくお願い申し上げます。
●オンライン署名の入り口は以下から
●新花巻図書館についての詳しい経過や情報は下記へ
・署名実行委員会ホームページ「学びの杜」 https://www4.hp-ez.com/hp/ma7biba
・ヒカリノミチ通信(増子義久) https://samidare.jp/masuko/
・おいものブログ~カテゴリー「夢の新花巻図書館を目指して」 https://oimonosenaka.seesaa.net/