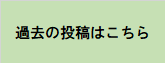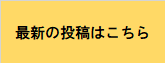川西町小松の豊年獅子踊り、お盆の8月16日に大光院で8月27日には諏訪神社で奉納される、衣装は紺色が牡獅子(おじし)、橙色が牝獅子(めじし)、黄色が供獅子(ともじし)となって、太鼓を持つ仲立(なかだち)、色鮮やかな衣装に身を包み花笠をかぶった花笠(はながさ)、早乙女(さおとめ)、まとい持ちがいます。 笛や太鼓の音に合わせて、獅子たちの花に酔い、火に狂う様子を表わした踊りを披露します、8月27日がちょうど休みで白鷹町散策行く途中で獅子踊り観てからということで見学しました、今年の町田絵画サークルの作品は大光院に入る獅子踊り一行を作品にしました・・・来年は何にするかと思ってるのだけれど諏訪神社の獅子にするか新山神社の獅子舞にするか・・
HOME > 歴史探訪
キリシタン生き埋めの地(白鷹町)
昨日は休みで白鷹町荒砥駅からレンタサイクルでサイクリング、涼しくなって風が心地よかった、駅出て朝日町、寒河江市にむかう国道287号線にはいり、最上川の難所であった黒滝跡を過ぎて黒滝橋から左手に深山のどか村に向かう途中、キリシタン生埋の地と言う看板がめに入ります、高岡の上ノ台にある。寛永年間(1624~1647)、鮎貝城主が春日氏の時、切支丹宣教師が山形に来て布教、約3000人に洗礼を授けたといい、高岡は特に盛んになったという。切支丹屋敷が出来たほどであったともいわれている。幕府の取締りが厳しくなった時、様々な説得をしてもそれでも受け入れない信者を生埋にし、後に供養として地蔵堂を建立した所という。すごい話ですよね、前にあった説明看板には、実際には殺さず、見逃して地蔵堂を建て偽装したと言い伝えがあり、「生き地蔵」と呼ばれている、と記載ありましたが、今たってる看板にはその部分が削除されてるのはなぜだろうか?
最上川最大難所黒滝
最上川は山形を代表する川、その源流は山形の米沢市最南端吾妻連峰の西吾妻山とされて、日本海に注ぎ込む、最上川の船運は平安時代から始まったとされ多くの難所がありました、江戸時代に山形城主最上義光が大がかりな開削整備を成し遂げると、舟運は一気に盛んになりました。山形県の経済や文化の発展を流通の要として支えた最上川、今日休みで山友ハイジさんと白鷹町散策ということになり荒砥駅でレンタサイクルかりて軽いサイクリング、荒砥駅から2kmほど最初に通った五百川渓谷、難所が多く船運に利用するには難しいとされてましたが、17世紀後半に上杉藩京都御用商人、西村久左衛門が私財を投じ、通船を妨げていた黒滝(落差は3m)を開削したことにより船運が可能となり、船陣屋や蔵屋敷が整備され、人の往来や京文化の流通が活発になったとあります、日本海までは165kmもあるところ、国道287号線から左に深山地区に渡る橋”黒滝橋”から見る最上川朝日町寄りに大きな岩盤群につぶて石が見えます。