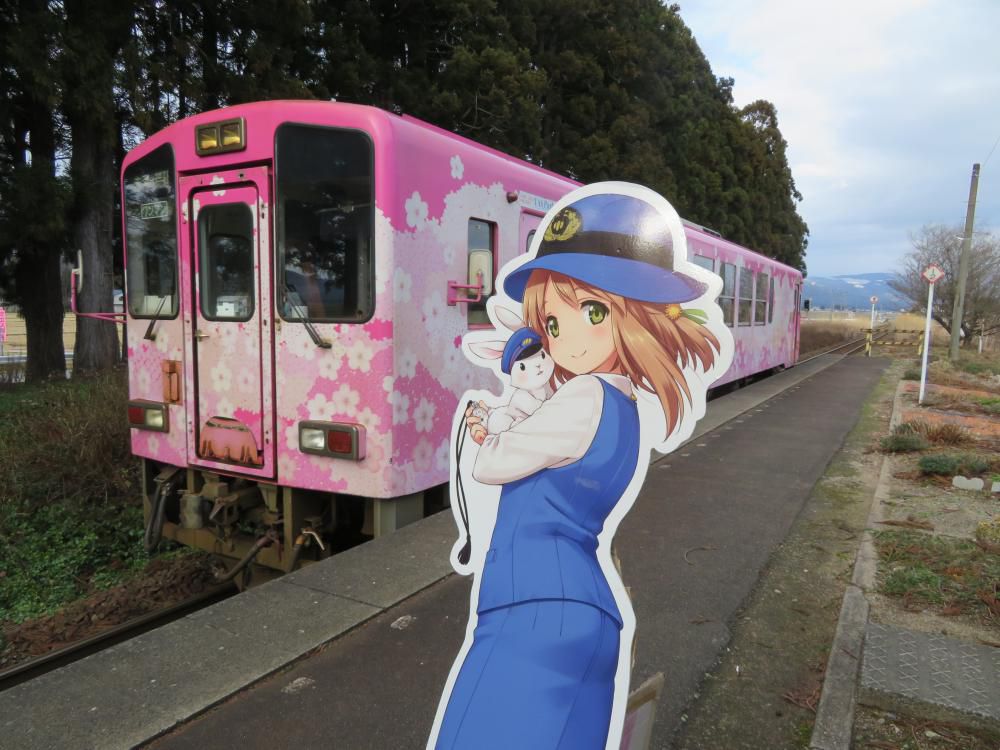書棚の奥の奥から「征峰」の雅号が記されたもう一枚の絵が出て来た。おらだの会第3代会長である故宮崎征一さんの作品である。宮崎さんは駅舎の修繕を行うと共に、鉄道写真家・広田泉さんとの「縁」をつくった方である。
期せずしてこの度、成田駅に多大な貢献をされた佐々木郁雄さんと宮崎さんの作品を同時に見ることになった。宮崎さんが書をたしなむのは知っていたが、絵を描くことは初めて知った。二人は平成6年頃から、駅舎で展示会をやろうと考えていたのかもしれない。酒飲み以外に会員個々の趣味や特技を持ち寄ることも楽しいことかもしれない。
2016年(平成28年)の同じ月に鬼籍に入られた二人である。雲の上で酒を酌み交わしながら、私たちのことを眺めているかもしれない。二人の思いに心を馳せ、時には時代の変節に翻弄されながらも、青竹のようにその節を重ねていきたいものだ。