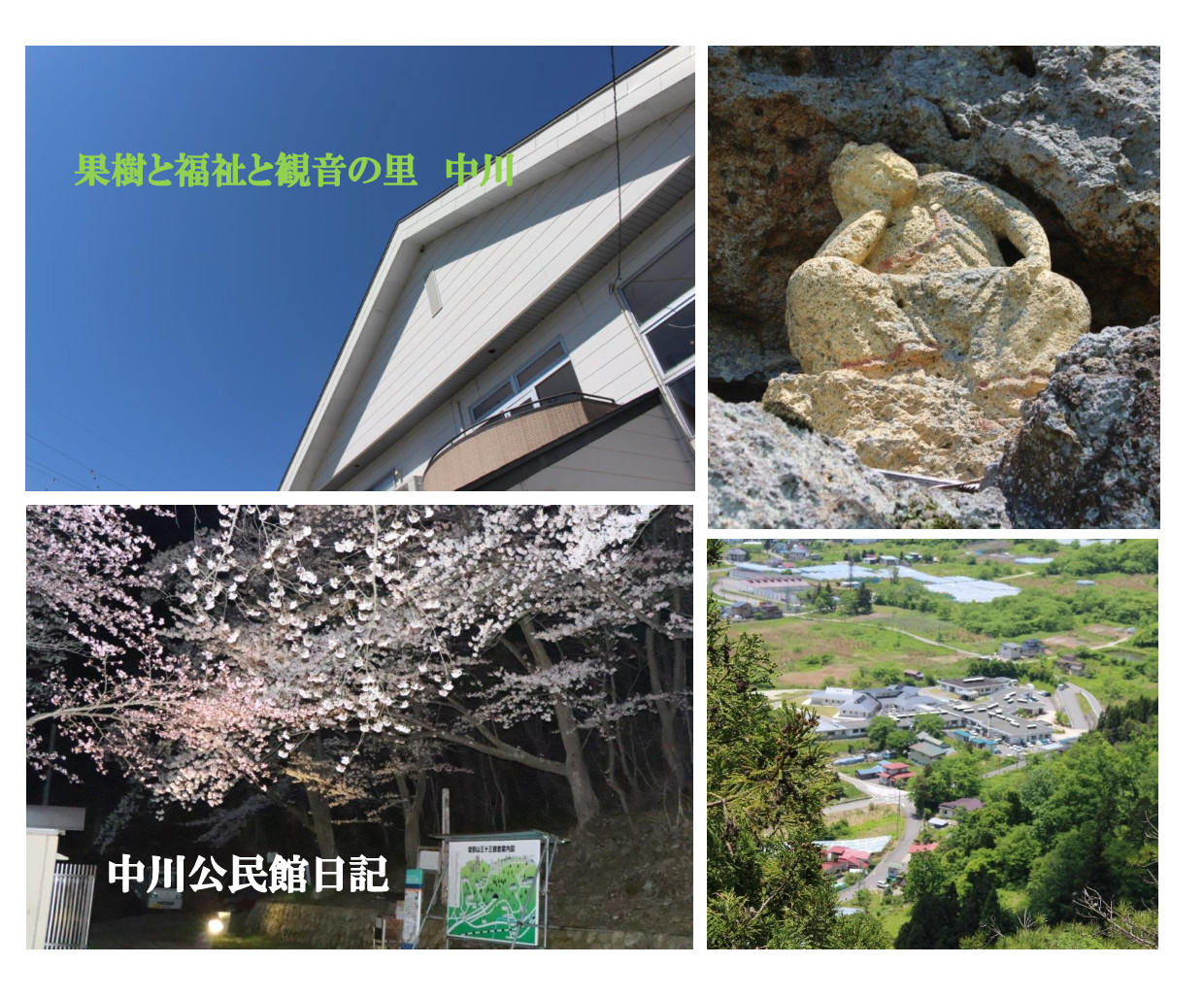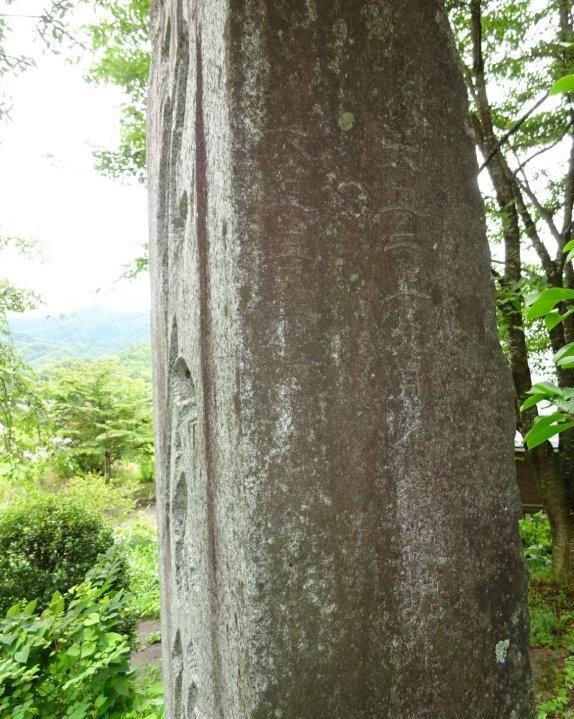元中山地区の字大貝(オオガイ)です。
上山市中山地区と隣接し、中山から釜渡戸を経由し宮内へ至る宮内道が通ります。
カイ(貝)は峡谷(峡:カイ)や崖地、また開墾地(開:カイ)をいう場合があります。
大貝は山と山に囲まれていますが、大きい(深い)峡谷ではありません。山麓の傾斜地に水田や畑が広がる場所ですので、開墾地の意で名付けられたと考えられます。
1595年頃の邑鑑によれば、中山村(元中山含む)は戸数72、人口434、村高1700石でした。
江戸時代、中山村では開墾が進められ、文政10年(1827)村目録では戸数199、人口979、村高2927石と大きく発展しました。
大貝もその開墾地の一つと考えられます。
参考:地名のなぞを探る~やまがた~ 木村正太郎著
南陽市史中巻