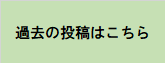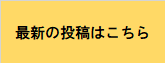兎平駐車場から浄土平~酸ケ平~一切経山のルートで7月19日山友と登山、魔女の瞳(五色沼)と花を観に行きました。一切経への途中で振り返ると見える”鎌沼”磐梯朝日国立公園内、標高1770mに位置し、形が鎌に似ているからその名がついたとされます。浄土平から一周約5.1km(所要時間2時間)の鎌沼自然探勝路があり、多くの高山植物をみることができます。浄土平ビジターセンターからそんなにかかりません。この日曇りで暑くなく、たいして汗もかかない、気持ちい風が吹く、下に点々と涙のような沼が・・一緒に行った仲間となんか名前をということで、同行の呼称”ハイジ”さんからとって”ハイジの涙”でどうでしょうか・・魔女の瞳に対抗して・・
HOME > 記事一覧