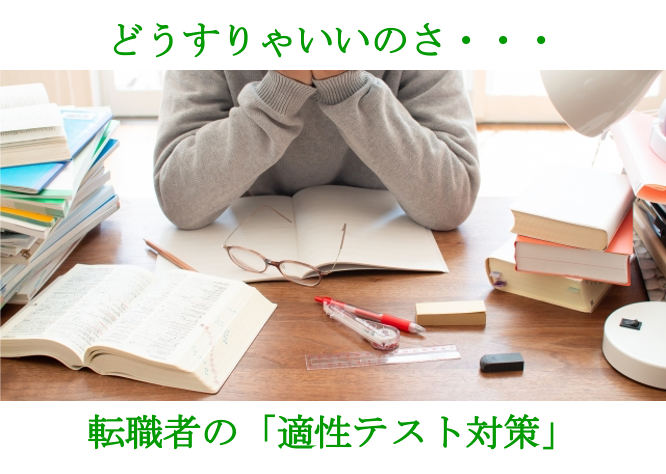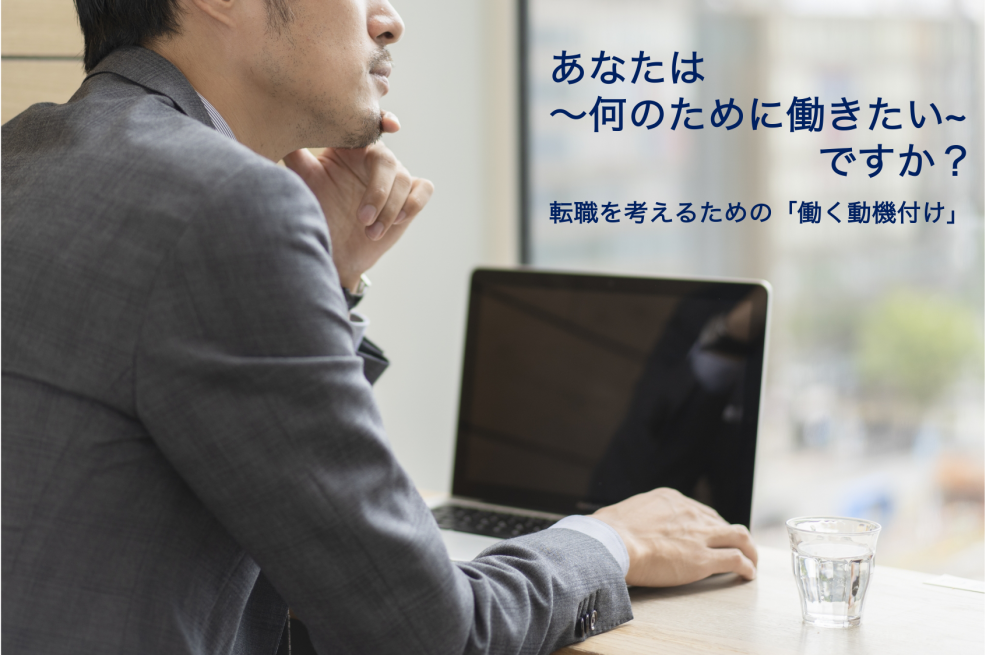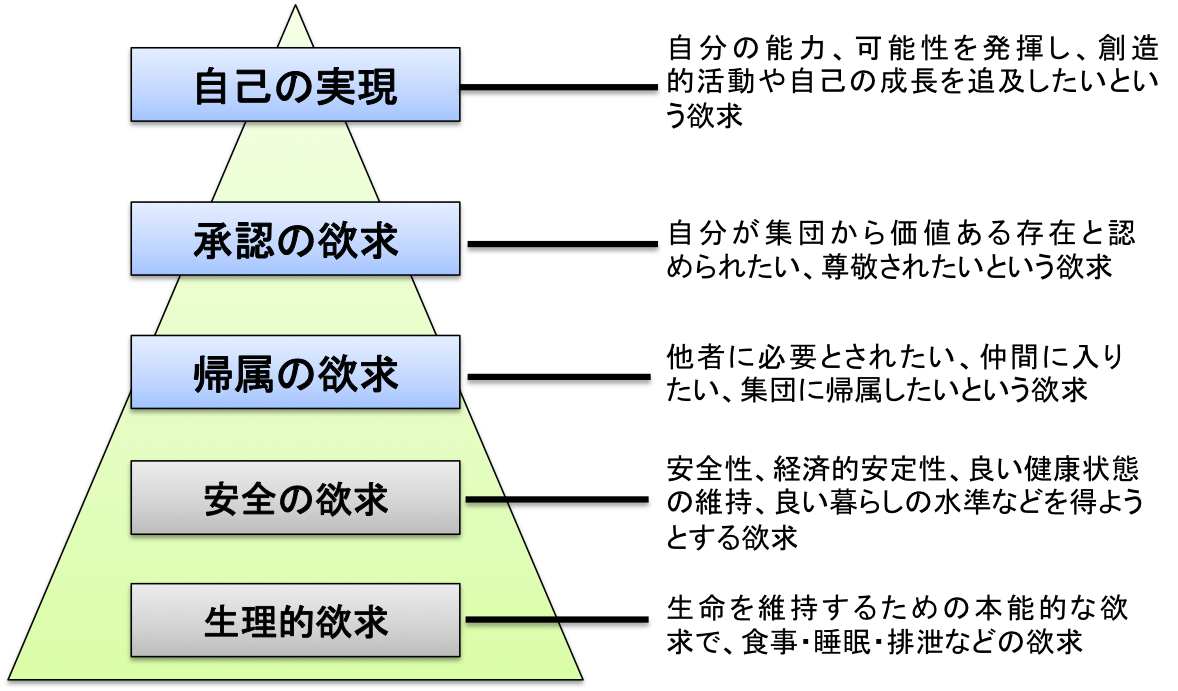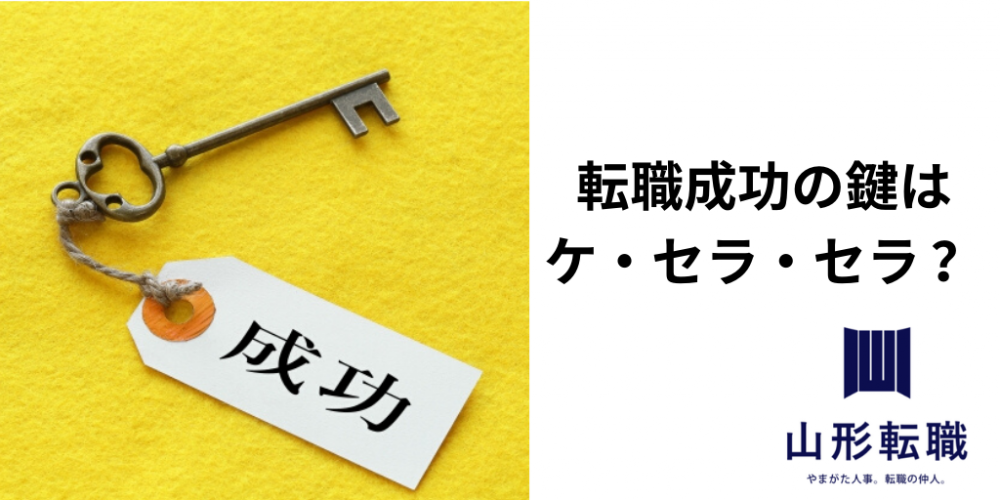みなさんは「営業の仕事」にどんなイメージがありますか?
「常にノルマがきつそう」「休みの日も関係なく仕事が入ってきそう」
お若い方は特に、こんな負の(?)イメージのみでとらえている方が多いなあと普段の転職相談を受けていて感じます。
実は、営業職も「種類がいろいろ」「環境もいろいろ」であること、ご存知ですか?
そんな営業職について知っておきたい「はじめの一歩」を、ご紹介しますね。
1.【誰に】営業するの?
<法人・個人>
法人がお客さまとなる「法人営業」と個人がお客さまとなる「個人営業」があります。
<ルート・新規>
既存客へ営業する「ルート営業」と、新規の取引先を開拓する「新規営業」があります。
2.【何を】扱うの?
<有形・無形>
業種により扱うもの(販売するもの)は異なります。
車・住宅・食品等のように「形のあるもの」を扱うのか、保険・広告のように「形のないもの」を扱うのか。
3.【どうやって】営業するの?
<店舗・訪問・オンライン>
お客さまに店舗に来ていただく「店舗型営業」もありますし、営業スタッフがお客さま先へ訪問する「訪問営業」もあります。また、状況に応じてオンラインを活用して(zoomなどで)お客さまと接点をとることもあるでしょう。
「常にノルマがきついかどうか」ですが、「ノルマ(目標)」の考え方や付与の仕方等は会社・上司によります。
営業部署全体として今期はこの目標に向けて全員で動いていこう!とする「チーム型」の場合もある一方、部署での目標を個人に割り振っていく「個人型」の場合もあるでしょう。そのノルマを何と比較・評価するかというのも、「新規獲得件数」「売上金額」「前年比」など指標はさまざまです。
また同様に、「休日もお客さまから電話が入るか」は、「その会社による」「その上司による」という点があると思います。
ですので、毎日どのように行動するのか、会社(チーム)としてどう動いていくのか、先輩や上司からのフォローはあるのかなどの「環境」も、営業として働くうえで大事なポイントになりそうですね。

また、「売る」だけが営業の仕事ではありません。
お客さまがどこにいるのか、どんな施策で集客するのか考えること等も営業の仕事になる場合もありますし、お客さまとどんな会話をしようか、どんなニーズを聞き取るかというコミュニケーションも営業の仕事です。販売後のアフターフォローが次のお客さまへとつながる場合も多々あります。
これまで、転職面談のなかで営業職のご経験者の方からはこんな声をお聞きしてきました。
「お客さまに合ったサービスを提案して、喜んでもらえたのがうれしい」
「どんなお客さまにどう説明するのか考えて、実践するのが面白い」
「目標を達成するために、チームで考えるのが楽しい」
「営業成果が数字となって表れるから、分かりやすいし達成感がある」
など、その方なりの「やりがい」を感じていらっしゃるようです。
ちなみに、私(コンサルタント:澤村)も過去に金融機関で営業の仕事をしていました。上記の種類で言うと、
<個人>の<既存先・新規先>に対して、<無形>商品を<店舗や訪問>にて営業という形でした。
前職や今の仕事においても「営業」の要素もあると思っていますし、どこにどんなお客さまがいて(いそうで)、どうやってお客さまのご希望に合うように、また自社の売り上げになるようにたどり着くか、という「営業的な視点」は、営業職を離れた今も役に立っていると思っています。
会社が存続していくのは、やはり「利益を生み出す」ことがあってのこと。
営業職はその最前線で働く、会社の要となり得る仕事です。
ジンジャーズで取り扱う営業職求人は、未経験でも挑戦できるものもあります。
「誰に」「何を」「どうやって」営業するのか、また職場環境はどうか?など、一つずつご説明したり、企業側へ質問したりすることももちろんできますので、まずはお気軽にご相談くださいね!