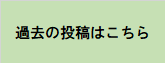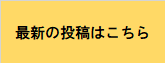山友さんから頼まれていた山形最上川流域散策絵図のポスターパネル2枚と、創芸作品の額1個、もともと現役時代相模原市の絵画サークルに所属して、その先生からキャンバスに額作り教わっていましたが先生もかなり額は適当でした、頼まれて本格的な額は初めて、昨年夏ころに頼まれていつでもいいと言われてついほったらかし、田舎に移住して母介護がきっかけで始めたミニ木工人形つくりは好きで、かなりのめり込んでしまったのだけれども大きなものは苦手というか大物の道具がそろっていない、実家の兄は小物ではなく家の修理とか小屋作りとかどっちか言うと大きなもの作りが好きで直線引きや角度だしの道具もそろっているんで創芸作品の本格額は兄に任せてポスターパネルの方を2枚ほど作成した、昨日は雨でスキーにも出かけられないし一日集中しての額作り、塩ビの透明カバーは機械カットすると割れるのでここは金ノコでゆっくりカット、抑え板は大型のカットする道具がないのでホームセンターでカットして、額部分は既成品で加工された長棒を使用、角度だしは丸鋸に角度調節機構があるので何とかできました
浅間山
軽井沢プリンスホテルスキー場ゲレンデから正面に浅間山がよく見える、暮れの30日が小雨、それ以降毎日快晴でした、穏やかに見える浅間山ですが昨年8月に小規模な噴火があり火口から4キロ内に入れない入山規制(レベル3)に引き上げとなってました、現在はレベル1ですが活発な活火山です、甚大な被害をもたらした大噴火は天明3年1783年5月から8月まで活発に活動して7月の大噴火は、日本の火山災害の歴史の中でも特に大きな被害をもたらしたとあります、現在の嬬恋村(旧鎌原村)を壊滅させた土石なだれ、当時の人口の八割が命を失い奇跡的に観音堂にたどり着いた93名が助かっている、地中の村と化した鎌原村は、昭和54年から発掘調査がが行われ、その土石は5から6メートルと村全体が埋まってしまった場所で「東洋のポンペイ」と呼ばれている、石段は当時50段あったが、上から15段を残して土に埋もれてしまい、「天明の生死を分けた15段」として語り継がれてきている、その石段の最下部には女性2人の遺体が発見されていて、遺体の骨の重なり方から背負った人と背負われた人と考えられその悲惨さを知ることが出来、災害について考えさせられます
めがね橋
昨年末30日に山形から軽井沢に移動、この日朝から山形は小雨、その途中もズーと小雨でした予報は寒波ということで雪と思ってたのですが、気温が高いようです、自宅から数キロで東北中央道に入れるんでそのまま、東北道、関越道で途中峠の釜飯で昼めしと給油、満タンであと一歩のとこなんですが、ふあんなんで給油します、まだじかんあるんで碓氷第三橋梁のレンガ橋見ていこうかと、旧道から軽井沢に、明治25年にできた橋、5基残っていて国の重要文化財に成っている、途中駐車場もあり天気よければ散策に良いようですが、あいにくの小雨道路から見れる範囲で見てきました、天気よければまたトンネルのほうもいきたいなとおもいます、軽井沢着いたらなんとここも雪でなく雨、びっくり暖かいんですね、あれから今日まで毎日快晴です、さすがに快晴率90%の軽井沢いいとこです