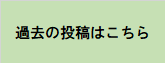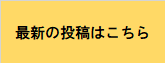一昨日ですが父が公立置賜南陽病院に移転入院したのでお見舞いに行きました、そのあと近いから熊野大社に初詣、遅ればせながらですが・・この熊野大社はフラワー長井線の宮内からだと歩いて15分、赤湯駅からだと車で15分ほどです、和歌山県の熊野三山、長野、群馬の県境にある熊野皇大神社と並ぶ日本三大熊野の一つ、そうそう定年後軽井沢プリンススキー場にスキーイントラで行くようになったけども、碓氷峠の頂上にある長野と群馬にまたがる熊野皇大神社がその一つ・・近くまた軽井沢行くので今度こそ寄ってみなくてはですがいつもスルーしてるんです、東北の熊野大社は大同元806年に平常天皇の勅命によって再興された東北屈指の歴史ある社、平安時代の本尊仏、鎌倉時代の面、室町時代の獅子頭など文化財が保存されておりすごい歴史あるところです、参道はきれいな石畳で大鳥居をくぐり進むと巨大な銀杏の木があります、これは源義家の命を受けて植えたと伝えられる、樹齢900年のイチョウで山形県の天然記念物指定、そこを過ぎ石段を上ると本殿がみえます、現在の本殿は江戸後期のものとあり屋根はいまでも萱吹き屋根です、今年の運勢とおみくじは大吉でした、ちょっとうれしい・・そして本殿裏へといくと縁を結びたい人への、最強のパワースポットといわれて全国からも大勢人がきてるといわれる3羽のうさぎが隠し彫りされて、3羽すべてを見つけると願いが叶うと評判になり、今では恋が成就するスポットとして有名なんです、平日の午後でしたが何組かカップルがなかなか見つけられずにいましたけども・・2羽までは簡単に見つけられるけども3羽めが難しい、他人に教えたり、聞いたりしては御利益がなくなるということでみな黙って探します・・3羽めはこれかなと思うところがいくつかあるのでこれだと思えばそれでもよしでしょう・・
上杉鉄砲隊
今年の相模原市の絵画グループ『どんぐり』のグループ展向け作品つくり、ベニヤのキャンバス作りからキャンバス下地作り、下地はペットボトルに水半分、木工ボンド半分入れてボンドをよく混ぜます、そしてキャンバスベースには漆喰または珪藻土を使用します、ボールに今回は漆喰を入れて水溶きボンドでよく混ぜてベニヤに塗っていきます、きれいに平らにするのは意外と難しいんです、今年のメイン作品は上杉鉄砲隊にしました、他に小物3点ほど作ります、今年の作品は昨年初めて春日山林泉寺を見に行って、鉄砲鋳造士の墓もお参りして、この林泉寺は1617年上杉景勝が米沢に建立、正室の菊姫、鷹山公の側室の信玄の6男他鉄砲鋳造士の墓もあります、兼続は1604年鉄砲先進地のから職人を招いて、白布高湯に鋳造所を作り1000丁ほど作ったとあります、1614年大阪冬に陣に上杉鉄砲隊は鉄砲680挺・大筒50挺をもって参陣、縦横にその威力を発揮したとあります、作品は鉄砲6人、太鼓や総攻撃の軍旗、予備の鉄砲他小物を作ってるところ人形部分が終わるとバックの絵にとりかかる、展覧会は4月21日から昨年は2月になってから作品つくりと遅く必死でしたが、今年は取り掛かりが早いです
額作りその2
山友さんから依頼があった額作り、購入した材料が半端に残ってしまう、板材とかの標準寸法は通称サブロク板という910×1820mmです、コンパネ、ベニヤなんかがこの寸法で日本の尺貫法で表している1尺が303ミリなので3尺と6尺だから909×1819となる少し丸めて910×1820といまでも尺が使われている国際標準のメートル法に代わっても建設業界は慣習で使われている、弱電電子回路設計業務に身を置いていたわたし、アメリカ向けはインチ、日本はミリとなる、基板設計で使うレイアウト用紙のメッシュはインチ、つまり部品の寸法がこのインチメッシュに並べないと都合が悪いしかし国産はミリ基本しかしその中で使う輸入部品はインチサイズの取り付けと実にややこしい、ねじ外すとインチありのミリもありで面倒だから、インチサイズで設計する人、純国産を目指して開発が進んだ1980年代国産化にこだわりねじも寸法もミリにするひと・・私と組んだ機械設計はミリ派でした、組み立てる方からすると混在していて実に面倒ですが混在はなくなんないようです、話が脱線したけど田舎暮らし夢見て定年して田舎に移住そのとき憧れのターシャさんの記念展が新潟であり2日間続けて観に行きました、そのとき新潟に住む従妹からもらったポスター余った材料で額作りして入れてみました、もう3年前の正月だったんですねはやいです、憧れのターシャさん、絵本作家であり、人形つくりドールハウスつくりもらり自給自足の暮らしいいですね