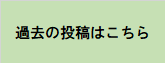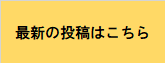自宅家庭菜園の梨の木の花が咲きました、一昨日のあったかかった土曜に咲いたようです、気が付くと咲いていたという感じです・・このところ肌寒くつぼみの状態でいつ開くかと思ってた、この一週間のうち温かかったのは25日の土曜だけだったような・・暖かいとあっという間に開くんです・・しかし毎日寒くて朝のストーブが欠かせない、こたつもまだ必要です・・横浜や相模原マンション暮らしの時建物の構造もいいからでしょうけど冬でも暖房なしでいられるくらい、今の古民家隙間風が入るからあちこち隙間を埋めるテープにサッシもテープで冬の間目張りするも寒いです、底冷えするというか腰が冷える朝はストーブ前に座ってはパソコンうち、ブログ更新、ニュースのチェックと仕事に出かけるまでいそがしい・・このところあまり店にもいかないし家と仕事の往復でパソコンに向かってる時間が多くなった
コレラ大明神
移住した窪田町東江股にある春日神社に石碑群がありますが、ここにコレラの終息を祈願して、その死者を慰霊する石碑があると初めて聞きました、赤芝にコレラの石碑があると友人から聞いたことはあったのですが、窪田にもあったのは初耳でした、そんでネットで検索したら米沢市の歴史探訪のとこに載ってました、一部抜粋すると・・日本で初めてコレラが流行したのは文政五年(1822)で安政五年(1858)には江戸だけで20数万の死者を出す大流行があり、明治にもたびたび流行した、石碑が建てられた明治12年(1879)には全国で大流行し、死者10万人、米沢では八月に白布温泉で発生(旅行者から伝染?)、当時は川水の利用が主であり、コレラは下流の小野川・赤芝に伝染して、市街にも蔓延、死者数百人に達した、さらに下流の窪田村にも伝染し、死者42名と記録にある、石碑はこうした状況のもと、コレラの終息祈願と死者の冥福を願ったもの、赤芝羽黒神社に虎列刺菩薩碑、窪田の虎列刺大明神の石碑が建てられた、今日その石碑に手を合わせて現在のコロナの感染終息を願いました、コレラは明治16年にコッホ博士がコレラ菌を発見し、そののちに治療法も発見されて、上下水道の環境整備も進んで現在ではコレラの流行はなくなり石碑も忘れ去られている・・たびたび起こる伝染病ですがコロナもやがて治療法が確立されるんでしょうけど・明治の時代4年かかって菌の発見その後治療法の確立・・医療技術が進んだ昨今いつ決め手の治療法が見つかるのか?今日桜が満開の窪田東江俣の春日神社
滑り収め
昨日で天元台高原スキー場の今冬シーズン営業を終了しました、コロナウイルスの影響で自粛営業として最後の日となりました、昨日スキーパトロールとリフト勤務して今シーズン自身としても最後の滑りになりました、ゲレンデで最後の客を確認してネットなどの回収を行いゲレンデ閉鎖しました、しかし第三リフトにはまだ3m近い雪残ってます、第二リフトもまだ十分残っていてこぶバーンもまだこぶの底が十分雪ある状態なんです、例年より4月に入って気温低く麓が雨でも高原は雪になるなど4月として異例の積雪、雪解けが進まない気温と季節が少しずれてるなという感じです・・今年異常気象に新型コロナと厳しい状況、経済停滞に医療の問題、人類突きつけられた試練なんでしょうか