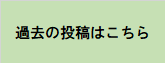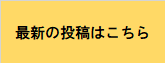昨日ラビスパ裏磐梯のすぐ下のキャンプ施設駐車場から雄国山経由で雄国沼湿原まで往復登山行きました。あいにくの曇り空でしたが、涼しくて大汗かかずに済みました。ラビスパ裏磐梯から雄国山案内では
?全長:6km
?所要時間(片道):2時間10分~2時間30分
?難易度:中級
とあります、スタート地点をキャンプ施設からだとほんの少し短縮できます。
雄国山は猫魔ヶ岳の噴火によってできたカルデラ湖・雄国沼を囲む外輪山のひとつ。その山頂からは雄国沼を望むことができ、日本百名山の磐梯山、安達太良山、吾妻山、飯豊山の山々を見ることができます。昨日はあいにく曇りで、磐梯山と会津盆地は見渡せました。