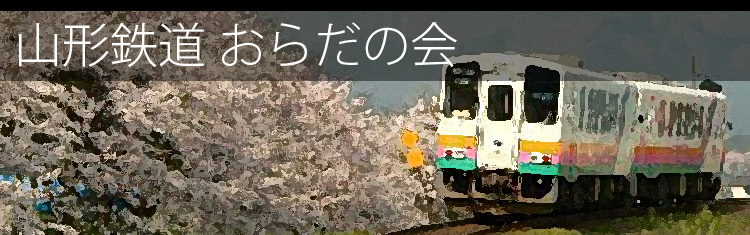故吉田東伍氏は、『大日本地名辞書』で、「優嗜曇」はアイヌ語であろうと示唆しています。ウキタムはアイヌ語で、ウ(広い)-キ(葦や芦のような植物)-タミ(谷地)で、「広い葦や芦の生えている谷地」という意味です。古代の置賜地方は、沼や湿地の多い地方であったので、ウキタムと言われたのが郡名になったという説です。
さらに、ポリネシア語から地名を読み取る研究をしている井上夢間氏は、ウキタマ・オイタミ・オキタマは、マオリ語で解釈すれば、「ウ・キタ・マ=乳房(のような山)で締め付けられた清らかな土地」の意味であるとしています。この解釈から浮かぶイメージがありませんか。
明治の初期に日本を訪れたイギリスの女流旅行作家イザベラ・バードが、紀行文「日本奥地紀行」の中で、置賜盆地の風景を評した感動に通じるものがあると,私は感じます。女史は、『(置賜盆地は)まったく「エデンの園」である。「鋤で耕したというより鉛筆で描いたように」美しい。米、綿、とうもろこし、煙草、麻、藍、大豆、茄子、くるみ、西瓜、きゅうり、柿、杏、ざくろを豊富に栽培している。実り豊かに微笑する大地であり、アジアのアルカディア(桃源郷)である。』と記述しています。
皆様には、このような諸説をどのように受け止められたでしょうか。故郷・置賜には悠久の浪漫があると思いませんか。そして,それが東南アジアやヨーロッパまで通じるものがあると思いませんか?あなたの故郷の語源を調べてみてください。
HOME > 記事一覧
羽前成田駅前変な民俗学者?⑦おきたまの語源Ⅲ
2012.07.27:orada:コメント(0):
羽前成田駅前変な民俗学者?⑦おきたまの語源Ⅱ
さて、「置賜」の地名が初めて記録に出てくるのは、持統天皇3年(689年)の『日本書紀』です。陸奥の国・優嗜曇郡の蝦夷が僧になりたいとの申し出を、天皇の詔により許可したと記述されています。優嗜曇は「ウキタム」、または「ウキタミ」と読ませており、承平4年(934年)頃に編纂された『和名類聚抄』では、「於伊太三(おいたみ)」の字があてられています。
「置賜は国のまほろば」と詠まれたように、この地域は、豊かな土地であったと思われます。それは、この地に天皇領や摂関家、後白河法皇の領地(本所)であったことからも推測できるものです。置き賜う=興玉=オギタマ(伊勢の二見ケ浦には興玉神社がある。)という名前からも、当時の権力者は、条件の良い豊かな土地を自分のものにしていたと考えられるからです。
さらにこの地方は、西東北における蝦夷と大和朝廷との境にあたり、国土防衛線の意味もあったと言われます。このことは、西東北地方における前方後円墳の分布においても、当地の南陽市に存在する稲荷森古墳の特異性からも伺うことができます。蝦夷集落を管理しなければならない最前線であったとすれば、置賜は「日置郡、置部(へきべ)」に関した名前とも考えられる。「へき部」とは、古代出雲族から出た氏族の名前であるが、その後役職名となり、「住民の戸数を調べる仕事で、税務と行政」を司る意味に使われるようになったと言われています。
「置賜は国のまほろば」と詠まれたように、この地域は、豊かな土地であったと思われます。それは、この地に天皇領や摂関家、後白河法皇の領地(本所)であったことからも推測できるものです。置き賜う=興玉=オギタマ(伊勢の二見ケ浦には興玉神社がある。)という名前からも、当時の権力者は、条件の良い豊かな土地を自分のものにしていたと考えられるからです。
さらにこの地方は、西東北における蝦夷と大和朝廷との境にあたり、国土防衛線の意味もあったと言われます。このことは、西東北地方における前方後円墳の分布においても、当地の南陽市に存在する稲荷森古墳の特異性からも伺うことができます。蝦夷集落を管理しなければならない最前線であったとすれば、置賜は「日置郡、置部(へきべ)」に関した名前とも考えられる。「へき部」とは、古代出雲族から出た氏族の名前であるが、その後役職名となり、「住民の戸数を調べる仕事で、税務と行政」を司る意味に使われるようになったと言われています。
2012.07.27:orada:コメント(0):
羽前成田駅前変な民俗学者?⑦おきたまの語源Ⅰ
全国の多くの皆さんにとっては、「置賜(オキタマ)」という地名は極めて難しい読み方であったと思います。そんな困難を乗り越えて、このページまでたどり着いてくれた方のために、ちょっと面白いお話を致します。この語源は,遠く東南アジアやヨーロッパまでつながる壮大なロマンがあります。今回はその第1回目で,「まほろば」について考えて見ます。多少の不正確さを念頭に、語源学を楽しんでください。
山形県が生んだアララギ派の歌人 結城哀草果は、映画スィングガールズのロケ地ともなった、長井地域の葉山の山並みを見て、次のように詠んでいます。「置賜は国のまほろば 菜種咲き若葉しげりて 雪山も見ゆ」。
まほろばとは、丘陵に囲まれたのどかで実り豊かな土地という意味です。日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が詠んだといわれる「大和は国のまほろば たたなづく青垣山こもれる 大和しうるわし」の句に通じるものです。置賜には、国の指定史跡「日向洞窟」をはじめ、縄文時代の遺跡が各所から発掘されていることからも、古代からまほろばであっただろうと思われます。
山形県が生んだアララギ派の歌人 結城哀草果は、映画スィングガールズのロケ地ともなった、長井地域の葉山の山並みを見て、次のように詠んでいます。「置賜は国のまほろば 菜種咲き若葉しげりて 雪山も見ゆ」。
まほろばとは、丘陵に囲まれたのどかで実り豊かな土地という意味です。日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が詠んだといわれる「大和は国のまほろば たたなづく青垣山こもれる 大和しうるわし」の句に通じるものです。置賜には、国の指定史跡「日向洞窟」をはじめ、縄文時代の遺跡が各所から発掘されていることからも、古代からまほろばであっただろうと思われます。
2012.07.27:orada:コメント(0):
羽前成田駅前変な民俗学者?⑦竹取物語
第五話 日本民族と竹取物語
ちょっと前に、「かぐや姫」というフォークグループがいたのをご存知ですか。この「かぐや姫」の元の題名は、「竹取物語」なのです。竹取物語に最初に出てくるのは、竹林の中のお爺さんです。それは月の夜、お爺さんが竹林の中から光る竹を見て、その竹を切るところから物語は始まります。
この物語の最初のポイントは、「月」です。女性と月とは切っても切れないものですよね。外国語のルナティックとは月の光の中に立つ女性の妖艶さを表現したものです。第2のポイントは、「竹」です。竹=節を持ったモノであり、私の記憶が正しければ,心理学で言う「リビドー(男性器)」を表現したものにほかなりません。
物語の最後にかぐや姫は、お爺さんとお婆さんに別れを告げて月に帰ります。かぐや姫が舞い降りた使命は、多分、子供のいなかった二人に夢を与えることでなかったかと思います。この物語は、女の子が主役であるために、多少なまめかしくて、エッチぽいお話になった事をお許しください。
互いに愛する夫婦にとって,子供を授かると言うことは,本当にありがたい事なのです。でも良くわからないのが,かぐや姫に振られた3人の男達ですね。勝手な思い込みですが,かぐや姫を好きになった男性が,お爺さんとお婆さんを好きになり,大事にしてくれたら,どうなったでしょうかね。もしかすると結婚できたもね。
私事になりますが、年をとると、女の子はつくづく可愛いいなあと思います。私には、女の子がいなかったので、せめて孫は女の子がほしいなあと思う今日この頃です。
ちょっと前に、「かぐや姫」というフォークグループがいたのをご存知ですか。この「かぐや姫」の元の題名は、「竹取物語」なのです。竹取物語に最初に出てくるのは、竹林の中のお爺さんです。それは月の夜、お爺さんが竹林の中から光る竹を見て、その竹を切るところから物語は始まります。
この物語の最初のポイントは、「月」です。女性と月とは切っても切れないものですよね。外国語のルナティックとは月の光の中に立つ女性の妖艶さを表現したものです。第2のポイントは、「竹」です。竹=節を持ったモノであり、私の記憶が正しければ,心理学で言う「リビドー(男性器)」を表現したものにほかなりません。
物語の最後にかぐや姫は、お爺さんとお婆さんに別れを告げて月に帰ります。かぐや姫が舞い降りた使命は、多分、子供のいなかった二人に夢を与えることでなかったかと思います。この物語は、女の子が主役であるために、多少なまめかしくて、エッチぽいお話になった事をお許しください。
互いに愛する夫婦にとって,子供を授かると言うことは,本当にありがたい事なのです。でも良くわからないのが,かぐや姫に振られた3人の男達ですね。勝手な思い込みですが,かぐや姫を好きになった男性が,お爺さんとお婆さんを好きになり,大事にしてくれたら,どうなったでしょうかね。もしかすると結婚できたもね。
私事になりますが、年をとると、女の子はつくづく可愛いいなあと思います。私には、女の子がいなかったので、せめて孫は女の子がほしいなあと思う今日この頃です。
2012.07.21:orada:コメント(0):
羽前成田駅前変な民俗学者?⑥最上川を下った子供達
「悲しすぎる子供達」の続編として,「最上川冒険の旅・200キロ」について書いてみたい。平成10年に行われたこの事業は、山形県の子供達を募集し、2泊3日で最上川源流の地・長井から酒田までボートで下るものである。キャッチコピーは「最上川よ、父の強さをこの子達に与えたまえ。母なる心を持ってこの子達を守りたまえ」。長井と新庄市の子供、さらに東京の子供も参加し、15人になった。スタッフは、職場の同僚や坊さん、学校の先生、そして万全を期すために国土交通省、建設協会のバックアップもいただいた。
初日は、長井に集まり、ボートから落ちたときの練習をやり、長井の参加者の自宅に民泊。翌朝、緊張した顔の子供たちは、それ以上に心配げな両親に見送られていよいよ出発。その日は、村山市の松田清男さんが主催する「卒業のない学校」に宿泊。カレーライスを自分達でつくり、楽しく過ごさせた後に、松田学長の講話の時間である。子供達には、「先生から足をくずして良いですよ」と言われるまでは、正座しなさいと伝えていた。板の間にである。その姿を見て、松田学長は「君達の姿勢は素晴らしい。背骨は人間の柱である」と話して、「県民歌」を教えてくれた。
2日目は、新庄市の本合海が終着点。そこで、最上川観光会社の会長である押切六郎さんの講話を聞き、本合海地区の人達が作ってくれたバーべキュウ大会と花火大会を楽しんだ。子供達が宿舎に帰る時間が近づき、押切さんが子供達を集めて話をした。
「最上川は山形県の背骨である。君達はその最上川を下って、ここまで来た。君達よ山形県を背負う人間になれ。私が、南洋の戦地にいた時に戦友と共に県民歌を歌ったんだ。その歌を君達と一緒に歌いたい。」。押切さんを中心にして「広き野を、流れ行けども、最上川」と歌い始めたときに、子供達は涙で声を詰まらせて歌を歌えなくなっていた。宿舎に帰るときに、一人一人が、押切さんと泣きじゃくりながら、握手をしていた。
そして、最終日、最大の難所が待ち受けていた。岩が両岸にせまり、大怪我をするかもしれなかった。中学生を中心にクルーを組んだが、東京から一人で参加した男の子が体調を悪くしてしまった。彼に「お前、行くか」と聞いた。彼は、目に涙を浮かべながら「行きます。行きます」と訴えてきた。「よし、行け。頑張れ!」と言って送り出した。後から聞いた話では、皆がボートを降りて引いて歩いた浅瀬から、急な深みに入るときに、彼は小学生を先にボートに乗り込ませ、最後に彼がボートに滑り込んだそうである。いよいよ酒田まで到着したとき、一人一人に感想や俳句を発表してもらった。その中の一人は「酒田には希望というものがあり」と詠んだ。自然との感動体験は、詩人にさせるものだと感じたものである。
今、心が荒れていると言われ,親子の関係も、子供同士の関係も異常としか思えない事件が報じられている。しかしながら、生まれてきた子供達は、純真無垢なものである。体に障害を持って生まれようと、「たった一つの宝物」の世界がある。子供が荒れるのは、大人のウソを見抜くからではなかろうか。初めて出会った押切さんに涙を流したのは,押切さんの心に触れたからであろう。「あー、夏休みになって子供達の顔を見ないですむ」と言ってスタッフとして参加した学校の先生は、最後に「子供は少しも変わっていなかったんだ」とポツンと語った。あるスタッフは「この旅は、自分探しの旅だったんだ」と語ってくれた。最上川が教えてくれたものは,それぞれに,大きいものがあったのだろう。
こんなことが,これを読んでくれた人にとって,何かの役に立ってくれれば幸いである。人生には早瀬もあれば澱みもあるさ,広き野を巡って生きれば,綺麗な夕日が見えるさ!
初日は、長井に集まり、ボートから落ちたときの練習をやり、長井の参加者の自宅に民泊。翌朝、緊張した顔の子供たちは、それ以上に心配げな両親に見送られていよいよ出発。その日は、村山市の松田清男さんが主催する「卒業のない学校」に宿泊。カレーライスを自分達でつくり、楽しく過ごさせた後に、松田学長の講話の時間である。子供達には、「先生から足をくずして良いですよ」と言われるまでは、正座しなさいと伝えていた。板の間にである。その姿を見て、松田学長は「君達の姿勢は素晴らしい。背骨は人間の柱である」と話して、「県民歌」を教えてくれた。
2日目は、新庄市の本合海が終着点。そこで、最上川観光会社の会長である押切六郎さんの講話を聞き、本合海地区の人達が作ってくれたバーべキュウ大会と花火大会を楽しんだ。子供達が宿舎に帰る時間が近づき、押切さんが子供達を集めて話をした。
「最上川は山形県の背骨である。君達はその最上川を下って、ここまで来た。君達よ山形県を背負う人間になれ。私が、南洋の戦地にいた時に戦友と共に県民歌を歌ったんだ。その歌を君達と一緒に歌いたい。」。押切さんを中心にして「広き野を、流れ行けども、最上川」と歌い始めたときに、子供達は涙で声を詰まらせて歌を歌えなくなっていた。宿舎に帰るときに、一人一人が、押切さんと泣きじゃくりながら、握手をしていた。
そして、最終日、最大の難所が待ち受けていた。岩が両岸にせまり、大怪我をするかもしれなかった。中学生を中心にクルーを組んだが、東京から一人で参加した男の子が体調を悪くしてしまった。彼に「お前、行くか」と聞いた。彼は、目に涙を浮かべながら「行きます。行きます」と訴えてきた。「よし、行け。頑張れ!」と言って送り出した。後から聞いた話では、皆がボートを降りて引いて歩いた浅瀬から、急な深みに入るときに、彼は小学生を先にボートに乗り込ませ、最後に彼がボートに滑り込んだそうである。いよいよ酒田まで到着したとき、一人一人に感想や俳句を発表してもらった。その中の一人は「酒田には希望というものがあり」と詠んだ。自然との感動体験は、詩人にさせるものだと感じたものである。
今、心が荒れていると言われ,親子の関係も、子供同士の関係も異常としか思えない事件が報じられている。しかしながら、生まれてきた子供達は、純真無垢なものである。体に障害を持って生まれようと、「たった一つの宝物」の世界がある。子供が荒れるのは、大人のウソを見抜くからではなかろうか。初めて出会った押切さんに涙を流したのは,押切さんの心に触れたからであろう。「あー、夏休みになって子供達の顔を見ないですむ」と言ってスタッフとして参加した学校の先生は、最後に「子供は少しも変わっていなかったんだ」とポツンと語った。あるスタッフは「この旅は、自分探しの旅だったんだ」と語ってくれた。最上川が教えてくれたものは,それぞれに,大きいものがあったのだろう。
こんなことが,これを読んでくれた人にとって,何かの役に立ってくれれば幸いである。人生には早瀬もあれば澱みもあるさ,広き野を巡って生きれば,綺麗な夕日が見えるさ!
2012.07.21:orada:コメント(0):