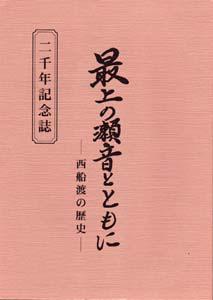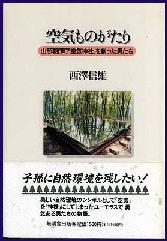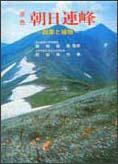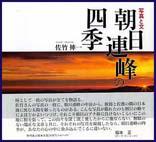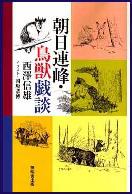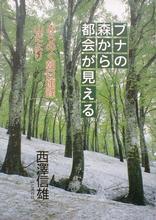朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
朝日連峰の原始の面影を残す、豊かな自然とスケールの大きい山岳景観に魅せられた人たちが集い、朝日岳をホームグラウンドとして、自然を慈しみながら活動を続けているのが、朝日山岳会です。国立公園管理員、環境庁自然公園指導員、県自然環境保全地域管理員、町山岳遭難救助隊員として活躍している人たちがいるばかりでなく、ヒマラヤ7,000M級の未踏峰の初登頂に2回成功したトップクライマーもいる会です。
お問い合わせ・入会希望の方は、下記事務局まで。年会費は二千円です。 朝日山岳会事務局 (朝日町役場産業振興課内 0237-67-2113) ホームページ →朝日山岳会 |
|
朝日鉱泉ナチュラリストの家は、昭和48年に廃業した「朝日館」を昭和50年に日本ナチュラリスト協会が譲り受け再建しました。(経営者/西澤信雄氏)昭和61年には大朝日岳を眺望できる現在地に新築されました。
大朝日岳登山や渓流釣り、山菜・茸採り、自然観察の宿泊基地として利用されています。二階には朝日町エコミュージアムブナの森サテライトとして展示コーナーも設置してあります。(見学は要問合せ) 宿泊料金 / 一泊二食付き10,000円(素泊まり6000円)。 ・道路通行止めになる冬期は休業 ・混み合う時は、相部屋になることもあります。 ・宿泊希望の方は、できるだけご予約ください。 ・登山シーズン以外では、不定期に休業日がありますのでご注意ください。 TEL 090-7664-5880(衛星携帯)西澤新地 公式サイトで道路状況などお確かめ下さい →朝日鉱泉ナチュラリストの家 (PCサイト) →アクセスマップはこちら |
朝日連峰の朝日川流域には蜜源樹の“トチノキ”が多く自生し、養蜂業が盛んに営まれています。
昭和63年(1988)日本ではじめての蜜ろうそく工房「ハチ蜜の森キャンドル」が朝日町に誕生しました。蜜ろうそくは養蜂で収穫される不用なミツバチの巣だけで作られます。 工房では購入はもちろん、製作体験(予約制)もできます。また、季節事のワークショップも人気です。工房では蜜ろうや養蜂についての展示も見学することができ、6〜9月は観察巣箱も設置されます。予約すればスライド映写による説明もして下さいます。営業日/土・日・祭日 お問い合わせ/電話0237-67-3260※見学は営業日のみ。 →蜜ろうの利用について →養蜂について →アクセスマップはこちら →ハチ蜜の森キャンドルHP |
故阿部幸作氏が、昭和57年に出版した朝日連峰初の本格的な写真集です。写真店を営む阿部氏が毎年十数回、合計300回以上朝日連峰に通い撮影したもので、県内外の多くの山岳愛好者に好評を博しました。(高陽堂書店)
※町立図書館で借りられます。 →阿部幸作氏について |
大朝日岳麓の山小屋「朝日鉱泉ナチュラリストの家」代表の西澤信雄さんが、朝日新聞山形版で10年間連載した「ブナの森通信」を一冊の本にまとめたネイチャーエッセー集です。(無明舎 1680円2009年刊)
※エコルームで販売しております。 |
朝日町在住の佐竹伸一氏(現朝日町山岳会副会長)が10年に渡り朝日連峰の四季を撮り続けてきた写真集です。写真一点一点に添えられた紀行文に朝日連峰の魅力や思いが感じ取れます。朝日新聞の山形版に「朝日連峰の詩」として50回以上、一年半にわたって連載された作品です。2854円(無明舎)
関連サイト(佐竹氏の写真が見られます。) →朝日連峰山のアルバム(PCサイト) |
エコミュージアムの小径第一集。朝日町で養蜂を営む方々に、始められたきっかけやエピソードを聞き取りしました。朝日岳山麓で営まれる養蜂の魅力を知ることができます。A5版 平成7年(1995)編集・発行/朝日町エコミュージアム研究会 500円
※エコミュージアムルームで販売しております。 |
日本ナチュラリスト協会カモシカ調査グループは、山形県朝日連峰において、1976年からニホンカモシカの生態調査および保護活動を実施しています。 ニホンカモシカをもっと知るために発行されました。A4版 編集・発行/日本ナチュラリスト協会・日本ネイチャーゲーム協会 1000円
※エコミュージアムルームで販売しております。 |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum