朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
日常では見られなくなってしまった町の花「ヒメサユリ」を、栽培を通じて普及・PRすることを目的として、平成9年に結成されました。椹平の棚田を見下ろす一本松公園には、種を植えてから開花まで6年の歳月を費やして育成した在来種のヒメサユリが数多く見られるようになりました。ポット入り苗の頒布も試みられています。
※写真は会長の長岡嘉一郎さん |
エコミュージアムの小径 第4集。大竹国治が保存していたものを、菅井進氏が粗石器として同人誌『縄文』に発表しました。これは旧石器第一発見とされている群馬県の岩宿遺跡よりも早い発表だったのです。
A5版 編集・発行/旧石器シンポジウム実行委員会 ※エコルームで販売しております。(郵送可)500円 |
朝日町エコミュージアムの小径第8集。水とくらしをテーマに、八ッ沼地区内に残る幻となった源次兵衛堰、五本樋、椹平の棚田(能中)など旧跡やため池をめぐり、先人の知恵のある暮らしに触れました。A5版 編集/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、山形県土地改良事業団、山形県
※エコルームで販売しております。500円 |
朝日町エコミュージアムの小径 第2集。朝日町有形文化財に指定されている藤原時代の作といわれる薬師如来立像と新宿地区の関わりを知ることができます。A5版 編集・発行/朝日町エコミュージアム研究会
※エコミュージアムルームで販売しております。500円 |
|
朝日町エコミュージアムの小径第8集。水とくらしをテーマに、八ッ沼地区内に残る幻となった源次兵衛堰、五本樋、椹平の棚田など旧跡やため池をめぐり、先人の知恵のある暮らしに触れました。A5版 編集/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、山形県土地改良事業団、山形県
※エコルームで販売しております。500円 |
山形県の大江町と朝日町、寒河江市の、最上川の一部とその支流、月布川とその支流、朝日川とその支流を管轄河川とする漁協です。遊漁券の販売や釣り情報の提供を行っています。
朝日町宮宿1184-8 電話0237-67-2207 →ホームページ(PC) |
朝日町北部地域の有志等により刊行されました。歴史と文化財がたくさんの写真で地区ごとに詳しく紹介されています。 編集・発行/朝日町北部地区郷土資料集編集委員会 平成14年発行
※エコルームで販売しております。(郵送可)1200円 |
朝日町のシンボル朝日岳に登り、朝日連峰の雄大さを肌で感じながら登山を楽しみ、併せて参加者どうしの親睦を深めることを目的として開催されています。
日時 / 10月初旬頃の一泊二日 コース / 白滝〜鳥原山〜小朝日〜大朝日〜鳥原小屋泊 主催 / 朝日町体育協会 詳しくは / 山岳会事務局 朝日町産業振興課 TEL0237-67-2113 |
朝日町出身(山形市在住)の柴田謙吾氏が長年続けられてきた最上川舟運に関わる研究の集大成。
著者:柴田謙吾 出版社:大風印刷出版局 価格:2,381円 出版日:2001年8月29日 ※朝日町立図書館で借りられます (朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」内) |
西船渡区の歴史を正確に記して後世に残そうと編集・発刊されました。八ッ沼城と西船渡のかかわりをはじめ、最上川水運、寺社、産業、行事、思い出話まで、近世から現代までの歴史が詳細に記録されています。
編集・発行/西船渡区史編纂委員会 発行日/平成6年3月31日 ※町立図書館で借りられます。 |
棟札によると、観音堂は安永9年(1780)に願主鈴木忠右エ門が創建したことが分かります。忠右エ門は観音信仰が厚く、西国、四国を始め全国の三十三観音を巡礼した碑が現存し、祭壇には西国88ヵ所の観音像(土製)が祀られてあります。
また雪谷は、五百川三十三観音の成立に尽力した石橋太郎が、西国88ヵ所を回り終え帰った10年後(1842年頃)、自分の家を最上川対岸に見つけ喜んだ場所として「五百川三十三観音」の最終札所に選んだとされています。(詳しくは縁起を参照) 五百川三十三観音第33番札所。 ※参考/『ふるさと朝日町散歩』 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら ※分かりにくい場所です。事前にエコミュージアムルームまでお問い合わせ下さい。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum
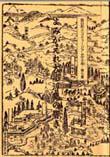






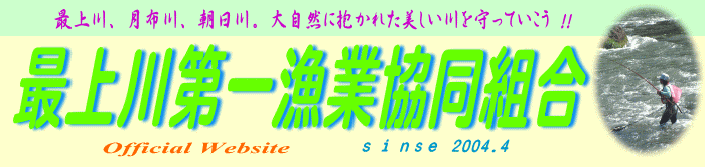



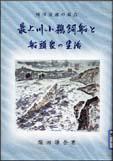









※エコルームで販売しております。500円(郵送可)