朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
神明神社の鎮守の森をはじめ、高田地区はもっとも身近にブナ林を楽しめる集落です。地区を挙げて整備したメダカの高田分校には朝日町在来のメダカや初夏にはホタルの乱舞を見ることができます。集落内を散策します。
案内 / 佐竹啓次 |
朝日岳山麓は、蜜源樹のトチノキが多く盛んに養蜂が営まれています。ミツバチの巣で作る蜜ろうそくの工房を訪ねます。スライド映写の説明やAsahi自然観近くの養蜂場を訪ねることもできます。ネットを被っての観察会(10人まで5000円)や蜜ろうそく作り体験(一人1500円)もたまわります。
案内 / 安藤竜二 |
朝日町エコミュージアム研究会〜NPO法人朝日町エコミュージアム協会の活動
平成元年10月13日 第1回研究会設立準備会議 10月20日 第1回研究会例会 平成2年 1月19日 第3回研究会例会 エコミュージアム研修会(講師 新井重三先生) 平成2年 5月19日 第6回研究会例会(基本構想委員会として活動開始) 《サテライト候補地調査 (新井先生、丹青総研)》 平成2年10月21日 「朝日町の暮らしと文化」町内めぐり(中央公民館と共催) 顧問、コンサルタントとの意見交換(第12回例会)(新井教授、丹青総研 里美部長、加藤研究員 来町) 平成3年3月17日「エコミュージアム・シンポジウム」(地域開発研究会主催、中央公民館) 平成3年10月4日 エコミュージアム基本構想調査報告書報告会 平成3年11月7日 第20回例会 (フランス視察研修報告会) 平成4年3月10日 第1回エコミュージアム・フォーラム(都道府県会館) 平成4年3月21日 第10回環境教育セミナー(埼玉県大滝村) 平成4年6月 5日〜6日 国際エコミュージアムシンポジウム(基調講演、パネルディスカッションほか) 平成7年 6月 「エコミュージアム国際会議」(日本エコミュージアム研究会と共催) 平成 8年11月 「旧石器発見60周年記念シンポジウム」 平成 9年12月 「大谷往来シンポジウム」 平成10年12月 「旧三中分校シンポジウム」 平成11年 1月 第1回朝日町の宝物カルタ大会 平成11年 8月 エコミュージアム・ガイド(まちの案内人)の会設立 平成11年10月 「大沼浮島シンポジウム」 平成11年12月 NPO法人朝日町エコミュージアム協会発足 平成12年 6月 エコミュージアムコアセンター「創遊館」オープン(協会でエコルーム・コーナーの管理・運営を受託) 平成12年12月 「ワインシンポジウム」 平成13年 6月 第1回「水とくらしの探検隊」 平成13年 7月 「センス・オブ・ワンダー」上映会 平成13年 8月 「山形県朝日町のエコミュージアム」VTR制作 平成13年11月 「リンゴシンポジウム」 平成14年 7月 第1回早稲田大学 留学生受け入れ (16年度まで) 平成14年 8月 「あさひまち宝さがし」キャンペーン 750 点以上の応募 平成14年 第1回「あさひまちの宝展」 平成15年 6月〜 「エコミュージアム宝紀行(見学会)」キャンペーン全10回 平成15年 3月 宝検索PC「あさひまちの宝箱」設置 入力開始 平成16年12月 「海野秋芳シンポジウム&紀行」 平成16年12月 「かみごう宝さがし展」 平成17年12月 エコミュージアムカルタのリニューアル 平成18年 3月 「暮らしの得手前楽習祭」 平成18年 7月 〜 「最上川学〜おらほの五百川峡谷〜 連続講座」 平成18年11月 「五百川峡谷シンポジウム」 平成19年10月 架橋70周年記念「旧明鏡橋 講演・思い出語り・周辺見学会」 平成20年5月〜 朝日町ふるさとミニ紀行の開催(13回、案内人の会) 平成20年10月 「最上川・五百川峡谷シンポジウム」(白鷹・朝日・大江) 平成21年 「〜朝日連峰初の山岳写真家〜故阿部幸作氏写真展」(3回) |
樹齢およそ700年とされる伊豆権現神社のご神木「種まき桜」が咲き始め、今年も地元有志らによりライトアップが始まりました。代表の長岡秀典氏は「境内には観賞用のベンチも設置した。歴史を感じる幹の迫力と美しい花の調和をゆっくりとながめて欲しい」と。ライトアップは、節電のため毎晩7時から9時までの2時間のみ行われています。
4/26現在で三部咲きですが、咲き始めの濃いピンクがとても美しいです。 →アクセスマップはこちら |
エリア地区 / 大谷
見どころ・注意/ ・菅原道真の太宰府左遷時に側室家族が移り住んだと伝わります。 ・江戸幕府のご朱印寺社がたくさんある由緒ある歴史を持つ地区です。 ・秋葉山山頂からの眺めは美しいです。 ・睡蓮ため池の見頃は6月中頃〜7月はじめです。 ・大谷地区は道が狭く小路も多いので迷いやすいのでご注意下さい。 ・小さな寺社やため池は、分かりづらい場所も多いので、エコミュージアムガイドの利用をお薦めいたします。 (お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |
朝日町で最大のミズバショウ群生地です。
藤沢盛治さんのお話 →杉山のミズバショウ →アクセスマップはこちら ※旧杉山分校跡より細道を南におよそ3km程登ります。道が狭いのでご注意下さい。途中、水田をはさんで分かれ道になりますがどちらからも行けます。 |
旧村社 白山神社 由緒
鎮座地 西村山郡朝日町大谷七三八ー一 祭神 菊理姫命 伊邪那岐命 伊邪那美命 与茂津言解之男命 境内社 稲荷社 末社 日月社(船渡) 例祭 七月十七日 大谷の白山神社は承和七年(八四〇)、加賀の国(石川県)の白山大権現より勧請し、天喜年中(一〇五三〜一〇五七)に源頼義が武運長久を祈願したと伝わる。昔からいくさの神として領主の崇敬厚く、特に寒河江の大江氏や山形城主の最上氏より十九石四斗余の社領を寄進され、さらに慶安二年(一六四九)徳川三代将軍家光より、石高同じく、朱印状(徳川将軍が朱印を押して発行した公文書)をもって安堵されたのである。 宝永四年(一七〇七)近郷九か村(大谷、大暮山、川通、栗木沢、船渡、左中、粧坂、中沢、富沢)の総鎮守として、各村々から寄進を受け、白山神社を再建した記録が残っている。 江戸時代、白山神社の西側朱印地に寺を建て白山寺と称し、真言宗寒河江惣持寺の末寺となったが、天保時代(一八三〇〜一八四三)に廃寺となり、跡地は畑になったといわれている。この場所に明治十二年(一八七九)大谷小学校が初めて建設されたのである。 明治七年官令により村内の御朱印社であった天満宮、八幡神社、愛宕神社、北野天神社、若宮八幡神社、二渡宮、日光神社を白山神社に合祀。 もとの白山神社は、旧大谷小学校の東側にあり、境内は広く、モミの木や杉、かえで、桜などの大木が茂り、千百年余の間、氏神として親しまれてきたのであった。しかし、終戦後、昭和二十一年(一九四六)五月、進駐軍(GHQ)より、大谷小学校と隣接する白山神社を教育施設より切り離すよう命令され、止むなく社殿を解体、恩賜郷倉(非常時の米倉)に一時保管。昭和二十五年(一九五〇)八月三十日、現在地に茅葺き屋根を銅板葺に変え昔のままの立派な社殿を再建したのである。当日深夜、松明の先導で別当南蔵院(小野家)より新殿に遷宮したと伝えられている。跡地には、新制の大谷中学校が建設され、今も残るヒバの木は、白山神社本殿跡に植えられた記念樹である。 [白山神社の本地仏である十一面観世音菩薩座像(朝日町の文化財に指定)は別当家であった南蔵院(小野家)で所蔵している。] 宮司 豊 嶋 宏 行 編纂 堀敬太郎氏(令和五年) → 大谷 白山神社 → 旧白山神社跡地 地図 |
最上川舟運と五百川峡谷 横山昭男氏(山形大学名誉教授) 〈金比羅・象頭山信仰と舟運〉 朝日町長寿クラブ連合会で調査し発行下さった『朝日町の石佛』によると、朝日町には象頭山・金比羅権現の石碑が全部で22基ある。江戸時代末期に作ったものが多い。香川県琴平郡にある金比羅権現は、舟乗りや舟乗りに関係する人たちやその家族が信仰していた。最上川を下って、日本海の西廻り航路を通って江戸に行くにも大阪に行くにもそこを通る重要な経過点なので、安全航海するためや家内安全も含めて信仰していた。舟の仕事をする人がだんだん増えた証拠といえる。 〈最上川舟運の展開と特色〉 舟運が急速に発展したのは、江戸時代に全国が幕府により統一され、税金を重たい米で納めるようになってから。便利な川舟や海舟がどんどん使われるようになった。 最上川舟運開発の大きな出来事は、最上義光による碁天、三河の瀬、隼(村山市)の三難所開削。ここを砕く事により、山形から酒田まで通れるようになった。 数十年後の寛文年間には、河村瑞賢が西廻り航路を開発した。これが大きな出来事になったのは、起点が最上川河口の酒田だったから。それは、最上川流域に二十万石近い幕府の領地ができ、税金としての米を幕府まで運ばなければならなかったため。海のルートも最上川のルートもしっかりしたものが必要だった。 〈元禄時代の最上川舟運とその後〉 元禄時代に、最上川舟運に米沢藩の参画があった。寛文年間まで、米沢藩は置賜地方と福島に30万石を持っていた。しかし、寛文四年に15万石に減らされ、今の福島県分がなくなってしまった。これにより、それまで江戸に米を出す場合は、福島へ陸送して阿武隈川から東廻り航路で運んでいたのを、最上川を通すようにしなければならなくなった。通るようにしたのが有名な西村久佐衛門の開削だった。西村は米沢藩の御用商人。自らも多額な投資をして五百川峡谷を開削した。 五百川峡谷にはおそらく、それまで作業用の舟や渡し舟はあっても、左沢まで一貫して通る舟はなかった。開削のおかげで常時川舟が通れるようになった。これは大きなこと。ここだけでなく、中流、下流まで通ったのだから、最上川全体にとっても大発展だった。この五百川峡谷開削は大革命だったと言える。 最上川船請負差配役は、いろんな人が所有している川舟をうまく動かすために全体を統括する人のこと。享保年間からはじまり寛政年間の60〜70年位続いた。ただ、最終的にはかなりの困難をきたし、差配役だけには任せられなくなり、川船役所を作った。差配役と幕府の役人と両方で川船の統帥をやって乗り越えた。 その頃、米沢藩では御手船(大名の船)を作った。上流は小鵜飼船だった。小鵜飼船は左沢からは下って行けない。左沢から下流の酒田まではひらた船(�、平田)だった。寛政4年の記録では、小鵜飼船は100俵積みが12艘、50俵積みが48艘。あわせて60艘位が左沢から上流、五百川峡谷とか白鷹、長井の方まで上り下りしていた。 〈五百川峡谷の舟運〉 朝日町大舟木村の川船番所の管理は米沢藩だった。船数、怪しい荷物の取り締まり、規定以上の荷物の取り締まりなどをしていた。一石楢村(夏草)の大庄屋佐竹長右衛門家は、米沢藩の通船差配役をしていた。船子(水主)雇い、綱手道の管理、梁仕掛けの管理、破船の救出における人足割り当て、払い米の世話などの仕事をしていた。米沢藩の安全な通船を図る仕事をしていた。 お話 : 横山昭男氏(山形大学名誉教授) 平成18年(2006)最上川学 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
会が発足してまず取り組んだのは、種子の採取。町外から栽培に適した強い品種を取り寄せることも可能でしたが、「朝日町の在来品種をこつこつそだてていこう」というのが会の方針でした。
自生のものは植物としてそう強いわけではなく繊細。手間暇がかかることを承知の上、能中の一本松公園に自生しているものから種子を採取し、平成9年秋に種まきを行いました。 その後、順調に発芽・生育し迎えた平成13年秋、栽培地が手狭になったため、広い土地に移植することになりました。しかし、これが悲惨な結果を生むことに。 移植場所が距離的に遠く、手入れが行き届かなかったことや土壌が合わなかったことなどが原因で数が激減。平成17年、やむなく当初の自生地である一本松公園に戻すことになりました。 これまで、いろいろな失敗がありましたが、その都度、会の志である「ヒメサユリの町」らしくなるまで頑張らなくてはならないという「使命感」を思い出し、がんばってきました。これからも会として、一本松公園などへの定植を毎年継続していきますが、これまでの挫折から学んだ栽培技術を、多くの人に伝えていくことが今後の私たちの役割と思っています。 毎年6月、家庭の庭先など、町内いたるところでヒメサユリが咲く風景…いつしかそんな日が訪れることを夢見ています。 お話 : 長岡嘉一郎さん (大谷六 ヒメサユリ愛好会会長) 『広報あさひまち平成21年6月号』より抜粋 →朝日町の花ヒメサユリ |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum






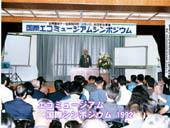



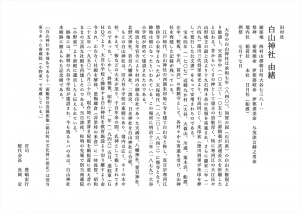









※お薬師様 / 木造薬師如来立像は山形県指定有形文化財。 脇侍の日光・月光菩薩像、眷属十二神将像あり。
コース / 創遊館〜新宿薬師堂〜館山鳥屋が森城跡〜昼食〜新宿ポンプ庫〜創遊館
案内 / 長岡秀典