朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
彼岸の頃、川通りのばあちゃんは「マスノスケは夜中に「マスノスケ今ここ通る!」と言いながら最上川を歩いてくんなだ。それを聞くと死ぬなだ」と教えてくれた。おっかなくてがらがら寝るんだっけ。マスノスケは、キングサーモンのことをいう。昔、少しは上ってきたんだ。
お話 : 熊坂正一氏(最上川第一漁業協同組合代表理事組合長)取材 : 平成18年 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
|
大谷往来
倩、徒然の紛れに、村の風景書き続け候わん。そもそも、大谷村東西南北山続き谷深うして、其の景殊に盛んなり。 先ず東に古館あり。清々たる最上川の流れ、前に当り帆懸船の往来を詠む。駒の頭に釣垂る人は水辺に居て竿の梢を見る。寔に(まこと)に用山の明神、粧坂の粧い眼下に相見え候。 後は愛宕山、山の頭に当り、草木の花帯び春の風に綻び落る風情は、秋後の雪の天に飛ぶかとうたがう。御伊勢原の雲雀霞の海に音あり、万世楽を囀る(さえずる)。日光山の鴉(からす)あやふきを告げ松椙に舎る。 南はかん嵯の鍵蕨寸尺延びて蛍に壱夜の宿を借す。面白岩に愛宕山、老若の男女袖を烈ねて参詣す。狐塚の百合草の花は小首を曲げて色を争う。間木山の残月梢の花清に入る。 西に当り社あり、大沼山と号す。其の景勝地森々たり、二十丈の松の枝、空吹く風のその音は颯々たり、琴の調べに耳を峙だて沼の浮島は形勢を揃え水浪に遊ぶ。 瀧の沢の兎子は、嶮岨の山腰を走り飯森山に居す。大暮山の在家夕陽の煙立って高山に登る。初木山の猿猴は杣人の往来を呼ぶ。 北に社あり、北野天神と号す。峯を登れば谷地山なり、岬伝いに所々に雪降り鹿の子斑に村消え、霞の内の松が枝茂蒼たり。後は、中丸、模様見田、狢森、前は田面打ち続き、西の溜井に鷺立ち、寺山の狼は鵜食沢の落馬を覘う。 (入力中) |
『大谷往来』は、今からちょうど303年前に作られたもので、作者が彦七となっています。残念ながら、この彦七については一切分かっておりません。資料も見つかっておりません。
しかし、この文章を見ると、的確に確実に順序よく書いてあるのが分かります。しかも、風景など見事に表現されています。こうした地元のことをよく知っているという観点からすれば、彦七は大谷に生まれ育った人ではないかと考えています。嘘を書いていません。 300年経った今ですら『大谷往来』の随所に、元禄の頃と変わりない情景が見られます。例えば「駒の頭の釣り人」ですが、今でも、その駒の頭で釣り人を見かけます。鯉の釣れる名所になっています。それから、文章の後ろの名所のところに出てきます「猿田山のツツジ」。全部で16の名所や名物が出ていますが、その猿田山のツツジは今でも大分残っています。また、「大清水のマタタビ」。大谷のはずれの大谷川沿いになりますが、夏に行くと葉が白くなって、大きな木々にたくさん絡んでいます。これも三百年たった今でも変わりがありません。時代を超えた自然の素晴らしさを改めて感じています。 お話 掘 敬太郎さん(大谷一) 平成9年12月「大谷往来シンポジウム」にて ※写真中央が「駒の頭」(秋葉山山頂より) |
私は明治三十七年生まれで、ずっと大谷で百姓をしてきたが、養蚕なんかもしていたこともある。 区長が終わってから、いろいろな歴史に興味を持って調べるようになったのだ。
〈『大谷往来』と原本について〉 『大谷往来』について初めて聞いたのは、堀敬太郎さんからだと思う。その昔は、長岡久蔵さんの空読みなんかも聞いたような気もする。 興味を持って原本なんかも見せてもらったが、和田さんのと久蔵さんのは同じだったが南蔵院さんのは少し違っていたので、和田さんのが原本だと思った。 南蔵院さんのは十丈の松だったが、十丈の松だったらどこにでもある。だから、二十丈の松の方が正しいと思ったな。 〈「彦七」について〉 左沢の白田佐院長は、白田内記家の出身で、白田家のことを詳しく調べて本を出したのだ。この本なんかを見せてもらい、いろいろと考えて、堀さんなんかとも話して、彦七は風和じゃないかと書いたんだ。 あの時代に、これだけの文章を書くのは、白田風和(秀勝)以外にはいないと思う。 〈私の記録帳に残っている〉 俳句なんか好きで、気がついたら帳面なんかに書いている。歴史のことも好きで昭和六十二年から書いている。この中に何回か『大谷往来』について書いたが、平成二年には「作者彦七を探る」というのを五ページにわたって書いている。 お話 大谷国勝さん 平成9年12月 元禄のエコミュージアム・大谷往来シンポジウムにて |
〈慶応生まれのばあさんも話していた〉
私は、大正十一年生まれで、『大谷往来』を覚えようと思ったのは、昭和三十六、七年頃だ。小学生の頃、俺のばあさん(慶応生まれ)が「かんかけのかぎわらび」なんて言っているのを聞いた事がある。でもばあさんは大谷生まれでないので、こっちに来て覚えてのだろう。 〈久蔵さんのを聞いて覚えようと思った〉 長岡久蔵さんが亡くなったのは昭和三十八年だから、その前に何度か久蔵さんから聞いて、俺の家にも原本があったので、それにカナふって覚えたんだな。 久蔵さん(明治十六年生まれ)がどうして覚えたのか知らないが、確かに節があった。かなり強い節をつけて語った浪曲みたいな節だった。藁仕事をしながら、語った何人かの人が聞いて覚えているのだと思う。 いつ頃から久蔵さんが語ったのかは知らないが、俺の家では何回か聞いた。 〈時々語ったが、あまり興味がないようだった〉 俺の家に何故原本があったかは分からないが、残っていたのだ。同じように百姓の道具のことを書いた本も残っている。 カナをふってから頑張って覚えた。だから、語ったりしたのは昭和三十六、七年以降だ。長寿クラブの総会なんかでも酒が入ると語ったが、そう多かったことはないと思う。でも、誰も興味がなかったようだ。 昭和四十年代、朝日ヌルマタ沢に木の伐採に行っていたので、その製材所で酒が入ると語ったりもした。でも、興味を持ってくれたのは、白田正蔵さん、鈴木幸次郎さんなどほんの少しの人だった。 〈この文章は覚えないと駄目だ〉 昭和四十八年に大谷小百周年で展示してから、たまに原本を借りにくる人がいた。でも、借りに来て写すだけじゃ駄目だ。覚えなくては駄目だと言った。この文章は、覚えるのに良い文章だ。文句も良いし、五七調だし、本当に美しい文章だ。文章が良かったので覚えたのだろうな。 この文章を読んでいるときは、作者彦七はきっと大谷のこの辺に座って作ったのだ。あの辺から見て詠んだのだと考えて読んでいる。すべての場所には行ったことはないが、大谷のことはよく知っているので、この文章の風景が目に浮かぶようによく分かる。 〈少し違うところもある〉 私の覚えているのと、今の解釈と違うところもある。解釈はいろいろあるし、原本もいくつかあるので何とも言えないが、最後のところは、作者は大谷を回って帰ってきて、家に着いて考えてみると、すべてのことが夢のようだと言ってるのではないだろうか。 でもとにかく、こんな機会によって『大谷往来』が、多くの人に知ってもらったのは嬉しい。もう少し若かったら、もっと正確に語ることができたのだが、今は少し不自由で満足のいく語りができなかった。 昔、堀さんと、この『大谷往来』の文章をもっと多くの人に知ってもらいたいと話し合ったことがあるが、今実現して嬉しい。 お話 和田新五郎さん(大谷浦小路) ※平成9年(1997)大谷往来シンポジウムにて |
〈郵便局たよりに載せた〉
若い頃から、歴史や地理に興味があったが、特別な勉強をしたことはなかった。 初めて『大谷往来』を知ったのは、昭和三十五年頃に大谷小の沖津先生が出した『私たちの村』という冊子に載っていたのを見たのが最初だと思う。 昭和五十年前後から、いろいろな原本を見てそれぞれに違うところがあるので、これは何とかしなければならないと考えて勉強した。 初めて皆さんに紹介したのは、昭和六十年頃に大谷郵便局の『郵便局だより』というものに、何か村の情報でも載せようと『大谷往来』のことを書いたんだ。 〈『大谷往来』の写真を同級会に見せようとして〉 昭和四十年頃から写真を撮っていた。北部地区の風景や神社仏閣を全部撮り、同級会でみんなが集まったときに見せようと思った。 昭和六十年頃からは、『大谷往来』の風景をすべて写真で撮ってやろうと思って、大谷のいろいろ名物や風景を撮り始めた。でも、今になっても撮れないものがある。「間木山の残月」「大沼の浮島」など、なかなかうまく撮れない。でも、秋葉山からの景色など、江戸時代と今でも全く一緒だと思う。 〈『大谷往来』を読む〉 『大谷往来』にはいくつか原本があるので、どれが一体本当かというので、各々の文章を集めてとこが違うか調べてみた。 特に鈴木勲先生からは、二冬にわたって文書の解読を北部公民館の行事として教えていただいた。 「落馬をねらう」が「落ち葉をぬらう」になっていたり、「面白岩」が「西白岩」、「北野天神」が「小野天神」になっていたり、いろいろと細かいところで違っていた。「二十丈の松」と「十丈の松」なんかも違うとこだった。 〈『大谷往来』の地名は現存するのか〉 この文章は、だいたい現在も当てはまる。三百年前の風景と今の風景はまったく同じではないが、ほとんど現在に当てはまるものだ。今でもはっきりと場所が分からないのは「狢森」「桐ヶ窪」くらいで、ほかはほとんど分かっている。 「大江の鰌」でも、こんな大きな川があったのかと疑っていたが、古い字限図には本当に大きな川があったようだ。「西堤の鮒」も当時西堤があったのか調べたら、千六百三十年頃には西堤ができていたという記録があった。 〈「彦七」と「風和」について〉 大谷は、白田外記内記と共に栄えてきたのだと思う。「白田」なんて、言葉の意味からいえば「水が無く乾いている土地」ということだから、そこに菅原道真を先祖とする人々がやってきて、いろいろな京風の文化を栄えさせたのだと思う。だから、村の中もT字の道が多かったり、神社仏閣が多いのだろう。 この『大谷往来』の文章をみると、この地方にほんの少し滞在したくらいでは書けないほど情報も多い。だからきっと作者彦七は「風和」じゃないかと思う。証拠がないので何とか探してみたいと思う。でも、彦七だけではなんとしようもない。 〈「風和会」について〉 郷土史講座を北部公民館で長くしてきたので、それを受けて民間の郷土史学習団体「風和会」を作った。自由に北部の歴史を考えたり、『大谷往来』だけでなく、いろいろな古いものを記録に残しておきたいと思っている。 今、大谷は基盤整備でいろいろなものがなくなってしまうかもしれないので、今のうちに見ておきたいと思っている。 写真に撮れるものは撮らないと、特に水に関することはすぐ変わってしまう。ほんの少し前は、「桜清水」「大清水」「香ヶ清水」なんかも良い水が出ていたが、もうすぐ分からなくなってしまうだろう。 「白田」というひどい状態だったところに、水を引っ張って田を開田して生きてきた先祖の苦労を少しでも知るために、いろいろと調べたいと思う。 〈『大谷往来』を永遠に残したい〉 まだまだ、『大谷往来』の文章については調べたい。初木山も間木山も歩いてみたいと思う。三百年も続いてきた文章とその景色が今無くなってしまうのは、本当にもったいない。 もっともっと『大谷往来』を勉強して、多くの人に知ってもらい、これから五十年も百年も先の人に残したい。それには、資料にしたり、本にしたりして残す必要がある。 こんなことが何の役に立つか分からないが『大谷往来』の文章が三百年経って、これだけ多くの人々を引きつけたのだから、またここで大切にすれば、何十年かは残るだろう。 お話 掘 敬太郎さん(大谷立小路) 平成9年(1997)大谷往来シンポジウムにて ※写真は秋葉山頂の秋葉山神社碑と『大谷往来』の説明板 |
林野庁の「森の巨人たち百選」に選ばれた幹周り9.27メートルのクロべの巨木と、新緑のブナの森を楽しみます。朝日町ふるさとミニ紀行Vol.2(朝日町エコミュージアム案内人の会)
日時 / 平成22年5月30日(日)午前 参加費 / 500円(資料・保険代) 集合 / 朝日鉱泉ナチュラリストの家駐車場 定員 / 10人(2時間半の登山ができる方) 案内 / 西澤信雄 ※弁当、飲み物ご持参下さい 申込み / エコルーム Tel 0237-67-2128 まで(月・木休み) もしくは左下お申込みフォームより。〆切5/20 →朝日鉱泉ナチュラリストの家 (PCサイト) |
エコミュージアムルームの臨時職員を1名募集しております。
期 間 / 2011年3月末日までの週5日 内 容 / ・朝日連峰初の山岳写真家故阿部幸作氏の8mmフィルムの整理・データ化 ・エコルーム一般業務の補助 詳細はエコルームまでTEL0237-67-2128(月・木休) |
エリア地区/宮宿
(お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |
承和11年(844)に延暦寺の僧安慧(あんえ)が奥州を巡り歩いて、講場をその地に開いた時、龍の神霊を祀って東五百川の鎮守として、別当東守寺を建立したと記されている。さらに慶長年間(1596〜1615)に寒河江肥前の守が社殿を再建し、明治維新の廃仏毀釈によって豊龍神社となり、東守寺住職は復職して豊嶋氏を称したとする。 明和年間(1764~72)に左沢在住の松山藩医であった羽柴玄倫が誌した『宗古録』には、安慧がこの地に天台の教えを広める決意をしたとき「瑞巌美麗の姫大神」があらわれ「我こそ海童神(わだつみのかみ)の娘なり」と名のり「汝の護法善神とならん」と誓ってくれたのが豊玉姫大神であるという。 さらに、安慧みずから大般若経600巻を書写して筐(はこ)に納め、この山上に埋めたと述べ、山号を「宝経といい或は宝筐と作る」と書いている。 ※『朝日町史 上巻』(朝日町)より抜粋 祭礼は5月3日。大獅子や宮神輿、樽神輿の行列など、宮宿地区を挙げて毎年盛大に行われています。 →アクセスマップはこちら ※駐車場は神社裏手にあります。 |
根周り11m、目通り幹囲7.5m。平安時代の承和11年(844)延暦寺の僧安慧によって豊龍神社創建時にご神木として植えられたと言い伝わっています。落雷や風雪により頂部や大枝を失くし樹勢を損なっていましたが、樹木医により適切な処置が施されました。山形県指定天然記念物(1965年4月指定)。
→豊龍神社 →アクセスマップはこちら |
エリア地区/常盤(夏草〜水口)
・佐竹家住宅の見学申し込みはエコミュージアムルームが受け付けております。直接申し込まないようお願い致します。 (お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum
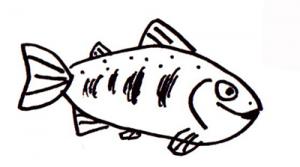


















・山形県朝日町のエコミュージアム 〜大谷風神祭のとりくみ〜
「エコミュージアム研究」No.20より抜粋(日本エコミュージアム研究会発行)
上記、ダウンロードボタンでpdfファイルを開けます。