ī��Į�����ߥ塼���������ī���ٻ�ϼ ī��Į�����Ͼ���
12.��ɴ�ë���ꥢ���ܺ٤ˤĤ���
Q1�������ķ��ߤ���ޤ�������
�嶿����η��ߤϡ�����35ǯ11��15���˹������幩��������37ǯ 2��23���˴����������������ȯ�ŤϤ��Ƥ���ޤ��� Q2�����ɤ��ȯ�ŤƤ��ޤ�����(ȯ��) �Ǿ�������˹⤵23.5��ȥ�Υ�����ۤ��ƿ���夲������ˤ�ä���������ˤ��ȯ�Ť�ԤäƤ��ޤ��� Q3�����ɤ��ȯ�Ť��Ƥ��ޤ�����(��) ȯ�Ž�Ǥϡ��Ǿ�������������ɴΩ����ȥ�ο���夷��������ϰ���5400������åȤ�ȯ�Ť�ԤäƤ��ޤ����ޤ���ǯ��ȯ�������̤���8000��������åȻ��ǰ��̲�����������ʬ�ȤʤäƤ��ޤ��� Q4�����ɤ������Ť��Ƥ��ޤ�����(���) ȯ�Ť����ŵ��ˤĤ��Ƥϡ��ϸ�ī��Į�仳�����դ�Ϥ���Ȥ��뤪���ͤ˶��뤷�Ƥ���ޤ��� Q5�����ɤΤ褦�ʻŻ��Ƥ��ޤ����� ȯ�ŤΤ����ɬ�פʿ�֎�ȯ�ŵ����ε���ΰݻ���������ӹ�����Υ�������ԤäƤ��ޤ��� Q6������ϫ���Ƥ��뤳�Ȥϡ� �嶿����ξ�ή��ꡢ�����Ѵ�ʪ����ޤ�����ߤ��籫�ΤȤ����̤�ή��Ƥ��뤳�Ȥ��顢���߽����˶�ϫ���Ƥ��ޤ��� Q7�������ߤˤĤ��Ƥ��к��Ϥ���ޤ����� ���ߤν����ˤĤ��Ƥϼ��������֤�����ư�����е��ˤ�ꡢ�����Φ�Ȥ��������ߤ�ʬ�̤Τ�����Ŭ���ʽ�ʬ����ӥꥵ�������»ܤ��Ƥ��ޤ��� Q8������ƻ�ˤĤ��ƶ����Ʋ������� ���桢�����ʤɤε����̾�Ǥ���褦�˳��ʾ��ο�ϩ�����֤��Ƥ���ޤ�����ƻ��Ĺ��330��ȥ뤢�ꡢ�����̤˴ط��ʤ���������ð�Ω����ȥ�ο��ή���Ƥ���ޤ��� Q9���������Υ��ԥ����ɤʤɡ�����¾�嶿����ˤĤ��Ƥ�¸���Ǥ����鲿�������Ʋ������� ����ȯ�Ž�η��߹����������Ԥǿʤ��졢¿�����Ȱ������������ϸ������������Ϸ���˽���ϫ̳�Ԥ��Фƹ��������Ư���Ƥ��ޤ�������������Ĺ�����֤��繩���Ȥ�ʤ�С����������ι�������˲����������������ޥβ֤��餭�������ε٤ߤ��ˤ���褦�ˤ��Ƥ����䤭��äƤ��벿�Ȥ��Υ��åץ뤬ȯ�����줿�����Ǥ������Υ��ޥ��Ȥ��䤬�Ƽ¤��ӡ�ȯ�Ž깩�������������ο͡������뤤�������뺢����Ǥ��������륤����ʹ���ޤ��� ���������������ϳ�����һ�����Ź ������������ή���������ڥ��롼�ס�����ǯ���ʿ��20ǯ�� �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
��ɴ�ë������1
�����������������������������������������ݿ����ʾ��ס� �����Ϥ���� ���Ǿ���ϡ��������Ϥ���廳���Ϥؤ�ή�����뤳�Ȥʤ����������Ϥ��������ˤ���Ĺ�����Ϥ˱��ơ��б����ͤ�Ӥ���ɴ�ë���̿ʤ����������黳�����Ϥؤ�ή���ʤ�Ƥ��ޤ��� ���Ǿ���ˤϸ�ɴ��ȺǾ嶮����Ĥζ�ë�����ꡢ���Τ������֡���������km����ɴ�ë�ȸƤФ�Ƥ��ޤ��� ������ιֺ¤Ǥϡ��Ǿ����δ���̤���̤Ȥ��ƺǤ��礭���ä����虜�虜�����ή���ɴ�ë���������������õ�äƤ������Ȥˤ��ޤ��礦�� �����Ǿ�������� �������飱��������ǯ��������������������Ⱦ�Ͽ��������������Ǥ��ޤ��������ߤλ������ˤ�����Ȥ��������褬������ˤ��ä��櫓�Ǥ�������������ǯ�����ˤʤ�ȡ�������������˹����äƤ������ο���������ν�˻�̮�Τ褦�ʹ�ޤ꤬�Ǥ�������������ϤΤ褦���Ϸ�����������ޤ����� �����������߲����줿��俼�����ϡ�����������ǯ�����ˤʤ�ȡ������ϰϤ����פ�δ���������Ȥˤ�ꡢ����˾������������ʤäƤ����ޤ��������ߤ������Ǹ����С����⤫�鿷���������������ˤ����Ƥΰ��Τ�Ĺ�����깾�Ȥʤꡢ���깾��ξ¦��Φ�ϤȤʤ�ޤ�������ޥ��������������奦�ϡ����Τ褦�����깾�������Ф뺫�ۤʤɤγ����٤����褷�Ƥ��ޤ����� ��������ǯ�����ˤʤ�ȡ����פ�δ���Ϥ���˿ʤߡ����ܳ�����³�����깾��ʬ�Ǥ���ơ������������������ν�ˡ��ܸۤ��ߤ����Ϥˤ�����Ȥ������о¤ȤʤäƤ����ޤ��������λ������Ϥ�ʬ�Ǥ��줿�о¤�Ĥʤ������������Τ����ϤκǾ���Ǥ��ꡢ�����Τ��䤫�����Ϥ����ͪ����ή��Ƥ����ΤǤ��� ������ɴ�ë������ �����ब����������͵��Ȥ��������फ����ȡ�����ޤǤ��䤫���ä��Ϸ��ϡ��㤷���ϳ���ư�ˤ�ä�Ħ���ۤɤ�����뤳�Ȥˤʤ�ޤ����������⤵�����������ǡ����Ϥ����ߤ�³���ʤ����δ���������Ϥ��鱿�Ф�Ƥ����ں������Ω�Ƥ��Ƥ������Ȥˤʤä��ΤǤ��� ��˽Ҥ٤��褦�˷㤷��δ����ư���Ϥޤ�������Ǿ���Ϥ��Ǥ����ϰ��ή��ξ�Ȥ�������Ǥ��ޤ����������ϸ��ߤ���������䤫��ή��Ǥ����������������դ����Ϥ�δ�����Ƥ����ˤĤ�ơ����Τ褦�ʴĶ��Ϸ��Ѥ��Ƥ������Ȥˤʤ�ޤ������Ư���ˤ�뿻���̤�����Ϥ�δ�����̤�����С���Ϥ���ή����Ѥ��Ƥ��ޤ��ޤ�����������δ�����̤��ʤ������ꡢ��Ϥ�꿼�����Ϥ��ꤳ��Ǽ��դ��ڤ�Ω�ä���ë�Ȥʤ�ޤ����Ǿ���ο������Ϥ����Ϥ�δ�������ϤȤ��������������ǯ�λ��֤��Ƹ�ɴ�ë�����������ΤǤ��� ���������ϳ���ư�ϡ��������ˤ����Ƥ�¼����ư�ȸƤФ�Ƥ��ꡢ������ǯ�����˻Ϥޤä��ȹͤ����Ƥ��ޤ���������ư�ˤ�äơ�����ޤǤΤäڤ�Ȥ����֤Τ褦��¸�ߤˤ����ʤ��ä�ī��Ϣ���������ر�ư��ȼ���ʤ���㤷��δ���������ߤΤ褦�ʹ⤯�������٤ȤʤäƤ����ޤ����ϳ̤ˤǤ�����������ޥ��ޤ��徺�������¢���������������Τ�Ʊ�������Ǥ�����ɴ�ë�������ϡ����������㤷���ϳ���ư�Ȱ�Ϣ�Τ�ΤʤΤǤ��� ʿ��18ǯ ���ݡ�����ʤ������������˻� ���£���ǯ�ʣ��������˻�����ض������´�ȡ���������������������ϵ�Ķ��ز�Ĺ�˻����Ű��˻ջ������ߡ�����ĮΩë���������ع���͡�� ���������ϼ��������ī�����ٲ�����Ĺ�������ж綨�������л�־����¡�Ʊ�͡� �����ī��Ϣ���λ͵��פʤɡ��ޤ�����ī��ĮĮ�ˡ��塦�����פ˼�ɮ�� ����ɴ�ë������2 �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
������ɴ�ë����Ĥηʴ�
��ɴ�ë�Ͼ嶿�ն�ˡ�ľ������ʤ���ή���ȡ��ʵ֤�ȯã����ή����������ή���Ȥ���ʬ����ޤ�����ɴ�ë���Ϸ�Ū����ʬ����븶���Ȥ��ơ��ޤ��ϼ��ΰ㤤���������ޤ����ϼ��ޤ�������餫�ʤ褦�ˡ���Ⱦ���Ϲż���ť���ؤǤ���Τ��Ф��ơ���Ⱦ��������ʥ���ȴ�亽���ؤǤ����ޤ����⤦��Ĥθ����Ȥ��ơ������ˣֻ����θ�������¤��δ���������ä����Ȥ��������ޤ����ֻ�������¦�ϳ�¦����δ���̤��������ä��Τǡ��Ǿ���˲�ƻ������;�Ϥ��Ĥ��줿�Ȥ������ȤǤ����ϼ��ι���κ��˲ä���δ���̤����٤κ�������ɴ�ë�˰ۤʤ���Ĥδ����������Ȥ������Ȥ��Ǥ��ޤ��� �ޤ�����ɴ�ë�β�ή�����ϼ���¤��Ǿ����ľ���������������̤Ǹ���ȡ����ؤ����������ʤ��֤��ĤĤ����Ū�ˤϸ��й�¤�ȤʤäƤ��ޤ������Τ褦�ʹ�¤��ʣ���й�¤�Ȥ������Τǡ��Ǿ����ʣ���Фμ����ն��ή��Ƥ��ޤ������Τ��Ȥ��顢��ɴ�ë�β�ή���ˤ����ơ��Ǿ���ϺǤ�δ���̤ξ��ʤ��ä���������ή��Ƥ���ȸ������Ȥ��Ǥ���ΤǤ��� �����ϴ��ʵ֤η����� �������ˤ���ī��Į�˵��Ť�ʿ�Ϥ�⤿�餷�Ƥ���Τ��ϴ��ʵ֤Ǥ��ꡢī��Į�ν���ΤۤȤ�ɤϤ����ʵ��̾�ˤ���ޤ��� ���ʵ֤ϰ���Ū�ˤ����Ϥ�δ���ˤ�äƷ������졢���ʤ���ʿó�̡��ʵ��̡ˤȤ��δ֤ˤ��볳����ʤäƤ��ޤ���ɸ��ΰۤʤ��ʵ֤�Ĥʤ�ƻϩ��ɬ����ƻ�Ȥʤ�Τǡ���̤Ȥ���ī��Į�ˤ�¿���κ�ƻ��¸�ߤ��ޤ����� ���ϰ��ή���Ǿ�����ʤ����ɴ�ë���ʵ��̤ϸޤĤ˶�ʬ����ޤ������ߤβϾ��Ȥ����ϡ��ʵַ������������������ȥ롢�ʵַ����������������ȥ롢�ʵַ��������������ȥ롢�ʵַ������������ȥ롢�ʵַ������ȥ�ʲ��Ǥ����ʤ����ʵַ���ɸ��ι⤤��ˤ����ΤۤɸŤ����㤤��Τۤɿ������ʤ�ޤ��� ���ʵַ���ϤۤȤ�ɻĤäƤ��餺���ܽ�����ƺ���Ϥ��¹�ʿ�ն�ʤɤˤ鷺����ʬ�ۤ��Ƥ�������Ǥ����ʵַ���ϡ��¹�ʿ��ǽ��Υ��̥�ʿ���ʵַ���ϡ�������̱�ۤΤ��뷧�λ���˭ζ���Ҥε��͡����ջ�����¦���ʵ��̤ʤɤǤ����ʵַ���ˤ����ι����ʵ��̤�¿�������������ס��ܽɡ��¹硦��ë�ʤɤ��ʵ��̤�����ޤ����ʵַ���ϸ��ߤβϾ��褤���㤯ʬ�ۤ��Ƥ��ޤ����������ʵַ��������������ˤϡ�����ޤǤ˺��줿�Ť��ʵַ���¦�������ˤ�äƺ�ꤳ�ޤ�Ƥ��ޤ��Τǡ���̤Ȥ��ƸŤ��ʵ֤Ϥ��ޤ�ĤäƤ��ޤ��� ������¾��ɸ�⣲������ȥ��ն�ˡ�����ʪ��¿�������ʵַ�������ޤ��������ϵܽ��ն�ǵ����ä��ȹͤ����뻳�Τ������ˤ�äƺǾ����ߤ��졢���ξ�ή���о¤Ȥʤä����θо�����ʪ����ʤ��Τǡ��������¥�ʿ�����θ��ʤɤϤ��������ʵ֤Ǥ��ꡢ������������ȥ�θ����Ǻ���Ǵ�ڤ����Ѥ��Ƥ��ޤ������ʤߤˡ����α�ߤ���ä��Τ��ʵַ���η�����������ʵַ���η������Ϥޤ�ޤǤδ֤Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ��������Ȥ����������ϤǤǤ���ŷ���Υ���ϡ������ο������Ϥˤ�äƤ��Ĥ����ä��Ƥʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ����� �ʵַ���������줿�����ϡ����Ҥ�ǯ��¬�꤫�飳��ǯ�����Ǥ��뤳�Ȥ����餫�ˤʤäƤ��ޤ��������λ����κǾ���ϸ��߰ʾ���礭����ή���Ƥ��ޤ��������θ塢�Ǿ����ήϩ��ľ��Ū���Ѥ�������ˡ���ή����¦�ˤϵ֤��Ǥ����פϻ�����ФȤʤäƻĤ�ޤ��������ʤ�����ܽɤ���ë�ϡ������礭����ή���Ƥ����Ǿ�������פˤǤ���Į�Ǥ��뤷��˭ζ���Ҥε֤Ƚ��ջ��ϡ����μ��꤬�Ǿ���˺�����뤳�Ȥˤ�äƤǤ������ͤʤΤǤ��� ʿ��18ǯ ���ݡ�����ʤ������������˻� ���£���ǯ�ʣ��������˻�����ض������´�ȡ���������������������ϵ�Ķ��ز�Ĺ�˻����Ű��˻ջ������ߡ�����ĮΩë���������ع���͡�� ���������ϼ��������ī�����ٲ�����Ĺ�������ж綨�������л�־����¡�Ʊ�͡� �����ī��Ϣ���λ͵��פʤɡ��ޤ�����ī��ĮĮ�ˡ��塦�����פ˼�ɮ�� ���ݿ��줵��ʾ��ס� ����ɴ�ë������3 �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
�һ��ȤΤ���ޤ���
����ĺǾ�����ή���ȿ������Ȥϡ�ī��Į�ͥ�������ȥ�ͥ�ǺǾ���ο���ꡢ�����ԤȻ���Į���廳�Ԥ�ŷƸ�Ԥΰ�����ä�������Į�ˤޤ��������Ϥ�����������äƤ��롣 ���������Ϥ���¦���ϸ����������ô֤�2t����¦��Ȫë��¡��Ӿ¡�����¤ʤɤ������о·�����3t�ޤǤȤ��褦�ˤʤäƤ��ơ��������ʤ�ʬ��Ǿ�������8t�ʸ��ߤ�4t�ˤޤǼ��Ǥ��롣�ϸ��������ϡ�����1t�����Ȥ�ʤ������ʤΤǡ��ۤ�Ⱦʬ�ϺǾ���ο����äƤ��뤳�Ȥˤʤ롣��˿�������¦�������ϰ��1500ha�����Ϥ˻Ȥ��Ƥ��롣��������졢�䤿�����ϲ��ɶ褬�������Ĥ�ԤäƤ��롣 ��º��̿�������ˤʤä��繩���� �����������ȥ�ͥ�ϡ�����Į�κ��ݤޤ�9.1km��Ĺ�������롣���δ֤ι��㺹��3.6m�����ʤ���2500ʬ��1�Τ��䤫�ʸ��ۤ�����ְʾ夫���Ƥ�ä���ή��Ƥ��롣������65���ߤ�������48ǯ���幩����10ǯ��ξ���58ǯ�˴������������Ϥο��Ĥ�ᤷ�����ͻ��夫�����꤬�����뤲��줿�� ��������������51ǯ��53ǯ�ˡ����٤Υ����ȯ��18�ͤ�º��̿��å��줿�����郎1�ѡ��ƥ�9�ͤǡ�ī��Į¦�Ȼ���¦�Ǥ��줾��9�ͤ��ĵ����ˤʤä����и��λ���Į�˰����㤬���Ƥ�졢ǯ�˰��ٰ�²�����⻲�ä��ư�����λ��Ҥ�ԤäƤ��롣�ȥ�ͥ��������ϡ��ͥ������������礭���������Ƕ�����ư������ɬ���������δ����Ӥ��Ƥ��롣 �ұ�������ѿ������ ����������������ɤȤ��äơ�Ƭ���ͻҤ䡢�ȿ嵡�ʥݥ�סˤα�ž���֤��İ�����������Ǥ���褦�ˤʤäƤ��롣�礭�ʥ�˥����ˤϡ��ͤ���Ƭ�ʼ����ˤθ��ߤ�ή����ͻҤ�Ǥ��Ф���Ƥ��롣���к�Ȥ�ī��Į�����ڤ���������ԤäƤ��äƤ��뤬���ä�¿�����ϡ�����Ϣ�������е���ȤäƼ������Ƥ��äƤ��롣�ޤ�������̤�Ĵ���ʤɤ������ǤǤ���褦�ˤʤäƤ��ơ��������夷�����ϡ���������ή����ޤʤ��褦�˥����Ȥ����夫��������ȥ����Ȥ�夲�ơ�����̤�Ĵ�����Ƥ��롣 �������ϰ�ο��ή�����ϡ�����ή���ȡ��⤤��ޤǥݥ�ץ��åפ���ή��ľ����ˡ��ȤäƤ��롣ϻ�䤬��ϩ�ʥѥ��ץ饤��ˤˤʤäƤ��롣�ݥ�פ��ξ㤹��ȡ�������ɽ������֥�����ʤ롣��ϩ���椬���ˤʤ�ʤ��褦�˻��ĤΥݥ�פϤ��Ĥ��Ư�Ǥ�����֤ˤ��Ƥ��롣������ˤʤ�ȡ�����˰콵�֤Ϥ����äƤ��ޤ����ɤ������ΤǤ����ʤ갵�Ϥ����ʤ��������Ȥ���⤫���뤷���佤�˻��֤������롣�夬�Фʤ��Ȥ����Ф��Ƥ���Ƥ����ȹ���γ�����˿������ʤ����ʤΤǡ���夷³���뤿�ᡢ�ݥ�פδ�����³���ʤ���Фʤ�ʤ������Τ褦�ʴ������������ޤäƤ����ǹԤäƤ��롣 ���̿��ϻ���Į¦�νи� ���� : ��ƣ���פ���ʺǾ�����ή���ϲ��ɶ������Ĺ�� ��� : ʿ��20ǯ7�� �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
��ɴ�ë�ν�ƻ�乽
������������������������������������������ƣ��Ϻ�������������Ƭ�� �ҽ�ƻ��ȯ���� ����ǯ�ο��Ĵ�����ˡ���ɴ�ë�δ��פν���ڤ��ܤ����äƤ���Τ��ԻĤ˻פäƤ���������Į�Գ�����嶿����ޤ�GPSĴ������̡���Ū���ٺ路����ƻ�Ǥ��뤳�Ȥ�ʬ���ä�����¬���������ޤ�30km���Ϥ�Ʊ���褦�ʹ�����������Ƥ��롣����ϡ���Ͻ������������Ѿ��ͤ���¼�����礬���路���乽�Ǥ��ꡢ�����Ĺ�ν�ƻ�Ȥ����롣 ��祤�����ʤ������� ����¼�����ܤ˳��������δꤤ����Ф����Τϸ�Ͻ5ǯ��1692�ˡ���6ǯ��1693�ˤ�����˵��Ĥ����ꡢ6��˹����幩������7ǯ��1694�ˤ�9��ˤϴ������Ƥ��롣�����Ƥ����ˡ������ͤ�����13,700ɶ��Ĺ��Ԥεܤ��鲼���Ƥ��롣��������30km���Ϥ��繩�����ä���ǯ������̤ǽ����櫓���ʤ������祤�����ʤ��ä��� ��ƻ�������������ˡʻ䴶�ˡ� ������Ϥ�Ϥ�ɽ�����Ǥ��ä����Ȥ�ʬ���ä�����¼�ϡ��������羱������Ȥˡ������̤��褦�ˤʤä��Τǡ���Ƭ�κ��ۤ佮���ߤ���Ƥ����Ϥγ��ݤʤɤ�Ǥ���������ݤ��ä�����Ф��Ƥ��롣���줬���ܤ�����Ĥ�������ǯ���θ�Ͻ��ǯ��1692�ˤ�����Τ��ȡ�����ˤ������ʬ�ι����Ϥ��Ǥ˽���ꡢ�����̤��褦�ˤʤäƤ������Ȥ����������롣 ����¼�ϡ����Ԥ��������ν�ƻ��������Υ��ͥ���ȳ��Ұ���ɤδ�ʼ�ҡʤޤؤ��ˤȤ���ͥ���ʵ��ѼԤ�ƤӴƤ��뤬��������������̤�����Ͻ7ǯ��1694�ˤΤ��褽10ǯ�����ˤʤ롣�����˳��﹩���β��ݤ�Ĵ���������Τ������� �������ơ����4ǯ��1687�ˡ�51�ͤλ�������¼�����礬���ष�Ƥ��롣���μ㤵�ǰ��ष���ΤϤʤ����������餯��������ǽ�Ȥ������Ȥˤʤꡢ���Ѿ��ͤβȶȤ�©�Ҥ�Ǥ�����ܿͤϤ��褤���ܳ�Ū�˳��﹩���˼���ȤߤϤ�����Ȥ��̣���Ƥ���ΤǤϤʤ����� ����ǯ�θ�Ͻ��ǯ�ˤϡ������Ĥ��齮�繩��ܽ������Ƥ��롣����Ⳬ�̤���ޡ�ϻǯ�����Τ��ȡ������ΰ٤ν�����Ϥ�ΤǤϤʤ����� �������餯�������ͤ������Τ�ȡ��ͼ��Ȥ��⡹�˴ؤ���γ����崱�ˤ⺬����ή�κ��������ή�˸���������������˿ʤ�Ƥ����Τ��Ȼפ��롣�����ơ��Ǿ�ή���ι����Ĥ����ܴۤ����ξ��֤˶�Ť����Ȥ����ǡ����������ꤤ��Ф����ΤǤϤʤ�������������γ���ʤ��ǯ������ǽ�ʬ��줿�������� �������ϡ�ʿ��ʽ���˷���ΤǤϤʤ�����ˤ��뼫���ο����ˤ�뿼�ߤޤ��Ҥ���褦�ˤ����������ؤ��عԤ��ƽФ�ĥ�äƤ�����פ�դ��Ƥޤä����ˤ��Ƥ��ä����դ��Τˤϡ�Ĺ����1m�̡�������10cm�̡��Ť���50kg�̤��褬���ä�Ŵ�Τ����ޤ��4��5m�ι⤵�Τ䤰�餫����Ȥ���������ϡ�������ȿ���δ��դ����˲��Ϥ����롣 ��������ϡ���������ξ�����ä��Ȥ��롣�ƤǴ�������ȸ��ߤ�20��������Ȥ���Ƥ��뤬�������������ϰ���ư쾣���١����ߤ�������������������ߤȤ��Ƿ��������ɴ���Ȥ���ɴ���ߤγۤˤʤ롣30km��֤��繩���⽼ʬ��ǽ���ä��Ȥ��ʤ����롣 �Ҵ��Ԥ�����ʸ��Ĵ���� ��ī��Į�������֤ϡ���Ͻ5ǯ������ˤϹ����Ͻ���ꡢ���α���Ϥ��ä��Ȼפ��롣�����Ϥ��Ǥ����夭��κǾ�ή�������ä�����ī��Į��֤����夭��Ȥ��Ƥ�Į�¤ߤ����¤��Ϥ�����ȸ����롣�ؤ��������ĤäƤ��ʤ��������������λ����Ǥ⤦���ٸ�ʸ������Ĵ��ľ�����ߤ����� ��� : ʿ��20ǯ7�� ��ƣ����Ϻ�ʤ��Ȥ����������˻� ������ض������´�ȸ塢���£���ǯ�ʣ���������������������ع���͡��Ǥ������Ĺ��̳��롣�Ǿ����Ϥο��Ĵ����Ʊ���ʳ����ǻ�Ƴ���졢ʿ����ǯ�ʣ��������ˤ������ǯ����ܡ��Ȥ�ή�����ʤ����������Ķ���Ĵ����»ܡ����ߤϹ��ڸ��̾ʺǾ�����ή��Ѱ���Ѱ����������Ķ����ɥХ������ʤɤγƼ�Ѱ����ͤƤ��롣����¿���� ���̿������������ν�ƻ�乽 ����ƻ������������ �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
��ɴ�ë�ο��������
������������������������������������ƣ��Ϻ�������������Ƭ�� �Ҹ�ɴ�ë�ϺǾ���ο�¡���� ���Ǿ���ˤϡ���������5���ꤢ�ꡢ�ͤ������������DZ��줿���������Ƥ��ޤ����ʤ��Ǥ�ָ�ɴ�ë�פϡ��Ǿ������ζ�ë�������������Ǥ���5�������ǡ��Ǥ��礭�������ϡ������Ϥ���ĤΤǡ���ϺǾ���ο�¡���ȹͤ��Ƥ��ޤ�����ɴ�ë���ʤ���С����Τ褦�ʺǾ���ο���ϰݻ��Ǥ��ޤ��� �Ҹ�ɴ�ë�ο�������Τ����ߡ� ����ɴ�ë�ˤϡ����Ȥ�Ω�Ľ꤬��������Τǡ�������������˸���Ū������̤����Ƥ��ޤ�������ϡ�������λ��Ǥ�ʬ����Ϥ����ޤ��Ƥ����Τǡ��������Ǥ���ץ�ȥ�����������ˤ�����ޤǡ����������ʪ����ȯ�˳�ư���������¤Ȥ��ƿ��٤Ƥ���뤫��Ǥ��� �Ҹ�ɴ�ë�ο�Τ��줤���� ��β���������͡˺Ǿ���ο���ǰ���¿���ޤޤ��Τϡ���ή����β���ۻ�����ή���β��������Ǥ���ή����ȼ���ͤϲ�����ޤ�������ɴ�ë�ǤϤ��ʤ겼����ޤ����ڡ��ϡ��ϡ����������������Ѥ��ޤ��� �����١���������ٷפ�¬��ޤ����������Ϥ������ۻԤ��������ˤ����ơ����꤬�ԡ����ˤʤ�ޤ�����Ĺ����������ȴ��ᤵ�졢����˸�ɴ�ë���������ն�ˤ�����������ä˲�����ޤ�����ή�DZ��줿�夬�����˴��ᤵ�졢©���֤��ơ������ܤˤ⤭�줤�����������Τ���ɴ�ë�Ȥ����ޤ��� ��TOCĴ���˱����dz�䤷�ƽФ������ú�Ǥ��̤��ֳ�����¬�ꤹ��Ĵ���Ǥ����������Ϥβ�ή�����Ķ���˱�趶�ն�DZ��줬�ԡ�����ã������ɴ�ë���������Τ�����ˤ����ư��ֲ�����ޤ��� ��CODĴ�������ʤˤ��Ĵ���Ǥ�����Ϥꡢ��ɴ�ë�θ�ɴ����������Τ�����Ǻ�����ͤˤʤ�ޤ���������Ǥ��ɤ��ʤäƤ��ޤ�����ή���ǿ������Ȥ��Ƹ�ɴ�ë���ɤäƤ���Τ�ʬ����ޤ��� �ʲ��40ǯ�֤ο���ˤɤξ���1960��70ǯ��˹��ٷк���Ĺ�Ǥ�������������ޤ��������θ塢�����ӿ�ε�����ˡŪ�ˤ�������졢1980ǯ�������Ȳ���ƻ����ڤ�������ϲ�������Ƥ��Ƥ��ޤ����Ǿ���β��40ǯ�֤�COD�ǡ�����ή��˱�趶����ή������������ή�Ͼ��ⶶ��3�ݥ���Ȥ���Ӥ���ȡ��������Ͼ�˺Ǥ⤤���ͤˤʤäƤ��ޤ��� �Ҹ�ɴ�ë�ο�ϩ�λ��ĸ��̡� �������ͤθ��Ѿ�����¼�����礬���路����ɴ�ë�ˤϡ����פ����Ȥ�ȱ���Ǥ����ϩ���繾Į�ˤ�����³���Ƥ��ޤ������ߡ���ϩ��¬�̤��Ƥ��ޤ�������ϩ����10��20m��������2��3m�⤢��ޤ��������Τ�Τ������ä���Τ��ϡ��ޤ�ʬ����ޤ��� ����ϡ����ο��������ˤ�ڤֿ�ϩ�����뤳�Ȥ�����������˽��פ�Ư���Ƥ���ȹͤ��Ƥ��ޤ�������ϡ������⿼�ߤ�Ʊ������¸�ߤ���Τǡ�������ʪ�ˤȤäƹ��Թ������Ǥ���¿�ͤ���������ΤǤ�����ϩ���椬�ɤ��ʤäƤ��뤫�ϡ�������楫���ʤɤ�ȤäƳ�ǧ����ͽ��Ǥ������Ƥ����餫�ˤ��Ƥ��������餷����ɴ�ë������˥��ԡ��뤷�����ȻפäƤ��ޤ�����ɴ�ë�Ϥޤ���ī��Į�����Ȥ����ޤ��� ��� : ʿ��18ǯ ��ƣ����Ϻ�ʤ��Ȥ����������˻� ������ض������´�ȸ塢���£���ǯ�ʣ���������������������ع���͡��Ǥ������Ĺ��̳��롣�Ǿ����Ϥο��Ĵ����Ʊ���ʳ����ǻ�Ƴ���졢ʿ����ǯ�ʣ��������ˤ������ǯ����ܡ��Ȥ�ή�����ʤ����������Ķ���Ĵ����»ܡ����ߤϹ��ڸ��̾ʺǾ�����ή��Ѱ���Ѱ����������Ķ����ɥХ������ʤɤγƼ�Ѱ����ͤƤ��롣����¿���� �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
��ī��ĮĹ�������Ϣ����Ĵ������ȯ�Ԥ������ä���ī��Į�����ǡ٤ˤ��ȡ�ī��Į�ˤϾ�Ƭ���������帢�������꤬����𤢤롣���ͻ��������˺�ä���Τ�¿����
�����ʿ���ˤ�������帢���ϡ������佮���˴ط�����ͤ����䤽�β�²�����Ĥ��Ƥ������Ǿ���äơ����ܳ����������ϩ���̤äƹ��ͤ˹Ԥ��ˤ����˹Ԥ��ˤ⤽�����̤���פʷв����ʤΤǡ������ҳ����뤿�����������ޤ�ƿ��Ĥ��Ƥ��������λŻ���ͤ���������������ڵ�Ȥ����롣������ ���� : �������˻� (�������̾������) ʿ��18ǯ �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
|
���Ǿ���ι��֡������֤ϸ�ɴ�ë�ȸƤФ졢��ή����꤬¿����ˡ��Τ϶�ë������ξԳ�������Į�ˤ˹���Ȥ�����;����ȥ�ˤ��줬���ꡢ���α��Ҥ��Ǥ��ʤ��ä������ä������ͤ����Ƥ�ʪ����ͳ�͢���ϻ��ۤ�����졢���Τ�ǯ���Ƥ�����ƽ����ëƽ�ۤ���ʡ��ޤ��ϤDZ��ӡ�����������Dz��ꡢ����β����ǹ��ͤޤDZ�����Τǡ����Ѥ���������ۤ����ˤߤ����ä���
����Ͻ����ɴǯ���ˤκ��������ͤθ��Ѿ�����¼������ϡ����ι����Ϥ���Ȥ����ɴ�ë�����魯��С��٤����⤫���������Ǽ��ĤޤDz������Ȥ��Ǥ���������¼�ˤ�곫ȯ����Ƥ������ܳ��������ϩ�˷�ӤĤ���С���ϩ�ϲ��ء������ⳤ������Ĺ���ʤ뤬�����ư����˲��ˤߤ�ʤ����ͤޤDZ��٤�ȹͤ����� ����¼���ܶȤ����������ä������������̤˳���λ���Ȥ��������ڼ¶ȲȤ����ꡢ���α���Ǵ�ʼ�ҤȤ���ͥ���ʼ��������������̩��Ĵ�������塢���繩�������Ĥ��顢������ϱ۸����Ļ��¼����ƤӴƽ��������ͤ�������ܤε��Ĥ����դ�����Ͻϻǯ�ʰ�ϻ�廰�˳���˼��ݤ��ä��� �����ι�ˡ�ϡ����ή�������夬�餻����ξ��ʲ���Фƴ��Ƥ�������ݤ��ƴ���ä��ꡢ���פξ�˹⤤Ϧ����ơ��Ť�Ŵ��������פ����ꡢ�������ߤ�夲����Ȥ��֤ɤ��ͤ���ˡ�פ��Ѥ����ꤷ���������ϰ�ǯ������������������ξ�ʸ��ߤǰ켷���ˤε�����ꤸ���⼷ǯ���̡���ʼ�����ȸƤФ줿�����������Ƥ��Ѥ�ǡ���ɴ�ë����Τ褦�˲�����Ĥޤ����������ΤǤ��롣���ξ岼���������⤿�餷�����äϤϤ����Τ줺���ޤ��˿屿�γ�̿�Ȥ������Τ��ä��� ���������ΤΤ��Ȥ椨�����������������ΰ����ˤϿ�ʩ�βø�뤳�Ȥ����ǡ���褤�˿�ʩ��Ʋ���κƷ����̸�����Ǽ�ʤɤΰ������꤬�Ԥ�줿���ޤ������ν������³���뤿�ᡢ�Գ��Ⱥ����ˤ����ز����֤������������������ˤ�������������֤��ơ�����Ȥ��夲��˼�ƻ����������������Ǩ���Ƥν����ʤɤ����� ����ɴ�ë��ī��Į��ˤ����������ɤ�������������ʤɤ���꤬¿�����ꡢ���Ф����������ˤ�����������Ǩ���Ƥ�����Ȥ���������ˤ���褤��ɴ������ޤ졢�����Ȥ����Ƥ�ʧ���������ߤ�Ĥ��������ǡ֤��֤����ߡפȸ���줿�� �������������ν����ϸ�������ä���¼�����ͱ��Ĥ��Ѥ�ä��������Ƹ�ǯ��Φ����̤�ȯã�Ǥ������ܤ������˼�ƻ�⺣�Ǥ��ؤɻѤ�ä������ʤ��ʤä��� ���� : ����(������)��ʿ��18ǯ �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
��ߤϥ����奢��
�����������������������������������á��к���ϻ�ʼ����̿��ȡ� ���Ǿ����ɴ�ë����ߤ��Ѳ����礭�������Ȥ����롣�������줿�ꤹ��������ϡ��ѥ����˥�Ū�ʿ�ʪ��¿�������䥭���Ϥ���Ȥ��ƿ�˶������ڤ�¿�������ڤ�빽���롣�ڤ�Ω�ä���ߤǤϡ������ʤꤹ����Ȼ٤����ʤ��ʤäƤ��ޤ��Τǵ��ڤȤޤǤϤ����ʤ���������Ǥ������ڤϤ��äѤ����롣 ���ʤˤ�ꡢ�ͤ�����ʤ��Τǡ�����ʪ������ƨ����ȤʤäƤ��ơ������奢��Ȥ��ƤȤƤ�Ťʾ��Ȥ����롣 ����������֤��Ť��˸�ɴ�ë�ä��Ȥ��ˤϡ��ĥ����䥴����������ޥ��ߤʤɤ������������ä˥��������ϡ��;�Ⱦ���餤�������Фߤ���ɴ���ʾ�ФƤ��ƶä����줿����ޥ��ߤϡ�������ȥ�ˣ����ϽФƤ���������Ļ�ϡ������˹Ԥ��ʤ��Ȥʤ��ʤ������ʤ��������Ū��ƴ���Ļ�ȤʤäƤ��롣Į����Ǥ���ʤ˸�����ΤϤȤƤ����������ȡ�Ļ��ѻ�����ͤ����ˤȤäƤϤȤƤ⤪�⤷�������ǤϤʤ����� ���� : �к���Ϥ��� (Ω��)����� : ʿ��19ǯ �кꡡ���ϡʤ��ͤ����������ޡ˻� ���£���ǯ�ʣ��������˵������ޤ졣ī��ĮΩ�ں߽��� �����Ӥ��鸶���Ӥޤ���������ο��Ӥ�ե�����ɤȤ��뼫���̿��ȡ�������ī��Ϣ����ϼ���ư���濴�Ȥ����Ҷ��Τ���Ρ֤����䤷�����������פ�ܥ��ƥ����ȤȤ�˹ԤäƤ��롣����ˡ֤Ϥ�ˤ�ס�ʡ���۽�Ź�ˡ��֤ϤäѤ���ʤ��衢�ܤ�������סʥ��ꥹ�ۡˤʤ�¿���� �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
���ʤ����������Ĥ��
���������������������������������������μ̿��ȡ�ʿ����ͺ�� �����������������������������������ʳ�����ҷʴѵ��ѥ�����ɽ������� �������������������������������������������� ��ʸ�����ä��Ƥ��ޤ���ΤŤ���� ����������߷ײ�Ҥ�10ǯ���߷פ�ؤ�����Ϥ���ϼ�����ä���������˥���ԥ塼���λ���ˤʤꡢ������¤������פʤ�Ρפ����Ū���߷פ������ˤʤä�������������������Ǻ�äƤϤ���Į��ʸ�����ä��Ƥ��ޤ��ΤǤϤʤ����Ȼפä���34�Фλ���1977�ˤ���Ω���ȼ̿�����˴������붶�Υ��������ɷʴ��߷פβ�Ҥ�������������Ż뤹�뤳�Ȥ��������ˤʤ�ΤǤϤȹͤ����� �����μ̿���Ϥ�Τϡ��ֵ������칻��Ω̿����ؤγ���ã�ˤ��줤�ʼ̿��Ƕ��������ä����顣����ȡ��Ť����������餷���Ȼפä�������ζ��ϡ��礭�������������������Ѥ������ʤɡ����ˤʤ�ʤ���ä����������̣���ʤ�����¿���� �����ܰ쿴�ʤ���ǥ�������������� ���������⡢���ʤ����������ʪ��ꤷ�ʤ������������Τ�̣���ʤ���ΤˤʤäƤ��ޤ������Ϥοͤ����ʤ��බ�������� �������ܤζ������ڰ仺�٤Ȥ���ʸ�������뤬��������˶���1000���̡��̿��ǺܤΤۤȤ�ɤʤ�����ɽ�ǾҲ𤵤�Ƥ��롣�������8��9��ϸ��Ƥ������������ߤ����������餷�����˽в�Τ�10���˰�Ĥ��ä����ɤ��ۤ����������ϲ��٤Ǥ���Ƽ̿��ꤿ���ʤ붶�ΰ�ġ���ԡ��Ȥ������ʤ붶�������ʤ��බ�Ȥ����롣�������ϳ�ʢ�����������Ǥ����ܰ�ο��ʤ��බ���ȻפäƤ��롣 ���������������餷������ͳ�� ����������Ǥϡ����������繾Į�κǾ嶶�����Ϲ��Ԥβ�ε���λ��Ĥ����������餷����2002ǯ4���ī���Τ������������餻�Ƥ��������������������ʤ������餷�����Ȥ����ȡ��������ζ����ʱ߸̤�ξ��ü��������ȱ߸̤�ĺ���Ȥι⤵�ˤ������礭���������3�ܤΥ�������3�繽�ˤΤ��줤�ʱ߸̤ˤʤäƤ��롣�ޤ�����Ȼ�����ܹ�����߸̤ǷҤ���Ƥ��롣�����߸̤ǥǥ��������줵��Ƥ��롣�Ǿ嶶�Τ褦�˥�������3�´�Ϣ³�ˤʤ�ȹ⤵���㤯�ʤ롣�������Τۤ����������ζ�������ä��ꤷ�Ƥ��롣 ���ڤ�ڤ���구�����˶ʤ���ȡ�ξü���Ϥ����������˹Ť��ʤ롣���������ε���⡢ξ�ߤȤ��ǤǤ��Ƥ��뤫�饢�������Ǥ��롣���Τ���꤬���ή�����ʤ�Τǡ��ξ֤Ρָ����ᤷ�Ǿ���פζ�ϡ�����ǤϤʤ��Ȼפ����������ˤ�����礭���ͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��뤫�顢ή����ᤤ�Ȥ����˶��Ӥ�Ω�Ƥ����ʤ��Ƥ����������ϳؤ伫���ˤ��ä����ˤʤäƤ��롣��Ĥα߸̤Ǥ���ʾ夭�줤�ʥ���ȥ������������ܤˤϤۤȤ�ɤʤ��� �� �һפ�����Τ����Τ���Ѥ�Į�Ť����� �����������ݤ���βȡʺ��ݲȽ���ˤγ��Ѥ��Ƥ��ä���¾�ˤ⤢��Ȼפ�����������������ħ�����ȤǤ��롣���Τ褦�ʺ��βȤ�¾�Τ�Ĥ��Ƥ�����Ȥ���Į�θؤ�ˤʤ�ΤǤϤʤ����� �����ߤϰ¤��ƾ��פʺ��������äѤ��в�äƤ��뤬�������������ϡ�Į�ηʴ������Τ���ʤǤ���������κ�����Ʊ����Τǡס˽������Ф��Ƥ����ƻĤ����ߤ����� �����ܤ�ʸ��������˻Ĥ��Τ����Ѥʶ�ϫ�����뤳�ȡ���ϵ������ޤ������1200ǯ�֤���ˤ����äƼ��Ѥ���Ƥ��������ΤϿ������Τ��������Ѥ����Ϥ����롣�ä˺��λ���Ϥɤ��餫�Ȥ����ȿ������ۤ������ޤ�Ƥ��뤬�������ǤϤʤ��������˻פ����줬���뤳�Ȥˤ�ä����ܤ�ʸ���������ΤǤϤʤ������äˡ����ϤΡָ��աסֿ���ʪ�סָ����Ρפ����ڤˤǤ����鿴�ʤ���Į������夬�äƤ����Ȼפ��� ���� : ʿ�ͺ�ʤҤ�Ρ��Ƥ뤪�˻� �ץ��ե����� 1943ǯ���ԻԤ����ޤ�롣1968ǯΩ̿�������������´�ȡ���Ҷ�̳��Фơ�1977ǯ��������ҷʴѵ��ѥ�����ɽ�������Ĺ��1992ǯ��2006ǯΩ̿��������йֻա�1988ǯ���й��ȹ�������ع����йֻա����ܼ̿������������ڳز�ե��������������Υ�ֲ��������˼̿��������ܤ�̾�ʡ����١ض��˹Ԥ����������������ܤζ����٤����롣 ���̿��ϡض��˹Ԥ����������������ܤζ����٤��ȴ�褷�ޤ����� �ʴѵ��ѥ������������ȡ�PC�� �������������ܤζ� �������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë�� ����ɴ�ë��̥�� ����ɴ�ë���ꥢ |
�����Ϥ�������CD���Ϥ��������ΰ콵�֤ۤ����λ����ˡ�ī��Į����������ͳ��˧�λ���Į��ͭ�֥��롼�סֿ��β�פ�ϯ�ɤ�CD�˼���Ȥ����������ФƤ��ꡢ��®ī��Į�����ߥ塼��������̤��Ƽ����Τ��ä���
�����˧�ˤĤ��Ƥϡ��ؤ�ޤ����������ή��-2006/��ޤ����λ���¸��-�٤ǡ�����ľ�һ�ˤ��Ҳ�ʸ���̤��ƤϤ�����Τä�������ϻǯ��1917�����ޤ�γ��˧�Ͻ�ϻ�ФǾ��ع������ʤ�´�Ȥ���������ɤν��߹���Ź���Ȥʤ롣�����ܳФ�ΤϤ��κ����������θ����л�Ϻ�˻ջ����ܳ�Ū�˻���˼���Ȥߡ�����Ū�˺��ʤ�ȯɽ���롣���ɤ�����°���Ƚ�ο����Ȥ���Ư��������¡��ˤ���ʿ������Τ��桢���½�Ȭǯ��1943����ϻ�Фμ㤵�����ޤ����� ������CD�Ȥ������˽Ф��줿�Τϡ�����25�Фλ���ȯ�����줿��ͣ��λ������̤�¼��٤�ϯ�ɡ�Į�Ǹ�ǯ���˳��Ť��줿�ֳ��˧����ݥ��塼��פλ��üԤ��椫����ͤ����ޤ�ֽ�˧�λ����ɤ��פ�������ֿ��β�פ�̾�Ť�������ν��ޤ����κ��ʤ��ɤ߲�ư��ŤͤƤ����ȤΤ��ȡ�CD�ˤϹ�¼����Ϻ�����줿��ʸ��34�Ԥκ��ʤ��٤Ƥ�ܤ����֥å���åȤ�ź�����Ƥ��롣ϯ�ɤϡ�11�ͤβ�������줾��3��4�Ԥ�ô�����Ƥ��뤬����ǯ���Υ��С��Ͻ�˧������ˤ�������ǯ�ǡ����ͤ�˴���ʤä��Ȥ��Ȥۤ�Ʊ���Ȥ����Τ��Τ褦�˻פ��롣 ��CD����Ϥ����ή��Ƥ���Τϡ��ɤ������������ۤ��ˤĤĤޤ�����ǥ������ŻҲ��ڤˤ�����ζʤ�ī��Ϣ���ο�������������Τ褦�������沿�٤��������������ΤΥơ��ޡ��ߥ塼���å��Ȥ��ä��Ȥ����� ����¼����Ϻ�ν�ʸ��³���ƻ���ϯ�ɤ��Ϥ��ޤ롣�դ뤵�Ȥ����ʤ��ʡ��������Ϻ��ˤ�������¼���ͻҡ����θζ��ؤλ��顢ϫƯ�ˤ��������Ԥλ�������������ؤ�ʣ���ʴ���-���͡��ʥơ��ޤκ��ʤ���ø���ȡ��ɤ�³�����롣�ɥ�ޥƥ��å���Ÿ����ѥե����ޥ�Ū��ɽ���ϤۤȤ�ɤʤ����������������ޤ����Ƥ���褦�˻פ��롣����ϯ�ɤΥץ������뤤�ϥ��ߡ��ץ�Ū�ʿͤ��ɤ�С����äȰ�ä��Һ��ʡӤ˻ž夬�ä��Ǥ�������Ψľ�˸��碌�Ƥ�館�С�������ƾ���ϯ�ɡǤȤϤ����ʤ���Τ⤢�롣�ޤ�����������������ȡǤ�ƥ���ȥ͡������Ǥʤɤˤ�����äơ���ʸ��Ĥ��褦�Ȼפ��Ф�����Ǥ�Ĥ��뤳�ȤϤǤ��뤫�⤷��ʤ�����������ʤ��ȤϤ����Ǥ������ʤ��Ȥ��Ȼפ鷺�ˤ����ʤ����ɤ�ϡ���Ⱦ�Ĥʿ��ʤɤĤ����ˡ����줾��λ��Τ��Ȥа�ĤҤȤĤ�Ƥ��ͤ��ˡ����Ȥ�����褦���ɤ�Ǥ��롣�ष������Τ�İ����ϼ�ʬ�ʤ�ν�˧������������뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ��äƤ⤤���� ��������Į������줿���Ѥʰ����CD���顢���˧�Ϥ錄���ʤ����ˤ���ʪ�פȤ�������ο͡���Ǯ���ۤ����ޤä���������äƤ��ơ��������Ǵ���Ʊ���˻�������100ǯ�ˤ�����2017ǯ�Ρ��������̤�¼��������Ǥν��Ǥ�����礷�����������Ǥ��롣 ���Ǹ��û�����ʤ�դ��ľҲ𤷤褦�� ���α� ���κ��Τۤ����Ӥ� ���ʿˤǤĤĤ��� �����ܤä����̤����� ���� ��������ʤ��餷�ˤˤʤ�Ƥ� �ݤष��̵�����Ф� ���δ��ʤͤ����ˤ��褦�� �Բؤ�ο���� ��餰���Τ����� ʹ���ʤ��Ǥ��� �ѤҤΤޤ֤��� ɴ��ζ⡡���ˤʤ��� ����ŷ��ؤ��� ���դδ������ꤢ�դƤ� ���֤Ȥ�����ȴ���� ���� �ߤΤꤹ�뽩���ΤäƤ��� ��E��14��١� E���β� 2009.10ȯ�ԡˤ��ȴ�� |
|
���ξ��ʻ�δ�ơʻ�����ʹ�ˤ����˧������ɳ���ä����Ȥʤ�ޤ�����
���˧�λ������������̱�����˿ʹ֤��ᰥ�� ����/���ʸ��� ����ˤǻ���õ���Ƥ����飱�����������������ФƤ��������˧�Ρ��̤�¼��٤Ǥ��롣����16ǯ��̹���ҡ�����ˤ���ФƤ��롣���1��70���� �������ϳΤ��ǤϤʤ�����������ǯ���˻䤬��������̱���ˡ٤�ɮ��˸��ܲ��Ǹ��Ĥ�����Τ餷����������ΰ��פ���夲����ɾ���������ǡ������Ϥ�ץ��ե����狼��̤ޤз�����������ɤ��λ�����������ˤ���ФƤ����Τϡ����˧��̾�Ȥ���λ��Ȥ����ΤޤޤǤϾä��Ƥ��ޤ������Ȥ�ŷ�ηٹ�˻פ��ƻ�ϵ�̳���ˤĤ�ư�����줿�������Ƥ��Υơ��ޤǡ�ľ���פ˰�ʸ���𤷡������ˡ֤�¸������������Хץ��ե�������ߤ����פȽ�ź������ �� ��������ܻ��Խ����ʻ�����ʹ�ˤ������ä����äơ�������ī��Į�νпȤǡ�����18ǯ�����Ф�¾�����Ƥ���ȤΤ��ȤǤ��ä����֤��λ���������Ĥ������ޤ����Τ��פȤλפ�������ζ����Ǥä��� �����̤�¼��٤�������¼�ζ��Ӥ���������Ԥ��ܤǤϤʤ�Υ���Ԥ�˾����Ǯ�������ǡ�¼�פ֤�Ф��Ƥ��롣�����⤢�λ���ˤ��äƱ���Υơ��ޤ���Ƥ����Τ��� ���������줿�Τ���ʿ��������ȯ��ǯ�Ǥ��ꡢ��ǯ�ϡֹĵ�����ϻɴǯ�פ����ˤ���Ի����ĤŤ��ֿ������ܡפ�ݿ᤹��ࡼ�ɤ����ޤ������������Ƥ����������������ܡפ���������ʤ餤���Τ餺����¼���Ϻ����郎�⤿�餹�ʹ֤��ᰥ���ʤ���Ȥʤ�С��Ȥδ������鴶���ʤ��ƤϤʤ�ʤ��ä������� ��������趨�Ϥλ�����Ȥˤʤ��¼����Ϻ�������λ����˽�ʸ��Ƥ��롣�ֺ���ˤ����̤��䳲�����롣�����ο�κҤ������롣ŷ������Τʤ��������롣��������̱���㤤���������դ�����פȤ����Ф��ǡ��㤯�����Ʋ������뤳�Ȥ����Ƹ��ޤ��Ԥ���Ǥ�פȤ�Ҥ٤Ƥ��롣���������աפ���Ȥ��ɤߤ��������Τ����տ�Ū�ˤܤ������Τ�����ԤˤϡֽƸ��ޤ����Ѷ�Ū�ʰռ��Ϥʤ��ä��Ϥ��Ǥ��롣 ���Ĥ��˰��Ѥ���ֱ��㤭���פˤϡֿ�ͧY���α���ؤ�פȥ��֥����ȥ뤬���롣 ������ ���ͤ�¦���� ����������ͤ� �����ä� ���Ȥۤ� ������ۤ� ��Ĺ���ΤۤȤ�� ��Ǥ̳�ˤĤ��� ����ž���� ���������Τ餺 ���������Ĥ�������⸫���� ���Ǥ��Ƥä��ޤ� ���ޤ���������� �����⤫�ؤĤ��褿 ��̵���Τ������������ޤ��� ��Ⱦ���˸���ʤ��� �����ޤ� ���ʤˤˤⱾ�ؤʤ� �����ϫ�� �����ϫ�� �� ���ۤ��˱����ơ��ޤˤ�����ʩ�֡ס��פ���व�����Фζ��������ͤ������ˤʤɤ����뤬�������λ�����̼�����ͤФʤ�ʤ��ä���̱��������¸�ؤλ����ȽŤʤäƤ��뤳�Ȥˡ���ϴ������ä������˧�ˤĤ��Ƥ��ܻ�Ρ��ܤζ��ڴۡץ�����Ǿ���������Ƥ������ʿ��7ǯ7��8���աˤ������ε���˰�ͤǤ�¿���ο͡������λ��ͤλ��ۤ˿���Ʋ�����Фȡ���äƤ�ޤʤ��� ��ʿ������ǯ�˻�����ʹ���̴�� ���ʸ���ʤޤĤʤ����������˥ץ��ե����� ���͡����å������ȡ�1930ǯʡ���������ޤ�롣Ȭ�����Ф���ض���8ǯ��1957ǯ�ʹ�ʸɮ���衣ʸ�ء�̱²�����ѡ������ʤɹ��ϰϤˤ錄��ɾ�����Τ�졢�Ȥ��˻Ҽ鱴����̱�������ꥷ�����奬�饹�θ���ԤȤ�����̾��������ʸ���ȿ��˻��ä�������������̱���ˡ���5�������ˤ����������ʸ�������̾ޤ�����롣�ƥ�ӡ��饸���б��¿�����ɥ�������Ȥ�����ˤ⤫����äƤ�������̣�γ����10���Ķ�����Ÿ��������ˤϡ����ܤλҼ鱴�١�ŷ�������١ػ���ؤΤ�����١إե����ĥ�����μ��١�Ϸ�����ʳʡ١ز��������ϩ�١ز�Ϸ�Υ�������١ض�ο��� ��ο����١ش�ư�νִ֡١إ��ޥ�ȥ�θ��ա٤ʤ�140�������롣2008ǯ�ס� |
�̤�¼��
�ʤ�������ޤ����Ԥ���� �������٤� ���դǽ�����ʤ餦�˽Ť�������Ԣ�ζ����ͤǤ��� ������ˡ������㤯���� ��������ŷ��ؤ��� ����ϡ������ޤ�������ϲ������Ю��ǤϤ���ޤ��� ��(�Ȥ�)�Ĥ�������(�ʤ��)���ԤĤƸ��������衡ŷ���դ��Ƥ뤫�� ��������������ʤ� �Ƥ⡡�Ҥ� ��ǯ������ү�ޤ����Ҥʤ��� ��������ʿ��Ĥγ���(����)��Ȥꡡ�˳�(����)���˽�(���)���ˡʤ����ˤؤ��Τ� �������ʤ��纬��(�Ҥ�)��Ǽ���ˤ��ޤդ�� ���줫��ݻ�����Ǹ�� �䱫�ߤ������ڤκ��ʤɤ��٤� �����֤ꡡ��줿����(�դ��֤�)�ˤϤ� ������(����)����ȱٶ���Ƥ��� ���Ϥʤ��Ǥ��졡�ˤι¡����ΰŤ��Ǥ��̤�ʤ����顽�� �������������Ϸ�Ҥ��Τ� �����ޤ��������ˤ��Ť��ޤꡡ��������⤻�����Ӥ줿 �����������ΤǤ��� �����äϡ���������Ť��Τ������Ĥ��Ԥ� ��(�դ�) �ʤ���ι���� �ۤ���Ω��ƻ����� �ŤؤĤ��Ԥ� ��ɤ����� �ɤĤȡ��������ߤ������(������)��٤ؤ� �䤭�Ĥ���줿������ ��餦�� �ͤӤ褦�� ���ޤ���ˡ���Τʤ��ŤؤĤ��Ԥ� ���Ƥ֤����� �������ؤ� �����ߤĤ�嫤�椹�֤Ĥ� ���ͤ��ФĤƤ�� �̤�¼���2�� �����٤��줽���ʻ�����¼��Ǥ��� �����ϲ��̲��Τ��˷���Τ��ƹԤä������ʡ��������� �����ǯ�餺���礭�ʤ�ʢ�������Ԥ���餦�� ���ڤ����ڤ�Ťͤ�̼���ü�������Ϻ���¼�Ǥ��� ���٤ϲ��ݤ�̼��������Τޤ֤���봤ޤ��������� ���㤬㮤äư��椬�Ĥ��Ω�Ĥ����� ����(�Ȥꤤ��)�Τʤ��� �Ԥ���������ʤǡ����ͤ��������ܤ��Ƥ�� ��������ã��Ĺ��������Ǥͤ��Ĥ��ʥ� ��������������㳤��Ӥ(����)�ؤ��ͤ��ǡ����Ĥ� �������ޤ��ޤ����������դ��Ȥơ��ɤ��ˤ�ʤ�ʤ��� �Խդޤ��ԤĤ��� ��ܤ����䡡���Ҷ��������̤� �Ҥ��भ�ˡ���Ԥ��Ф����������̥�� �������줬�������������� �������ؤ�ʤ������Ӥ�椯 ¼��θ��ʤ�ͼ��Ǥ��� ���¼�ǯ����������פ����峲�Ϻ���˺���� �褦�Ȥ��Ƥ�롢˺��ƤϤʤ�ʤ���¼�� �뿴�����Ĥ��뿴�����������½���ǯ�ա��� ���Ҥ������� ����-ͧ�ͣٷ��α���ؤ�- ���� �ͤ�¦���� ��������ͤ� ���Ĥ� �Ȥۤ� ����ۤ� Ĺ���ΤۤȤ�� Ǥ̳�ˤĤ��� ���ۤ��� �������Τ餺�� �������Ĥ�������⸫���� �Ǥ��Ƥä��ޡ� �ޤ��������Ԥ� ���⤫�ؤĤ��Ԥ� ̵���Τ������������ޤ��� Ⱦ���˸���ʤ��� ���ޤ� �ʤ�ˤⱾ�ؤʤ� ���ҩ�� ���ҩ�� �췿 �ʤ������ȡ��������������⤬�ġ����� ¿���γ�ɳ����٥Ʈ˹���椫�� ���ޤؤϡ�������ȸƤ�Ǥ��줿 ���ϡ�����ǹԤĤ��Ԥ� ���Ĥ����ޤؤξ��� ���ޤ����դ����졡�������ɤ��Ĥ���Τˤ���Ϥ�� �����عԤ�ʼ�⡡ ɴ��δ����ĸƤ���ɤ� ������ǡ������꤫�ؤ����ޤؤξ� ���ϡ�������˺���� ¿���γ�ɳ����٥Ʈ˹����� ��ĤȤɤ��Ĥ������ξ��餻�Ƥ����ޤ� ���¶�������ԤĤƤ��� ���ޤؤ�˺��ʤ��Ǥ��� �����ۤؤ����ĤƤ� �Ĥʤ��ĤƤ���Τ����� �ʤ�����Τ����� ����Ƥߤ� �ɤ��Ĥ⤳���Ĥ⡡���ꤿ������(���å����)�� ��Ω�ˤʤĤƤ椺�ꤢ�ռ��(�Ƥ���)�ɤ� �ˤ�ˤ�ФҤʤ�����ꤳ��ǽ��դʤ� ���ä�Ω�����ˤ��Ĥݤ�����Ф����Ǥʤ��� �����������줬ƻ���������-���ˤ��ͤ��տ�(���)�ο� �����ȱ��դ�Τ� ��Υ��ޥܥ����ؤ��ʤ�Ǥ��餦 �Ѥζߴ������ʤ�Ǥ��餦 ����(�Ȥʤ�)�Τġ��ޤ���ҩƯ�Ԥ�ߤ뤬���� ���ΤΥ��ơ��֥�ե����С��� ���ΤΤդ������м�(�����)�Ǥ��뤫�� �Ǥ��ܤ���ƻ�ϡ��֤������Τ� ��֤ʤ���ư���֤�����Τ� ��줭�Ĥ����ۼԤ餬���٤Ƥε����Ȥʤ� �������衡�������Ƥ��Ƥ椯��Τα�á����ʹ�� �����Ĥ������Ĥ������ؤθ�Ѥ����ĤƤ�� ���äƤ椯�������ϡ��ʤ������κз��˺�줿�� ��ƤĤ�������Τ�����ˤʤ������Ͽ������Ҷ��λ��� ����ʹ���ͤФʤ�̤Τ� �����ޤ����Ǥߤ� �ʤ�Ǥ��餦�ȡ�����Ƥߤ� ����Ƥ��Τ��ȷ���Ǥ��Ƥߤ� �� �������줫���Ĥ���ʪ�Τ䤦�� ����Ĥ������Ϥܤ�⡼�ȥ������� �ҤȤ顡���Τʤ����Ȥ���뿦��Ǥ��� ���κ��ο������Ĥʤ����餻�� ������ޤ���ʬ�εٷƤ�̵����������Ҥ��ԤĿ� Ĺ�������ȤΤ��Ȥεٷƥ٥뤬�Ĥ� ɬ��β��ۤ���©���뵡�������Ԥ����� �褴�줭�Ĥ���ǯ���ΤϤ����ʤ��̾Ф������ ����Ͻ��Ҥ��������ܤ������ �ޤ�Ǥ��κ������ȱ�Ĥ������Ĥޤ�ʤ�����˻� ���Ƥ�� �뤴���ˤ���Ĥ���̳����λ����ˤդ�� ���Ĥ����ܤ�������ʥ���åڤ�̵���� �����ɤҵͤ��줿���꤮��ΰ����ˤ�������Ǥ��� �뤬�����ơ�Ы��ʤ줿����ż֡��ϤĤȤ���϶ȤΡ��������������������������������������� �٥롡��Ĺ���䤱�˰�ĥ��Τ� �����˥�����Ȥ������Τ䤦�� ̣��ʤ����ݤ����ޤؤ�Τ䤦�ˤ��벶�� ���Ĥ�á���Ĥ���������ʤɤ⤢�� ���Ǥ����ƽ��Ҥ����Х��ȡ��ɥ�� ���줬���ᤪ�ả���⸤���Ǥ���ؤ� ��ĤѤ겶�ϰ����Ϥ��ʤ������ո��Ϥ��� �٥뤬�Ĥ롡�϶ȡ����˿��ޤ����������� ���äȥ����å������줿�����ϤΥ⡼���� �������Ӥơ�����եȤ����ס�������٥�Ȥ����ۤ��� ����Ρ������Ρ����줿�ڥå�������֤� ʹ�������������θŤӤ��⡼�ȥ�Τ��Ĥʤ������ �ʤ˸ΤΡ�������«��(����)��줿��Τ���ԥ�̤Ǥ��餦�� �����˧�������̤�¼��٤��ȴ�� �����ޤλ��� ���˧ |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum











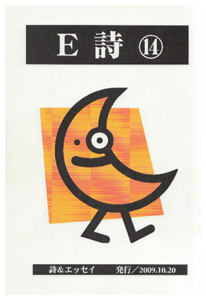







�Ǿ�����ȸ�ɴ�ë
���������������������������������������������˻�ʻ������̾��������
�Ҷ����塦��Ƭ�����ĤȽ�����
��ī��ĮĹ�������Ϣ����Ĵ����ȯ�Բ����ä���ī��Į�����ǡ٤ˤ��ȡ�ī��Į�ˤϾ�Ƭ���������帢�������꤬������22�𤢤롣���ͻ��������˺�ä���Τ�¿���������ʿ���ˤ�������帢���ϡ������佮���˴ط�����ͤ����䤽�β�²�����Ĥ��Ƥ������Ǿ���äơ����ܳ����������ϩ���̤äƹ��ͤ˹Ԥ��ˤ����˹Ԥ��ˤ⤽�����̤���פʷв����ʤΤǡ������ҳ����뤿�����������ޤ�ƿ��Ĥ��Ƥ��������λŻ���ͤ���������������ڵ�Ȥ����롣
�ҺǾ������Ÿ�����ÿ��ӡ�
����������®��ȯŸ�����Τϡ����ͻ�����������ܤˤ�����줵�졢�Ƕ��Ť����Ƥ�Ǽ���褦�ˤʤäƤ��顣��������䳤�����ɤ�ɤ�Ȥ���褦�ˤʤä���
���Ǿ������ȯ���礭�ʽ�����ϡ��Ǿ�����ˤ���ŷ�����Ϥ�����Ȼ��¼���ԡˤλ���곫�������դ����ˤ�ꡢ����������Ĥޤ��̤��褦�ˤʤä���
������ǯ��δ�ʸǯ�֤ˤϡ���¼���������ϩ��ȯ���������줬�礭�ʽ�����ˤʤä��Τϡ��������Ǿ���ϸ��μ��Ĥ��ä����顣����ϡ��Ǿ���ή��������жᤤ���ܤ����Ϥ��Ǥ����Ƕ�Ȥ��Ƥ��Ƥ����ܤޤDZ��Фʤ���Фʤ�ʤ��ä����ᡣ���Υ롼�Ȥ�Ǿ���Υ롼�Ȥ⤷�ä��ꤷ����Τ�ɬ�פ��ä���
�Ҹ�Ͻ����κǾ�����Ȥ��θ��
����Ͻ����ˡ��Ǿ�����������ͤλ��褬���ä�����ʸǯ�֤ޤǡ������ͤ��ֻ�������ʡ���30���Ф���äƤ���������������ʸ��ǯ��15���Ф˸��餵�졢����ʡ�縩ʬ���ʤ��ʤäƤ��ޤä�������ˤ�ꡢ����ޤǹ��ͤ��Ƥ�Ф����ϡ�ʡ���Φ�����ư������������ϩ�DZ���Ǥ����ΤǾ�����̤��褦�ˤ��ʤ���Фʤ�ʤ��ʤä����̤�褦�ˤ����Τ�ͭ̾����¼������γ�����ä�����¼�������ͤθ��Ѿ��͡������¿�ۤ����Ƹ�ɴ�ë�路����
����ɴ�ë�ˤϤ����餯������ޤǺ���Ѥν����Ϥ����Ϥ��äƤ⡢�����ޤǰ�Ӥ����̤뽮�Ϥʤ��ä�������Τ������Ǿ������̤��褦�ˤʤä���������礭�ʤ��ȡ����������Ǥʤ�����ή����ή�ޤ��̤ä��Τ����顢�Ǿ������ΤˤȤäƤ���ȯŸ���ä������θ�ɴ�ë��������̿���ä��ȸ����롣
���Ǿ��������麹����ϡ�������ʿͤ���ͭ���Ƥ�����ޤ�ư������������Τ����礹��ͤΤ��ȡ�����ǯ�֤���Ϥ��ޤ괲��ǯ�֤�60��70ǯ��³�������������ǽ�Ū�ˤϤ��ʤ�κ������������������ˤ�Ǥ�����ʤ��ʤꡢ���������ä�������������ܤ���ͤ�ξ����������������äƾ��ۤ�����
�����κ��������ͤǤϸ��������̾�����ˤ��ä�����ή�Ͼ����������ä������������Ϻ�������ϲ��äƹԤ��ʤ����������鲼ή�μ��ĤޤǤϤҤ餿�������ʿ�ġˤ��ä�������4ǯ�ε�Ͽ�Ǥϡ�����������100ɶ�Ѥߤ�12�ۡ�50ɶ�Ѥߤ�48�ۡ����碌��60�۰̤����������ή����ɴ�ë�Ȥ����롢Ĺ������ޤǾ�겼�ꤷ�Ƥ�����
�Ҹ�ɴ�ë�ν�����
��ī��Į�置��¼�������ֽ�δ����������ͤ��ä�����������������ʪ�μ�����ޤꡢ����ʾ�β�ʪ�μ�����ޤ�ʤɤƤ�����������¼�ʲ���ˤ��羱������Ĺ������Ȥϡ������ͤ�����������Ƥ��������ҡʿ��˸ۤ����˼�ƻ�δ������»ųݤ��δ����������ε߽Фˤ������������ơ�ʧ���Ƥ����äʤɤλŻ��Ƥ����������ͤΰ�����������ޤ�Ż��Ƥ�����
���� : �������˻�ʻ������̾��������
ʿ��18ǯ��2006�˺Ǿ����
�������ɥ֥å��ظ�ɴ�ë��
����ɴ�ë��̥��
����ɴ�ë���ꥢ