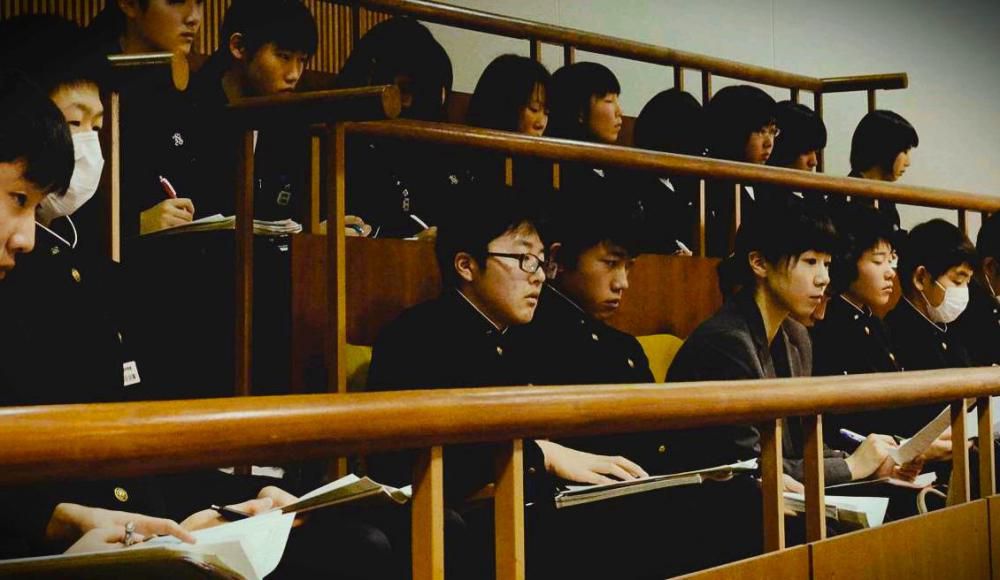旧総合花巻病院跡地の取得(譲渡)価格を審議する「花巻市財産評価審議会」(委員5人)が1日開かれ、その結果が5日付のHP上で公表された。それによると、対象面積は16,159,36㎡(花城町)で、価格は323,995千円。当該病院跡地については平成29(2017)年3月6日付で、「総合花巻病院の移転整備に関する協定」を締結。建物の解体や汚染土壌の入れ替えなど更地化が完了した時点で、双方で不動産鑑定評価を行う段取りになっていたが、価格交渉が難航し、延びのびになっていた。
「公益財団法人」である病院側の管理執行体制は10人以内で構成する「理事会」が担う。「市民に開かれた病院」を目指すとして、この中には医療福祉関係の有識者や行政関係者も含まれ、八重樫和彦副市長も理事のひとりに名を連ねている。病院側が移転先の旧厚生病院跡地を市側から取得した際の価格は3億8千万円。等価交換を求めたい病院側に対し、市側はなるべく低く抑えたいという位置関係にある。いわば、双方の利益が衝突する“利益相反”の中にあって、八重樫副市長はその双方を代表するという微妙に立場にある。
「…職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする」(第1条)―。「花巻市職員倫理規定」(平成25年5月訓令)はこう規定し、「この訓令に規定する総括倫理監督者の職務は、副市長が行うものとする」(第2条第5項)と定めている。八重樫副市長の「二足の草鞋(わらじ)」はただちに法令違反とは言えないものの、少なくとも倫理上の責任は問われなければなるまい。
一方、今回の「跡地」取得は新花巻図書館の立地問題にも微妙な影響を与えそうだ。所有権が市側に移転することによって、「市有財産」として正式に登録されることになるからである。現在、新図書館の立地候補地はJR花巻駅前と病院跡地に絞られており、この2か所についての「(事業費)比較調査業務」をコンサルタントに依頼。その結果が10月中旬には出る見込みになっている。
これに関して、注目されるのが立地に伴う用地費の取り扱いで、新規取得になる駅前のJR用地は1億3千万前後と見積もられている。一方、もうひとつの候補地である病院跡地は既存の市有財産として、今回の比較調査の対象から除外されるというのが一般的な見方だが、果たして…。さらに、調査を受注したコンサルタントがJR各社の鉄道事業などを請け負う独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」(JRTT鉄道・運輸機構、前身は鉄建公団)の有資格業者の名簿にリストアップされていることにも「果たして公平性を担保できるのか」という不信の声が聞かれる。
「≒1・3億」(駅前)VS「≒3・2億」(病院跡地)。どっちが安いか高いかといった単純な数字のマジックが示される可能性がないともいえない。「駅前は新規取得で、病院跡地は今回、正式な市有地になった。駅前に新たに土地を購入することは明らかに税金の二重払い(無駄使い)ではないのか」―。“立地”論争の原点に立ち返るチャンスかもしれない。
(写真は突然、視界が開けたように広がった病院跡地=2022年9月17日、花巻市花城町で)