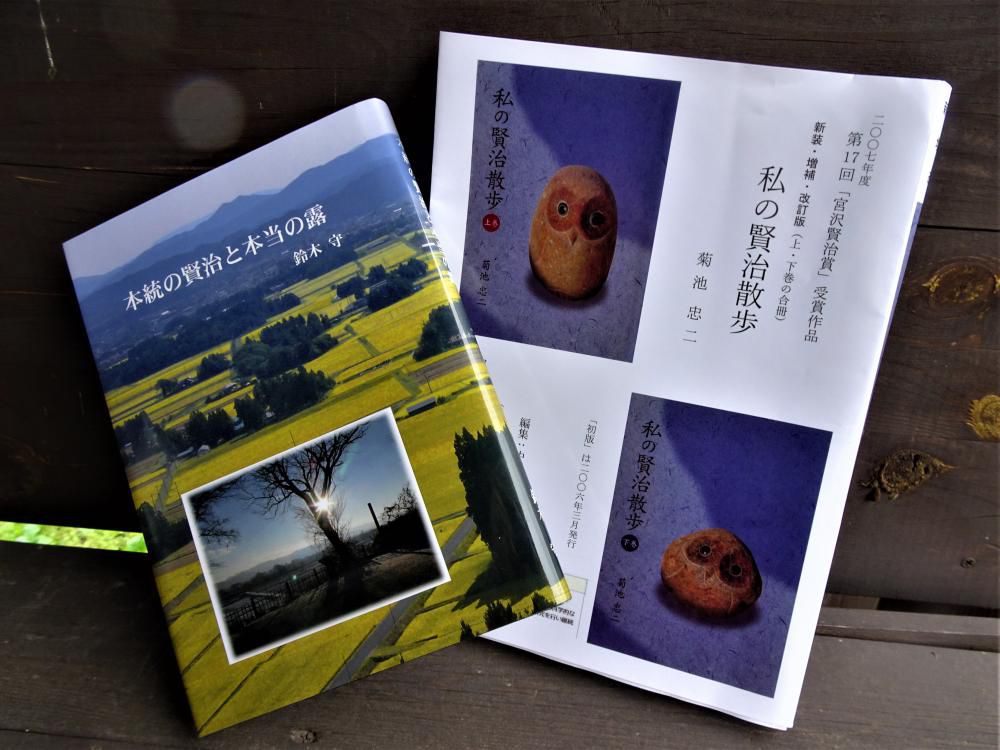「旅行代金/50万円前後」―。この数字を見たとたん、冥途(めいど)のみやげに最後の外国旅行を夢見ていた老残の気持ちはペちゃんとしぼんでしまった。花巻市は米国・ホットスプリング市との姉妹都市提携30周年を記念する市民ツア-への参加者(先着15人)を21日から7月31日までの間、募集するとHPで告知した。勢い込んで見た目に飛び込んできたのが冒頭の数字である。年金暮らしの身にはとても無理だとあきらめた。
ツア-の旅程は10月26日から11月1日までの5泊7日で、市の「公式訪問団」15人が同行するとあった。念のため、担当の国際交流室に問い合わせると、その内訳は市長や議長、教育長のほか国際交流に関わる民間人などで、当然のことながら自腹はゼロ(自己負担なし)。担当者が苦し紛れな表情で言った。「5年前の25周年の際の旅費は半分の25万円程度。今回は燃料費の高騰や円安などの影響で倍にはね上がってしまった。現場としては心苦しいが、30周年という節目でもあるし…」―。”公務出長”の是非をことさら、あげつらうつもりはない。私が困惑するのは「納税者」意識とかけ離れた“市民感覚”がまかり通っていることについてである。新花巻図書館をめぐる市民説明会でのやり取りを私は思い出していた。
「駅前への立地」か「病院跡地への立地」か―。“立地論争”に揺れる説明会の席上で、ある老人が絞り出すように発言した。「病院跡地はすでに市側で取得することが決まっている。駅前用地を新たに取得しようとするのは税金の二重払いになるのではないか。私たち市民は爪に火をともすような気持ちで、納税義務を果たしている。こうした下々の実態にも目を向けてほしい」―。現下の水光熱費など物価高の直撃を受けているのは、コロナ禍で苦しんだ一般市民その人たちである。
開会中の6月定例会で上田東一市長はそんな「声なき声」は歯牙(しが)にもかけないといった風情で、駅前立地に向けたJR交渉に舵を切った。この秋にはダラス観光も兼ねた訪問団の団長として海を渡る。「公務」費用は10人分で計500万円。「爪に火をともした」市民一人ひとりの汗の結晶がこの原資である。現役の新聞記者時代、私は浮世離れした“公費天国”(親方日の丸)を告発する取材班の一員に身を置いたことがある。あの時のあざましい光景のあれこれが目の前に去来する。
(写真は姉妹提携30周年を記念したオンライン懇談会のひとこま。今年1月15日、市長室で。前列左側が上田市長=花巻市のHPから)
《追記ー1》~「通りすがりの市民」を名乗る方から、さっそく、こんなコメントが…
市長の右の方、調べてみるとこんなことを話している方のようですね。
ユニオン建設~あちこちでJR東日本の仕事をしていることが書かれていますね。
《追記ー2》~「個人情報保護条例」を名乗る方からのコメント
まだあるでしったっけ?ツアーの申込みのリンク先が市のアドレスになっているんで、市が収集した個人情報を外部の業者に提供して良いのかなあ、と思い、市HPの個人情報の取り扱いについてを見たら、花巻市個人情報保護条例に沿って適切に管理する旨書かれていました。今も個人情報保護条例ってあるんでしたっけ?えらい人教えてください。