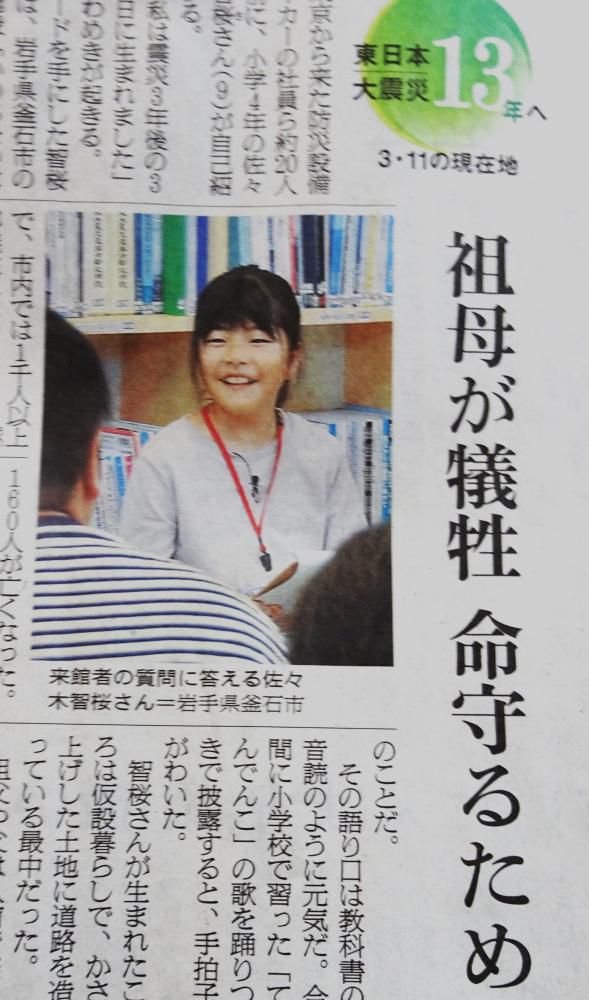「新花巻図書館/皆で考えたい」―。12月27日付岩手日報「論壇」に花巻市在住のパ-ト従業員、高橋明子さん(68)の投稿が掲載された。「ピンポ~ン」…勇気をふるって、一軒一軒のチャイムを押しながらの“図書館”論議の結果、賛成署名をしてくれた市民は500人以上。その奮戦記の一部を同紙から以下に転載させていただく(要旨)。高橋さんはクリスマスイブにおこなわれた署名活動にも参加し、粘り強い対話を重ねた(24日付当ブログ「“夢の図書館”をクリスマスの贈り物に」参照)。
そういえば、今宵は今年最後の「コールドムーン」(満月)。一年で一番高く昇るというお月さんが天上から”夢の図書館”の実現を願っているかのよう…。投稿の原文と冬の満月の表情はコメント欄から、どうぞ。
※
花巻市では今もなお、市と市民の間で新花巻図書館の立地場所をどこにするか、話し合いが続いています。市側は花巻駅前JR所有地(スポーツ用品店)を購入し、立体駐車場を建設する方向で考えているようですが、私は市の所有地があるにもかかわらず、あえて多額の税金を投入して土地を購入する必要があるのか?と疑問を感じ、市民の皆さんの声を知りたくて新花巻図書館を考える会の署名活動に参加し、約1カ月取り組みました。実際歩いてみると、皆さんきちんと意見を持って話してくれました。
その結果、「旧総合花巻病院跡地がいい」という意見に同意をいただき、524筆もの署名をいただきました。立地場所は「駅前がいい」という意見は片手ほど、「まだ決めかねている」という方もいましたが、多くの方は「市所有地で整備してある旧花巻病院跡地がよい」という意見でした。考える会の署名活動全体としては4730筆の貴重な署名が集まりました。この花巻市民一人一人の貴重な署名は会の代表から市長へお届けしました。この声をどう受け止めたのでしょうか?
10年ほど前から、新図書館建設については一進一退で長い間、市民活動を続けている皆さまがいます。新花巻図書館を考える会、まるごと市民会議、イーハトーブ(図書館)をつくる会の皆さんへの敬意を表します。図書館のことを含め、今後の花巻市のあり方を考えるきっかけにしてもらいたいとも考えています。宮沢賢治が考えていた自然とともに生きることを大事に、誰もが行きたくなる魅力ある新図書館を皆で考えていきたいです。
(写真は手作りの“うちわメッセージ”を掲げて、署名を呼びかける高橋さん=
12月24日午後、イトーヨーカド花巻店で)
《追記》~「記憶の継承」…ガザの悲劇と夕張のそれと…
イスラエル軍が今月中旬、パレスチナ自治区「ガザ地区」にあるハマスの地下トンネルに海水を注入したというニュースを聞きながら、とっさに思い出したのが42年前、北海道夕張市で起きた「北炭夕張新炭鉱」のガス突出事故だった。93人が犠牲になり、坑内にまだ生存者が残っている可能性があるにもかかわらず、会社側は坑内火災の延焼を防ぐという名目で近くの川水を注ぎこんだ。「お命をちょうだいします」と言い放った当時の社長の言葉がいまだにこびりついて離れない。
そんな折しも、旧知の北海道新聞元編集委員の往住嘉文さん(69)から「先輩のこの貴重な体験をぜひ、大学生に伝えたい」と連絡があった。北星学園大学(札幌市)の「新聞活用プログラム」の一環として紹介したとして、こんなメールが届いた。「事故発生の第一報と会社の注水提案が同じ紙面に載るという異常を当時の新聞記事で見せました。今パレスチナ問題で何ができるか考えてほしいと締めくくりました。少なくとも10人はずっと顔を上げ、凝視していました。このような記事を残してくれた増子さんに感謝申し上げます」
<署名延長のお知らせ>
新花巻図書館の旧病院跡地への立地を求める署名運動は全国の皆さまのご協力により、4,730筆という予想以上の賛同をいただくことができました。支援者の一人として、感謝申し上げます。行政側の動向が不透明な中、主催団体の「花巻病院跡地に新図書館をつくる署名実行委員会」(代表 瀧成子)は引き続き、全国規模の署名運動を続けることにしました。締め切りは2024(令和6)年1月末必着。送付先は:〒025-0084岩手県花巻市桜町2丁目187-1署名実行委員会宛て。問い合わせ先は:080-1883-7656(向小路まちライブラリー、四戸)、0198―22-7291(おいものせなか)
署名用紙のダウンロードは、こちらから。 「全国署名を全国に広げます!~これまでの経過説明」はこちらから。署名実行委員会の活動報告などは「おいものブログ」(新田文子さん)の以下のURLからどうぞ。