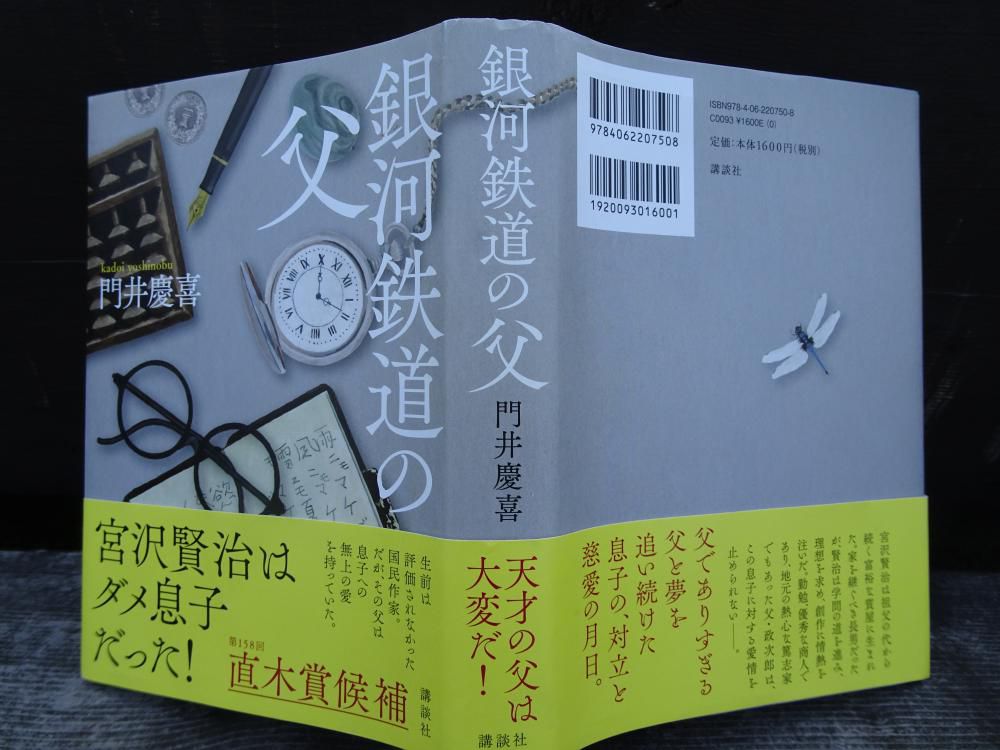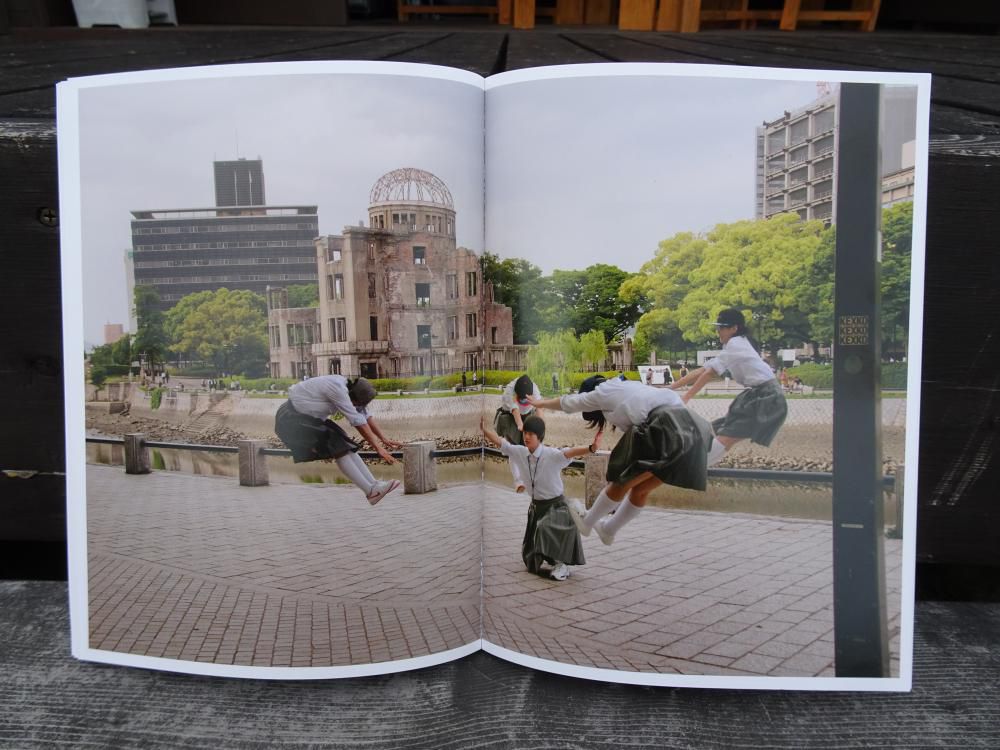第159回芥川賞・直木賞(日本文学振興会主催)の選考会が7月18日に行われ、前者には高橋弘希さん(38)の『送り火』、後者には島本理生(りお)さん(35)の『ファ-ストラヴ』が選ばれた。芥川賞候補にノミネ-トされたものの、他作品との類似表現が指摘されていた北条裕子さん(32)の『美しい顔』(群像新人文学賞)は選外となった。同作品は東日本大震災で被災した女子高校生が一人称の形で揺れ動く心を紡(つむ)ぐ内容。ところが、作品中にはノンフィクション作家、石井光太さんの『遺体』など3・11を題材とした5作品からの引用と思われる個所が多数見つかり、その捉え方をめぐって出版界で議論が続いていた。
この件について、出版元の講談社は文芸雑誌『群像』(8月号)で、こう謝罪した。「主要参考文献として掲載号に明記すべきところ、編集部の過失により未表記でした。文献の扱いに配慮を欠き、類似した表現が生じてしまったことを、石井氏及び関係各位にお詫び申し上げます。また、東日本大震災の直後に釜石の遺体安置所で御尽力された方々に対する配慮が足りず、結果としてご不快な思いをさせたことを重ねてお詫び申し上げます」―。これに対し、『遺体』の発行元の新潮社は「単に参考文献として記載して解決する問題ではない」と反論。講談社は著作権の侵害にまで及ぶものではないとして、今月4日付で自社ホ-ムペ-ジに『美しい顔』を全文公開し、読者に当否の判断を委ねている。
「小説の作法とは何か」―。今回の問題は著作権のあり方などを含めた文学作品の表現形態のあり方を問うたものとして注目される。その本質的な議論は今後に期待するとして、出版に際しての「マナ-」や「ル-ル」に関し、講談社が公に謝罪したのは評価される。実は第158回直木賞を受賞した同社発行の『銀河鉄道の父』(門井慶喜著)について、同じような懸念を抱いた経緯があった。400か所以上に及ぶ文中の「方言」個所の“翻訳”が外部委託されていたにもかかわらず、その旨の表記が記載されていなかったのである。その意味では、今回の「類似表現」問題と同じ次元の構図ではないかと思う。
方言表記が同書の心臓部分を形成していただけに、とくに宮沢賢治の地元・花巻には違和感を表す読者も少なからずいた。このため、私は公開質問状を講談社に送り、その見解をただした。今後の留意を促すのが本意だったため、これまで公開を控えてきたが、今回の問題に接し、当方の真意がきちんと伝わっていなかったのではないかという思いを強くした。小説の「作法」論争の一助に資すると考え、以下に全文を公開する。大手出版社が陥りやすい、読者不在の“おごり”はなかったのか―この懸念が杞憂(きゆう)に終わることを願っている。大方の読者の判断を仰ぐことができればと思う。
※
株式会社 講談社 文芸第二出版部御中
《公 開 質 問 状》
この度は御社発行『銀河鉄道の父』(門井慶喜著)の直木賞受賞、おめでとうございます。さて、突然のご連絡をお詫び申し上げます。私は岩手・花巻在住の増子義久(ますこよしひさ)といい、現在、花巻市議を務めています。実は本書に関連し、2018年1月21日付の地元紙「岩手日報」に同封の記事が掲載されました。宮沢賢治記念館の学芸員の立場にある筆者が、御社から依頼されたという「本文会話の花巻言葉化(方言化)」はざっと数えただけでも500か所前後に上っています。この本の生命線は何といっても宮沢賢治の父、政次郎など親族の間で交わされた方言による会話部分だと考えます。
今般、同じように賢治にちなんだ作品で芥川賞を受賞した『おらおらでひとりいぐも』(若竹千佐子著)も方言の力強さが評価されたと言われています。しかし、若竹本が“母語”としての方言であるのに対し、門井本は第三者によって“翻訳”された方言という点が決定的に違っています。昨年秋に歌人、石川啄木のうたを東日本大震災の被災地、岩手・三陸の「おんば」(おばあちゃん)たちが“翻訳”した『東北おんば訳/石川啄木のうた』(新井高子編著)が出版されました。歌人の俵万智さんは「訳というのは、単なる言葉の置き換えではない、心の共有なのだと感じました」と評しています。
とりわけ、今回の芥川賞と直木賞はさながら東北弁という「方言力」の競演の趣さえありました。最近では「ありがとがんす」(賢治)、「なんもだ」(政次郎)と花巻弁を口にする二人の写真入りの新聞広告(つまり御社のPR)が紙面を飾るというフィ-バ-ぶりです。花巻人として、手放しで喜んでいいものやらと複雑な気持ちにもさせられます。以上のようなことを念頭に置きながら、以下について質問します。「土地の言葉(方言)には言霊が宿っている」―故石牟礼道子さんがのこした“遺言”が今さらのようによみがえってきます。
記
1、本書は厳密な意味で、門井さんの「単著」と言えるのか
2、方言化などの編集協力について、「付記」などの記述がないのはなぜか。今後の増刷に際して、その点を再考する考えはないか
3、編集協力のきっかけについて、上記「岩手日報」紙には「その出版社(御社)校閲部に高校の同級生Oさんが勤めており、門井さんが大阪住まいで<花巻弁>がわからないということから、私のことを紹介したのだった」と記されている。こうした安易な依頼自体が読者不在ひいては読み手への冒涜につながるとは考えなかったか
4、本作のようにその核心部分へ第三者が関与した場合の著作権の帰属はどうなるのか。末尾に「本書のコピ-、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除いて禁じられています」と書かれているが、今回のケースとの整合性をどう考えるか。編集協力者に対する印税の配分などはどう定められているのか
5、第三者による方言化に際してはどうしても翻訳者の主観が入ると思われるが小説の作法上、その点をどう認識するか
6、方言化の第三者への依頼など今回の出版に至る経緯について、選考委員会への説明はなされたのか。選考協議はその点を踏まえたうえでなされたのか
以上
《追記》
今回の直木賞受賞作品については、同じような疑問が市民から寄せられたため、開会中の花巻市議会3月定例会の一般質問(3月8日)で、学芸員としての関与の在り方などについて、市当局の見解をただした経緯があります。そのうえで、出版当事者の御社のお考えをお尋ねする次第です。2018年3月31日までに文書にてご回答をいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。なお、御社とのやり取りの経緯については、私のブログ「イ-ハト-ブ通信」に公開することもあることをつけ加えさせていただきます。
2018年3月9日
岩手県花巻市桜町3-57-11 増子 義久
増子義久様
拝復
本年3月9日の消印にてお送りいただきました弊社発行の門井慶喜さんのご著作の『銀河鉄道の父』についての公開質問状にお答えいたします。
記
1、本書は著者である門井慶喜さんが作家としての想像力を駆使して作り出した著作物であり、完全な「単著」です。本書は広く日本国民に親しまれている宮沢賢治とそのご家族を材にしております。これまでにもさまざまな形で伝えられ研究されてきました歴史的事実には従っておりますが、それは実在の人物を描く歴史時代小説としては当然のことです。しかし、賢治の父である政次郎についてはあまり多くの資料がありません。その数少ない事実は曲げないなかで、多くの場面や会話を著者はすべて自らの創意によって描いています。
2、一つの作品が出来上がるためにはさまざまな協力、影響、参照などがあり、それらを作品に付記するかどうかは個別の判断に任せられています。本書についてはすべて付記しませんでした。
3、方言指導の依頼は通常の編集作業であり、今回の依頼の経緯が「安易」「読み手への冒涜」とは考えません。
4、「核心部分へ第三者が関与した」とありますが、方言指導を受けている会話は①に記しましたようにもともとすべて著者の創作のままで、本作の方言化部分も著作権は著者に帰属すると考えています。ですから、方言指導をいただいた方へも著作権に基づく印税ではなく原稿料の形で報酬をお支払いしています。
5、本作の場合、地の分も含めた全体ではなく、会話に絞って方言指導をお願いしました。指導を受けた個所は多数かもしれませんが、それらは特定の言葉への置き換えであったり語尾の変化であったりしており、指導者の主観が大きく入るとは考えません。また、本作では指導者のご指摘を著者が一度検討して方言の度合いを調整するという手順も踏んでおりました。
6、「選考委員会」というのは直木賞を運営している日本文学振興会ということかと思いますが、前述してきましたように本作は門井慶喜さんの単著ですので、方言指導の扱いについてこちらから説明することはありませんでした。
以上、ご理解いただけますと幸いです。
敬具
2018年3月27日
東京都文京区音羽2-12-21
株式会社 講談社
第五事業局 文芸第二出版部
担当/小林龍之