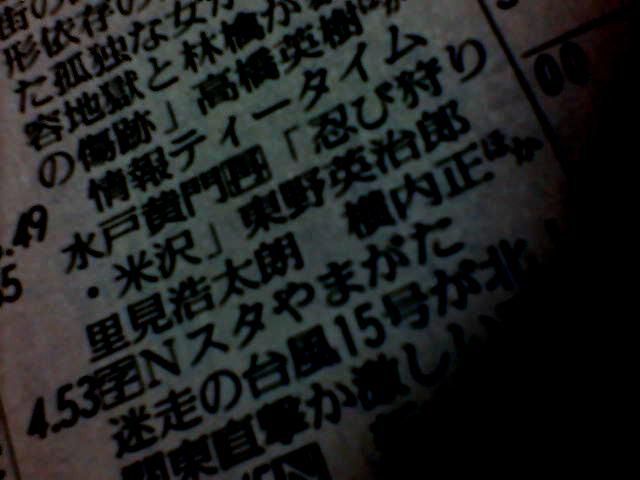息子はガールフレンドのところに遊びに行ったので、ゆっくり東野英治郎の水戸黄門を見ることができました。ちょうど米沢篇ということなので。
第4部、8話、1973年3月12日放映のものです。
このころはチャンバラのシーンのロケもあったのはすごいものです。
配役も安部徹、牧冬吉、宇都宮雅代、伊吹吾郎などなかなかなのです。
エンディングでちょっとフィルムがよれて、芥川隆行のナレーションがなかったのが残念でしたが。
米沢市協力とあったのですが、多分笹野一刀彫が一杯出てきたのでそれを提供したのでしょう。
それにしても今から38年前、チャンバラの後の罪状を光圀本人がかなりの長台詞を言っているのがびっくりです。
しかも、静まれ水戸のご老公と言っていたのがなんと弥七でした。まだそれほどカタチにこだわっていなかったことがわかります。
あとチャンバラのときに出てくるクラリネットの曲は、後年よりも随分テンポが遅く、全体的に殺陣もゆっくりのような気がします。
それはそれで独特の味を感じます。
地名としては小野川と御成山が出てきました。御成山は元々化物沢、あるいは鷹打羽呼ばれていましたが、昭和11年1月18、19の両日に開催された全日本学生連盟スキー大会に秩父宮殿下(昭和天皇の弟)が来臨(らいりん=お成り)され、これを記念して御成山スキー場と改名されたものだということです。だから水戸黄門の当時は御成山とは言いません。
まあまあいろいろありますが、こうやってフィルムで作られた映像は、しっかり残っているのでありがたいですね。
HOME > 記事一覧
運動会現況。
17日うちの息子が行ってる興譲小学校の運動会が行なわれました。
天気は曇天でそれほど暑くもなく、応援日和でした。
私は東部小学校だったのですが、あの頃は1,500人超の子供がいたので、最初は組みわけが紅白だったのが、途中で青とか黄色、その後に紫などが現れました。
確か、ハチマキは一人ひとり自分で作ってくる、というか母が縫うということで、白はいいのですが、紅の場合、中々同じ色というわけにもいかず、家のような織物買継なんかやってるところや、機屋の息子などは八掛(着物の裏地の生地)などで作ってもらったりするので、紅というよりは臙脂色(エンジ)のような渋い色のものもありました。
玉入れの玉も、各自作ってくるということになっていたと思います。
息子の徒競走が終わり、10時前には店に戻ることができました。
近くてイイノデス。
天気は曇天でそれほど暑くもなく、応援日和でした。
私は東部小学校だったのですが、あの頃は1,500人超の子供がいたので、最初は組みわけが紅白だったのが、途中で青とか黄色、その後に紫などが現れました。
確か、ハチマキは一人ひとり自分で作ってくる、というか母が縫うということで、白はいいのですが、紅の場合、中々同じ色というわけにもいかず、家のような織物買継なんかやってるところや、機屋の息子などは八掛(着物の裏地の生地)などで作ってもらったりするので、紅というよりは臙脂色(エンジ)のような渋い色のものもありました。
玉入れの玉も、各自作ってくるということになっていたと思います。
息子の徒競走が終わり、10時前には店に戻ることができました。
近くてイイノデス。
ムサシの野辺に、
身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂
というのが吉田松陰の辞世の句とされています。
朝買い物があり、ホームセンタームサシに自転車でGO!
9時半からのオープンなので、大体店を9時15分ぐらいに出れば間に合います。
コースとしてはいろいろありますが、今日は門東町から元細工町、表町に出て座頭町から裏へ抜けて北寺町西之町、堀立川を渡り信夫町から徳町と行きました。
帰りはどうしても何となくこの小径を通りたくなるのです。どう見ても正式な道ではないのですが、この道を通ると近道なのです。
そばにはキャベツ畑があり、この節でもモンシロチョウが遊んでいました。
というのが吉田松陰の辞世の句とされています。
朝買い物があり、ホームセンタームサシに自転車でGO!
9時半からのオープンなので、大体店を9時15分ぐらいに出れば間に合います。
コースとしてはいろいろありますが、今日は門東町から元細工町、表町に出て座頭町から裏へ抜けて北寺町西之町、堀立川を渡り信夫町から徳町と行きました。
帰りはどうしても何となくこの小径を通りたくなるのです。どう見ても正式な道ではないのですが、この道を通ると近道なのです。
そばにはキャベツ畑があり、この節でもモンシロチョウが遊んでいました。
この瀟洒な洋館は
あら町辻西の加藤眼科です。現在は誰も住まれていないようですが。
場所は北部小学校に入る歩道橋の下の家です。
ここの角に石碑があります。それには「吉田松陰投宿の地」とあります。
それによりますと、
吉田松陰は常に内外の情勢に意を注ぎ、二十三歳のとき、東北遊歴の情やみがたく、嘉永5年(1852年)3月25日長崎以来の知友であった米沢藩士高橋玄益を訪ね、諸学士と談合しようとして、この地あら町の旅篭遠藤権内方に宿をとったが、たまたま藩主斉憲が参勤交代で江戸に上る前日とあって果たせなかった。
松陰はその後安政4年(1857年)郷里の萩(山口県)に松下村塾を開いてその地の子弟を薫陶しあまたの志士を養成した。
松陰はその後幕政に抗して捕らえられ、雄国空しく安政6年(1859年)10月27日数え年三十歳で武蔵野の露と消えたが、彼の志をうけついだ人の多くは元勲とたたえられこれらの人によって廃藩置県は実を結び、明治維新の大業は成就し、今の日本の元が出来上がったことを思慕するのあまり、ゆかりの地に碑を建て後世に残す。
とあります。この碑が建つ前は簡単な白いペンキの角材に「投宿之地」というのがあったような気がします。そしてその昔ここに立ち食いそばの自動販売機があったように思うのですが、記憶のある方はいらっしゃいませんか。
このマシンに関しては、機械の調整も難しく、現在全国でもかなりレアな状態らしいです。確かかなり詳細なHPがあった筈です。
群馬、栃木にはまだ随分現役があるようですが、武蔵野の露と消えたものも多いかもしれません。
場所は北部小学校に入る歩道橋の下の家です。
ここの角に石碑があります。それには「吉田松陰投宿の地」とあります。
それによりますと、
吉田松陰は常に内外の情勢に意を注ぎ、二十三歳のとき、東北遊歴の情やみがたく、嘉永5年(1852年)3月25日長崎以来の知友であった米沢藩士高橋玄益を訪ね、諸学士と談合しようとして、この地あら町の旅篭遠藤権内方に宿をとったが、たまたま藩主斉憲が参勤交代で江戸に上る前日とあって果たせなかった。
松陰はその後安政4年(1857年)郷里の萩(山口県)に松下村塾を開いてその地の子弟を薫陶しあまたの志士を養成した。
松陰はその後幕政に抗して捕らえられ、雄国空しく安政6年(1859年)10月27日数え年三十歳で武蔵野の露と消えたが、彼の志をうけついだ人の多くは元勲とたたえられこれらの人によって廃藩置県は実を結び、明治維新の大業は成就し、今の日本の元が出来上がったことを思慕するのあまり、ゆかりの地に碑を建て後世に残す。
とあります。この碑が建つ前は簡単な白いペンキの角材に「投宿之地」というのがあったような気がします。そしてその昔ここに立ち食いそばの自動販売機があったように思うのですが、記憶のある方はいらっしゃいませんか。
このマシンに関しては、機械の調整も難しく、現在全国でもかなりレアな状態らしいです。確かかなり詳細なHPがあった筈です。
群馬、栃木にはまだ随分現役があるようですが、武蔵野の露と消えたものも多いかもしれません。
2011.09.15:mameichi:コメント(0):[米沢城下に江戸を訪ねる]
手拭い
無論これそのものも売ってはいたのでしょうが、本来はやはり配り物だったのではないでしょうか。
落語の真打披露などでは、今もオリジナルの手ぬぐいを配ります。
いつの頃だったか、家の小屋から沢山の配り物の手拭いが出てきました。
あら町や座頭町などの店のものが多く、多分うちの母が嫁入りしたときに、母の母、つまり私の祖母が持たせてくれたものだろうということでした。
箱に入ったそのものはその後発見されていません。どこかにあるはずなのですが。
今は中々配り物ということもないので、お気に入りのものを一枚如何でしょう。
正方形の小風呂敷で、お弁当を包んでもいい感じです。
落語の真打披露などでは、今もオリジナルの手ぬぐいを配ります。
いつの頃だったか、家の小屋から沢山の配り物の手拭いが出てきました。
あら町や座頭町などの店のものが多く、多分うちの母が嫁入りしたときに、母の母、つまり私の祖母が持たせてくれたものだろうということでした。
箱に入ったそのものはその後発見されていません。どこかにあるはずなのですが。
今は中々配り物ということもないので、お気に入りのものを一枚如何でしょう。
正方形の小風呂敷で、お弁当を包んでもいい感じです。