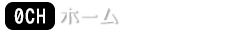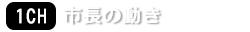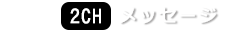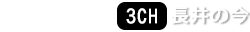平成28年度長井市地域おこし協力隊活動報告会が3月13日、市保健センターで行われました。報告会には、関係者や市民、他市町村の地域おこし協力隊など約70人が参加。全地域おこし協力隊7人のうち6人が、それぞれの活動報告が発表しました。
平成29年4月から開始予定の「BabyBoxプロジェクト」を発案した佐藤亜紀隊員は、何度も壁にあたってきたことや、市内事業者と共同で事業化に取り組んできたことなどを発表。そのスピード感のある活動内容に、他の地域おこし協力隊から質問を受けていました。
なお、各隊員の発表は以下の通りです。
①佐藤大隊員 伊佐沢地区の地域おこし活動
②渋谷達郎隊員 まちおこし戦略による活性化促進活動
③佐藤亜紀隊員 子育て支援×産業振興
「シティプロモーション推進活動」
④丸山真美隊員 水源地域ビジョン実施活動
⑤秋元悟隊員 けん玉のふるさとプロジェクト推進活動
⑥松崎綾子隊員 芸術文化による地域おこし活動
※⑦佐藤桃菜隊員 地域資源を活かした滞在交流型観光推進活動
(当日欠席)
※問い合わせ 市地域づくり推進課☎0238(87)0817
平成28年度長井市地域おこし協力隊活動報告会(H29.3.13)
ー長井市とタンザニアの未来へのチャレンジー ホストタウン登録記念講演会(H29.3.17)
長井市は2020年東京オリンピック・パラリンピックで、タンザニア連合共和国を相手国とするホストタウンに登録されました。その登録を記念した講演会が3月17日、タスビルで開催されました。この講演会には約80人が参加し、中には高校球児の姿もありました。講演では、認定NPO法人アフリカ野球友の会代表の友成晋也さんから、JICA職員としてや野球を通してのアフリカでの支援活動や現状について、そして長井市がホストタウンとしてタンザニアと交流していくことの意義について熱く語っていただきました。友成さんは、ガーナ代表の野球チームの初代監督を務めたのち、タンザニアでも野球を普及させる活動を続けています。
友成さんは、日本の野球をはじめとするスポーツについて「規律、礼儀、正義が特徴であり、日本のスポーツはアフリカを変えられる」と話し、さらに「ホストタウンでの国際交流、国際協力は地方活性化の種になる。長井の人のためにもなるホストタウンになるように、皆さんで盛り上げてほしい。長井市が第二の中津江村(サッカーワールドカップでカメルーン代表の事前合宿地となり、その交流はいまも続いている)になるようなコミュニケーションとなるよう期待」と訴えました。
また、講演のあとには、参加した皆さんから交流やホストタウン後についての質問などもあり、今後の交流へ向けて弾みが出る講演会となりました。
伊佐沢小学校モジュール授業
長井市では、「教育・子育て」を戦略の柱とした長井市総合戦略をつくり、人口減少を改善するための子育て支援と融合して、子どもたちを〝食べていける大人””世界を相手に挑戦できる大人”に育てる教育システムづくりに取り組んでいます。
そして長井の教育現場では、その足がかりとして「英語教育」の充実に取り組んでいます。市内にある伊佐沢小学校は、教育課程特例校としてH27年度からの2年間、先生やALT(英語指導助手)の皆さんの努力により独自のカリキュラムを作成し、英語教育を実施してきました。
詳しくは、あやめレポをご覧ください。
http://www.city.nagai.yamagata.jp/backnumber/4093.html
今回は、その中からモジュールという毎朝10分の英語活動の様子をお届けします。これは違う言語を聴くことによる「脳を鍛える」という効果で、知能そのものを育て英語以外の教科にも好影響をもたらします。子どもたちは、先生たちといっしょに、英語を身近に感じ、トライしつづけた2年間でした。昨年11月から始めたインターネットを活用したマンツーマン英会話レッスンでは、外国の人ともスムーズに会話が進んでいて、この2年間の成果がうかがえます。
平成29年度からは、市内全小学校で同じように英語教育の取り組みを始めます。
※問い合わせ 長井市学校教育課☎0238(88)5767、伊佐沢小学校☎0238(88)2710
◇伊佐沢小学校のホームページでも英語教育の様子がご覧いただけます。
http://www2.jan.ne.jp/~isazawa/
内閣府審議官 羽深成樹氏 講演会を開催(H29.3.3)
「内閣府審議官 羽深成樹氏 講演会」が3月3日(金)、タスビルで行われました。
講演会では近年の日本や世界の経済情勢、人口問題、就業の改善など、具体的な数値データや知識を交えて説明。日本が抱える人口問題に対し、「このままでは、2030年頃に現在の鳥取県の総人口にあたる65万人が毎年減り続け、2040年には山形県の総人口にあたる100万人減ることとなる。今はその入り口に差し掛かっている」と警鐘を鳴らしました。出生率を高めるためには、産み育てやすい環境づくりが重要とのことで、「長井市に限らず、地域経済の向上には外から技術者や若者を呼び込み刺激を受けることが大事。また、市民が一丸となることは大前提」と提言しました。
長井市や山形県の人口推移・就業率など他県市町村と比較し客観視することで、住んでいながら見えていなかった長井市の良さ・問題点が見えてきました。
羽深氏は東京大学法学部を卒業後、大蔵省に入庁し、内閣総理大臣秘書官や内閣府政策統括官などを歴任しています。1986年には米沢税務署長も務めており、当時税務署長に就任され奮闘した出来事、置賜で過ごした思い出などを紹介する場面もありました。
けん玉交流会in長井ーけん玉王決定戦ー(H29.3.5)
【けん玉交流会in長井が開催されました】
けん玉交流会in長井が3月5日(日)、タスビルで開催されました。この催しは、けん玉を通して、いろんな地域の人と長井を含めたこの地域の人たちとの交流の場をつくろうと、長井市地域おこし協力隊である秋元悟さんが企画。山形県内はもちろん、宮城や秋田、新潟、東京、遠くは大阪から、また、中には衣装を身にまとった人など、およそ100人が会場に詰めかけました。交流会では、けん玉決定戦や即席チーム戦、段位認定会のほか、最後には参加者全員で長井式大皿ドミノ(昨年長井市でギネス世界記録を達成)を行うなど、けん玉を通した交流を楽しんだ一日となりました。
午前中に行われたけん玉王決定戦の予選会には、40人の申し込みがありました。競技内容は、通常のけん玉とは異なる形や糸の長さ、中には糸をゴムに変えたものなど、秋元さん考案のおもしろい5種類のけん玉を使用し、どのくらい早く決められた技をこなしていくかというもの。いままで触ったことのないけん玉や、不規則なけん玉の動きに、会場全体が笑いに包まれていました。
午後はけん玉王決定戦決勝の前に、即席チーム戦が開催されました。この競技は、参加する人たちがくじを引いて5人一組の即席チームを結成し、5人で1つのけん玉を使い、1人1人決められた技を決め、次の人にけん玉を渡していくというリレー形式でおこなうもの。初めは知らない人同士の即席チームがチーム戦を行うことで1つになり、選手も観客も皆が大興奮し、会場は大いに盛り上がりました。
即席チーム選の後に行われたけん玉王決定戦決勝は、予選を勝ち残った20人で開催。予選とはまた違った6種類のけん玉が登場。3分という持ち時間内でどれだけ早く決められた技すべてを決められるかというルールでしたが、全てを決められた人自体が6人という難易度の高い決勝戦となりました。そんな中、見事けん玉王を勝ち取ったのは山形在住の小学生、武田佳起くんでした。並み居る強豪の大人たちを抑えての優勝、おめでとうございます!
その他、けん玉の級や段位の認定会も行われ、子どもから大人まで、多くの人が昇級、昇段に挑戦する姿がありました。