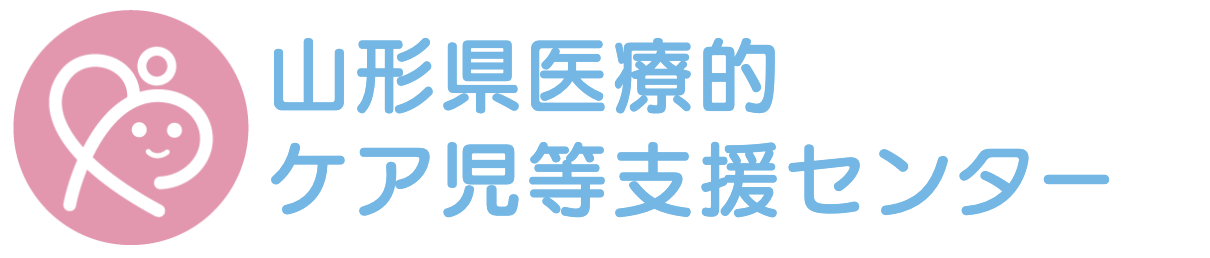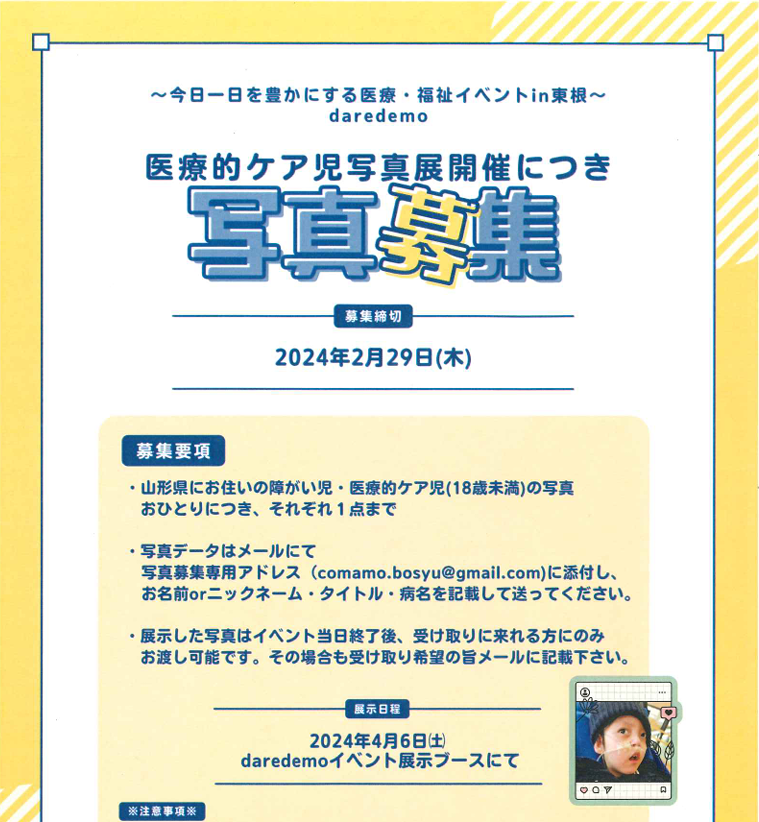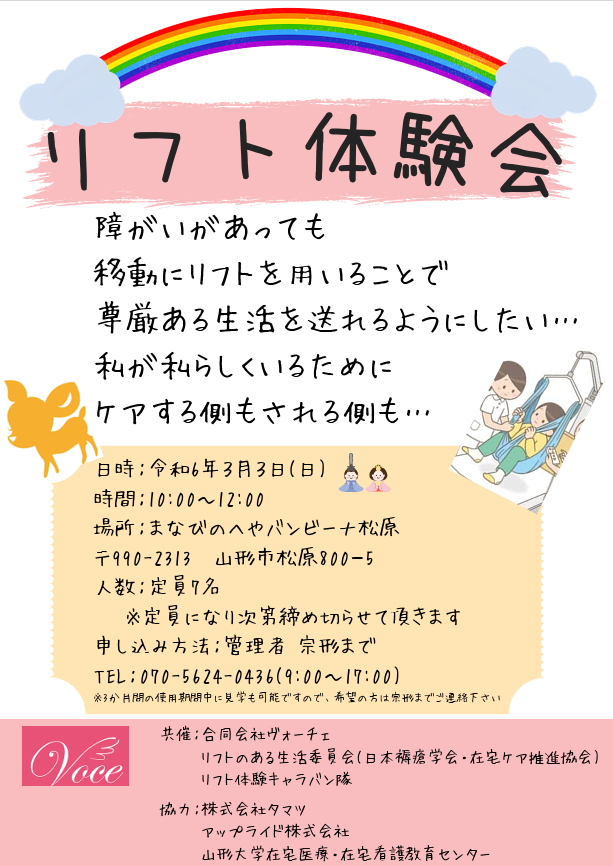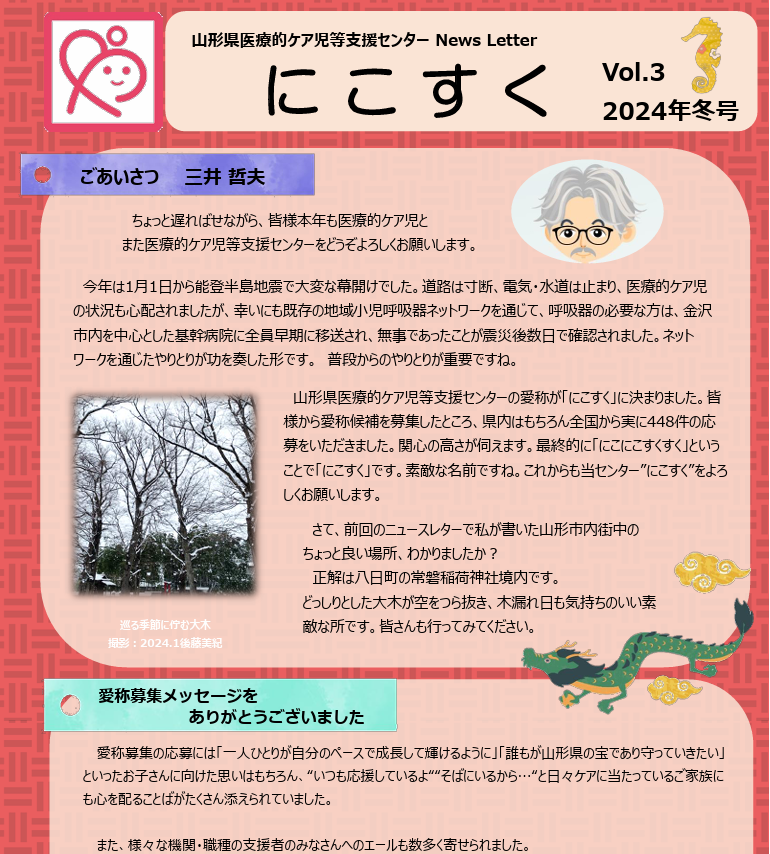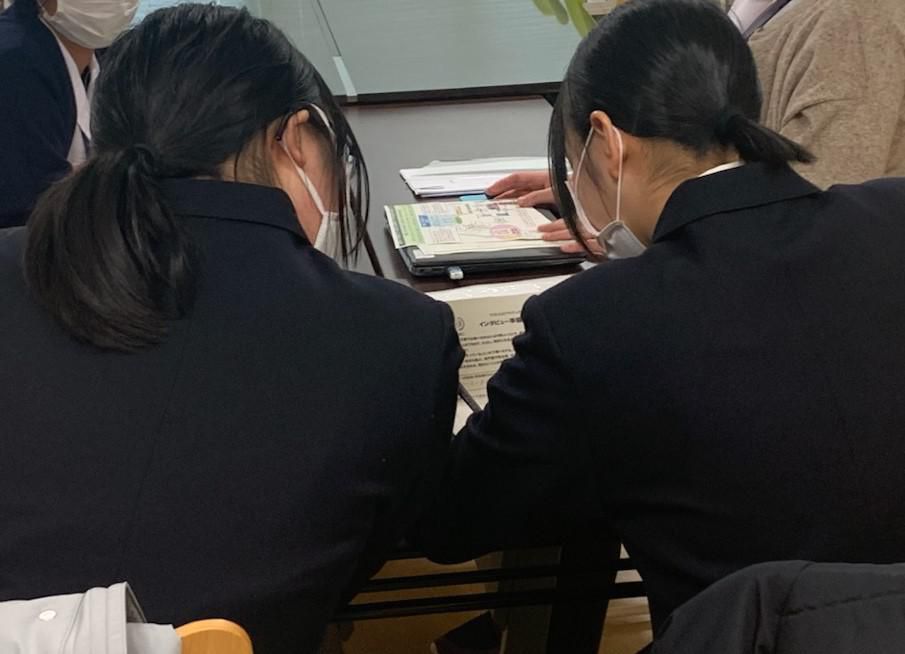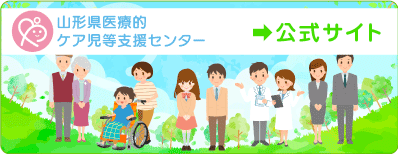蔵王のふもとにある指定相談支援事業所まんさくにお伺いしました。
児童発達支援センター、生活介護、共同生活援助といった様々なサービスを運営されている総合福祉施設まんさくの丘にあり、お子さんから大人の方までご相談や計画作成をお受けしている人数は400名を超える頼もしい事業所です。
日頃の相談支援のみならず医療的ケア児コーディネーターの活用や共有ツールを用いた情報の把握、災害時個別避難計画、地域つくりなど幅広い情報共有、意見交換の機会となりました。
ちょうどまんさくの花も満開!
複数の種類のまんさくがあること、よく開花のニュースといった撮影に使われている木を紹介いただきました(写真)。
先駆けて咲く花に春を感じますね!