軽部さんが作る、丹精込めた真紅の宝石「紅秀峰」
晩成種の「紅秀峰」は、現在主流の「佐藤錦」に継ぐ新品種として、8年前にデビューした"山形のさくらんぼ"です。大玉で糖度が高く実が確りしており、ガツンとした歯ごたえとフレッシュな後味が特徴です。 <出荷の流れ> 軽部さんの畑→直販(露地物のみ)→JA→東京・大阪の市場→消費者のみなさん ※晩生種なので、佐藤錦が終わった頃の6月下旬〜7月上旬に出回ります。 >>> さくらんぼ農家 軽部賢一さん >>> 軽部さんの安全栽培にかける熱き思い |
堀さんのつくる、生でうまい昔ながらの味のきゅうり「プリティ」。
皮に張りがあり、中は柔らかて弾力もある。生でぱりぱり食べると、口の中にほのかな甘みが残ります。サンドイッチとかに使用すると最高です。姿のいいキュウリを作ることが、堀さんの信条です。 ・地面に這わす方法で育てたキュウリを「地這いきゅうり」といいますが、プリティは地這いの味がします。 ・水分と肥料のバランスが悪いと、曲がったキュウリになってしまう。 <出荷の流れ> 堀さんの畑→JA→市場→青森、関東→営農センターで直販 ※出回るのは5月〜7月中旬まで。プリティのイボは小さめなのが特徴です。 >>> きゅうり農家 堀弘一郎さん >>> 堀さんの安全栽培にかける熱き思い |
|
生でも茹でても炒めても良し。食べ方も万能選手のキャベツは、一年中店頭で見ることができますが、どれも同じ味という訳ではありません。
熊谷さんが育てているのは、高冷地野菜(こうれいちやさい)。標高600m〜1000m位の冷涼な気候を利用して栽培される野菜のことで、葉がよくしまって、しかも柔らかく、みずみずしく育つのが特徴です。畑にうかがったのは9月中旬でしたが、すでに厚手の上着が必要なほどの涼しさ。この辺りは5月でも雪が残っているそうです。約30年前、この土地を求めて土づくりから始めた熊谷さん。 「戦後の食糧難の時にカボチャを植えた場所だったらしく、土の質はよかったんですよ。ただ石が多くてね」。最初の1年は石との格闘だったとか。 |
|
「栽培で気をつけることは、防除と土寄せです」とキャリア約20年の加藤さん。長ネギは白い部分ができるだけ長くなるよう、土寄せといって伸びてきた根元に何度か土をもり、日に当てずに育てていきます。
ただし長ネギの病原菌は根から入り、どんどん広がってしまうため、葉っぱとの分岐点が土に埋まらないよう、慎重に行わなければなりません。 「地温が高いと菌が繁殖してしまうから、25度以下の早朝から8時頃までに作業をおわさないと。盛夏の時期は特に危険ですし、雨上がりの日は出来ないんです」。 土には酪農家や有機センターから取り寄せたもみ殻を入れた堆肥を使っています。「化学肥料よりもちがいい。それに土の中に空気の層ができてやわらかくなる。長ネギは酸素が好きなんで成長が早くなるし、適度なしまりがでてきます」。 |
夏が旬のきゅうりですが、最近はハウス栽培によって一年中出回るようになりました。
18歳からきゅうりの栽培をしている武田さん。現在手がけている品種は、寒さに強いオーシャンと、今年から始めたグリーンラックスの2種類。「グリーンラックスは、その名の通り、グリーンが濃くて見た目の色ツヤが鮮やかなんですよ。歯触りもパリパリッとしていますから、サラダや漬物にはもってこいです」。 きゅうりの苗づくりは年明け早々、1月10日頃に始まり、約1週間後に種まき開始。土の堆肥はもみ殻、米ぬかなどで、時々カブトムシの幼虫がまぎれていることもあるそう。苦労する点は、苗づくりの温度管理。「20年ほど前から温水器を導入し、うねの中を地下暖房のような状態にしています。あったかくしながら育てるんですよ」。 |
笹沼さんが作る、宝石のような色のなす「蔵王サファイア」。
皮が柔らかいのが特徴なので、一夜漬けにいいです。色つやも良く、食欲をそそりますよ。山形を代表する夏の味を、もっと早い季節から味わえるようにして、消費者のみなさんによろこんでもらいたいという思いで、ハウス栽培は無理と言われていたナスづくりに挑戦しました。 <出荷の流れ> 笹沼さんの畑→JAやまがた→市場→主に山形・秋田・福島・仙台の消費者のみなさん ※出回るのは4月〜10月末まで。表面にテリがあるものを選びましょう。 >>> なす農家 笹沼和裕さん >>> 笹沼さんの安全栽培にかける熱き思い |
|
農薬問題やトレーサビリティなど、食の安全・安心について関心が高まるなか、そうした食生活を実現するためには、どうしたらいいのか。立場が異なる方々に意見交換を行っていただきました。
◎安全・安心に関して取り組んでいることがあればお聞かせください。 佐藤:観光果樹園を開いたのは、消費者に近い立場で栽培をしたかったからなんです。レストランをオープンすることをきっかけに、本格的に低農薬に取り組むことにしました。 椎名:金曜市は生産者が直接販売する形なので、たとえ虫食いがあったり、形が整っていなくとも「それは生産者の方々の顔が見える、責任ある生産物だから」と消費者の方々は信頼してかっていかれます。 瀬尾:直売所は販売しているおばちゃん達から料理法を聞いたり、おまけをもらったり、楽しんで買い物できますよね。「安全」については、無登録農薬の問題が出たときに、再認識することになりました。一番まちがいなのは自分なりの方法として、20年ほど前から、レタス、トマト、キュウリなどの家庭菜園をやっています。でも無農薬だから虫が付くんです。家で食べるので気にしませんが。 佐藤:虫がついているものは食べて安全なのだけど、売り物にはならないんですよね。見た目がいいものを作ろうと思えば、農薬を使わざるを得なくなるし。私が疑問に思うのは、皆さん農薬に対して厳しい反応をされる割りに、日頃インスタントなどの添加物たっぷりの加工食品は平気で食べているような。 深瀬:最近は学校でも「食」に関する教育を取り入れているようです。私の子どもも一人暮らしを始めたのですが、加工食品を買う時は表示を見て、添加物が少ないものを選ぶようにしているって言っていました。 瀬尾:やはり一人一人が勉強することが大事なんですよね。賢い消費者にならないと。 ◎安全・安心への思いや、これから実現するために必要なことは何でしょう? 椎名:金曜市は、農薬やBSEなどの食に関するニュースが流れた時期でも集客が落ちなかったんです。毎年、顔ぶれの同じ生産者に出店してもらっていますので、固定客がついています。やはり、作る側と買う側の信頼関係を確立してこその安全・安心といえるのではないでしょうか。 瀬尾:直売は新鮮さが違うし、スーパーにはない価格交渉だとか、生産者との対話が楽しいですね。年輩者は特に遠くまで買い物に行くことも難しいので、直売所はもっと増えてほしいですね。 深瀬:最近、スーパーは有機栽培や低農薬といった表示が少なくなった気がするんですよ。産地だけでなく、信頼できる生産者の表示も徹底してほしいです。消費者は少なからず、農薬使用には疑問を感じています。でもそこから一歩踏み込むことがなかなか出来ていないんです。 佐藤:農薬を使った安いピカピカの野菜を買うか、無農薬だけど割高なデコボコ野菜を買うかということですよね。アオムシが付いているキャベツをきたないと思ってしまう消費者でも、子どもの頃は平気だったんじゃないかな。小さいうちから、作物はどうやってできるのか、どんな作物が安全なのかを、きちんと教えていくことが、今の大人に課せられた責任なのではないでしょうか。 コンシューマー達  |
JAみちのく村山 尾花沢営農ふれあいセンター メロン部会長
生産者 早坂勝広さん スタッフ 奥様 事業内容 メロンの栽培 その他/スイカ・米 連絡先 JAみちのく村山 尾花沢営農ふれあいセンター 尾花沢市新町5-7-39 0237-22-2020 ・以前は高級品でしたが、今は手軽な果物に変わってきました。家庭で普通に食べて欲しいです。 ・ハウスは12棟あります。 ・流通に乗るのは糖度14%以上のものになっています。 |
|
○発生する主な病害虫
・つる枯病・炭そ病・斑点細菌病・アブラムシ ○病害虫に使用する農薬 ・ロブラール水和剤・ダコニール1000・ビスダイセン水和剤・DDV乳剤50 ○農薬使用で心掛けていること つる枯病になってしまうと、ほぼ全滅してしまうので防除に注意を払います。基本的に農薬は使いたくないと思うのが当然ですから、最小限の使用量です。メロン部会は現在18名。畑での講習会を独自で行っています。 |
大切なのは、何といっても温度と水
メロンは十分な水分が必要なので、井戸水と併用して与えていますが、ハウス内は水をやることで湿度が高くなり、そうすると病害虫が発生しやすくなってしまう。もともと病気に弱いから、管理が非常に難しいですね。基本は土づくりと丈夫な苗をそだてること。この周辺は畜産農家も多く、親戚も牛を飼っているので、自家製の堆肥づくりから始めています。 |
繊細なネットが美しい尾花沢の『アールスナイト夏2』です。
メロンを育て始めて30年になります。 メロンの評価は見た目、つまりネットのきれいさが大切な要素なんですよ。いろいろな品種を作ってみましたが、ここ10年位は『アールスナイト夏2』を栽培しています。ふわっとした網目状で、なんというか女性らしい感じの形状で、栽培している時の玉のび(成長)もいい。この土地の気候にも合いますね。栽培を始めて30年になりますが、いいメロンが出来た時は最高ですね。 <出荷の流れ> 1.早坂さんの畑 → JA → 東京の市場 2.早坂さんの畑 → 直販 ※9月初旬から10月いっぱいまで出回ります。買ってすぐより、少しおいてからがおいしいです。 |
安全で安心な食生活の実現にむけて
農薬問題やトレーサビリティなど、食の安全・安心について関心が高まるなか、そうした食生活を実現するためには、どうしたらいいのか。 Vol.4では、生産者の紹介のほか、観光果樹園や自然レストランを営みながら教育ファームに取り組む佐藤さん、山形市食生活改善推進員として地産地消を推進している深瀬さんと瀬尾さん、「七日町・朝どりほっとなる金曜市」で商店街の活性化に尽力している椎名さんに、意見交換を行っていただきました。 |
農園からお伝えしたいこと
農作物は、人間と同じ、生きていますから、病気になることもあります。人との違いは、一度発生してしまうと、ほとんどが治らないことです。 予測できる病気が発生する前に、被害が悪化する前に、先手を打つことを防除といいます。いまの農業は、減農、有機栽培へ向かっています。エコファーマーの認定は、それを推進する制度で、安全・安心の農業に取り組む生産者の証です。山形の土地に住み、本気で情熱をかたむけ、食生活を支えてくれる人たちを紹介します。 Vol.3では、地域にある「おらほの郷土料理」をまとめた母親委員会の方にお話をうがかい、消費者としての願いも掲載しました。 |
おいしくて安心な食卓を。生産者の気持ちも同じです
私たちが病気になった時、最も大切なことは初期症状への対応です。 症状の軽いうちに治療ができれば、早い回復が見込めます。 またインフルエンザが流行しそうな時には、事前に予防接種をすることで、 病気の感染から身を守ろうとします。それは、農作物の栽培でも同じこと。 害虫や病気が発生した場合、すぐに農薬を散布するなどの手当をすれば、 病害虫を効果的に駆除できるし、病気の進行を防ぐことができます。 また、予防のため、害虫のすみかとなる雑草の草刈を行ったり、防虫ネットを張ったりすることで、 害虫がつきにくく、病気になる確率が低くなり、もし農薬の散布必要となったとしても 最小限で済ませることができます。 私たちが行う病気の「予防」と「治療」が、農作物では「防除」なのです。 |
(C) Stepup Communications Co.,LTD.


















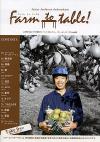





「山形の果物といえば?」の質問に、
ほとんどの人が「さくらんぼ」と答えるはずです。
栽培の発祥は、なんと紀元前1世紀のイタリアで、明治の始め、
日本への導入とほぼ同時に、上山市でも栽培が始まりました。