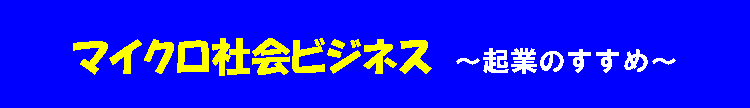従来、敷地や予算、施主の意向といった様々な制約は、建築家の抵抗勢力だと思われていました。
しかし、僕は、がんじがらめの中に、建築をいい味にするための様々なヒントがあると思ったんです。
もしも制約が全くなかったら、制約を探しに行きますね。
現場に行けば、必ずその場所に制約があるから、現場に行く。
まさに宝なんですよ、制約は。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)
HOME > 記事一覧
負ける建築家の意味とは
負ける対象はいろいろとあります。場所や実際に使う人、建てる人など・・・。
そういう人の気持ちを聞くということですね。
その人が「1」言ったとしたら、その裏には「100」くらいの気持ちがあると思っています。
そんな「1」の中から本当の気持ちを聞きとろうとするわけです。
そして、その部分をどう生かしていくか、それをプロジェクトの強さにしていくわけです。
負けることで強くなるというのが大事なんです。
最初から自分のスタイルを決めて押しつけたものは、独りよがりですごく脆いと思います。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)
そういう人の気持ちを聞くということですね。
その人が「1」言ったとしたら、その裏には「100」くらいの気持ちがあると思っています。
そんな「1」の中から本当の気持ちを聞きとろうとするわけです。
そして、その部分をどう生かしていくか、それをプロジェクトの強さにしていくわけです。
負けることで強くなるというのが大事なんです。
最初から自分のスタイルを決めて押しつけたものは、独りよがりですごく脆いと思います。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)
スタッフの能力を伸ばす
人間は、すごい能力をそれぞれ持っていると思うんです。
その能力がどれだけ伸びるかは生かし方次第でしょう。
そのためには、抑えつけるようなことはしないようにしています。
話すときも一方的にしゃべったり、断定的には話しません。
そうやって自分がいい耳を持ちつづけられるような環境をつくろうと心がけています。
そのためには人数は多すぎてはダメですね。
また、言葉がうまい人が勝つようではいけません。
雄弁な人がその場を支配しないように、必ず模型などを置いて、モノに即した議論になるように場をつくっています。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)
その能力がどれだけ伸びるかは生かし方次第でしょう。
そのためには、抑えつけるようなことはしないようにしています。
話すときも一方的にしゃべったり、断定的には話しません。
そうやって自分がいい耳を持ちつづけられるような環境をつくろうと心がけています。
そのためには人数は多すぎてはダメですね。
また、言葉がうまい人が勝つようではいけません。
雄弁な人がその場を支配しないように、必ず模型などを置いて、モノに即した議論になるように場をつくっています。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)
仕事はどんなバカンスより面白い
基本的に休みはゼロです。正月休みもほとんどありません。
でも、設計を考えることがすごく楽しいんです。
どんなバカンスよりも面白いですね。
ほかに趣味といえば、本を読むくらいでしょうか。
例えば仕事先が下関なら、長州藩だったころの話を読む。
そういった歴史を踏まえておくと、その場所を見る目が変わってきます。
いろいろな発見があり、それが建築のディテールに反映されるわけです。
土地というのは、そこに住んできた人々の生活の積み重ねです。
だから、歴史を調べるとか、その土地の人たちの気質を知ることはすごく大事だと思います。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)
でも、設計を考えることがすごく楽しいんです。
どんなバカンスよりも面白いですね。
ほかに趣味といえば、本を読むくらいでしょうか。
例えば仕事先が下関なら、長州藩だったころの話を読む。
そういった歴史を踏まえておくと、その場所を見る目が変わってきます。
いろいろな発見があり、それが建築のディテールに反映されるわけです。
土地というのは、そこに住んできた人々の生活の積み重ねです。
だから、歴史を調べるとか、その土地の人たちの気質を知ることはすごく大事だと思います。
By隈研吾
(プロフェッショナル仕事の流儀15 File No.45より)