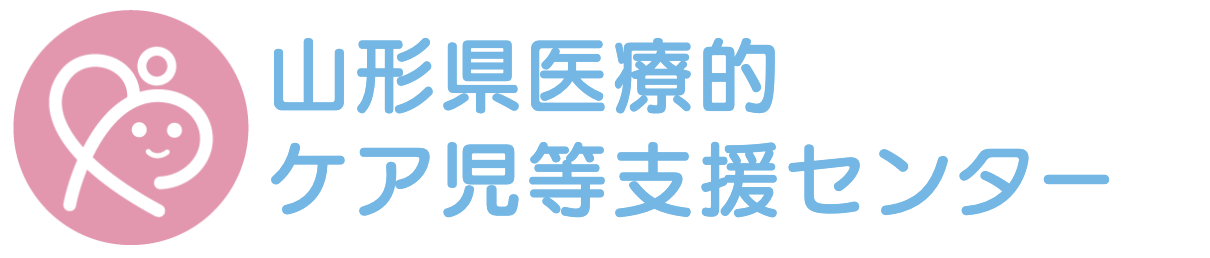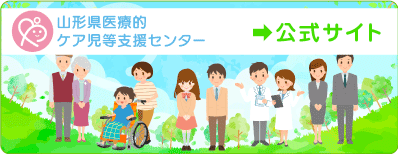https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/tdc2025
2025年9月13日(土)・14日(日)に東京ビッグサイトにて第1回日本小児在宅医学会第1回学術集会が開催されます。
「こども・きょうだい・家族によりそう在宅医療 ~他職種のプロフェッショナリズムを追求する~」として医療的ケアに関する支援について学ぶことができます。
医療的ケア児支援センター及びコーディネーターの役割をはじめ、海外事情、保育・学校教育、災害、2026年の医ケア児支援法法改正など、課題となる項目、分野、職種にスポットを当てたセッションが行われます。
医療的ケア児者の支援に関わる皆様はご参加をご検討いただいてはいかがでしょうか。
(医療ソーシャルワーカー)