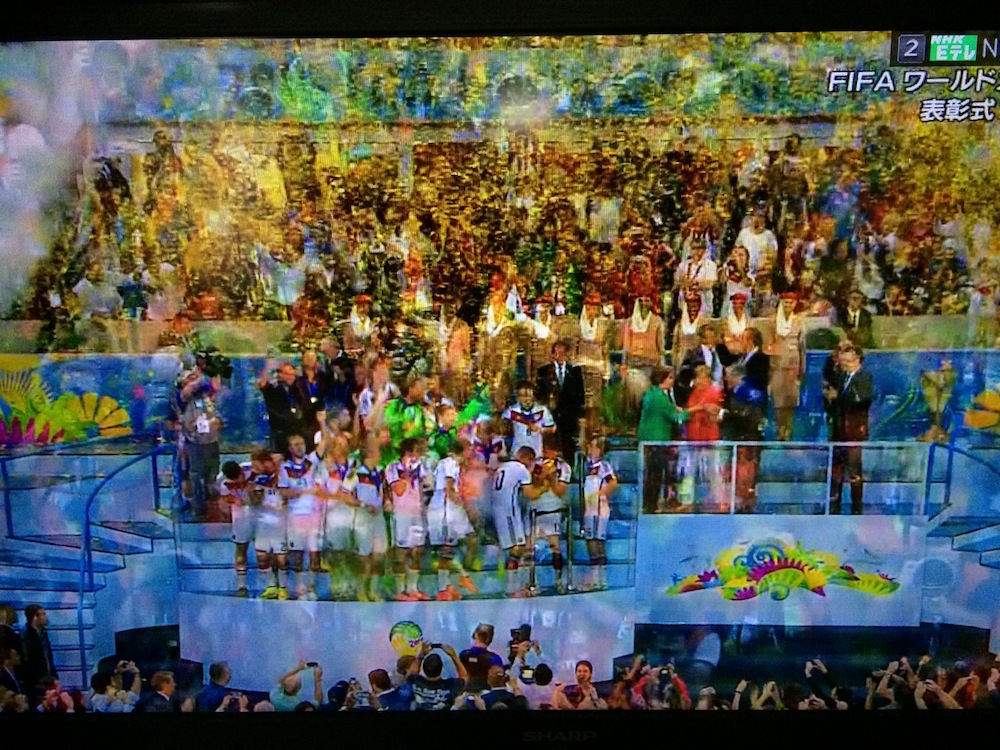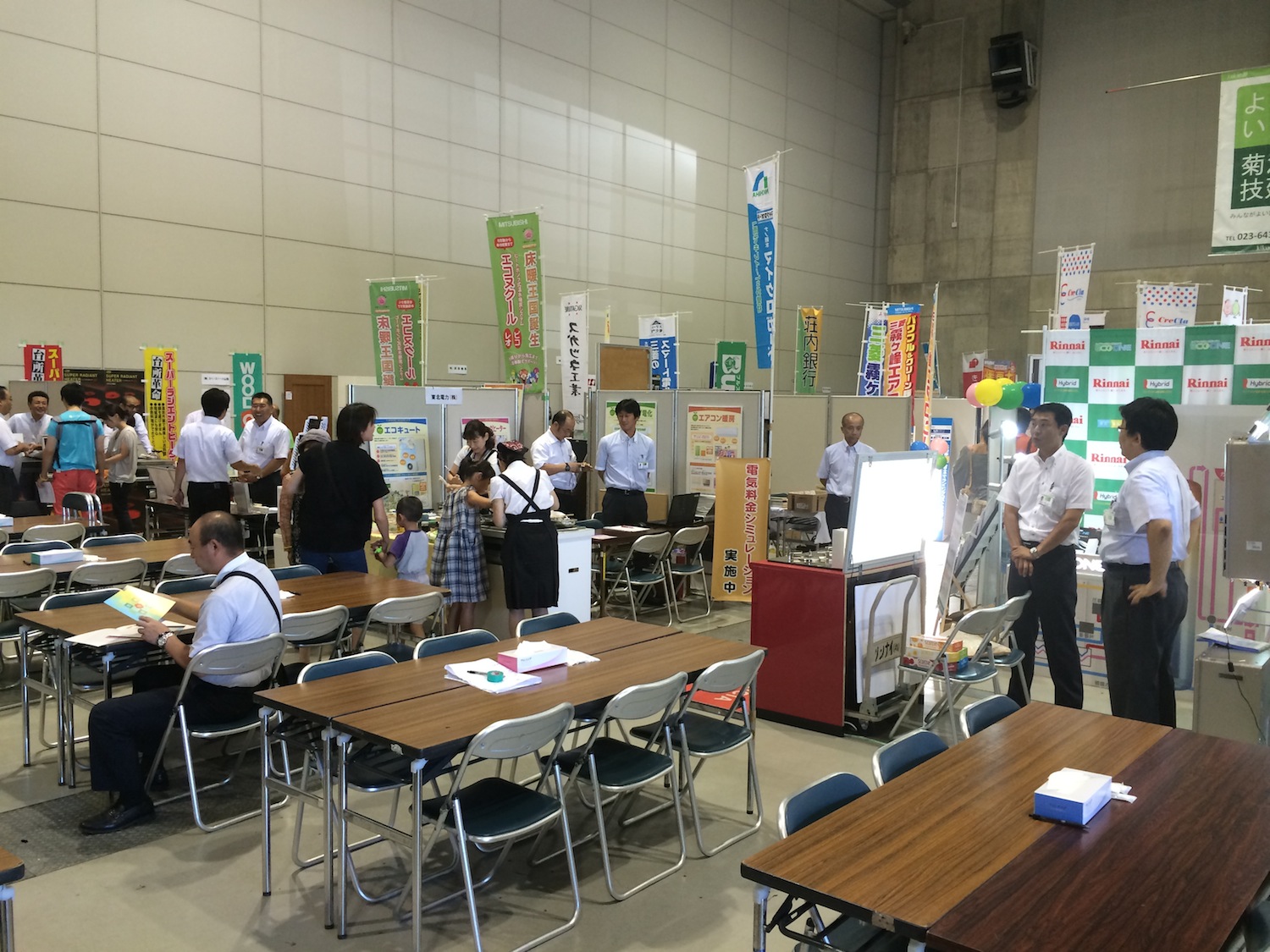私自身は今年初の現場での建て方だけに
梁の上を歩くだけで初めは緊張しましたが、
職人の流れや現場の管理体制を働きながら
感じるために一緒に汗を流しました。

幸い、風が吹き、暑すぎない気温のため
働きやすい方ではあったなと思いますが、
肉体労働は大変疲労を伴いますね。
これまでの安全管理の徹底や
効率よい仕事の流れを見るのには
参考になりましたし、若手職人の
成長を見ることができて
人事評価や個人面談をこれから
行いますので参考になりました。

梁と梁のつなぎを強化するため
プレートを付けている状況です。

こちらは曲りを見ていて下げ振りを垂らして
50㎜に合わせて南に5㎜とか声を掛け合い、
道具で押しつけて垂直を取っています。

羽子板ボルトを設置している所です。

こちらは羽子板ボルトを
締めつけている状況です。
ボルトのつけ方で締め付けにくい
時もあるので注意です。

空の状況を見て、雨が降るかもしれないと
天気予報では降水確率0%で大丈夫でしたが、
通り雨を想定して合板を防水養生しました。
この気遣いの配慮にさすが自社大工さん
と頭が下がりました。
今日はこれらの作業を現場で手伝いました。
午前10時30分から午後3時まででしたが、
社員の皆さんの働きに感謝してすごいな
と体力勝負の強さを感じました。
人とのコミュニケーションは
とにかく自ら動くことが重要だと思いますので
忙しくなってきた時期ですがしっかりと時間を取って
現場の声を聴き取り、社内環境整備を
進めていきたいと実感しました。