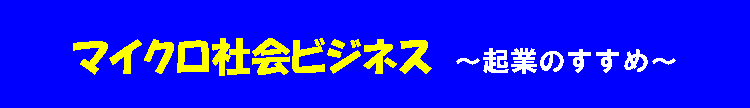カウンセラーになりたいという人が増えている。また、カウンセリングを受けたいという人も多くなった。しかし、職業としてのカウンセラーになるには大変である。
たとえば、もし、ある日、音楽を聞いて感激して、それでは早速これから「音楽家」というものになろう!と思う人がいるかどうか。
また、花が好きで、自分で花を生けるのはできるが、お花の先生になるというなら相当の習練、努力、その他もろもろの条件が必要だというのは誰にもわかる。
カウンセラーになるというのも同じで、専門家になるのは大変である。人は誰でも、悩んだり苦しんだりして生きたわけだから、その分、自分の人生経験はなかなか豊富だと思える。
で、この豊かな人生経験を生かして人の役に立ちたいと思う人がいるけれど、そんなものほとんど役に立たない。
自分の人生経験で人の役に立てる部分は微々たるものということをよく認識すべきであろう。
(こころの天気図より)
HOME > 記事一覧
「ただ座っていること」
「何もしないことが一番難しい」。
このことは教師としての私に強いインパクトを与えた。
あれも教えよう、これも教えようと動き回っているよりも、教師は「ただ座っているだけ」の方がはるかに教育的なのではなかろうか。
教師のピタリと安定して座っている姿を支えに、生徒達が自主的に動き出し、自分の力で学び始めるのである。
しかし、実際やってみるとこれは実に難しい。他人と関係なく座っているのであれば誰でもできるかもしれない。
生徒と関連をもち、生徒の動きを見ていながら、自分の内面では大いに心を働かせつつ、「ただ座っているだけ」だからこそ生徒の自主的な活動が生じてくるのである。
(「おはなしおはなし」より)
このことは教師としての私に強いインパクトを与えた。
あれも教えよう、これも教えようと動き回っているよりも、教師は「ただ座っているだけ」の方がはるかに教育的なのではなかろうか。
教師のピタリと安定して座っている姿を支えに、生徒達が自主的に動き出し、自分の力で学び始めるのである。
しかし、実際やってみるとこれは実に難しい。他人と関係なく座っているのであれば誰でもできるかもしれない。
生徒と関連をもち、生徒の動きを見ていながら、自分の内面では大いに心を働かせつつ、「ただ座っているだけ」だからこそ生徒の自主的な活動が生じてくるのである。
(「おはなしおはなし」より)
「回帰現象」
人間には人それぞれの基本的な行動のパターンがあるようだ。
たとえば、何か新しい場面に出合うと、はしゃいでしまって、つい、しなくてもよいようなことまでやっていしまうとか、逆にどうしても引っ込み思案になってしまうとか。
しかし、このようなことに気がつくと、案外それは変えられるもので、他人にもあまり気づかれないくらいにはなる。
だが、自分もだいぶ変わったかな、などと思っていても、いざという場面、緊張や思いがけないことが生じたときになると、知らぬ間に以前の型にかえってしまうということはよくある。
それは無意識に起こり、自分でも気がつかないときさえあるが、傍らで見ている人には明瞭に見えるものだ。
このような人間の行動の「回帰現象」とでもいえるようなことがあるのを知っておくと、便利であると思われる。
何しろ、この現象は、大切なときに生じる上に、それが生じていることを本人が気がつかない場合があるので、なかなか厄介なのである。このようなために、取り返しがつかない失敗が起こることもある。
野球の投手が盗塁されるのを防ぐために牽制球を投げるように、自分の心の中で、「回帰現象に注意」という牽制球を投げていると、これもだいぶ防げるようである。
あるいは、回帰現象を起こしても、自分で気づいて、それについて相手に説明して了解してもらったり、自分の姿勢を立て直したりすることによって、決定的な失敗を免れることができると思う。
スポーツと同様、人間関係も訓練によって少しずつ上達するようである。
(「おはなしおはなし」より)
たとえば、何か新しい場面に出合うと、はしゃいでしまって、つい、しなくてもよいようなことまでやっていしまうとか、逆にどうしても引っ込み思案になってしまうとか。
しかし、このようなことに気がつくと、案外それは変えられるもので、他人にもあまり気づかれないくらいにはなる。
だが、自分もだいぶ変わったかな、などと思っていても、いざという場面、緊張や思いがけないことが生じたときになると、知らぬ間に以前の型にかえってしまうということはよくある。
それは無意識に起こり、自分でも気がつかないときさえあるが、傍らで見ている人には明瞭に見えるものだ。
このような人間の行動の「回帰現象」とでもいえるようなことがあるのを知っておくと、便利であると思われる。
何しろ、この現象は、大切なときに生じる上に、それが生じていることを本人が気がつかない場合があるので、なかなか厄介なのである。このようなために、取り返しがつかない失敗が起こることもある。
野球の投手が盗塁されるのを防ぐために牽制球を投げるように、自分の心の中で、「回帰現象に注意」という牽制球を投げていると、これもだいぶ防げるようである。
あるいは、回帰現象を起こしても、自分で気づいて、それについて相手に説明して了解してもらったり、自分の姿勢を立て直したりすることによって、決定的な失敗を免れることができると思う。
スポーツと同様、人間関係も訓練によって少しずつ上達するようである。
(「おはなしおはなし」より)
「太平洋」
「おはなし」のひとつとして「歴史」がある。歴史書は外的に起こらなかったことを書くことはできない。
しかし、多くの事実の中のどれをいかに書くかということで、それは「おはなし」性をもってくる。
「おはなし」としての歴史という意味で感心させられる本は、フランク・ギブニー著「太平洋の世紀」である。
本書の魅力は「おはなし」を形成する中核として「太平洋」が取り上げられている点にある。
「太平洋」というイメージが人類の中で、この一世紀の間に変化してきたことが上手く語られている。
太平洋はかって、日付変更線によって「世界の切れ目」であった。それは「世界の果て」でもあった。
しかし、現在は太平洋上の貿易量と旅行者数は極端に増加している。つまり、太平洋は「つなぐもの」としての役割を担っているのである。考えてみると。我々が近い関係と思っている親子、兄弟、夫婦、師弟、友人などの間にも思いがけない広さを持った太平洋が存在しているとも思われる。それはいつも「太平」とは限らない。
「つなぐもの」として作用させるためには、それ相応の努力が必要であろう。
(「おはなしおはなし」より)
しかし、多くの事実の中のどれをいかに書くかということで、それは「おはなし」性をもってくる。
「おはなし」としての歴史という意味で感心させられる本は、フランク・ギブニー著「太平洋の世紀」である。
本書の魅力は「おはなし」を形成する中核として「太平洋」が取り上げられている点にある。
「太平洋」というイメージが人類の中で、この一世紀の間に変化してきたことが上手く語られている。
太平洋はかって、日付変更線によって「世界の切れ目」であった。それは「世界の果て」でもあった。
しかし、現在は太平洋上の貿易量と旅行者数は極端に増加している。つまり、太平洋は「つなぐもの」としての役割を担っているのである。考えてみると。我々が近い関係と思っている親子、兄弟、夫婦、師弟、友人などの間にも思いがけない広さを持った太平洋が存在しているとも思われる。それはいつも「太平」とは限らない。
「つなぐもの」として作用させるためには、それ相応の努力が必要であろう。
(「おはなしおはなし」より)