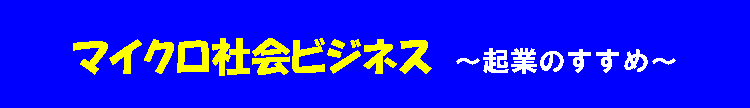「工夫して、心くだくる想いには、花鳥風月みな料理なり」湯木貞一の詠です。
工夫を凝らして、相手のことを思えば、すべとのものがもてなしとなる。
料理とは、その人の生き方が形になったものかも知れません。
一品一品に、ぼくの全てが入っている感じ。
一つひとつの素材にも、生産者の情熱や気持ちが込められています。
そんないろいろな要素を全て集めて、一つの形にするのが料理だと思います。
だから絶対に気が抜けないんです。
By徳岡邦夫
(プロフェッショナル仕事の流儀7 File No.21より)
HOME > 仕事の流儀
究極の料理とは
目指しているのは、レシピのように見えるものではなく、人がともに生きつづけるために必要なものを提案するということです。
同じメニューでも年配の人と若い人は嗜好が違うはず。
それを形にするのが料理だと思っているんです。
でも、勝手にそれを出して喜ばれるとは限らない。
だから、「私どもでは、量や味付け、切り方などが選べるサービスがあります」とお知らせする。
料理人は、細かなオーダーを見て、お客様のことを思いながら料理をつくる。
お客様は、期待が膨らんで出てくる前から美味しく感じられる。
そんなふうに、お客様とサービス係、料理人とが気持ちを通わせることが、理想の料理に近づくのだと思います。
By徳岡邦夫
(プロフェッショナル仕事の流儀7 FileN o.21より)
同じメニューでも年配の人と若い人は嗜好が違うはず。
それを形にするのが料理だと思っているんです。
でも、勝手にそれを出して喜ばれるとは限らない。
だから、「私どもでは、量や味付け、切り方などが選べるサービスがあります」とお知らせする。
料理人は、細かなオーダーを見て、お客様のことを思いながら料理をつくる。
お客様は、期待が膨らんで出てくる前から美味しく感じられる。
そんなふうに、お客様とサービス係、料理人とが気持ちを通わせることが、理想の料理に近づくのだと思います。
By徳岡邦夫
(プロフェッショナル仕事の流儀7 FileN o.21より)
こだわりを捨てる
徳岡の祖父は、昭和初期、和食の世界に旋風を起こした湯木貞一。
「最高の食材をさりげなく」という演出にこだわり、料理人として初の文化功労
者となった。
湯木は一代にして高級料亭を全国各地に構え、日本料理界にその名をとどろかせた。
徳岡が料理の道に入ったのは15歳のとき。
大阪や東京の姉妹店で修業を重ね、やがて、頭角を現す。
7年後、修業を終えた徳岡は、意気揚々と嵐山に戻った。
しかし、周囲の反応は冷ややかだった。
ベテランの板前たちの陰口が聞こえてきた。
「苦労知らずのお坊ちゃん」
一時は、ノイローゼみたいになった。
そのころ、店にも異変が起きた。
バブル崩壊で、接待客が激減し、売上が大きく落ち込んだのだ。
料理長をはじめ、10人の料理人が見切りをつけ辞めていった。
その結果、35歳の徳岡が、料理長になった。
しかし、落ちはじめた客足は止まらない。
経営会議に出るたびに、怒鳴られた。
「お前がいるからだめなんだ」。
「吉兆は三代目になって、つぶれた」といううわさも流れた。
根も葉もないうわさ話が、徳岡を奮い立たせた。
すがるような気持ちで、スタッフに客の声を拾ってもらった。
間もなく本音が聞こえてきた。
若い客は、和風のおさえた味を単調で物足りないと感じていること。
日本酒よりも、ワインやシャンパンに合う料理を好む客が、増えていること。
こだわってきた祖父の料理は、時代に合わなくなっていることに気づいた。
「吉兆はこうあるべきだ、とか湯木貞一はこういう人とか、にこだわっていたん
ですね」
徳岡はなりふりかまわず、新たな料理に取り組んだ。
次第に、日本料理の枠にとらわれない、新しい味が生まれ始めた。
ある日、客の一人が言った。
「料理に勢いが出てきたね」
追い詰められて、こだわりを捨てたとき、初めて開けた新しい道だった。
(プロフェッショナル仕事の流儀7 File No.21より)
「最高の食材をさりげなく」という演出にこだわり、料理人として初の文化功労
者となった。
湯木は一代にして高級料亭を全国各地に構え、日本料理界にその名をとどろかせた。
徳岡が料理の道に入ったのは15歳のとき。
大阪や東京の姉妹店で修業を重ね、やがて、頭角を現す。
7年後、修業を終えた徳岡は、意気揚々と嵐山に戻った。
しかし、周囲の反応は冷ややかだった。
ベテランの板前たちの陰口が聞こえてきた。
「苦労知らずのお坊ちゃん」
一時は、ノイローゼみたいになった。
そのころ、店にも異変が起きた。
バブル崩壊で、接待客が激減し、売上が大きく落ち込んだのだ。
料理長をはじめ、10人の料理人が見切りをつけ辞めていった。
その結果、35歳の徳岡が、料理長になった。
しかし、落ちはじめた客足は止まらない。
経営会議に出るたびに、怒鳴られた。
「お前がいるからだめなんだ」。
「吉兆は三代目になって、つぶれた」といううわさも流れた。
根も葉もないうわさ話が、徳岡を奮い立たせた。
すがるような気持ちで、スタッフに客の声を拾ってもらった。
間もなく本音が聞こえてきた。
若い客は、和風のおさえた味を単調で物足りないと感じていること。
日本酒よりも、ワインやシャンパンに合う料理を好む客が、増えていること。
こだわってきた祖父の料理は、時代に合わなくなっていることに気づいた。
「吉兆はこうあるべきだ、とか湯木貞一はこういう人とか、にこだわっていたん
ですね」
徳岡はなりふりかまわず、新たな料理に取り組んだ。
次第に、日本料理の枠にとらわれない、新しい味が生まれ始めた。
ある日、客の一人が言った。
「料理に勢いが出てきたね」
追い詰められて、こだわりを捨てたとき、初めて開けた新しい道だった。
(プロフェッショナル仕事の流儀7 File No.21より)
料理を食べて、感動で涙を流す
うちの店は一人あたり五万円いただくわけですから、美味しくて当たり前。
お客様に感動してもらって、また来ていただくために、一生懸命やっているわけ
です。
料理人もサービスの人も、庭掃除の人も、電話を受ける人も全員で。
だったら、感動して泣けるようなサービスや料理を考えようではないかと。
そうはいっても、本当に泣かれるお客様がいるとは思っていなかったのです。
ところが、初年度で三人、三年後には八人の方が泣かれた。
日常とは異なる空間やサービス、料理、さらには時間の流れといったものを演出
しています。
いつもより時間をゆっくり感じながら、過去の自分を振り返ったり、
久しく会っていない人を思い起こしたりする。
そして、今の自分と比べて、そのギャップで涙が出るのだと思います。
By徳岡邦夫
(プロフェッショナル仕事の流儀7 File No.21より)
お客様に感動してもらって、また来ていただくために、一生懸命やっているわけ
です。
料理人もサービスの人も、庭掃除の人も、電話を受ける人も全員で。
だったら、感動して泣けるようなサービスや料理を考えようではないかと。
そうはいっても、本当に泣かれるお客様がいるとは思っていなかったのです。
ところが、初年度で三人、三年後には八人の方が泣かれた。
日常とは異なる空間やサービス、料理、さらには時間の流れといったものを演出
しています。
いつもより時間をゆっくり感じながら、過去の自分を振り返ったり、
久しく会っていない人を思い起こしたりする。
そして、今の自分と比べて、そのギャップで涙が出るのだと思います。
By徳岡邦夫
(プロフェッショナル仕事の流儀7 File No.21より)