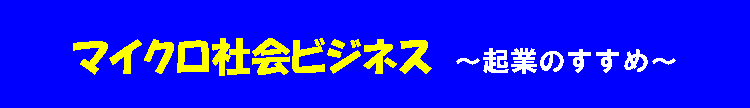高度経済成長の時代。木村さんは農薬と化学肥料に頼る大規模農業を目指した。
しかし、妻とともに、農薬による炎症に悩まされ始めた。
ある日、立ち寄った書店で、一冊の本に出合う。
農薬も肥料も一切使わない、自然農法の本だった。
木村さんは、この方法でりんごをつくろうと決めた。
二か月が経ったころ、りんご畑におびただしい害虫が発生した。
さらに、病気が追い打ちをかけ、秋にはすべての葉が落ちた。
一年経ち、二年経ち、さらに四年経っても、実はおろか花さえ咲かなかった。
りんごが採れなければ収入はない。
生活費を稼ぐために、キャバレーの呼び込みをやった。
雑草を食べ、食費も切り詰めた。
心の中で、二人の自分が葛藤していた。
「もう諦めろ」という自分と、「もう少しの辛抱だ」という自分。
(プロフェッショナル仕事の流儀13 File NO.35より)
HOME > 仕事の流儀
いかにして経済的に成り立たせるか
この仕事を始める前は、りんごを実らせるだけではなく、どこで買ってもらえるかまで考えなければなりませんでした。
まずは、りんごを実らせてみようと、階段を上がるような気持ちでやってきたんです。
経済的には、売上金額は重要ですが、そこから費用を差し引いて残る金額を大きくできれば持続できるのではないかと考えました。
私の場合は、手作業で用が足りているし、働き手も家族だけだから、コストはよその数割でしょう。
それに、生産量は一般の八割ですが、虫や鳥による被害が少ないのでカバーできています。
どんなすぐれた栽培方法でも、それで生活ができなければ続けることができません。
しかし、このやり方で経済的にも軌道に乗せられることがわかった。
いまでは、この栽培方法をみなさんにお勧めしているわけです。
By木村秋則
(プロフェッショナル仕事の流儀13 File No.35より)
まずは、りんごを実らせてみようと、階段を上がるような気持ちでやってきたんです。
経済的には、売上金額は重要ですが、そこから費用を差し引いて残る金額を大きくできれば持続できるのではないかと考えました。
私の場合は、手作業で用が足りているし、働き手も家族だけだから、コストはよその数割でしょう。
それに、生産量は一般の八割ですが、虫や鳥による被害が少ないのでカバーできています。
どんなすぐれた栽培方法でも、それで生活ができなければ続けることができません。
しかし、このやり方で経済的にも軌道に乗せられることがわかった。
いまでは、この栽培方法をみなさんにお勧めしているわけです。
By木村秋則
(プロフェッショナル仕事の流儀13 File No.35より)