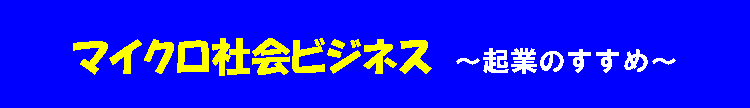2年をかけて丁寧に落ち葉を取り除くと、遠州の石組が姿を現した。
その調和のとれた美しさに圧倒された。
遠州の技術を自分のものにしたいと強烈に思った。
遠州に関する古文書を探し出し、必死に読んだ。
そして、修復にとりかかった。
ようやく納得のいく庭ができたときには、10年の歳月が流れていた。
いにしえの姿を取り戻した遠州の庭。
それはただ淡々と自然に溶け込んでいる簡素な庭だった。
声高に主張していないのに、遠州らしさが匂い立つ。
北山は、そこに庭師の極意を見た。
~己を抑えてこそ、心は伝わる~
(プロフェッショナル仕事の流儀14 File No.40より)
HOME > 仕事の流儀
北山安夫のターニングポイント ~10年に及ぶ庭との対話~
自分を出さず、主張しないことで人の心を動かす。
北山の哲学は、ある庭との10年に及ぶ対話の末に生まれた。
父親が植木職人だった北山は、大学卒業後、迷わず庭師の世界に飛び込んだ。
石組の名人と言われた小宮山博康に師事し、庭づくりのいろはを学んだ。
通常10年かかる修行も、わずか4年で独立の許しを得て、自信満々で会社を立ち上げた。
しかし、世間は甘くなかった。腕があるだけでは若い庭師に仕事は来ない。
寺の庭掃除で日銭を稼ぐのがやっと。親の援助で食いつないだ。
3年後、人生を大きく揺さぶる仕事が入った。
京都・東山にある圓徳院。名園として名高い北庭を修復する仕事だった。
庭は名匠・小堀遠州の手による枯山水。
長らく手入れがされていなかったため、樹木は伸び、石組も落ち葉に埋もれていた。
自慢の技術を存分にふるえると、勇んで現場に入った。
伸び放題になっている樹木は、必要ないと見るや、根元から切り落としていった。
だがある日、住職に呼び出され、怒鳴りつけられた。
「なぜその木が植えられているか、お前は深く考えたのか」
その言葉にはっとなった。
庭師がその木を植えた意図まで、思いが及んでいなかった。
この庭ととことん向き合おうと決めた。
つづく
(プロフェッショナル仕事の流儀14 File No.40より)
北山の哲学は、ある庭との10年に及ぶ対話の末に生まれた。
父親が植木職人だった北山は、大学卒業後、迷わず庭師の世界に飛び込んだ。
石組の名人と言われた小宮山博康に師事し、庭づくりのいろはを学んだ。
通常10年かかる修行も、わずか4年で独立の許しを得て、自信満々で会社を立ち上げた。
しかし、世間は甘くなかった。腕があるだけでは若い庭師に仕事は来ない。
寺の庭掃除で日銭を稼ぐのがやっと。親の援助で食いつないだ。
3年後、人生を大きく揺さぶる仕事が入った。
京都・東山にある圓徳院。名園として名高い北庭を修復する仕事だった。
庭は名匠・小堀遠州の手による枯山水。
長らく手入れがされていなかったため、樹木は伸び、石組も落ち葉に埋もれていた。
自慢の技術を存分にふるえると、勇んで現場に入った。
伸び放題になっている樹木は、必要ないと見るや、根元から切り落としていった。
だがある日、住職に呼び出され、怒鳴りつけられた。
「なぜその木が植えられているか、お前は深く考えたのか」
その言葉にはっとなった。
庭師がその木を植えた意図まで、思いが及んでいなかった。
この庭ととことん向き合おうと決めた。
つづく
(プロフェッショナル仕事の流儀14 File No.40より)