恵日山常楽院は始め御影堂(みえいどう)と呼ばれ、遍照寺中興開山
宥日上人が隠居(閑居)されたところであった。上人はこの寺で時を過 ごされるうち、77才の正月13日(文政4年)その行方がわからなくなった。 その時この井戸の端に履物が脱ぎそろえられてあったため、さてわと井 戸替えをしてみたが、出てきたものは古い石塔一つだけだったので、こ の石塔を井戸のほとりに建て置き上人の形見としてあがめまつった。の ちに御影堂を建立してその仏壇に安置したと伝えられている。 上人は不思議な霊力を具え、ことに火伏せの霊力が著しかったとされ るため、ご命日には近郷近在からこの井戸の水を汲みに来る者群をなし たといい、今もなおお水取りに来る人が跡を絶たないという。 昭和59年度設置。平成17年度修復。  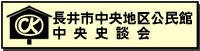
|
All Rights Reserved by nagai_ck
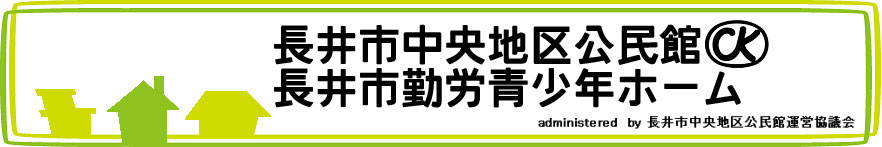

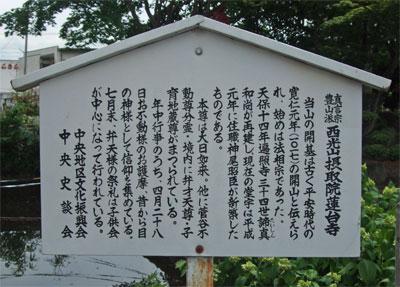

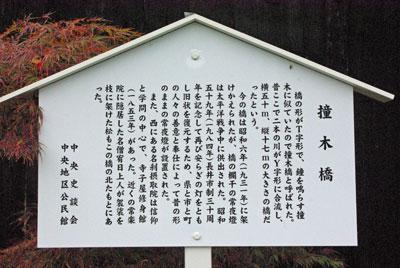









同じ境内にあった白山寺(明治3年廃寺)が別当寺であった。明治初年
の神仏分離に際し、白山神社と改め宮村一村の鎮守とした。明治6年
宮村大火で類焼した後、土蔵造りの本殿に再建した。昭和6年3月不審
火により社殿焼失、氏子の寄付によって9月に再建したのが現社殿で、
棟梁は黒坂秀吉であった例祭には十日町子供会の獅子舞が行われる。
昭和61年度設置。平成5年度再設置。平成29年度修復予定。