|
平成17年1月25日、宮城県志津川で開催さた
第16回「リアス四季海岸観光塾」で基調講演いたしました。また、「広域観光トーク」では助言者としても参加させて頂きました。 今回の全体テーマは「今、そしてこれからの観光産業」でした。 それを受けて「観光産業は感動のドラマ!!」と題して講演を行いました。 今回の開催趣旨にもあるように、気仙沼・本吉圏域は海と山に囲まれ三陸の豊かな物産と観光資源に恵まれたところで、この自然を生かし観光を広域的に、また産業化やまちづくりの面からも考えて学び合う場として位置付けられており、圏域の活性化を目的として行われています。 これは、私がかねてよりお話ししている「広域連携の重要性」を正に実践されていることで、大変嬉しい取り組みです。 今回で最後とのことでしたが、とても内容のある塾であったのではないかと評価しております。 |
|
平成17年1月24日に、社団法人塩釜法人会の平成17年新春講演会・賀詞交歓会が行われ、
「ピンチはチャンス!逆境を克服し、夢を実現する! 『観光と農業を結びつけたユニークな商品づくり』と題して講演いたしました。 講演前に、塩釜市内の観光施設や商店街を歩くことが出来ました。実際に自分の肌で、体で、言葉で、目で町を感じることが出来ました。 塩釜には有名な塩釜神社があり日本有数の漁港があり、名所旧跡も豊富です。恵まれた地域資源がたくさんあります。ただ少し残念だったのは時節的なものか、「元氣・活氣・氣力」をあまり感じることが出来ませんでした。 これはどこの地域でもあることですが、外部から見ると地域資源は豊富でも、内部にいる住民サイドはそのことを余り理解していないことが多いものです。 とても良い資源も、点でのみ存在してはその魅力は半減致します。点を線にして、面にしてこそ地域は輝きを増すと考えます。 そして、住民1人1人が町に愛着を感じ、セールスマンになることだと考えています。 塩釜にとって必要なのは、横の連携ではないかと講演で指摘申し上げました。 私の実践体験を踏まえた上で導き出した一つの真理ですが、常に「愛と夢(ロマン)」を持ち続けることで、その時の阻害要因を克服することが出来ます。 情熱や頑張り、何度も何度も挑戦する熱意と努力は、未来に対する夢や希望があるからこそ、持続ができるのです。 今回は、終始そういった内容でお話しして参りました。 魅力ある資源がたくさんある塩釜です。今後の取り組みに大いに期待いたしております。 |
|
(5年前に講演した際の助言に対して寄せられました。)
寒中お見舞い申し上げます。 先生には元気でお忙しい毎日をお過ごしのことと思います。 1月7日に町の新年祝賀会があり、私達は町長をはじめ、議員さん、企業の社長さん250名の前で七福神の大黒舞を舞ってきました。笑顔と思いながら緊張の数分でした。 5年前の工藤先生の助言で始まったことを一言挨拶させて頂きました。 〜中略〜 今年も頑張ります。先生の益々のご活躍お祈り申し上げます。 |
|
(岐阜県下JA営農指導員交流会 於:岐阜県岐阜市)
先日は大変お忙しい仲、また遠路はるばる岐阜の地にご指導に来ていただきありがとうございました。 もっともっといろいろな話をお聞きしたいと思っていましたが、十分な時間がとれず残念に思っています。 先生のお話大変参考になりましたし、私が今日の研修会の中で意図することすべてお話いただき感謝しております。 〜中略〜 今「岐阜県の農業の将来をどうするか」といった議論を内部でしているわけですが、いい発想はでていません。「地域興しを」と思うのですが、自分が農家とういう立場から本当に農家はそんなことを考えているのだろうか、と思います。かといって、先祖から預かっている農地は荒らさないよう、何とか守っていかなければという気持ちはどこの農家にもあるようです。 「水田地帯や補助金を考えているところはいい発想は出てこない」と先生は言われました。実は私も何年も前から本県のそうした政策に対し、そう思ってみてきました。本県は水田の生産調整に対し、県と一緒になって取り組み、常に100%以上達成してきましたが、反面売れる米づくりへの取り組みは遅れています。 〜中略〜 私達JAに勤める者は、農業あっての、組合員あってのJAです。黙って見ているわけにはいきません。「JAや中央会は農業、農家のために一定の役割を果たしてきた。」などと客観的なことをいっておられません。後輩のためにも知恵を出さなくてはなりません。 現在、農政部では農政、営農、生活・高齢者、広報の事業を持っていますが、今回は営農事業の中で、営農指導員に元気になってもらうために企画をしたものです。たぶん、多くの営農指導員は先生のパワーをもらって帰ったと思います。 〜中略〜 私の部署では、元気な高齢者づくりを今考えているところです。むしろ、少子高齢化対策として、高齢者の生きがい対策として、地産地消を軸とした地域振興を図ることの方がリスクも少なく取り組みやすいのかな、と思います。 直売所を交流の場として、少数品目の農産物、伝統食品、手づくり食品、加工品へと発展させ、スーパー、百貨店にもない品揃えをし、一大名所としていくことはまんざら不可能ではないと思われます。もちろん行政や地域の異業種と連携することが必要です。 新年度には、こうした視点でまた考えてみたいと思います。その際にはまた是非ご指導いただきますようお願いいたします。 |
|
平成17年1月20日に長野県中野市で講演を行いました。
「命を育む中野市農業を目指すフォーラム」ということで、農業者年金と売れる農業をテーマに行われました。参加者は230名にのぼり会場は熱気にあふれました。 意見発表ということで、地元で積極的に農業に関わっている4名の方のお話を伺い、それぞれの特徴ある取り組みに共感いたしました。 中野市は環境もよく地域資源がいっぱいでした。今後はますます「売れる農業」「面白い農業」を推進していくとのこと。やはり官民一体となっての農業と、それを結びつけた形の観光(一時滞在型)で人を呼び込み、是非「中野市」自体を全国ブランドへ育て上げて頂きたいと思います。今後の活躍に大変期待が持てます。 また、中野市の青木市長との対談が実現し、地元ケーブルテレビでも放映される運びとなっております。 今年5月の豊田村との合併を前に、基幹産業である「農業」そして今後期待が寄せられる「観光」を利用した仕掛け作り、営業戦略の話が中心となりました。 市長の考えた方と私の考え方は相似しており、大変盛り上がった60分でした。 その後は、懇談会ということで特産のきのこ料理のコンテストで入賞した作品の試食会と特産ワインを囲んで、華やかに和やかに時間を過ごしました。大変楽しかったです。 |
Powered by samidare®
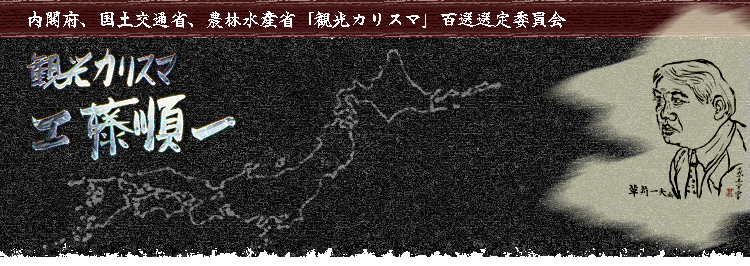




(財)都市農山漁村交流活性化機構の主催で
平成16年度グリーン・ツーリズムビジネススクール
「グリーンツーリズム・マネージメント講座」が行われました。
全国各地、遠くは熊本からも受講生が訪れている講座で、積極的な姿勢をかいま見ることが出来ました。
行政担当者が多かったことから、私が周年観光に取り組んだ当時の状況や時代背景をお話しし、横連携の重要性を強調。
地域興しは、関わる人みんながメリットを享受し儲からなければならないこと。
リーダーになる人には、必ずそれを守る楯になる人が必要であることなどを、お話し致しました。