|
平成17年6月29日(水)に、長野県中野市農業委員会(会長 高橋光芳氏)の皆さんが優良事例先進地研修視察で我が町寒河江市にいらっしゃいました。
中野市へは、今年1月に「命を育む中野市農業を目指すフォーラム」で訪れたばかりです。関係者の皆さんに再会できたことを大変嬉しく思います。 中野市は、長野県の北東部に位置し長野市から電車で30分ほどのところにあります。今年4月に1市1町(旧中野市・旧豊田村)が合併し中野市になりました。気候的には寒河江と同様な内陸性気候で、夏期は30度以上、冬期は−10度以上になるとのこと。昼夜の気温差も大きくて、年間降水量は全国平均を下回る少なさになっています。人口は4万8千人弱で、農家は36.4%という比率。 私のHPでもご紹介したように、中野市農業委員会は「信州農業いきいき運動」と「農業委員会だより全国コンクール」の2部門で全国農業会議所会長賞を受賞しており、農業振興にご努力されているところです。今回の合併により旧豊田村が加わったこともあり、農業委員に女性が7名在籍しております。これは大変珍しいことだと思います。研修には事務局を含む31名が参加されています。 研修スケジュールは以下の通りです。 ●寒河江市農業委員会訪問 寒河江市の農業に関する概況を把握 ●寒河江市チェリーランド管理センター チェリーランド全体説明 ●チェリーランド各施設視察 ●寒河江まち案内 ○中心市街地 … 空洞化防止の戦略 ○花咲フェアー・チェリークアパーク、さくらんぼ友遊館 など 街中を目で足で肌で耳で体感 → 寒河江市と中野市の違いを理解 例:道案内の標識、観光資源の再発見・再認識・掘り起こし、住民参加型イベント 私が今回提案しているのは人をいかに集めるか以上に、地域にお金を落とす、いわゆるどうやって経済効果をもたらすかといったこと。そしてそれが地域活性化に直接結びつく点。例えば、地域おこしイベントは単発ではなく継続性が重要であること。現在寒河江では、第19回全国都市緑化やまがたフェアの跡地の公園を利活用して独自の観光資源に仕立てている。 また、何においてもスピード、決断、実行が重要であり、そのためにも腰の強い粘りあるリーダーを育成する必要があること。 以上の様なことを、お話ししています。 また、天童ホテルで行われた懇親会では乾杯の音頭をとらせて頂くなど、高橋会長さんをはじめ参加された委員の皆さんと活発な交流をさせて頂き楽しい懇談をいたしました。私がこれまで取り組んで参りました様々な事業を成功するためには、悩みや苦労がもちろんありましたが、それを乗り越える秘訣などもご披露でき、農業にかける思いをお話しすることが出来て大変有意義なひとときを過ごしました。改めてお礼を申し上げます。 今後も私でお手伝いできることがあれば、何なりと申しつけて頂きたいと思います。 |
|
(藤島町商工会婦人部がこの度「優秀賞」を獲得したことに対してお祝いを申し上げたことに対する手紙です。斉藤さんとは、5年前に私が講演で助言して以来のお付き合いです。)
前略 先生には益々お元気でご活躍のご様子お慶び申し上げます。 先日は電話をいただき有り難うございました。 こちらからご報告させていただこうと思っておりました。 毎年、商工会女性部のリーダー研修会では、県内四地区6人の主張発表を行っており、今年は藤島町が担当になりました。何を発表したらいいか迷いましたが、これしかないと思い、大黒舞の話をいたしました。5年前、先生の講演会から始まった大黒舞。今年正月の新年祝賀会での披露までの経過と私の感じたことなどです。大勢の前で話をするのは心配で1ヶ月前ほどから憂うつな気持ちになっていました。原稿を見ながらの発表でしたが、終わってほっとしました。始まる前に他の発表者にどんな活動をしているのか聞いたところ、この日のため特産品の開発に取り組んだ所もあったようでした。最優秀の寒河江市はとても良かったです。最後の審査員の批評で、他の地域にはない女性部らしくてユニークな活動で良かったと言われました。12月のチャリティー演芸会では大黒舞を踊る予定です。山形新聞に6月19日の町内さなぶりまつりの記事に私達の踊っている所が載っていました。他の上手な踊りの会があったのですが、ちょっと嬉しいものですね。 また何かありましたら報告させていただきます。先生のホームページのぞかせていただきます。 草々 |
|
理楽社発行の月刊誌「りらく」2005年7月号の、特集「寒河江界隈旨いもんの旅」と題して我が町寒河江がクローズアップされています。
「さくらんぼ狩りは、体験、体感、感動です。」の見出しのもと、さくらんぼのシーズン前に実際に寒河江へおいで頂き、私が色々とお話申し上げた内容を掲載頂きました。 書店・コンビニエンスストア(東北地区)で発売中です。是非一度ご覧下さい。 りらく7月号 |
|
平成17年6月23日の河北新聞朝刊に「目指せ『山形ブランド』」県産品認証制度 県が創設へ、と題した記事の中に私のコメントを掲載頂きました。
コメントは短く掲載されておりますので、内容的には以下を参照ください。 今回のブランド化は山形産の商品の付加価値が高まる意味で、とてもよい取り組みだと思っています。しかしその一方で、消費者あっての商品、つまり消費者の理解を得られない、売り手側だけを意識したブランドで、実際に売れなければ机上の空論となってしまい、ただ単に言葉だけが独り歩きすることになると思います。その辺りは十分な配慮が必要だと思っています。 |
|
平成17年6月9日〜10日、天童温泉ホテル王将に於いて平成17年度東北地区社会就労センター協議会総会が行われ、10日の午前中の講演会で私が講演して参りました。
当日の演題は「発想の転換を求めて〜生かす智慧と工夫〜」約50名の方々を前に様々にお話させて頂きました。 「元氣」こそが発想の原点である。固定観念や先入観を捨てること。本当に考えて智慧を絞ると、新しいアイデアが生まれる。それには、これまでとは違った視点(外から)でものを見ることが重要。 何か始めるときに、失敗したらどうする?誰が責任を取る?そういったことが阻害要因になり、新しい発想やアイデアは決して生まれない。管理者は、部下を育てるにしても、長所を見る努力をし褒め称えること、部下の楯となり応援することででその人材を「人財」にしていく必要がある。 私が従事してきた観光農業で開発した商品(バラ風呂、生きたアイスクリーム、雪中いちご狩り、サクランボオーナー制 等々)は、その頃の時代背景の元どんな発想から生まれ、何をお客様にアピールしたのか? それには、お客様のニーズに則した価値観を提供し、納得、満足いく商品であること。通年型から周年型へ移行し、それを可能にするために異業種とのネットワークを構築したこと。商品に物語、ストーリーを入れてドラマづくりをおこなったこと。ドラマとは愛であり、ロマンであり、希望、笑い、涙、汗、苦労、温もりといった人間の感情を揺さぶるもの。そういったものを盛り込めば人は心打たれ感動する。もちろん、それを売り込むための営業力(工夫・戦略)や信頼関係は重要であるが、まずは困難に屈せず前向きにいつも「元氣」でいることが肝要。 現代は、決断にスピードが求められている。特に高度情報化(IT)は、HPを駆使して商品提供を簡単に行える時代をもたらし、ネット上で商品売買を行える。顧客層は地元に限らず多岐にわたる。これは口コミの時代とも言える。そういった意味でも、協議会と異業種とのネットワーク構築が強く望まれるところだ。 (私が取り組んだバリアフリーの例も少しお話しています。) 寒河江では、昭和63年からバリアフリーのさくらんぼ狩りを開催。その頃民間にはまだ整備されていなかったトイレなどは、行政施設のモノを利活用。これは官民一体となって事故防止に心掛けたもの。たかがもぎ取りでも、高齢者、障害者といった方々にも満足感を提供したいと、サクランボの着色に関してもみんなに協力頂き反射シートを敷き込んで上枝と下枝の差をなくした。 時代の流れにより、社会全体の変革と同様に福祉環境も大きく変化しております。そんな中で行われた講演会で、少しでも私の話が今後の活動にお役に立てば幸いです。 |
Powered by samidare®
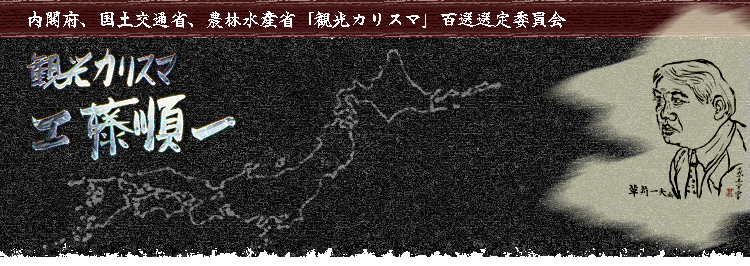




今年はさくらんぼの生育の遅れなどにより出荷が通常より約1週間ほどずれ込みました。その間、雹の被害があったり、梅雨の時期だというのに夏のような暑さ(30度以上)が続いたこともあり、さくらんぼによる初夏の季節感を感じることがなかったように思います。わずか数週間のさくらんぼ狩りも生産計画がくるうとダイレクトにさくらんぼ狩りの入込み客数にひびき、今年は減少傾向にありました。
また、昨今は団体客から個人客がレジャーを楽しむ形に移行し、インターネット(携帯)を介して各種情報を検索し収集して予約をするといったパターンが目立つようになりました。今年の場合、団体客も宿泊での利用より日帰りが多かったようです。その他にも、個人で農園を確認し電話して生産地の生育状態や動向まで関心を持つなど、とても敏感な反応が見られます。ITによる情報化社会が相互交流を促すと言った図式を見て取れます。言い換えれば、ITに対応できていない生産地(生産者)は早急なる意識改革が必要とされているということです。そしてもうひとつ言えることは、消費者が納得し価値を感じて満足しないと購買には繋がらなくなっているということです。施設は時代のニーズそれも個人ニーズを把握することに努力しない限りは、今後の観光客の入込数にも大きな影響を及ぼすことになりそうです。
高速情報化時代に、今後どういった戦略でさまざまな事業を結び付けていくのか?これは山形のさくらんぼだけに限らず、次代の大きなキーになるようです。