「つや姫」が全国デビューを果たしました。
私も毎日もりもり食べてます。
この「つや姫」や「はえぬき」「ササニシキ」
「コシヒカリ」「あきたこまち」…などなど。
古くから品種改良に改良に改良に改良に…改良を重ねた結果、
私たちがおいしく頂けているわけなんですね。
(現在も毎年のように新しい品種が登場しているということで、
改良の改良の改良…はこれからもずっと続けられるのでしょうかね?)

まるで家系図のようです。
品種改良は、よりおいしく、寒さや病気に強く、
雨風に負けない強いお米になれ!ということで、
現在ある品種の特徴を考えながら掛け合わせるんだそうです。

つや姫の家系はこんな感じでした。
「つや姫」や、上記であげたようなおいしいお米のルーツのひとつに
明治時代、山形県の庄内地方で生まれた
「亀ノ尾」という品種があげられます。
この「亀ノ尾」ですが、ある人物の汗と涙の結晶なんです。
阿部亀治といって、庄内の小作農でした。
当時の山形県の稲作は思わしくなく、
あちこちに倒れた稲が見られる状態でした。
とりわけ、冷害に悩まされていました。
(猛暑も作物に影響を及ぼしますが、
気温があがらないことも稲の成長に影響するんだそうです)
そんなとき、参拝に訪れた神社の近くで
亀治は倒れた稲のなか、
無事に起立していた3本の稲を発見し、持ち帰ります。
明治26年のことでした。
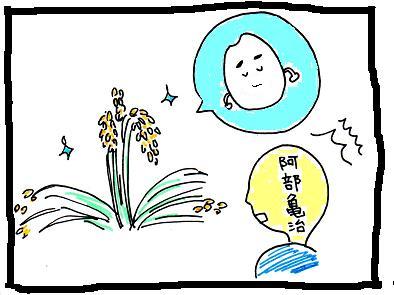
研究熱心だった亀冶。
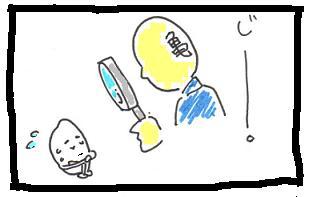
失敗しても…

あきらめず、様々な工夫を凝らします。

明治30年となり、この年は
ウンカという害虫、そして冷害も発生します。
亀冶の稲の運命やいかに…。

悪条件にも関わらず、
全国平均を上回る収穫に成功します!!
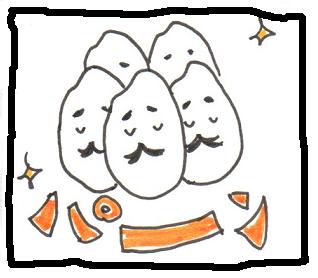
友人である太田頼吉が亀治から一字とり
「亀の王」と名付けるのはどうかと提案したところ、
亀治は「王ではなく、せいぜいしっぽ(尾)だ」
と言ったそうです。

(他にも「種もみ」を譲ってほしいという人々に無料で譲るなど、
謙虚でお金もうけにこだわらず、農業に熱心な人柄だったようです。
すばらしい!)
こうして「亀ノ尾」は誕生し、
その後20年間、山形県内で最も多く作られる品種になるのでした。

前述したとおり、「亀ノ尾」の優れた遺伝子は
現在の品種、「はえぬき」「ササニシキ」「コシヒカリ」「あきたこまち」
もちろん、「つや姫」にも引き継がれています。
亀治の熱意があってこその、おいしいごはんなんですね。
<続>
・・・・・・・・
参考文献
つや姫HP
亀家~かめはうす~
つたえたいふるさとの100話
社団法人農林水産技術情報協会HP
宮城米コメナビweb
お米とごはんの基礎知識
Wikipedia



この記事へのコメントはこちら