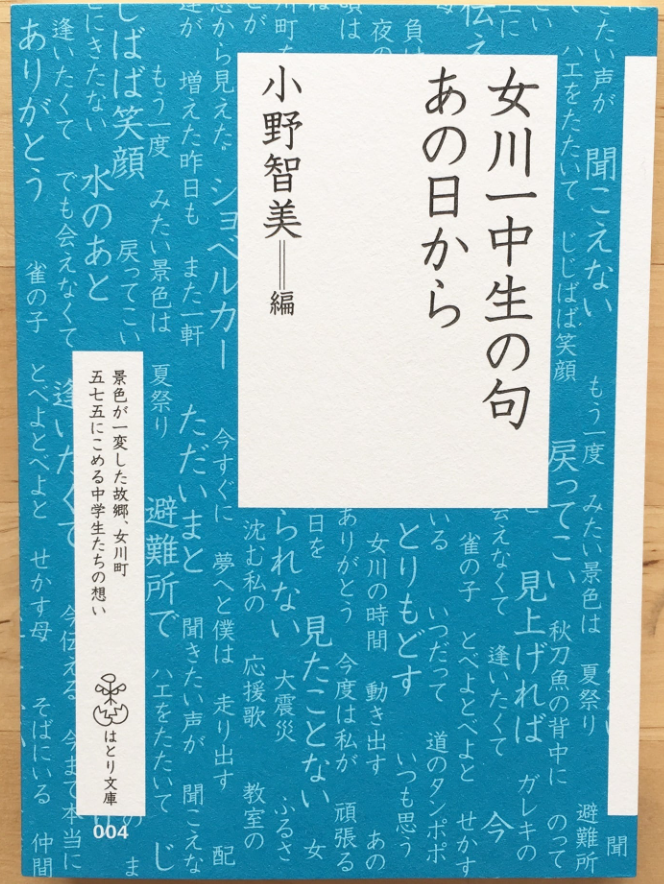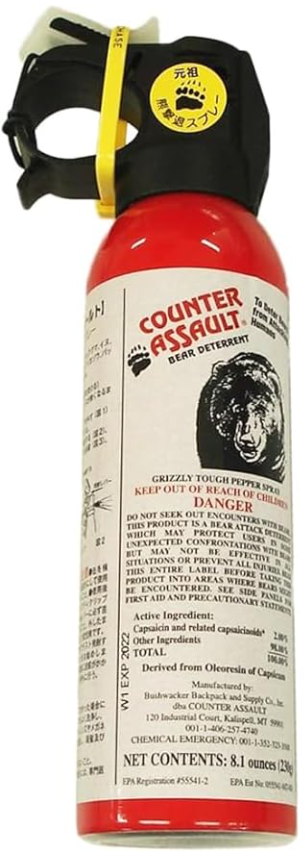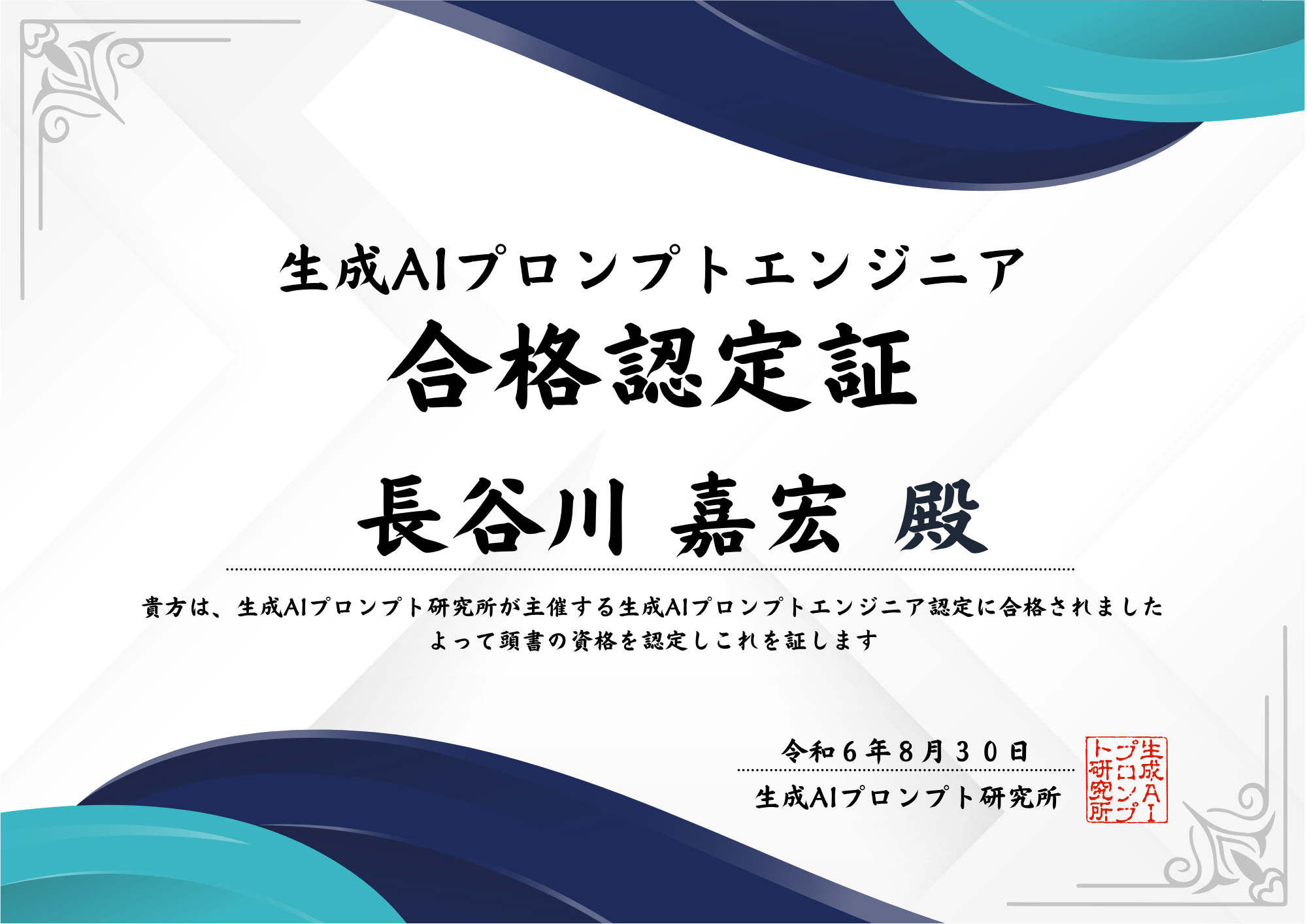
生成AIの黎明期とはいえ、進んでいる人はどんどん進んでいて、まったく手をつけてない
人との差は広がるばかりです。
AIよりもHI(ヒューマン・インテリジェンス)の方が大切だ!などと豪語したいところ
ではありますが、どちらも大切であることは間違いなく、時代の波に乗り遅れないよう
ひとまずこの検定合格に向けて諸々勉強しました。
先日、ある生成AIエンジニアの方から興味深い話を聞きました。
私たちは、本人が自覚しているかどうかは別として、すでにAIを多方面で活用している
わけですが、意識的にこれを使っている人の割合は、日本全体で10%に満たない、と。
まだ一度も使ったことがない人が9割!
日本が諸外国からどんどん遅れをとってきていて、国力の低下が明らかなのは皆さんも
肌で感じ取っていると思います。どうやらAIに向き合ってない人の割合も日本という国が
坂を下っていることを物語っている! 間違いなく。
私自身、得意な分野でないことは百も承知なので、せめて多少は自分も勉強し、そのあと
は、得意な人と連携して、社内はもとより周りの人々のそして東北のAIリテラシー向上の
ために動こうと思っています。
具体的には、「はじめてのAIセミナー」というものを仙台でリアル開催します。
講師は、弊社とつながりの深いプランナーの柴田聖一氏(株式会社ステップアップコミュ
ニケーションズ代表取締役)と生成AIのプロ安永智也氏(株式会社ステップアップコミュ
ニケーションズ)のお二人です。
詳細は追ってご連絡します。乞うご期待!