川西もさくらの開花期になりました。田んぼではトラクターのエンジン音が鳴り響き、いよいよ農作業も忙しさを増してきました。
チューリップの蕾も大きく膨らみ、いよいよガーデナー達の花壇作りの始まりです。 さて、花屋さんやホームセンターに背丈の低いダリア(ミニダリア)がカラフルな花を咲かせながら「花苗」の出回る季節となりました。5月の連休に入ると植え付けが始まりますが、まだ寒さが残っていますので、降霜の心配が無くなる時期(5月中旬以降)まで待つことが良いのかと思います。 「ミニダリア」は、草丈が30cm前後で花径も5〜10cm程の可憐ダリアです。昔からよく栽培され「姫ダリア」とも呼ばれ親しまれ、花壇やプランターなどの栽培に適した身近で育て易い草花のひとつです。(写真はミニダリア・ピンボール混合の種子袋) ...続きを見る |
『ダリア』の色彩が人々の心を強く引き付けている。
ダリアが、草花の楽しみ方を紹介する園芸専門誌に掲載される機会が増えている(「NHK趣味の園芸」7月号でもダリアが取り上げられます)。ガーデンフラワーとしてのダリアの人気が定着して来ました。また、近年急速に伸びているのが切花としての利用法。日持ちがしないために人気が低かったダリアだが、デザイナーの目に留まり、フラワーアレンジメント関連の雑誌やテレビCMなどに登場すること増えたことが引き金となっている。 写真の切り花は、熱唱(赤)、マナーサンセット(オレンジ)、エイミーK(ピンク)、マジックモーメント(白) ...続きを見る |
ダリア染めが始められています。ハンカチやスカーフ、ネクタイなど。
先日、秋田国際ダリア園で「素敵に染め上げられた帽子」を見た。話によると「ダリア染め」教室での残った液に淡いベージュの帽子を入れてみたら、淡い黄色に染め上がったとのこと、見るととても上品でいい感じ。 ダリアの花びらが染料となるようです。豊かな色彩を持つダリアの中でも黄色やオレンジ、赤花の花びらが良い色合いを作り出すとのこと。深い色合いには開発者の苦労と愛情の跡が滲み出ています。 ダリア染めは、山形川西町、秋田市雄和、福島塙町(いずれもダリア園がある)などで行なわれています。 |
ダリアとジョゼフィーヌ
天竺牡丹日記ではナポレオン1世時代のダリアについて取り上げていますが、ダリアがその研究によって大きく変化し、社会に認められる転機が1800年前後のこの時代です。(天竺牡丹日記Vol.23) 花言葉『移り気』(天竺牡丹日記Vol.24) ナポレオン妃となった「ジョゼフィーヌ」は、パリ郊外のマルメゾンの邸宅にバラやダリアの珍しい品種や各地から集められた草花を植えていました。 特にダリアはお気に入りで、満開のころにたくさんの客を招いて園遊会を開いていました。ある日のこと、侍女の一人が大きく開いたダリアを指指し、「私に分けてくださいな」と言うのです。 しかし、ジョゼフィーヌは決して一輪の花も分けることはしませんでした。 侍女は諦めません。ダリアを手入れする庭師を買収し(金と色仕掛け?)、まんまとダリアの球根を手に入れる事に成功するのです。侍女は手に入れた球根を育て、自分の庭で見事なダリアの花を咲かせるのです。その噂を聞きつけたジョゼフィーヌは、庭師や侍女、関わった貴族を解雇、破門すると共に、急激にダリアへの興味が冷めてしまいました。 このジョゼフィーヌの気持ちの変化が、ダリアの花言葉のひとつ「移り気」の語源と言われます。 庭師は首になり出て行くときに、「花は多くの人に見られ、愛されてこそ本当の花ではありませんか。独り占めされた花は幸せでしょうか」と言葉を残しました。 ...続きを見る |
多種多彩なダリアの分類方法について
ダリアは花径の大きさによる分類と併せて、花弁の形(花型)によっても分類されます。 ダリアはキク科の球根草、コスモスやマリーゴールド、百日草などもキク科の仲間たちです。 ダリアははじめコスモスのような一重(花弁8枚)の可憐な花びらを持つ花でしが、交雑を繰り返す中で、二重の花が生まれ、多重、八重に進化していきました。「ダリア・コッキネア」「ダリア・インペリアリス」など原種と言われる種類が数種類存在しますが、いずれも一重咲きから多重咲き花となっています。 花びらの多重化の中で、ダリアの花びら(花弁)は変化を見せるのです。 一重咲き(シングル)、アネモネ咲き、デコラ咲き、カクタス咲き、ポンポン咲き、ボール咲き、オーキッド咲き、コラレット咲きなど18種類に分けられます。 写真は「ジェシカ」、中輪カクタス咲きの名花です。 なお、詳細な花型の区分法については「AGS」さんのHPをご覧下さい。 http://www.agsfan.com/dahlia/knowledge.html |
『日本ダリア会』
江戸後期に国内に持ち込まれたダリア(初めは天竺牡丹と呼ばれる) 日本国内におけるダリアの最初の流行期は、種苗が本格的に輸入され、また国内の愛好家の中でも採種と品種改良が始められた明治時代の後期。 北海道から九州地方まで都市部や城下町を中心に広まってゆきます。 そん中、ダリア展示会の開催などを期に大正14年に日本ダリア会が発足しました。その後、園芸家や種苗業者、愛好家が集い、お互いが切磋琢磨し合いながら本格的な栽培研究と普及が始まりました。 戦中戦後、住環境の変化に伴い広い土地を必要とするダリアは、苦しい時代を経験するのです。そんな中、ダリア会も幾度か活動の中断を余儀なくされました。 平成17年2月、岩佐園芸研究所・岩佐吉純氏(横浜市)のご尽力で「日本ダリア会」は復活するのです。(岩佐氏は理事長に就任) ...続きを見る |
趣味の園芸で「ダリア」が!
NHK趣味の園芸7月号で「ダリア」が取り上げられました。(7月30日放送予定) 千葉の山口まりさんが寄稿され、放送では品種の選定や栽培法についてレクチャーをなされます。 山口さんは、千葉の品種改良家・黒相惇氏のご子息で永くダリアの普及に関わっておられます。 黒相さんは既に亡くなられておりますが、切花に最適な中小輪種の改良に努められ、数多くの品種を世に送り出しています。国内のダリアの切花生産は、関東を中心とする小輪系を山形の大輪系に2分されますが、小輪系切花ダリアの殆どが黒相さんの作品です。 また、山口まりさんは千葉を拠点に活躍されていますが、日本ダリア会の中でも中心的な存在です。 http://www.nhk-book.co.jp/engei/news/dahlia_2004.html |
All Rights Reserved by acocotori
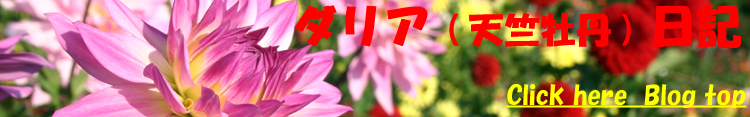















どちらも、キク科の球根草でダリアと良く似ている。(写真はキクイモ)
特に、最近爆発的な人気が出たキクイモの主成分は「イヌリン」であり、ダリアの球根も同じ「イヌリン」である。(イヌリンの含有量が一番多いのがキクイモ)
さて、イヌリンはなぜそんなにも人気なのであろうか。インターネットで検索すると・・・
イヌリンは、難消化多糖類・可溶性食物繊維。低カロリーの消化吸収されない多糖類のことで、胃で分解されず、腸に入りビフィズス菌のえさとなり、ビフィズス菌を増殖、活発にさせる働きがあるとのこと。
ダイエット食品としての効果はもとより、「生活習慣病」特に肥満や糖尿病、高脂血症、高血圧への効能が高く注目されている。
いま、ダリアの食用研究が進められている。