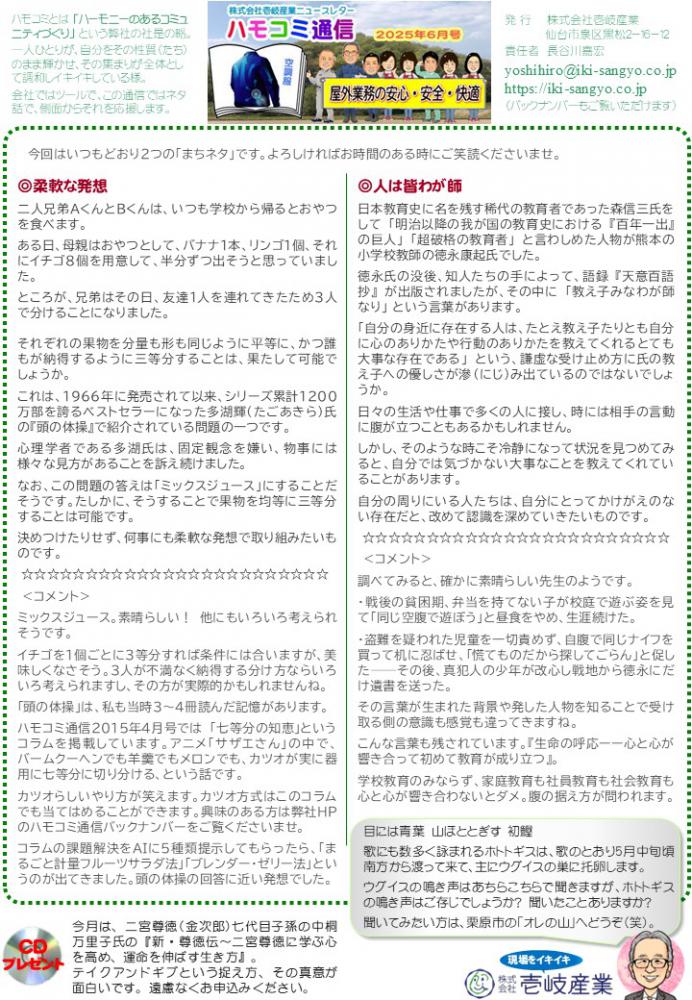生活に取り入れたり、仕事で生かすなどしていただけると本望です。
◎柔軟な発想
二人兄弟AくんとBくんは、いつも学校から帰るとおやつを食べます。
ある日、母親はおやつとして、バナナ1本、リンゴ1個、それにイチゴ8個を用意して、半分ずつ出そうと思っていました。
ところが、兄弟はその日、友達1人を連れてきたため3人で分けることになりました。
それぞれの果物を分量も形も同じように平等に、かつ誰もが納得するように三等分することは、果たして可能でしょうか。
これは、1966年に発売されて以来、シリーズ累計1200万部を誇るベストセラーになった多湖輝(たごあきら)氏の『頭の体操』で紹介されている問題の一つです。
心理学者である多湖氏は、固定観念を嫌い、物事には様々な見方があることを訴え続けました。
なお、この問題の答えは「ミックスジュース」にすることだそうです。たしかに、そうすることで果物を均等に三等分することは可能です。
決めつけたりせず、何事にも柔軟な発想で取り組みたいものです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<コメント>
ミックスジュース。素晴らしい! 他にもいろいろ考えられそうです。
イチゴを1個ごとに3等分すれば条件には合いますが、美味しくなさそう。3人が不満なく納得する分け方ならいろいろ考えられますし、その方が実際的かもしれませんね。
「頭の体操」は、私も当時3~4冊読んだ記憶があります。
ハモコミ通信2015年4月号では 「七等分の知恵」というコラムを掲載しています。アニメ「サザエさん」の中で、バームクーヘンでも羊羹でもメロンでも、カツオが実に器用に七等分に切り分ける、という話です。
カツオらしいやり方が笑えます。カツオ方式はこのコラムでも当てはめることができます。興味のある方は弊社HPのハモコミ通信バックナンバーをご覧くださいませ。
コラムの課題解決をAIに5種類提示してもらったら、「まるごと計量フルーツサラダ法」「ブレンダー・ゼリー法」というのが出てきました。頭の体操の回答に近い発想でした。
◎人は皆わが師
日本教育史に名を残す稀代の教育者であった森信三氏をして 「明治以降の我が国の教育史における 『百年一出』 の巨人」 「超破格の教育者」 と言わしめた人物が熊本の小学校教師の徳永康起氏でした。
徳永氏の没後、知人たちの手によって、語録 『天意百語抄』 が出版されましたが、その中に 「教え子みなわが師なり」 という言葉があります。
「自分の身近に存在する人は、たとえ教え子たりとも自分に心のありかたや行動のありかたを教えてくれるとても大事な存在である」 という、謙虚な受け止め方に氏の教え子への優しさが滲(にじ)み出ているのではないでしょうか。
日々の生活や仕事で多くの人に接し、時には相手の言動に腹が立つこともあるかもしれません。
しかし、そのような時こそ冷静になって状況を見つめてみると、自分では気づかない大事なことを教えてくれていることがあります。
自分の周りにいる人たちは、自分にとってかけがえのない存在だと、改めて認識を深めていきたいものです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<コメント>
調べてみると、確かに素晴らしい先生のようです。
・戦後の貧困期、弁当を持てない子が校庭で遊ぶ姿を見て「同じ空腹で遊ぼう」と昼食をやめ、生涯続けた。
・盗難を疑われた児童を一切責めず、自腹で同じナイフを買って机に忍ばせ、「慌てものだから探してごらん」と促した――その後、真犯人の少年が改心し戦地から徳永にだけ遺書を送った。
その言葉が生まれた背景や発した人物を知ることで受け取る側の意識も感覚も違ってきますね。
こんな言葉も残されています。『生命の呼応ーー心と心が響き合って初めて教育が成り立つ』。
学校教育のみならず、家庭教育も社員教育も社会教育も心と心が響き合わないとダメ。腹の据え方が問われます。