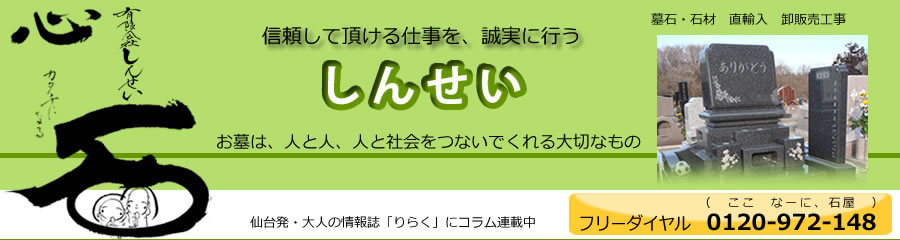先日家族に誕生日を盛大に祝ってもらった私は、これから五十歳後半の人生を淡々と生きて行くことになります。大学生の末息子の就職も決まり、長男も結婚します。それと、広島の義兄の誘いで足を踏み入れた『石の仕事』も、何時しか三十年に成っていました。その様な区切りの年に、誰も経験したことのないような災害が起こり、世の中の流れが変わっていく気がするのは、私だけなのでしょうか。
三十年前、私が入社した会社は、輸入石材を全国の石材店に卸売をすると言う仕事をしていました。創業して十数年が過ぎた頃で、小さなプレハブの事務所では、二十人近い社員がひしめく様に働いていました。その数年前の「オイルショック」の時は驚くほどの量の石材需要が有ったそうで、営業活動をしなくても飛ぶ様に輸入石材は売れたそうです。
しかし、私が入社する少し前から墓石の需要が減少し、それと同時に輸入石材の販売も頭打ちになったようです。営業マンは自分の売上金額を確保する為に、その頃まだ需要が多く有り、輸入材より高額な金額で販売できる国産石材の『お墓』製品を大都市圏の石材店に売って回り、自分の業績を確保すると言う様な状況に成っていました。
その頃(三十年前)の石材業界を簡単に説明すると、山から原石を産出する『採掘業』。その原石を流通させる『石問屋』。問屋から原石を買い取って加工生産し、都市部の石材店に墓石製品を卸す『製造業』。そして、その製品を買い取って消費者に販売・建立する『製品仕入型の小売石材店』と、石問屋さんから直接石材を買って、墓石を加工・販売する『自社加工型の小売石材店』の二通りの小売店が有りました。山石屋・石問屋・輸入業者、そして加工業・小売店と、昔ながらの日本の流通経済がそのまま、そこに存在したのです。
そうした石材業界で、大都市から地方の田舎町まで一番数多くあったのが『自社加工型の小売石材店』でした。そうした店は、各種の石材切削機と石材研磨機、文字彫刻用機械、石を動かすためのフォークリフト、墓石を建立する為のクレーン付きのトラックと建墓専用の道具等、ありとあらゆるものを持たないと出来ない様な仕事です。
それ以前、まだ石材に関する機械化が進んでいない頃は、作業工程の全てを手作業でやっていました。『割・切り・研磨・彫刻』と一つ一つの作業が独立し、それぞれの能力を発揮する職人達が集まって一基のお墓を造り上げていたのです。しかし機械化が進むことによって、ひとつのお店が『販売・加工・建て込み』までの全行程を、わずかな人数の職人で行う様に成ったのです。
それは一人の職人が石材加工の全工程を理解し、作業しなければ成らないと言う事ですから、いっぱしの「石屋さん」と呼ばれるまでには何年も掛かりましたし、また他の業界から思いつきで『石屋になろう』と言って簡単に始められる職業でもなかったように思います。
その当時私が商売させて頂いていた石材店は、「私で七代目だ」とか、「うちの店は江戸時代から続いているよ」と言った様な石材店も多く有りましたし、初代だというお店でも「私は○○石材店で十数年修行して独立した」とか、店毎に代々受け継がれた技能に裏付けされた職人が店を持っていると言う、商売と言うよりは職人の世界がそこには有ったのでした。それは、小さくても繁盛している石材店が多数あり、商売の大きさが店の大きさに比例するものでも無かった事で、実証されていました。
そうした歴史を感じる仕事にも関わらず、中には「なんだ、てめえら石屋か・・」と言った感じの見方をされる人も多く居ましたので、ある面では閉鎖的な業界でも有ったのです。それは何故かというと『死』にまつわる仕事をする人間全てに向けられていた、いわゆる偏見の様なものだったと思います。あの映画『おくり人』の中でも『納棺師(綺麗な造語)』の主人公が友人から罵倒されるシーンが有りましたが、あの様な事は普通にあった事で、よほど技術に自信の有る職人でなければ「わたし石屋です。」と言う顔は出来なかったのです。
『おくり人』の前には『アルゼンチンババア』と言う、役所広司の演ずる石屋が主人公の映画もありました。映画は我々が従事している仕事を皆さんに知って頂くチャンスですし、その事で我々の職業も見直されて来ています。それは、時代と共に商品の形態、流通の方法が変化して来た事にも関係しているのかも知れません。
そしてまた、今度の震災以降は、今までに無い「石屋」が現れてきました。そのことは次回にさせて頂きます。