朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
永林寺開祖の道愛禅師が尊崇した虚空蔵菩薩の御堂は、永林寺があった開山に建立されています。二間四面のお堂で創建は古く、応永5年(1398)といわれています。徳川将軍から五石七斗のご朱印状を受け、由緒ある虚空蔵様として信仰されてきました。
※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら ※分かりづらい場所にあります。地区の方に尋ねるかエコミュージアムルームにお問い合わせ下さい。 →秋葉山エリア(大谷) |
北の村落
なあんだ また雨來るだべ そうだべな けふで十日もならうに重すぎる北國の空模様である この樣に 雨空低くたれ 粟の穂先天を指す秋 それは すざまさしい海浪の迫る豫告ではあるまいか 父(とっ)つあ 行田(なめだ)さ行つて見ろ 穂先 天コふいてるから 俺あ 見たくもない 親も 子も 今年こそと勵ましあひながら たぎる樣な水田の害草(くさ)をとり 稻株(かぶ)の繁出(もで)を數(かぞ)へたのに 仕方がない大根葉(ひば)を納屋にしまふんだ それから飮水を汲んで呉れ 冷雨降る日を 木の根などくべて 膏薬をあぶり 疲れた關節(ふしぶし)にはる おつ母(かあ) 白髪拔いてやるべ 構はないでくれ 針の溝 この暗さでは通らないから―― 野良着繕ふ母も老ひたのか 賣薬袋さげた下にうづくまり 振り向きもせず 荒れた 掌をうごかすのである 野良話は 雨の日を暗くのしかゝつて來る 蕗(ふき) ながい旅から ほこり立つ道をゆられ 歸へつて來た もどかしく どつと かけ込みたい氣持(こヽろ)を支へて やきつけられた 日傘 戻らうか 詫びようか いまさらに 顔のなく歸へつて來て 母を呼ぶこゝろ うかがへば しがみつく絆をゆすぶつて 女人が笑つてゐる 北の村落(2) 押し潰されそうな山峡の村落である 今日は下駄屋のよね坊が賣られて行ったそうな‐‐―あれ も一年足らずで大きなお腹をかゝえて來るだらうよ 前借に前借を重ねて娘を銘酒屋に沈める貧困な村である 今度は何處の娘が 泣寢のまぶたを覺ますだろうか 大雪が祟って稲穂がつんと立つたきり 收穫(とりいれ)のない秋 淋しい田圃の畔で 爺様たちがこぼしてゐる ―――俺達も長生きするでねがつたなア ―――全くだ 祿な飯も食(くら)へられねいで いつそ ―――まあまあ そう云ふたとて どうにもならないし 來春まで待つだね 齢ぼうけや 女子供寒々と殘り ひたむきに 若者が出かせぐ都會の魅力 あこがれがあこがれを引いて 義理さへもなく さびれゆく 村落の光なき夕暮である 昭和七年東北地方を苛んだ冷水害は今や忘れられ ようとしてゐる、忘れてはならない、村を愛す る心は先祖を愛する心だ―――昭和十五年春―― 雲ひくき日に -友人Y君の英霊かへる- 君は 僕の側から 隙間風の様に 征つた とほく 海を越へ 長江のほとりで 任務についた 廻轉する 世界も知らずに すきだつた論説欄も見ずに 固く銃を握ったまゝ また 秋が來て 君もかへつて來た 無言のすがた いたましく 半旗に護られながら いまは なんにも云へない 御苦勞様 御苦勞様 血型 ながいこと カーキ色の從隊がつゞいた 多くの顎紐をかけた戰闘帽の中から おまへは 兄さんと呼んでくれた 章 元氣で行つて來い 握つたおまへの掌は 逞ましくふしくれ 何か どぎついものにおもはれる 前線へ行く兵隊 百千の旗に歡呼するどよめき その中で 握ぎりかへすおまへの掌 章 今日を忘れるな 多くの顎紐をかけた戰闘帽の中に もつとどぎつい その掌を握らせてくれるまで 私は其の日を待つている おまへも忘れないでくれ 海山越へて征つても つながつてゐるものがある ながれるものがある 飢ゑてみろ どいつもこいつも 坐りたい車席(クッション)を 總立になつてゆずりあふ手合(てあい)ども にやにや笑ひながら坐りこんで終ふなら いっそ立たずにそつぽを向けばいゝでないか 色褪せたそれが道徳か 博愛か-世にすねた盲人(めくら)の仁 義と云ふものか 金のカマボコ指輪がなんであらう 狐の襟巻きがなんであらう 隣席(となり)のつゝましい勞働者をみるがいゝ 何故のステーブルファイバーか 何故のふしくれ双手(もろて)であるかを でこぼこの道は 車がゆれるものだ 絶間ない振動が車を壊すのだ 疲れきつた運轉者らがすべての犠牲となる 日毎夜毎 足元から翔けてゆくものの羽叩きを聞け そいつらの諦めきつた虚空への後姿を見送つてやれ さってゆく眞白な翼は なぜ灰色の歳月を忘れたか 凍てついた寒月のあたりになぜ神々は新しい子供の産聲 を聞かねばならぬのか 蒼白い爪を噛んでみろ なんであらうと 飢ゑてみろ 飢ゑてそのあと血を吐いてみろ 錆 背柱の腐れかゝつた生物のやうに ありつたけの力をしぼるモートルを据えて ひとら 油のなかに糧を求める職場である あの頃の心を いげつなくずらせて 今日もまた十分の休憩を無上の生きがひに待つ心 長すぎる作業のあとの休憩ベルが鳴る 必死の廻轉に太息する機械の沈默がある よごれきつた少年工のはしたない談笑が崩れて おれは習ひかけた語學を落し書きする まるであの頃母の白髪を見つけた つまらない感情に似 てゐる 窓ごしにちらつく特務工手の視線にふれて いつかしぼんだ可憐なグルッペの無駄話 今は追ひ詰められたぎりぎりの一日にゐる彼等である 夜があけて 乘りなれた割引電車 はつとする始業の ベル 工長がやけに意張るのだ ――ニグロを使ふ奴等のやうに 味氣ない日課がおまへらのやうにある俺だ いつそ叩きつけたい書類などもある 磨滅させて終ひたいバイト ドリール それがおめおめ今日も犬齒をかんでこらへた やつぱり俺は意氣地がないか 意固地だか ベルが鳴る 始業 油に蝕まれる一日がある グッとスイッチを入れた二十五馬力のモーター あか錆びて シャフトが プーリーが ベルトが廻轉する 工場の 機械の 汚れた菜ッパ服の仲間ら 聞くがいゝ あの古びたモートルのせつない獨白を なに故の 所詮は束縛(しば)られたものの地團駄であらうか ※海野秋芳詩集『北の村落』より抜粋 →夭折の詩人 海野秋芳 |
九月はじめ一枚のCDが届いた。その一週間ほど前の山新に、朝日町が生んだ詩人海野秋芳の詩を、町の有志グループ「燭の会」が朗読しCDに収めたという記事が出ており、早速朝日町エコミュージアムを通して取り寄せたのだった。
海野秋芳については、『やまがた現代詩の流れ-2006/やまがたの詩の存在-』で、鈴木直子氏による紹介文を通してはじめて知った。大正六年(1917)生まれの海野秋芳は十六歳で小学校高等科を卒業し上京、薬局の住み込み店員となる。詩に目覚めたのはこの頃だが、その後泉與史郎に師事し本格的に詩作に取り組み、精力的に作品を発表する。薬局を退職後金属工業所の職工として働くが、腎臓結核で太平洋戦争のさ中、昭和十八年(1943)二十六歳の若さで夭折した。 今回CDとして世に出されたのは、詩人25歳の時に発刊された、唯一の詩集『北の村落』の朗読。町で五年前に開催された「海野秋芳シンポジューム」の参加者の中から数人が集まり「秋芳の詩を読む会」を結成、「燭の会」と名づけ、月一回の集まりで彼の作品を読み解く活動を重ねてきたとのこと。CDには高村光太郎から寄せられた序文と34編の作品すべてを載せたブックレットも添えられている。朗読は、11人の会員がそれぞれ3〜4編を担当しているが、最年少のメンバーは秋芳の大甥にあたる青年で、詩人が亡くなったときとほぼ同じというのも縁のように思われる。 CDからはじめに流れてくるのは、どこか懐かしい想いにつつまれるメロディー。電子音楽による手作りの曲は朝日連峰の裾野を吹きすぎる風のようだ。集中何度か挿入され特注ののテーマ・ミュージックといったところ。 高村光太郎の序文に続いて詩の朗読がはじまる。ふるさとの風景や情景、当時の貧困にあえぐ寒村の様子、その故郷への思慕、労働にたずさわる者の思索、そして戦争への複雑な感情-、様々なテーマの作品が、淡々と、読み続けられる。ドラマティックな展開やパフォーマンス的な表現はほとんどない。感情移入も極力抑えられているように思われる。演劇や朗読のプロ、あるいはセミ・プロ的な人が読めば、ずっと違った〈作品〉に仕上がったであろう。率直に言わせてもらえば、いわゆる‘上手な朗読’とはいえないものもある。また‘正しいアクセント’や‘イントネーション’などにこだわって、注文をつけようと思えばいくらでもつけることはできるかもしれない。が、そんなことはここでは瑣末なことだと思わずにいられない。読み手は、生半可な色などつけずに、それぞれの詩のことば一つひとつをていねいに、いとおしむように読んでいる。むしろそれ故に聴き手は自分なりの秋芳の世界をイメージすることができるといってもいい。 小さな町で制作された素朴な一枚のCDから、海野秋芳はわたし(たち)の宝物」という、会の人々の熱い想いがまっすぐに伝わってきて、手放しで嬉しく、同時に詩人生誕100年にあたる2017年の、詩集『北の村落』復刻版の出版を心から応援したい気持ちでいる。 最後に短い作品をふたつ紹介しよう。 故園 あの頃のほころびを 木綿針でつついて 日向ぼっこの婆さんがいる 土 この生活(くらし)になれても 苔むした無縁墓石に 何の希(ねがい)をかけようか 都会がへりの人見れば ゆらぐこのこころ 聞かないでくれ 粧ひのまぶしさ 百千の金 何になろう 稲穂天を指す秋 一杯の粥すすりあふても しぶとく生き抜いて 俺ら みのりする秋を知っている 『E詩14号』( E詩の会 2009.10発行)より抜粋 |
|
この松永氏の寄稿(山形新聞)が海野秋芳を改めて紐解くきっかけとなりました。
海野秋芳の思想伝える〜農民視点に人間の悲哀〜 詩人/松永伍一氏 書庫で資料探しをしていたら1冊の珍しい詩集が出てきた。海野秋芳の『北の村落』である。昭和16年に鵡鸚社(東京)から出ている。定価1円70銭。 記憶は確かではないが、三十数年前に私が『日本農民詩史』を執筆中に古本屋で見つけたものらしい。その中の一遍を取り上げて論評しただけで、出生地もプロフィルもわからぬまま歳月が過ぎたが、こんどこの詩集が偶然書庫から出てきたのは、海野秋芳の名とかれの詩業がこのままでは消えてしまうぞ、との天の警告に思えて私は義務感につき動かされた。そしてこのテーマで「直言」に一文を草し、末尾に「ご存じの方があればプロフィルを教えて欲しい」と書き添えた。 すると本紙編集部(山形新聞)から電話があって、山形県朝日町の出身で、昭和18年に二十七歳で他界しているとのことであった。「あの詩集1冊を残して夭折したのか」との思いが、私の胸を打った。 『北の村落』は東北農村の凶荒をうたい、土着者の目ではなく離農者の望郷の熱い視線で「村」をあぶり出している。しかもあの時代にあって厭戦のテーマが書かれていたのだ。 詩集が書かれたのは太平洋戦争勃発の年であり、前年は「皇紀二千六百年」を奉祝する行事がつづき「神国日本」を鼓吹するムードがちまたに満ち満ちていた。「美しの日本」をうたいあげるならいざ知らず、農村の貧困や戦がもたらす人間の悲哀を訴えるとなれば、身の危険すら感じなくてはならなかったろう。 後に戦争協力の詩を書くことになる高村光太郎が、この詩集に序文を寄せている。「此処には東北の冷害がある。北方の水の災いがある。天をさす稲穂のなげきがある。そして農民の低いが凄い言葉がある」という書き出しで「低く生きて下を深く見ることこそ銃後をまもる者の責任」とも述べている。「凄い言葉」の中身を読みちがえたのか、意図的にぼかしたのか、作者には「銃後をまもる」積極的な意識はなかったはずである。 つぎに引用する「雲低き日」には「親友Y君の英霊かへる」とサブタイトルがある。 君は 僕の側から 隙間風の様に 征った とほく 海を越へ 長江のほとりで 任務についた 回転する 世界も知らず 好きだつた論説欄も見ずに 固く銃を握ったまま また 秋が来て 君もかへつて来た 無言のすがた いたましく 半旗に護られながら いまは なににも云へない 御苦労様 御苦労様 ほかに厭戦をテーマにした「仏間」(夫を戦死させた姉の狂おしい様を描く)などがあるが、それらの視点が娘を売らねばならなかった農民たちの生存への視点と重なっていることに、私は感じ入った。海野秋芳については本紙の「本の郷土館」シリーズで松坂俊夫氏が触れておられる(平成7年7月8日付)が、この機会に一人でも多くの人々がこの詩人の思想に触れて下さればと、願ってやまない。 (平成 年)山形新聞特別寄稿 松永伍一氏(まつなが ごいち)プロフィール 詩人・エッセイスト。1930年福岡県に生まれる。八女高校を出て中学教師8年、1957年以降文筆生活。文学・民族・美術・宗教など広範囲にわたる評論で知られ、とくに子守唄・農民詩・キリシタン・古代ガラスの研究者として著名。あらゆる文学組織に参加せず。『日本農民詩史』全5巻の大作により毎日出版文化賞特別賞を受ける。テレビ・ラジオ出演も多く、ドキュメンタリー番組の制作にもかかわってきた。趣味の絵画で10回を超える個展を開く。著書には『日本の子守唄』『天正の虹』『散歩学のすすめ』『フィレンツェからの手紙』『老いの品格』『花明かりの路』『快老のスタイル』『金の人生 銀の人生』『感動の瞬間』『モンマルトルの枯葉』など140冊がある。2008年没。 |
もともと、うちのりんごを受粉させるのが一番の目的で飼った。人工授粉では全部くっけるのは大変だからね。さくらんぼに置くようになって、なり過ぎて困るほどなった。(設楽弥八さん/和合平)
ミツバチの花粉交配は、メロンには絶対になくてはならないものだね。蜂以外ではだめだ。人工受粉にしても、百つけて五つ位だけど,蜂だったらまず百発百中だね。(遠藤 理さん/栗木沢) スイカは人工受粉はできない。なるべく葉っぱが根っこから数えて10枚以上のところに実をならせたいけど、その時期には成長が止まらないから、どの花を受粉させたらいいか見当つかねなだ。着果して4、5日してピンポン玉から野球の球ぐらいになった所で調整して摘果するんだ。(長岡寛治さん/上郷) ミツバチを飼う前は、マメコバチを花粉交配用に飼っていた。取ってきた葦を仕掛けておくと、花粉を運んできて卵を産むんだ。次の年の春にそこから生まれて働く仕組みだね。寒い時も飛ぶからいいんだけども、リンゴの花の時に出てくれる確実性がないし、蜂数もミツバチと比べるとまるで少ないからね。(渡辺進太郎さん/送橋) イチゴ、メロン、スイカ、ナシ、サクランボ、モモ、リンゴと、今はポリネーション(花粉交配事業)が増えたね。人間の手は花の成熟が分かってないけども、蜂はちゃんと分かっているんだ。自然界はそうなっているから虫のほうが確実なだ。(多田光義さん/太郎) ミツバチは花の少ない季節以外は、独特の限定訪花性を持っているから、同じ種類の花だけをめぐって働いているんだ。りんごだったらりんご、タンポポだったらタンポポだけを訪花している。足に付けてくる花粉だんごを見ると一色だから分かる。植物にとってはありがたい習性だったなね。自然はうまくできているんだね。(安藤光男さん/宮宿) 取材/平成6年(1994) |
杉山の花山傳夫さんの家には、代々伝わる船曳き絵があります。
舟運が盛んであった時代、酒田や最上川の川港から、荷物を積んだ川船が上流に上る場合、帆(ほ)と綱(つな)を使いました。風のないときや難所の多いところでは、曳き網に頼りました。そのため、各地に綱手道が設けられ、船曳き集落や船曳きを専門とする人々もいたそうです。 この絵について花山さんは、「子どもの頃からあった。いつの時代に手に入れたものかは不明だが、おそらく三百年位前のものかも知れない。舟が描かれず三人の人足衆だけが描かれている点など、大江町の若宮簗所有のものと作風が似ている。」 また、山形大学名誉教授の横山昭男氏からは、「上半身裸で前傾姿勢になり、ありったけの力で曳いているようだ。船曳き人足の実際の様子が生々しく表れている。帰りといっても舟は空ではなく、ある程度沈めて安定させなければならないから、塩などの帰り荷は必要な物だった。重さが足りない時は石や灯篭を積んでいたようだ。 五百川峡谷は瀬が多いので特に大変な場所だったのではないか。船曳きの写真は明治時代のものが少ししかないので、仕事振りを知る上で貴重な絵といえる。」と教えていただきました。 取材 : 平成18年 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
立木にある朝日川河川公園は、川遊びや芋煮会など、最も朝日川と親しめる場所となっています。8月第一週に開催される渓流まつりは毎年大勢の人が参加します。朝日川の川遊びはコシジロアブの出始める8月初めまで楽しめますが、河川公園は周りに林がないためかアブは少ないようです。
※アブは排気ガスに集まりますのでエンジンはすぐに切りましょう。 →アクセスマップはこちら |
現在水田になっているかつての果沼の沼縁には、明応年間(1492〜1500)に旧家佐竹三郎兵エ家が建立した薬師堂があります。傍らには南寿庵や屋敷がありました。婚礼を前にして五百川合戦に巻き込まれるという悲話「弥生姫伝説」の弥生姫と兼通は、薬師如来の祭礼の時、ここではじめて出会ったと伝わります。
→アクセスマップはこちら ※細い農道につき走行ご注意下さい。 |
「八ッ沼七名勝」の一つ。現在は水田になっていますが、天保13年(1842)以降に若宮寺住職盛恬法印が村人の暮らしが豊かになるよう開田しました。小松家文書によると、布山にあった朝日嶽社の僧“山仙坊”という者が沼に入水し命果てたのでそう呼ぶようになったとあります。また、八ッ沼城落城の際、一子兼通と婚約者の弥生姫が落ちのび身を沈め、一族郎党も自害した場所とも伝わっています。
→アクセスマップはこちら ※八ッ沼〜西船渡に至る道路から眺められます。 |
夏草三中堰は、果沼の薬師沼水田に水をひくために、常盤堰の水を分ける水口分水新堰として安政二年(1855)に考えられ、惣代名主阿部与三郎を筆頭に八ッ沼村名主佐竹三郎兵衛が中心となり計画。秋から冬にかけ工事が進められ、翌年の春から夏にかけては岩を切り通し堰路工事に従事しました。旧西五百川公民館(水口)の上まで引かれていた常盤堰の水を、西五百川小グラウンドの下を引き回し、夏草墓地の下を通り、沢を越えて果沼の薬師沼水田に流すルートです。様々な苦難を乗り越え、安政四年(1857)に完成しました。
その後、大正3年(1914)に東北電力・旭発電所(夏草)が完成し、電気沼(発電所の貯水池)から引かれるようになりました。 →夏草三中堰と椹平の棚田(水とくらしの探検隊2005) |
佐竹家住宅への石段を上る途中左側の観音堂は、宝暦の大洪水の時、米沢市春日町の旧家堀江家の守護仏が流れ着いたのを拾い上げて祀ったと伝わります。宝暦9年(1759)建立。五百川峡谷三十三観音第30番札所。朝日町常盤い84-1
※抜粋 /『ふるさと 朝日町散歩』朝日町広報委員会 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら |
|
魚の番人しながら
私が子供の頃、昭和20年代の話だが、夏に、カヌーランドの所の西側の流れをまるっきりせき止めて魚を捕まえることがあった。私の父も、その4〜5人いた仲間の一人で、5年に1回位ずつ、2回やったことがある。コイやヘラブナがたくさんか獲れた。獲りきれない魚を誰かに持って行かれないように、夜通し“えるが汁”(塩クジラ汁)を食べながら、魚も焼きながら、番人として過ごすっていうのも芋煮会の一つだった。 なじみがなかった牛肉の芋煮 青年会とか男女共同でやった芋煮会は、古い明鏡橋の少し上流や、橋の下の川原でやった。そこらにある玉石を重ねて、釜みたいに作って、大きな鍋を載せて、焚き木は流木が山ほどあるから心配なかった。今みたいに、「焚いで悪い、煙だして悪い」という法律もなかったから、もんもん焚いていた。 こんにゃくやじゃがいも、えるがを入れて作るのだけれど、あの頃は余程の収入がないと、えるがなんて買えなかったから、安いほっけを入れたりした。青年会で、えるがを入れられたのは、今の年代でいうと76、7歳くらいの先輩方だな。 それからあの頃、兎(うさぎ)の肉を入れて食べさせられた記憶がある。皮を売るためにどの家でも飼っていた。半年に1回位ずつなめした皮を買いに来る業者がいて、その時の肉を芋子汁にいれたりした。上手な芋煮会だとユウガオも入れたものだった。小麦粉とじゃがいもを練って作る“すっぽこ”も入れた。私などは、今の牛肉の芋煮には余りなじみがない。えるがとか兎とか、鶏や鴨の肉しか食べられなかった。芋子汁と言うよりは、えるが汁とか鳥汁、兎汁だったな。 夏の芋煮会は男女の出会いの場 特に私が小学校四、五年生の頃は、青年会の人たちが賑やかだった。夜中の2時になろうが3時になろうが構わなかった。おまわりさんが来るわけでもないし、青年会の行事だって言えば、夜通し酒を飲んでいられるものだった。好きな者どうしが寄って恋愛の話をしたり、踊ったり、芋煮会は男女をそういう風に導いてくれるような集まりだった。明鏡橋は“男女の出会いの場”って前も話したけれど、橋の下の芋煮会もそんな風だった。でも、私が青年会に入る頃は少し冷めたような感じだったな。 すたれた夏の芋煮会 えるが汁の芋煮会がすたれたのは昭和42年頃だった。理由はやっぱり物が豊富になったこと。それに上郷ダムができたから水が汚くなって、川に行かなくなったこともあるな。私などは昔のきれいな川を見ているから、今はあんまり行く気が起きないね。 お話 : 志藤正雄さん(栗木沢) 取材 : 平成19年 |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum




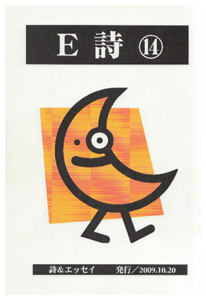














毎年、二百十日の前夜8月31日の風祭りに奉納するほか、8月15日には「送り盆の供養獅子」として永林寺本堂前で踊っている。
この獅子踊りも戦後、後継者難のため解散寸前にあったが、大谷4区(浦小路)の青年たちが、伝統ある郷土芸能の保存継承を決意、幾多の困難を克服して飛躍的に発展させたのである。その努力と功績が認められ、昭和57年(1982)に朝日町無形文化財に、平成3年(1991)には山形県無形文化財に指定された。
※『大谷郷』より抜粋 写真は送り盆の供養獅子
→大谷獅子踊りの由来
→大谷獅子踊り保存会
→大谷獅子踊りの思い出
→映像(Youtube)
→大谷の獅子踊り/佐藤孝男さん
→大谷の風神祭
→小径第15集『大谷風神祭』
→秋葉山エリア(大谷)
→白山神社・永林寺マップ