朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
朝日町で最も身近なブナ林を、今年も地元高田地区の皆さんが案内して下さいます。
途中にはヤマナシの大木や、伝説の残る地獄沼、かつての朝日修験者の古道もあります。カタクリ群生地もみごとです。コース途中の西展望台からは「大朝日岳ビューポイント33」にも選ばれた朝日連峰やAsahi自然観を、東展望台からは宮宿の町並みを望むことができます! 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 日 時 / 5月10日(日)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集 合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) 服 装 / 軽登山スタイル(あれば登山靴、ストックなど) 持ち物/ 飲み物、昼食(おにぎり等)、雨具(小雨決行) 主 催/ 高田区 協 力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、朝日町エコミュージアム案内人の会 問合せ・申し込み / エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月8日(金)まで ※左側のお申し込みフォームもご利用下さい。 →高田のブナ林について →ツイート |
高田山には、朝日町で最も身近なブナ林があります。今年も高田地区の皆さんが案内して下さいます。
途中にはヤマナシの大木や、伝説の残る地獄沼、かつての朝日修験者の古道もあります。コース途中の西展望台からは「大朝日岳ビューポイント33」にも選ばれた朝日連峰やAsahi自然観を、東展望台からは宮宿の町並みを望むことができます! 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 日時 / 5月11日(日)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) その他 / ・山歩きの服装(小雨決行いたしますので雨具も) ・飲み物、おにぎり等ご持参下さい。 問合せ・申し込み / ・エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月9日 ※左側のお申し込みフォームもご利用下さい。 協力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会 →高田のブナ林について →ツイート |
朝日町で最も身近なブナ林を、今年も地元高田地区の皆さんが案内して下さいます。
途中にはヤマナシの大木や、伝説の残る地獄沼、かつての朝日修験者の古道もあります。カタクリ群生地もみごとです。コース途中の西展望台からは「大朝日岳ビューポイント33」にも選ばれた朝日連峰やAsahi自然観を、東展望台からは宮宿の町並みを望むことができます! 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 日 時 / 5月7日(土)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集 合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) 服 装 / 軽登山スタイル(あれば登山靴、ストックなど) 持ち物/ 飲み物、昼食(おにぎり等)、雨具(小雨決行) 主 催/ 高田区 協 力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、朝日町エコミュージアム案内人の会 問合せ・申し込み / エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月5日(木)まで ※左側のお申し込みフォームもご利用下さい。 →高田のブナ林について →ツイート |
今年も最上川五百川峡谷のごみ拾いが開催されます。カヌーの皆さんは川下りしながら、一般の皆さんは水辺を拾います。最後に芋煮を囲んで恒例の交流会もあります!五百川峡谷が好きな方、カヌーに興味のある方もぜひご参加下さい!
日 時 9月26日(日)午前9時〜 集 合 朝日町カヌーランド(栗木沢) 参加費 500円(芋煮会費) 主 催 五百川峡谷クリーンアップ大作戦実行委員会 お問い合わせは →カヌー参加 SD SPORTS 公式サイトより →一般参加 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 Tel 0237-67-2128 協 力 アットホーム →カヌーランドについて →第3回の報告(PC) |
|
27年度は、朝日町の歴史的 建造物について、聞き取り調査や現地見学会、シンポジウムなどを開催しました。11箇所の建造物や、シンポジウムでの基調講演・パネルディスカッショ ンの様子などを収録しました。
※エコルームで頒布しております。 500 円 ※郵送もできます。(送料別)左記のお問い合わせフォームよりお申込みください。 ※売り上げはエコミュージアム活動費に充てられます。 |
エコミュージアムの小径第14集『大朝日岳物語』をついに発刊いたしました。朝日町の母なる山として、平成21年から3年にわたり聞き取り調査やシンポジウムを行ったものでしたが、諸事情により印刷が遅くなっておりました。
内容は、朝日岳を愛した地元写真家阿部幸作氏にはじまり、茅葺き職人や山菜やきのこ採りの名人、材木業者などのくらし、上杉家の朝日岳軍道について、さらに一般から募集した大朝日岳ビューポイント33も掲載しております。 制作にあたりましては多くの皆様にご協力いただきました。心から厚く御礼申し上げます。 ※エコミュージアムルームで500円で頒布中。郵送も致しております。(別途切手代をご負担下さい)☎0237-67-2128 ■朝日町エコミュージアムの小径第14集『大朝日岳』 発行/NPO法人朝日町エコミュージアム協会(A5版38頁) 〔目次〕 朝日連峰初の山岳写真家(阿部幸作氏略歴)・・・1 夫、阿部幸作のあれこれ話し 阿部きよヱさん・・・5 朝日町最後のカヤ葺き職人 白田吉蔵さん・・・9 山と共に生きた日々 長岡周眞さん・・・13 山と共に生きる 長岡幸司さん・・・21 直江兼続が開いた朝日軍道 北畠教爾さん・・・25 幻の道、朝日軍道の踏破記録 山田栄二さん・・・27 大朝日岳周辺の朝日軍道について 花山忠夫さん・・・29 広報誌掲載記事・報告・・・31 朝日町から見える大朝日岳ビューポイント33・・・32 〔発行者あいさつ〕 NPO法人朝日町エコミュージアム協会では、平成二十一年度から三ヵ年にわたり、朝日町のシンボルである大朝日岳に光を当て、「大朝日岳山麓と住民の関わり」というテーマのもとに調査活動やイベント開催を行って来ました。 朝日連峰初の山岳写真家であった阿部幸作氏につきましては、遺された多くの写真やネガ、八ミリフィルムを提供していただき、朝日連峰だけでなく、懐かしい昭和の朝日町に関する写真展や映像のDVD化等貴重な記録を残すことができました。 また、NHKの大河ドラマ「天地人」に合わせて、朝日町エコミュージアム二十周年記念事業として「直江兼続が開いた朝日軍道」のパネルディスカッションでは、今に残る歴史の跡をたどることができました。 平成二十二年には、日本エコミュージアム研究会全国大会が朝日町エコミュージアムで開かれ、その際に阿部幸作氏が遺した映像の上映会を行い、全国の研究者からも注目されました。平成二十三年には、締めくくりの事業として「朝日町から見える大朝日岳ビューポイント33」の募集を行い、町内外の方々から寄せられた地点より33ヶ所を選定させていただきました。 これらの事業と共に大朝日岳山麓に関わる住民の方々のお話をまとめたのが、この冊子です。お読みいただくことで、大朝日岳山麓に暮らす人々について認識を深めていただければ幸いに存じます。 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 理事長 長岡信悦 |
エコミュージアムの小径第14集『大朝日岳物語』をついに発刊いたしました。朝日町の母なる山として、平成21年から3年にわたり聞き取り調査やシンポジウムを行ったものでしたが、諸事情により印刷が遅くなっておりました。
内容は、朝日岳を愛した地元写真家阿部幸作氏にはじまり、茅葺き職人や山菜やきのこ採りの名人、材木業者などのくらし、上杉家の朝日岳軍道について、さらに一般から募集した大朝日岳ビューポイント33も掲載しております。 制作にあたりましては多くの皆様にご協力いただきました。心から厚く御礼申し上げます。 ※エコミュージアムルームで500円で頒布中。郵送も致しております。(別途切手代をご負担下さい)☎0237-67-2128 ■朝日町エコミュージアムの小径第14集『大朝日岳』 発行/NPO法人朝日町エコミュージアム協会(A5版38頁) 〔目次〕 朝日連峰初の山岳写真家(阿部幸作氏略歴)・・・1 夫、阿部幸作のあれこれ話し 阿部きよヱさん・・・5 朝日町最後のカヤ葺き職人 白田吉蔵さん・・・9 山と共に生きた日々 長岡周眞さん・・・13 山と共に生きる 長岡幸司さん・・・21 直江兼続が開いた朝日軍道 北畠教爾さん・・・25 幻の道、朝日軍道の踏破記録 山田栄二さん・・・27 大朝日岳周辺の朝日軍道について 花山忠夫さん・・・29 広報誌掲載記事・報告・・・31 朝日町から見える大朝日岳ビューポイント33・・・32 〔発行者あいさつ〕 NPO法人朝日町エコミュージアム協会では、平成二十一年度から三ヵ年にわたり、朝日町のシンボルである大朝日岳に光を当て、「大朝日岳山麓と住民の関わり」というテーマのもとに調査活動やイベント開催を行って来ました。 朝日連峰初の山岳写真家であった阿部幸作氏につきましては、遺された多くの写真やネガ、八ミリフィルムを提供していただき、朝日連峰だけでなく、懐かしい昭和の朝日町に関する写真展や映像のDVD化等貴重な記録を残すことができました。 また、NHKの大河ドラマ「天地人」に合わせて、朝日町エコミュージアム二十周年記念事業として「直江兼続が開いた朝日軍道」のパネルディスカッションでは、今に残る歴史の跡をたどることができました。 平成二十二年には、日本エコミュージアム研究会全国大会が朝日町エコミュージアムで開かれ、その際に阿部幸作氏が遺した映像の上映会を行い、全国の研究者からも注目されました。平成二十三年には、締めくくりの事業として「朝日町から見える大朝日岳ビューポイント33」の募集を行い、町内外の方々から寄せられた地点より33ヶ所を選定させていただきました。 これらの事業と共に大朝日岳山麓に関わる住民の方々のお話をまとめたのが、この冊子です。お読みいただくことで、大朝日岳山麓に暮らす人々について認識を深めていただければ幸いに存じます。 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 理事長 長岡信悦 ※エコルームで頒布しております。 500 円 ※郵送もできます。(送料別)左記のお問い合わせフォームよりお申込みください。 ※売り上げはエコミュージアム活動費に充てられます。 |
{PDF} ダウンロード 907.6KB_Adobe PDF
朝日町で最も身近なブナ林を、今年も地元高田地区の皆さんが案内して下さいます。 ヤマナシの大木、伝説の地獄沼、朝日嶽修験の古道、カタクリ群生地をめぐり、 西展望台からは朝日連峰、東展望台からは宮宿の町並みを望みます。多くの皆様の参加をお待ちしております。 日 時 / 5月6日(日)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集 合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) 服 装 / 軽登山スタイル(あれば登山靴、ストックなど) 持ち物/ 飲み物、昼食(おにぎり等)、雨具(小雨決行) 主 催/ 高田区 協 力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、朝日町エコミュージアム案内人の会 問合せ・申し込み /エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月2日頃(水)まで ※チラシを上記ダウンロードボタンでpdfが開きます。 |
朝日町で最も身近なブナ林を、今年も地元高田地区の皆さんが案内して下さいます。
ヤマナシの大木、伝説の地獄沼、朝日嶽修験の古道、カタクリ群生地をめぐり、西展望台からは朝日連峰、東展望台からは宮宿の町並みを望みます。今年は第10回の開催を記念して、ワラビ汁の振る舞いもあるそうです。多くの皆様の参加をお待ちしております。 日 時 / 5月7日(日)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集 合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) 服 装 / 軽登山スタイル(あれば登山靴、ストックなど) 持ち物/ 飲み物、昼食(おにぎり等)、雨具(小雨決行) 主 催/ 高田区 協 力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、朝日町エコミュージアム案内人の会 問合せ・申し込み / エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月5日(金)まで ※左側のお申し込みフォームもご利用下さい。 →高田のブナ林について |
{PDF} ダウンロード 907.6KB_Adobe PDF
朝日町で最も身近なブナ林を、今年も地元高田地区の皆さんが案内して下さいます。 ヤマナシの大木、伝説の地獄沼、朝日嶽修験の古道、カタクリ群生地をめぐり、 西展望台からは朝日連峰、東展望台からは宮宿の町並みを望みます。多くの皆様の参加をお待ちしております。 日 時 / 5月6日(月)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集 合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) 服 装 / 軽登山スタイル(あれば登山靴、ストックなど) 持ち物/ 飲み物、昼食(おにぎり等)、雨具(小雨決行) 主 催/ 高田区 協 力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、朝日町エコミュージアム案内人の会 問合せ・申し込み /エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月1日頃(水)まで |
尾花沢丹生の巣林寺10世和尚の開創しました。裏山にありましたが延宝年間(1673~1680)に現在地に移り、二度火災に遭った歴史があります。寺の宝に永正年間~寛文年間(1504〜1672)に長岡久郎左衛門家で使用した大はかりやほら貝があります。また本堂内の蔵に祭られている金毘羅様やおしら様は火災の焼失を免れた貴重なものです。天井絵「花」も有名です。曹洞宗。五百川三十三観音第7番札所
※参考文献/『郷土学習辞典』阿部美喜男編著 『続・山形のお寺』大風印刷発行 ※本堂内の見学は直接お問合せ下さい。祥光院 Tel0237-67-2444 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら |
平成11年(1999)春、朝日町立大谷小学校大暮山分校は、児童数減少に伴い閉校しました。同時に、一世紀の歴史を持つ校舎も取り壊しの予定でした。惜しまれる声も聞かれる中、地元朝日町の若者たち「おもしろ塾」が、なくなるまえに思いで作りをしようと、試行錯誤の中、第一回の白い紙ひこうき大会を計画しました。それは、ただの競技会ではなく、あったかくて懐かしい夏のワンシーンをみんなで作るような、そんな大会をめざすことになりました。
すぐに、使われなくなった花壇にひまわりの種をまき、その苗は地元の小学生たちが水やりをしてくれました。大会一週間前には校舎を大掃除しました。地元の農家の皆さんは、校庭の雑草を刈って下さいました。また、閉校式の折、ぬかるんだ校庭に大量に敷かれていた砕石も重機できれいにかたずけて下さいました。 そして、ひまわりも咲いた大会当日、たくさんの白い紙ひこうきは、ゆっくりと、ふわりふわり校庭の空を気持ちよさそうに飛行しました。 その後、校舎解体は延期され、新しいスタッフによる新実行委員会も結成され、毎年夏恒例のイベントとして開催され人気を得ましたが、平成21年(2009)に惜しまれる中、校舎は取り壊されました。前年に開催された第10回の最終大会には、分校や大会のファンが全国から300人参加し、歴代スタッフも50人、アマチュアカメラマンも数十人押し寄せ、最後の夏を楽しみました。 →大暮山分校と白い紙ひこうき大会の写真 |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum






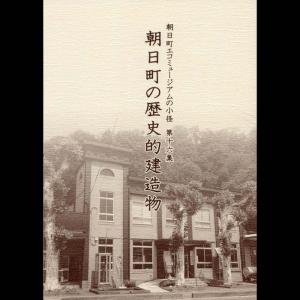
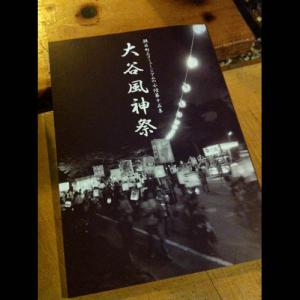
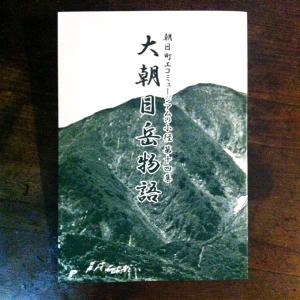
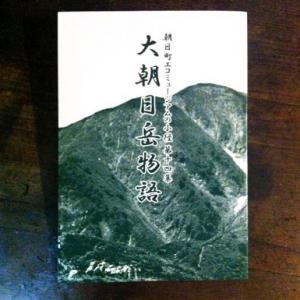











お話 : 能中婦人会のみなさん
平成21年5月、一本松公園売店にて購入。とってもおいしかったです。