朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
昭和39年(1964)最上川で初めての吊り橋として、今平〜大瀬の渡船場に、朝日・白鷹両町により架橋されました。大瀬の「大」と今平の「平」の字を使って「大平橋」と名づけられたそうです。500枚以上の渡り板が貼られた橋上からは、スリルと共に美しい五百川峡谷の風景を眺められ、人気のスポットとなっています。昭和の終わりにはNHKテレビの人気ドラマ「おしん」の撮影にも使われました。
→アクセスマップはこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
この追分石は、大沼浮島経由で出羽三山にお参りする人達のための道標でした。上部には大日如来(湯殿山権現)を表す梵字が記され、右側に文政5年壬午年(1822)大や村、中央に「右大ぬま山、左よねさハ」と刻んである。
もとは山の上の旧道に建っていたものが何回かの道路改修で現在地に移動したといわれています。 ※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら |
明治時代の大土木工事。寒河江市、中山町、山辺町の水田を潤す用水のための取水堤が設けられました。
四ノ沢頭首工とともに、山形盆地の農地には相当量の五百川峡谷のきれいな水が利用されています。 →アクセスマップはこちら ※国道287号線から用のはげ下に見ることができます。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
{PDF} ダウンロード 214.7KB_Adobe PDF
お話 : 北畠教爾氏(朝日町史編纂委員) 〔なぜ朝日軍道が必要だったのか〕 天正年間、庄内地方が上杉家の領地になりました。その後、上杉家は慶長3年(1598)に豊臣秀吉によって、所替えを命ぜられ、越後の国から会津へ移されます。越後・北信濃を削られまして、庄内と佐渡と長井・会津・仙道の方が領地になりました。120万石ということで、石高はぐんと増えて五大老の一人になるんですが、今まで、越後と繋がっていた庄内が切り離されます。それで庄内と置賜の経営にあたっていた直江兼続にとって、両地方を結ぶ連絡路がぜひ必要だということになるわけです。それが朝日軍道ということになります。(地図参照) 兼続は庄内を治めるために、出羽三山の力を利用しようとして、湯殿山に沢山いろんな物を納めたり、寄進したりしています。さらに、佐野清順という腹心の坊さんを羽黒山に派遣しますが、文禄4年(1595)には寂光寺法頭清順という羽黒の別当に就任し、羽黒全部を押さえたことになります。その後、清順は、関ヶ原合戦の後出羽三山から追われ、朝日軍道を通って米沢へ逃げます。米沢では笹野観音の別当になり、後には定勝の侍者として儒教の先生になっています。 〔置賜の史料に見られる朝日軍道〕 慶長4年(1599)上杉家の家臣である春日右衛門が、朝日軍道の番人頭だと思われる源右衛門にあてた黒印状によると、朝日軍道のことを「庄内すく路」と書いてあります。「直路」と書いて「すぐろ」と言ったのでしょう。また、その小屋番をさせるにあたり、檜材で曲げ物をつくったり、材木を切り出したり、狩猟をするのに係る税金を免除するということと、田地を持たず、百姓でない者がいたなら、だれでも山の小屋に連れて行って番をさせろということを命じております。 朝日軍道の入り口である長井市草岡の青木家所蔵文書によると、同じく慶長4年に、春日右衛門が、軍道の案内役をしてくれた草岡村の修験者や村人5人に対して、苦労をかけたので役義(租税や課役)を免除した記録があり、その後約200年経った寛政8年(1796)になっても、子孫に対して先祖が貰った褒美をそのまま認めている安堵状の記録もあります。 〔朝日町の史料に見られる朝日軍道〕 慶長4年(1599)上杉家の家臣である春日右衛門が、朝日軍道の番人頭だと思われる源右衛門にあてた黒印状によると、朝日軍道のことを「庄内すく路」と書いてあります。「直路」と書いて「すぐろ」と言ったのでしょう。また、その小屋番をさせるにあたり、檜材で曲げ物をつくったり、材木を切り出したり、狩猟をするのに係る税金を免除するということと、田地を持たず、百姓でない者がいたなら、だれでも山の小屋に連れて行って番をさせろということを命じております。 朝日軍道の入り口である長井市草岡の青木家所蔵文書によると、同じく慶長4年に、春日右衛門が、軍道の案内役をしてくれた草岡村の修験者や村人5人に対して、苦労をかけたので役義(租税や課役)を免除した記録があり、その後約200年経った寛政8年(1796)になっても、子孫に対して先祖が貰った褒美をそのまま認めている安堵状の記録もあります。 お話 : 北畠教爾氏(朝日町史編纂委員) 朝日町エコミュージアム20周年記念事業(09'11.08) パネルディスカッション「直江兼続が開いた朝日軍道」より ※上記ダウンロードボタンで印刷用のpdfファイルを開けます。 |
町民から寄せていただいた宝報告書(約1000点、現在も募集中)をデータベースに、大テーマに精通する町民の皆さんや関係する機関からの聞き取り調査を主にしています。学術面では朝日町教育委員会や各分野の学術者の皆さんに、ご協力をいただいております。
調査報告はエコミュージアムノートやガイドブックに編集しています。 →エコミュージアムノート(PCサイト) |
朝日町の花「ヒメサユリ」は、棚田を見下ろす一本松農村公園で見ることができます。昔は家畜用にいつも草を刈って日当りを良くしていたのでいたる所で見られたのだそうです。種を蒔いてから6年でやっと一輪花を咲かせます。一本松公園は地元「ヒメサユリ保全の会」の皆さんの活動により、昔と同じ風景を楽しむことができるようになりました。見頃は5月末から6月初め頃。毎年ひめさゆり祭りも開催されています。
長岡嘉一郎さんのお話 →「町在来種の栽培を」ヒメサユリ愛好会の取り組み →棚田とヒメサユリ見学会(PC) →アクセス |
{PDF} ダウンロード 247.3KB_Adobe PDF
朝日連峰のブナの原生林や高山植物に魅せられ、「朝日のカモシカ」の異名をとった朝日町が生んだ山岳写真家。 昭和24年(1949)より西五百川村常盤に写真店を営むとともに、朝日連峰の写真を撮り始める。昭和26年(1951)に故安斉徹博士(山形大学教授)の磐梯朝日国立公園指定のための調査に同行したのがきっかけで、大朝日岳の美しさ、魅力にとりつかれる。 「写真技術はいい腕もさることながら、シャッターチャンスだ。動かぬものはともかく、流れのある被写体は2度同じものを撮ることはできない。」(毎日新聞より)と、山には3台のカメラを持って、気象が織りなす大自然をなんとか写真にしようと、毎年十数回、合計300回以上朝日連峰に通い、多くの写真を撮影する。 特に昭和27年(1952)旧郵政省の磐梯朝日国立公園記念切手シリーズの「朝日岳」「月山」の原画に選ばれた時は、県内の多くの人々が喜んだ。 昭和57年(1982)に発表した「朝日連峰 四季と植物」(高陽堂書店刊)は朝日連峰最初の本格的な写真集であり、「学術資料としても高く評価されるだろう。」(元県立博物館長 結城嘉美氏談)など多くの方面から関心を呼んだ。 氏は山岳だけでなく朝日町の原風景や風物も数多く撮影し、3万枚以上の写真を撮ったといわれる。 趣味も多才で、文筆、焼き物制作、刀剣、骨董などに造形が深く朝日町の文化活動に多くの足跡を残した。 略歴 大正13年(1924) 西五百川村常盤に生まれる。 昭和19年(1944) 海軍を志願、舞鶴海兵団に入隊。 昭和20年(1945) 終戦後、復員する。 昭和23年(1948) 東京神田の写真館に助手として就職。 昭和24年(1949) 帰郷後、西五百川村常盤に写真店を開店。(東京へ修業に通いながら) キヨエさん(西五百川村太郎)と結婚する 昭和25年(1950)12月 朝日岳の組み写真が全日本観光写真コンクール1位入選。 昭和26年(1951) 磐梯朝日国立公園指定のための調査に同行し朝日連峰の広大無辺なブナの原生林や高山植物に魅せられる。 日本写真協会観光写真展特選。 昭和27年(1952) 磐梯朝日国立公園記念切手の原画(大朝日岳と月山)として採択される。 昭和27(1952)〜昭和56年(1981) この間、朝日連峰に毎年十数回のぼり寝袋とパンとカメラを持って寝泊りして山岳風景や高山植物の写真を1万枚以上撮り続け、県内各地で写真展を開催する。 昭和56年(1981)8月 産経新聞山形版に「涼線・大朝日岳をゆく」を30回にわたり連載する。 ラ・ポーラギャラリーで「朝日連峰・光と闇」の写真展開催。 この写真展がきっかけとなって、写真集の出版が決まる。 昭和57年(1982) 「朝日連峰・四季と植物」をA5判高陽堂書店より発刊、県内外の多くの山岳愛好者に好評を博する。 昭和62年(1987) 長い間の統計調査員の活動に対し「藍綬褒章」を受章する。 平成7年(1995)11月30日 72歳で死去。撮影総数は3万枚以上にも及ぶ。 →第一回阿部幸作写真展 →『朝日連峰 四季と植物』(高揚堂書店) ※上記ダウンロードボタンで印刷用のpdfファイルを開けます。 |
|
|
意外なことに大谷地区は朝日連峰を近くに見る事ができる場所です。猿田越峠や日光山の麓にかけてがビューポイントとなっています。また、たくさんの白鳥が餌を探しに大谷の水田を訪れる場所でもあります。3月下旬まで見ることができます。
→アクセスマップはこちら |
意外なことに大谷地区は朝日連峰を近くに見る事ができる場所です。猿田越峠や日光山の麓にかけてがビューポイントとなっています。また、たくさんの白鳥が餌を探しに大谷の水田を訪れる場所でもあります。3月下旬まで見ることができます。
→アクセスマップはこちら →秋葉山エリア(大谷) |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum
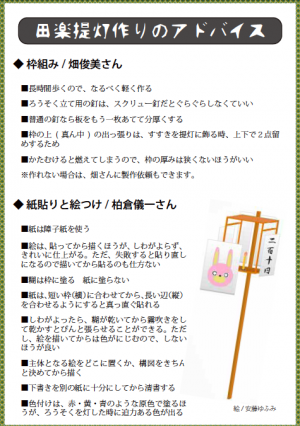




















上記ダウンロードボタンより印刷用pdfを開けます。↑
→大谷の風神祭
→小径第15集『大谷風神祭』