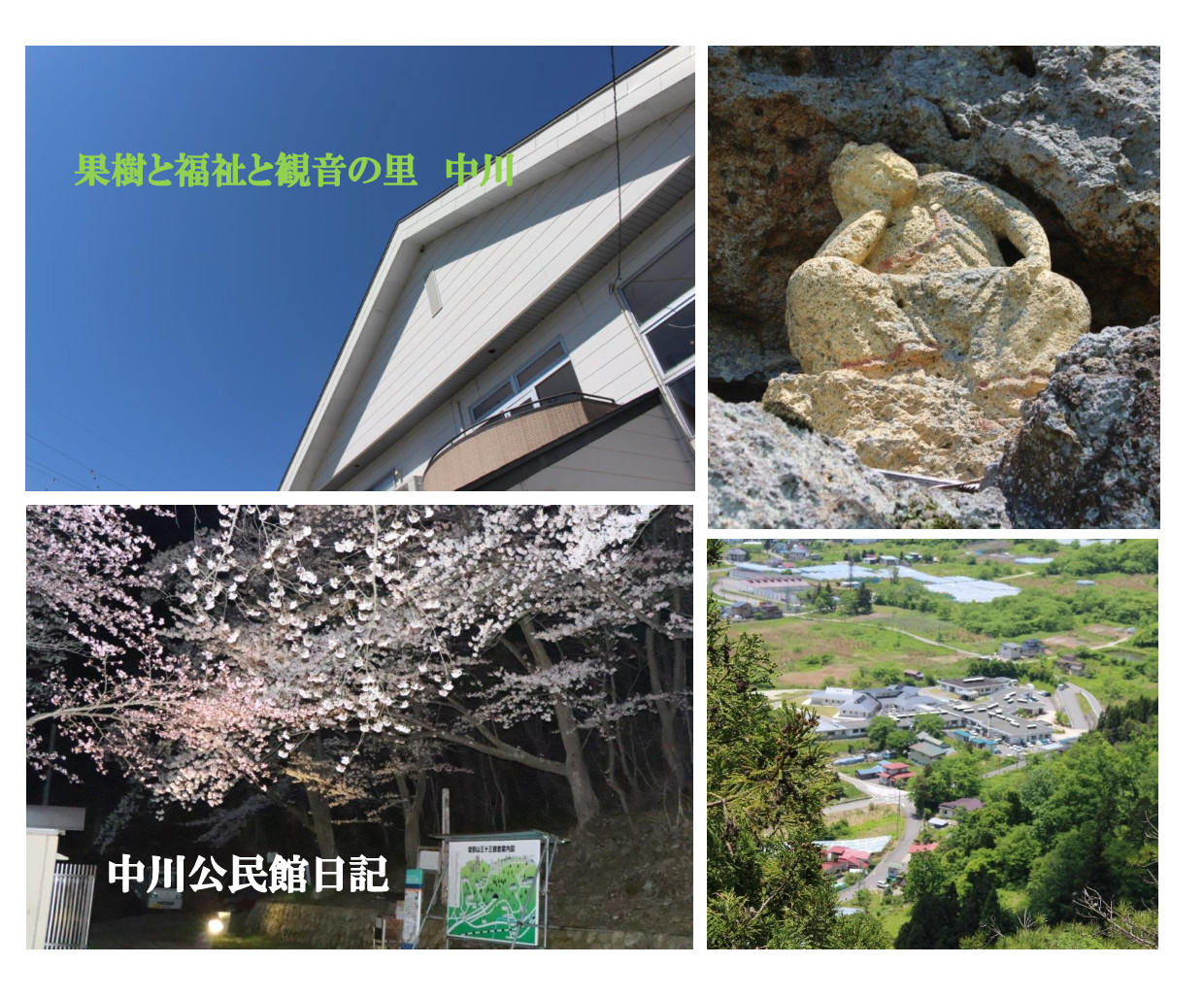国道13号を赤湯から山形に向い、鳥上坂を越えると右側に独立丘陵が見えます。
中世には野中森館があった場所で、地元では「森こ山」と呼んでいます。
(字名が中ノ森なので、中ノ森館跡とも云います)
「米沢事跡考」によると、野中森は粟野十郎藤原義広の後裔(子孫)で粟野十郎左衛門尉宗次※1の父が隠居した館と伝えられています。
周囲を大谷地に囲まれ防御としていました。
享保の絵図には「蒲生氏※2の舘跡」と記してあり。近くには「首塚」と記されていますが、首塚の場所は定かではありません。
参考文献:赤湯町史・山形県歴史の道調査報告書
※1 16世紀の伊達氏家臣で赤湯にあった二色根城主と云われています。
※2 天正19年(1591)奥州仕置により伊達氏は転封、蒲生氏の領地となりました。
以前紹介した宝山塔の大沼家は蒲生氏の家臣で、この地に残り百姓になりました。