|
平成18年2月8日(水)から9日(木)、カシオペア連邦本物食材消費推進会議向けの産直等に対する改善提案と講演及び意見交換会を行って参りました。
講演テーマは「地域資源(地域農産物)の活かし方について」でした。 レジュメ内 ●「いま、商品に求められているもの」では、消費者の心をいかにつかむか?をお伝えしました。 ●「企画、決断、実行」では、兼ねて私が開発した「さくらんぼ丼」「菊(もってのほか)薬膳料理」「菜花一夜一本漬」「生きたアイスクリーム」等を例に挙げながら、産地と季節感を売る手法をご紹介しております。また、最近どこの地域でも取り上げている「地産地消」ももっと旬にこだわり、食彩にこだわり、食物の健康的な効能なども重要だとお話しいたしました。 ●「リサーチの重要性」では、フルに五感を使ってのリサーチを行い、その情報を活かして商品開発に臨むことを強調しております。特に1歳〜15歳までの乳幼児及び児童から学生は、率直な食味感覚を持つために貴重なモニター的存在となります。私自身の経験でも、この世代に好評だった商品は確実にヒットしています。 ●「異業種とのネットワークの構築=共存・共生」では、関わる方々みんなにメリットのもてる関係性をお話しています。特に官民が一体となることにより生まれる相乗効果は目を見張るものがあります。 ●「人材→人財」づくりこそが、鍵」では、地域住民みんながトップセールスマンになりうることをお伝えしながら、何気なくさりげなくプライドを捨てて自然にとけ込み、感謝の気持ちと心地よいホスピタリティーで対応することの重要性を述べました。 |
|
平成18年2月27日(月)於:東京都港区 三会堂ビル 石垣記念ホールで、第5回地域特産物マイスターの集いが開催されました。主催は日本特産農産物協会で、参集者としては、地域特産物マイスター認定者、農林水産省(本省・地方農政局特産担当者)、各都道府県(本庁、地方事務所、農業改良普及センター特産担当者)、市町村、農業協同組合、関係団体等でした。
当日は「元気のあるところに未来が見える・これからの農業を語る」をテーマに、約1時間お話いたしました。 平成17年度地域特産物マイスター認定者は18名。 山形県からは金山町の栗田和則さんが「楓の樹液」で、庄内町の山澤清さんが「ハーブ」で認定されました。それぞれの商品を拝見させて頂くと、商品を開発するまでには多くのご苦労があり、また努力されてきたことが伝わってきました。 これまでの認証人数ですが、全国で118名で、年度別には以下の通り。 平成12年度 19名 平成13年度 20名 平成14年度 23名 平成15年度 19名 平成16年度 19名 認定及び登録に関しては、以下の規程があります。 (1)地域特産物の栽培、加工等におおむね10年以上携わっている実践的な農業従事者、農産加工関係者等であって、次の各要件を満たす者をマイスターとして認定する。 ア.地域特産物の栽培・加工技術等に卓越し、その技術の伝承と開発に意欲的であること イ.地域特産物の産地育成を支援する役割を担えること この度の講演では、パワーポイントを使用してこれまで寒河江で開発した観光商品を写真でご覧頂いております。 <紹介した商品> ○雪中いちご狩り ○以外菊(もってのほかきく)摘み ○菜花摘み(一夜一本漬け) ○体験そば打ち ○虫取り体験 ○もってのほか長寿風呂 ○バラ風呂 ○生きたアイスクリーム(9年11ヶ月で300万個達成) ○キムチ(韓国の味を日本風にアレンジ) ○さくらんぼ丼(お腹いっぱい食べたいという声に応えて開発) ○菊花を使ったお膳 当日配布レジュメから、お話ししたキーワード ●発想の転換の重要性 (1)先入観、固定観念を捨てる (2)地域資源の再発見、再認識 (3)アイデアを裏付ける根拠(ストーリー展開) ●リサーチの重要性 (1)消費者のニーズ・価値観の把握 (2)いま、商品に求められているもの 夢、愛、遊び、癒し、本物、安全、安心、季節感、健康 等 ●企画・決断・実行を急ぐ (1)3年一昔 → 30日一昔 (2)産地(季節感)を売る話題づくり 地産地消、地笑、地商 (3)官民一体となった取組み 官民それぞれの特性の理解と利活用 「縦割機構」→「横の連携」 (4)常に情報発信で公開を(マスコミ・タウン誌・インターネットの利用) ●時代が農業に求めているもの (1)分かり易い表示、説明(本物、新鮮、安心、安全 等) (2)異業種とのネットワーク、及び近隣市町村との共存・共生 (3)遊び心(体験、体感、実感、感動) → 面白い、売れる、儲かる (4)人づくり(土づくり) 「人材→人財」 何をするにおいても障害はあるものと思い、それを克服してこそ未来が開ける。 継続と持続が原動力となる。 今後は、特産物・商品開発に頑張っている方、意欲のある後進の方向けに、アイデアの生み方や技術力、販売力などの御指導をお願いしたいものです。 |
|
平成19年9月4日(火)於:新庄市「ゆめりあ」、東北農政局山形農政事務所地域第二課主催で「食の安全に関する意見交換会」が行われ、その際に「つながる食育・地産地消」をテーマに講演を行って参りました。
今、食を取り巻く環境が大きく変化し、こうした中で食育基本法及びそれに基づく食育推進計画ではこのような様々な問題に対処し、国民が健全な心身を培い豊かな人間性を育む「食育」の取り組みを国を挙げて推進するため、効果的な展開を図るために、関係者間の連携も進んでおります。 講演は、消費者、生産者、食品関係者、関係機関、約60名の方に聴講頂きました。尾花沢市、新庄市、村山市、山形市、西川町、真室川町、金山町、戸沢村、鮭川村等、県内各地からご参加頂いたようです。 ●情報提供 「最近の食を巡る情勢について」 東北農政局 山形農政事務所 消費安全部 部長 高木原秋雄さん レジュメに基づき、以下のようなお話をしています。 ○食を巡る現状 … 個食、孤食、消える旬、家庭の味 ○農業がくれる夢、感動、ロマン ○伝統食が伝えるふるさとの食文化 … 若者と伝統食 伝統食を見なおす必要性 ○地産地消から見えてくるもの … 地域、人、笑顔 ○みんなの食育、みんなで食育 講演後には、食の安全に関する意見交換も行われ、「ふるさと」「心に残る感動の食」等について話しがなされました。 |
|
平成17年9月20日(火)於:山形県総合社会福祉センターで平成17年度山形県社会就労センター協議会の「授産製品・商品 品評会」が開催され、その審査委員に今年度も就任いたしました。
これは、県内の授産施設及び共同作業所等における授産活動を活性化し、障害者の自立意欲、社会参加意欲の助長を図ることを目的に実施されるものです。その審査委員として私をご指名を頂き、大変嬉しく思います。 |
|
この度の民主党代表に選出された小沢さんが記者会見で話された言葉「私が変わります」が話題になっておりますが、この言葉は大変重要だと思います。
私のこれまでの体験から、講演の中で発想の転換の重要性を説いてきました。観光の振興や地域づくりなど、ありとあらゆることに当てはまることで、新しい発想をする際の阻害要因として固定観念や既成概念が邪魔すると指摘して参りました。そして「過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えることができる」ことを伝えてきております。 自分が変わらない限りは周りは変化しないのです。先にやるべきことは、周りに期待するよりもまず自分の目線や行動を変化させてみることでしょう。そこから新しい未来が創造されると信じております。 |
Powered by samidare®
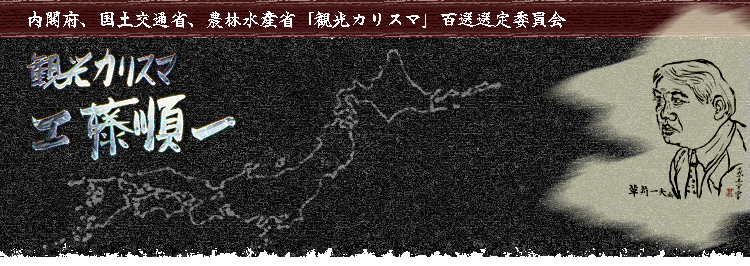




環境、地理的条件の違いがあればこそ、工夫と意欲と実践のあるところには明るい展望がある。
観光農業は大きなヒントになる。その気になれば農業に売れないものはない。あとはどう仕掛けるかである。
夢は無限、そこに観光農業の無限の可能性がある。