|
新「地域」ブランド戦略 〜合併後の市町村の取り組み〜
編者:関満博(財団法人日本都市センター) 発行:日経広告研究所 発売:日本経済新聞出版社 定価:1470円 平成19年10月25日発売 第1章 地域ブランドづくりのポイント 合併市町村を取り巻く環境と課題 第2章 合併市町村の地域ブランドの取り組み 第3章 地域ブランドづくりへ識者からの提言 地域ブランド戦略研究会委員 座長:関満博(一橋大学大学院商学研究科 教授) 委員:斎藤修(千葉大学園芸学部 教授) 榊田みどり(農政ジャーナリスト) 西原昌男(食のデザイン) 安井美沙子(マーケティングコンサルタント) 横田浩(日本経済新聞社) アドバイザー: 瀬脇一(総務省自治行政局合併推進課 課長補佐) (財)日本都市センター研究室 田部美博、黒崎武英、清水浩和、原清 地域ブランド戦略研究会の委員は、農業問題、食品販売、マーケティング、ブランド論、地域産業論などの専門家7人で構成されており、全国各地の実務担当者の報告を受けそれぞれの力を結集してディスカッションを重ねた内容が、この本に網羅されています。地域活性化の次なる一手となる情報が満載ですので、是非購読して頂きたいと思います。 農政ジャーナリストの榊田みどりさんが、「ヨソモノ」の視線で地域を見つめ直す「ここにあって、よそにないもの」を見極める事例として、「寒河江の周年観光農業」を紹介して下さいました。 |
|
平成21年12月4日(金)於:新潟市ANAクラウンプラザホテル新潟で『平成21年度JA営農指導員活動実績発表研修会における、記念講演(主催:新潟県農業協同組合中央会 会長 萬歳 章)にお招きをいただきうれしく思います。
JA営農指導員活動実績発表研修会の趣旨は、組合員の農業経営の安定向上と地域農業の振興をすすめるため、JA営農指導員は県内各地域で業務に取り組み多くの成果を積み重ねている。このような貴重な実績を交流し県内全体に共有化させることが重要である。このため各地区を代表する営農指導員が取り組んできた活動実績の発表を通じ、相互の研鑽と各営農指導員の資質向上をはかる。 また、本県農業の重要課題である園芸振興に向け、先進的な実践者の講演を聴くとともに第35回JA新潟県大会決議事項を確認し、その実践の決意を固める。 【発表者及び発表のテーマ】 ◎農業法人への営農指導のあり方 JAえちご上越頚南営農生活センター 石平義治さん ◎リモートセンシングの活用による米の有利販売について JA越後さんとうこしじ地区営農センター 田中忠政さん ◎魚沼米ブランドに値する品質と食味の確保のための取組み JA津南町営農部営農センター 桑原 清さん ◎米粉用米の生産拡大に向けた取組 JA黒川村営農経済課 課長補佐 前田喜一さん ◎水稲疎植(坪37株)栽培普及促進事業 JA新潟みらいしろね営農センター 尾竹勝則さん が発表されました。 JA時代の営農指導員として、営農活動に日々努力したことがなつかしく思い出されました。 記念講演では『発想の転換で元氣と活力ある園芸産地づくり』について ※発想の転換を図る ※元気を「元氣」に ※アイデアを生む要件 ※園芸産地づくりの要件「基本は土づくり」 ※今後園芸農業に求められているもの など営農指導員108名が熱心にご聴請下さいました。 講演終了後、営農指導員の皆さまと親しく苦労話しや喜びなど、たくさんお話ができて大変うれしく思い、10年前「観光農業は感動のドラマ」家の光協会から出版、是非講演をまち望んでいたおり感激いたしました。 |
|
寒冷の候、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
先日は、年末の御多用な時期にもかかわらず、当県にお越しのうえ御講演等いただき、誠にありがとうございました。 昨今の農業情勢は、その変化も急であり、農業に関係する者にとってはとまどう場面もあります。そのため地域の力を結集し、地域住民の明確な役割分担(やる気の発揮)と農業所得確保を進めることは普遍の課題であり、このことは「農業の6次産業化」として整理し、今後とも積極的に進めていく必要のある事と考えています。 当日は限られた時間の中で、実例に基づいた対応方法など、豊富な経験をもとにした「生きた事例」として来場者にわかりやすく熱のこもったお話しで御紹介していただき、おかげ様で農業の6次産業化に向けた機運の盛り上がりと具体的な実践への意識の高まりを強く感じるなど盛況のうちに研修会を終えることが出来ました。深く感謝申し上げます。 農村のみならず、山林、水産など資源に恵まれた当地域といたしましては、今後とも、活力ある農山漁村づくりに向け、リーダー育成やグリーン・ツーリズムなどの地域資源の活用による新たな所得確保の方策検討、新たな商品開発及び販売などを今後とも鋭意進めていくこととしておりますので、引き続き、御指導くださるようお願い申し上げます。 終わりに、工藤様のますますの御活躍と御健勝を祈念申し上げまして、略式ながらお礼のあいさつとさせていただきます。 |
|
平成22年12月13日(日)於:村上市教育情報センター視覚ホールで平成22年度『元氣な岩船地域づくりを考える集い』が、主催・岩船農業振興協議会村上地域振興局農林振興部、共催・岩船地域生産組織協議会が地域基幹産業である農林水産業や地域活性化に向けて、地域資源と活用した商品開発農商工連携等による6次産業化を地域を上げて推進する必要があるため、研修会が開催されました。意義ある研修会の基調講演の講師にお招きを頂き、大変光栄に思います。
【基調講演前に話題提供】 〜 村上地域における6次産業化の取り組みについてインタビュー 〜 『朝日村まゆの花の会/代表 横井栄子さん』 『大毎地域活性化戦略協議会/代表 佐藤勝敏さん』 『有限会社板屋農産/加藤芳明さん』 『ひどこの会/事務局長 中山吉典さん』 以上の方々より、活動内容と成果が発表された。 【各賞表彰】 ≪北 陸 農 政 賞≫ 朝日村まゆの花の会 ≪県 知 事 賞≫ 大毎地域活性化戦略推進協議会 ※受賞、おめでとうございます。 基調講演では 〜 発想の転換が時代を切り拓く 〜 『元氣で活力ある地域づくりに向けて』 について、次の内容をお話いたしました。 ◎地域資源は再認識が鍵・・・ ◎商品開発の極意は・・・ ◎ユニークなアイデアを生む条件は・・・ ※知恵→『智慧』に変えるアイデア! ― アイデア商品画像で紹介 ― ※アイデアの発想のヒント! ※ヒットするまでの苦労・障害は! ※克服するには! ※その当時は!今は!現実は! 〜ドラマがある〜 …など… ◎商品開発の重点項目は・・・ 〜観光農業の極意とは〜 ※異業種との連携について (6次産業化に必要なことは) 《例》寒河江市周年観光農業推進協議会の事例・体制・取り組みを紹介しながら80分お話いたしました。 岩船地域の皆さま150名が熱心にご聴請いただきました。6次産業化に取組みの意欲がうかがえることができました。 すでに企業化されている方もおりますので、頑張って下さい。 |
|
(平成18年度聖籠町観光協会会員研修講演会 於:新潟県聖籠町)
5-1. 良かった点 ・わかりやすくて面白かった。 ・ざっくばらんの講演でよかった。 ・楽しく勉強できた ・身近な話題をわかり易く話してもらえた ・元氣をもらいました。 ・良かった ・足りなかった欠点がわかった感じ ・地域としての各産業の連携 ・納得=価値観=満足=おもしろい=売れる=儲かる→自立自活 ・楽しくわかりやすい講演でした。 ・話が非常に楽しかった。 ・人間の原点を考えました。元気が出ました。 ・身近でわかりやすい ・人に対する言葉遣い、観光対策の知恵 ・ことわざ ・話が面白かった。 ・感じで納得と理解力 ・わかりやすく、的を射た内容 ・体験に基づいた話で大変わかりやすかった。 ・ものの見方を教わった。 ・山形弁とユーモアの講演会。楽しく聞くことができた。 5-2. 悪かった点 ・少し言葉がわからなかった。 ・言葉で方言が多すぎる ・別の話題がほしかった。農業関係の話題が多すぎる。 ・方言が強かった 6. 今後どのように役立てる? ・自分だけでなく全体がひとつ。聖籠町全体がひとつになる。 ・魅力ある観光さくらんぼ園を経営して行きたいと思います。 ・活かしていきたい ・何度か訪れた寒河江のチェリーランドを思い出しながら、興味深く聞かせていただきました。一つ一つ納得でした。“過去と他人は変わらない。トンボに・・・。”というお話。初老ですが、低空でも飛び続けようと思いました。 ・お客様のことを大切に笑顔と、横のつながりの大切さ。自分自身前向きに笑顔でがんばりたいです。 ・また、お願いします。 ・観光、さくらんぼのヒントとする。 ・地元観光資源の連携を考えたい。 ・ゴルフ場運営に役立てたい。地域の一員として役に立つことを見つけ実行する。ありがとうございました! ・元気を出してがんばっていこうと思いました。 ・私の生活に役立てたい ・人とのお付き合い、当然商売にも ・聖籠町を元氣にしていただきたい ・顧客との信頼感。お客様は人とのふれあいを求めてくるのでおしゃべりをだいじにしていきたいと思います。味のしっかりした物を作る。 ・ぶどう園に役立てたい。常に役立てたい。もう一度聞きたい ・人と人との対応、お礼の言葉、ありがとうを忘れないように、感謝の気持ち、今度も宜しく今一度あいたい ・お客様との信頼を保つこと。 ・観光の発展の全般的なアドバイスがほしかった。具体的な話がほしかった。 ・知恵、絆、出会い、愛を忘れずにがんばります。 ・聖籠町へ来る道路案内図がない。店が少ない(食堂がない)地から強い話でよかった。町の観光の宣伝が足りない。 ・相手をほめたたえ、我が身を繁栄させる。年間サイクルで観光資源を活かし、地域を上げて協力し、観光客集めとお客様の満足感で町を売り込む。運命共同企業体となり、漢字をうまく使い表現で活力ある町づくり。 ・とれたて市場などに。生産=販売活動 ・地産地費を進め、農産物に付加価値を付けてインターネットなどで発信・販売する。 ・自分の町を見直してみる。 ・建設業における公共工事の年々の削減により、新分野への移行も考える時期に来ているように思い、講演会に参加。いずれにしても心の絆を役立てたい。何事にも人と人との信頼関係が大切であることを素直に感じた。 1.年齢 10代 0 20代 0 30代 2 40代 0 50代 9 60歳以上 16 計 27 2.性別 男 16 女 11 計 27 3.職務 農業 14 会社員 5 営業 2 無職 1 その他 2 空白 4 計 28 |
Powered by samidare®
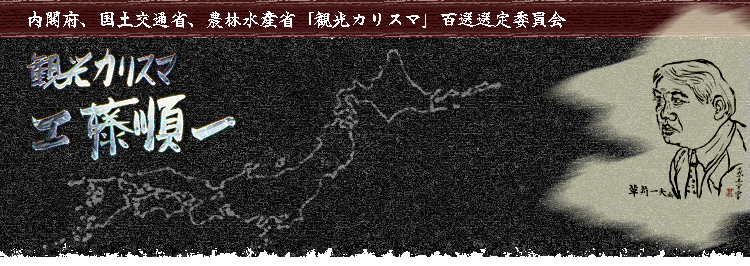




未来に夢ある農業!!「農業の発展が地域活性化の要だ」元氣の源はロマンと笑いと題して、以下の内容を盛り込み約40分話しています。
○生き残れる農業経営の要件
○アイデアを生む要件
○産地づくりの要件(基本は土づくり)
○経営が成り立つためには
○今後農業にもとめられているものは
これまでに私の話を2〜3回聴講している熱心な方も見受けられました。
講演会後には懇親会もあり、参加された1人1人にご挨拶させて頂き、有意義な懇親を図ることができました。
...もっと詳しく