|
平成21年11月5日(木)於:奈良県御杖村開発センター、宅陀郡議会議長・副議長会(会長:中谷誠氏 御杖村と曽爾村で構成)主催で、平成21年度宅陀郡村議会議員研修会が開催されました。その講師としてお招きを頂き「発想の転換で過疎の村を活性させる」と題し講演したことを大変光栄に思います。
講演前には、奈良県町村議会議長会 事務局次長 菊川さん、副主幹 柚木さんから、システムブレーン 斎藤さんと一緒に曽根村と御杖村内にある各種観光施設および観光資源をご案内頂いています。訪問先は、曽根村内では曽根高原、お米の館、お亀の湯、屏風岩公園、小太郎岩を、御杖村内では中谷議長会会長、森谷事務局も同行されて、三峰山、伊勢本街道、姫石の湯、三季館、道の駅を巡りました。 〜開会行事の流れ〜 ○会長挨拶 ○表彰式 ○来賓祝辞 ○研修会 講演でお話ししたことは... ●発想の転換…意識改革 ●アイデアを生む条件 ●過疎の村を活性させるには (1)自分の村を知ること (2)自分の住んでいる村がどこよりも好きであること 再発見・再認識 (3)お客さんの目線になること ●一時滞在型 → 外貨の獲得 → 経済効果 → 元気になる ●履歴より実績(数字)を残す ●IT(メディア)、口コミの積極的利活用 ●官民、異業種との連携 90分に渡り、熱心に聴講頂きました。 |
|
平成16年11月25日「南那須地方の明日の農業を拓くフォーラム2004」にお招き頂き講演して参りました。
当日は「農業は無限の観光資源」と題し約1時間45分お話させていただきました。 事前にまちの農業体験施設をはじめ直売所を拝見させて頂き、色々と土地の食材を試食することも出来ました。 南那須地方は大変資源に恵まれているところであり交通の便も良いことから、関東圏の主要都市からも誘客が可能という、今後大いなる可能性を感じる土地でした。 それにはまず地元に住む人が、地元にある資源(場所・食・文化・伝統・人 etc.)の素晴らしさを再認識・再発見することが肝要だと思います。 更なる発展をお祈りしています。 |
|
(「かぬまの農業農村・活性化セミナー」 於:栃木県鹿沼市)
3月22日の鹿沼での講演につきましては、大変お忙しい中有り難うございました。講演の方は大変好評で、鹿沼の農業公社の担当者も喜んでおりました。また、一般農家の方に伺っても、元気が出たと喜んでいました。鹿沼市は観光関係は元気の良い部分があるのですが、農業とのマッチングが出来ていないため、今後の課題として良い刺激になったものと考えています。 まずはお礼まで! |
|
(旅のジャーナリスト会議総会記念講演会 於:東京)
拝啓 過日は旅ジャーナリスト会議で貴重なお話しありがとうございました。 観光はユニークな発想と激しい程の熱、リーダー次第で決まります。今後ますますのご活躍祈念しております。 敬具 |
|
平成19年1月3日(水)の読売新聞朝刊で、「観光を拓く 第一部 出羽三山・最上川」の欄に私の取材コメントが掲載されております。これは、世界遺産登録を目指している我が山形の出羽三山エリア・最上川に関して紹介しているもので、西川町大井沢で進める体験農業や月山トレッキング等の民主導型の観光について書かれております。
その中で私は「観光客は普段接していないものを求めて旅をする。受け入れる側はありのままの空間を生かすことが必要。行政主導でなく、実際に現地をよく知る地元住民が動かなくてはいけない。月山エリアは、それがかなり実現できた好例だ」「(世界遺産登録を目指す動きについては)住民を無視して登録を焦ると、観光客を受け入れるべき住民が息切れし、その土地本来のすばらしさを訴えにくくなるのでは」以上の様な見解を述べさせていただきました。 |
Powered by samidare®
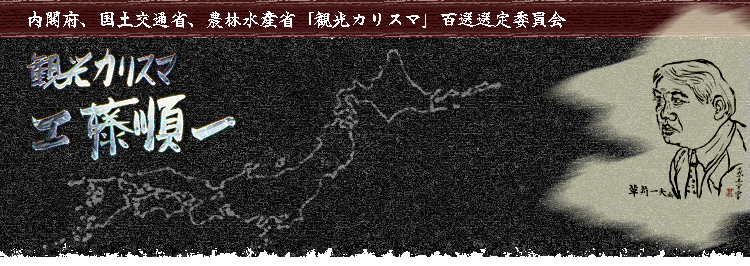




これは担当室が現場の声を直に聞き、意見交換を行うことで、今後のニーズの把握に努めることを目的に行われたもので、地域再生に取り組んでいる他の関係機関(国・自治体職員、NPO、大学関係者、総研、マスコミ、医師等約50名)も出席頂き会場はいっぱいでした。当日は、東京はもちろん全国的に台風の影響でフェーン現象が起き、37度という猛暑日になりました。そんな中、多くの方にご参集頂き感激致しました。
講演ではこれまで地域と人材育成に係わった経験とその実践から得た事例をちりばめながら、以下のレジュメの内容をお話しています。
○意識改革の要件
○地場産業(異業種)とのネットワークの構築
地脈=人脈
共生
○人材育成のポイント
○あってはならない3つのキーワード
○「得した感覚」を活かす方法
○5つの経営キーワード
講演後には大勢の方と名刺交換を行い、また懇親会では約30名の方々にご出席頂いて意見交換を行う機会を得て、大変嬉しく思います。
また、公聴頂いた千葉県庁政策推進室の戸崎将宏さんから、早速翌3日に講演内容のメモをお送りいただきました。昨今、行政に求められている「スピード、実行力」ですが、戸崎さんのこの素早さには感服・感激いたしております。