|
天正18年(1590年)3月、豊臣秀吉の命を受け上杉景勝公は直江兼続公を従えて小田原城の北条氏政征伐に出陣しました。同年7月、北条氏政の自害という結末で小田原城は開城され、戦を終えた上杉景勝公は更なる奥州検地に備え一旦越後へ戻ることになりました。その帰途、直江兼続公は富士山麓の社で 曽我兄弟 の木像と出会います。逸話に心打たれた直江兼続公は、この木像を譲り受け実父樋口惣右衛門兼豊が城主を務める越後国安塚直峯(のうみね)に大きな御堂を建立し「神達明神(かんだつみょうじん)」と名付けて祀りました。その後木像は慶長3年の上杉家会津120万石移封により米沢へと移され現在に至っています。
米沢では直江兼続公の実家樋口家の屋敷内に建てられた「神達明神」。 越後国安塚直峯の地図 神達明神の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |
|
米沢の聖徳太子尊は 大工の神様 (番匠 = 大工)として祀られています。これは聖徳太子が中国から建築の技術や道具を日本に導入したことに由来するもので、社が建つ山形県米沢市中央1丁目付近はかつて「地番匠町」と呼ばれ町人の大工が多く住んでいた町でした。
聖徳太子尊の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |
|
西條天満神社(にしじょうてんまんじんじゃ)は、唯一現代の米沢に遺された米沢城三の丸の堀の土居跡上に建つ神社です。 五穀稲荷神社 が建つ三の丸の土居跡とともに大変貴重な歴史遺産となっています。商店街の駐車場を造成する際に撤去の話もあったようですが、結果として遺されることになりました。そのため開けた土地の中に土居跡と神社が建つという独特の景色をかもしだしています。
西條天満神社の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |
|
上杉景勝公が入部された頃の米沢は、城下を南から北に流れる松川(最上川)が度々氾濫を繰り返し、米沢城の東側には居住はもちろんのこと耕作も出来ない土地が広がっていました。そこで直江兼続公は、暴れ川「松川」を鎮めるためこの赤崩山 (あかくずれやま)に登り治水工事の計画を立てたと言われています。
尾根の先端部分にはかなり古い年代の板碑群がある他、伊達政宗公もこの場所に登っていたことが伝わっています。直江兼続公もその事実を知りこの山に登ったものと考えられています。 山そのものの高さはさほどではありません。 登山道が整備され登りやすくなりました。 山の頂からは、松川(最上川)とその下流部が一望出来ます。 尾根の先端部にある板碑群。風化により文字は読めません。 こちらは古くからの登山道。 途中に板碑となる石を切り出した跡が残されています。 何百年も前、ここに石を切り出した人がいたんですね。 熊が出没する地域です。くれぐれもご注意ください。 赤崩山の登山口の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |
|
上杉家の領地替えとともに越後国の上越中越から多くの寺が米沢に移されていますが、千眼寺(せんがんじ)は下越の 岩船郡平林(新潟県村上市) から米沢に移された寺です。
平林城主を務めていた色部長真(いろべながざね)は、上杉謙信公の急逝後の上杉景勝公と上杉景虎の家督相続争い 御館の乱 が起きると、領内の揚北衆(あげきたしゅう)をまとめ上げいち早く上杉景勝公側に付きました。 その後上杉家会津120万石移封、米沢30万石減封では、上杉家の重臣となり家臣団の揚北衆を従えて金山(山形県南陽市)、窪田(山形県米沢市)に入り、上杉景勝公、直江兼続公の命を受け領地を接する山形の最上義光に睨みを効かせました。千眼寺は菩提寺として色部家と行動を共にし米沢に移されています。 山形の最上や高畠の屋代庄に対しての上杉の北の塞だった「千眼寺」。 「保呂羽堂(ほろはどう)」には、近郷の農民が虫害で困っていた時にお堂の縁の下の土を畑にまいたら虫がたちまちいなくなったという言い伝えが残されています。そのため今でも6月4日には「虫除けのお札」が出され、12月4日には収穫した米で餅をつき奉納されています。 千眼寺の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |
All Rights Reserved by 上杉時代館
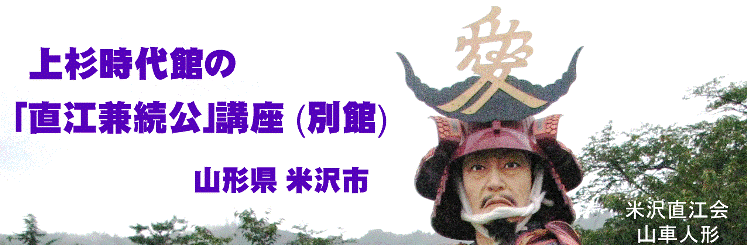



真福寺は、 直江兼続公が造った防衛機能「寺町」 の東寺町にあります。
真福寺の地図
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重
福島県 八重をもっと知り隊 事務局
会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)