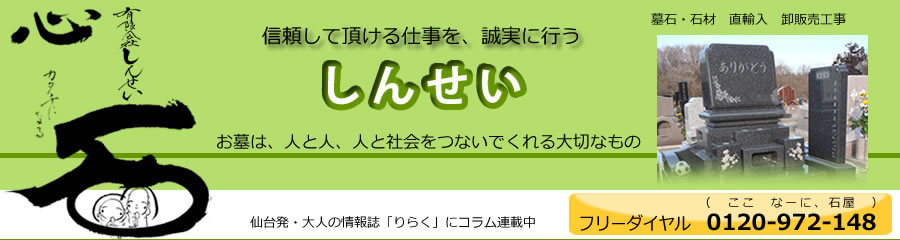これから始めるお話は、石屋の私と同年代で、雑誌「りらく」を人生の友として愛する読者諸兄と、一緒に考えていかなくてはならないお話、若いときには、思いもつかない様なお話です。
いきなり重い話です。われわれ人間はいつか「死」を迎えます。この世に「生」を受けた次の瞬間から、「死」に向かって人生という「長い旅」が始まるといってもよいかも知れませ。
石屋である私は、今まで色々な「死」の場面に立ち会ってきました。葬儀が終わってからすぐの納骨(お骨を墓石のカロートに収めること)の場合は、葬儀の緊張感がそのまま墓地まで持ち込まれたような、かなり重い雰囲。
四十九日の納骨の時は、遺族の皆さんもかなり落ち着かれて、ゆっくりと故人を偲ばれるような、凛とした空気の中にも、なんとなく落ち着いた雰囲気があります。
新たにお墓を建立してからの納骨の場合は、大切な「お墓の建立」という仕事をしたぞ、という満足感からか。または、虚脱感なのか、ご自分の生活の中から、亡くなられた方の「死」を、ご遺族各人それぞれの立場から、客観的に見られるようになっているようです。
そう言えば、このところ、新聞や週刊誌・月刊誌の紙面にも多く、葬儀・墓石等の記事を見かけるような気がするのは、私が石屋という職業なのだけでしょうか?
今年は映画「おくりびと」のヒットも有ってか「死」に対する考え方が、少しずつではありますが変化してきたように思えます。忌み嫌うものであって、非日常的なものであった「死」が、大切な人を送る為の「入口」として表現されたからでしょうか?
「死」は突然訪れます。何人もそれから逃れることは出来ません。その「死」を、私たちは何もせず、ただ待つだけでいいのでしょうか?自分の最後くらい、自分の思い描く形で迎えるよう、今から考え、計画しておいたほうが良いのではないでしょうか。
戦前の日本の社会は、三世代、四世代の家族が一つ屋根の下で暮らしていました。長い時間の中で人々は、自然と地域の行事(祭りや冠婚葬祭)を先祖代々の「ならいごと」、として受け継いできました。
家族が孤立してしまった現代の家庭にとっては、生活の一部として受け継がれてきたものの多くを、誰からも教えて貰えないうちに迎えなくてはなりません。
いつか来る「死」に備えて、葬儀・仏壇・墓石・保険・遺産。どれも忘れることの出来ないことです。
先日、知り合いの家で雑談をしていたとき、その家のおばあさんから質問を受けました。
「お墓」は引越しして良いのかな?という内容でした。今から十数年前にお亡くなりになられたおばあさんの連れ合いのお墓が、自宅から高速道路を利用して一時間あまり離れたお寺の墓地にあるそうです。
お彼岸、盆はもちろんのこと、月に一度は、同居の息子さん家族と皆で墓参りを兼ねた、ドライブを楽しまれるそうです。
おじいさんの遺言で、故郷の、その地にお墓を建立したとの事ですが、今になれば、たった一時間のドライブでも、ご高齢の身には、年々負担になってきているようです。
息子さんが高校生までは、その地に御住まいでしたが、大学に入学とともに息子さんも都会に住むようになり、おばあさんの連れ合いの死後は、その地を離れ、息子さんと同居しておられます。
お孫さんにいたっては、年に数回しか訪れない土地になっています。果たしてこのままにして置いて良いものなのか。
お墓を立てた場所が、年々縁遠い場所になってきているのです。
すぐに何をしなくてはならない、と言った話ではありませんが、ご家族でゆっくり話し合う事が必要な内容だと思います。
死に行く人が、残される人たちに、何を求めているのか。残される人は、死に行く人に対して、何をさせて頂けるのか。しっかり考える時代になったのだと思います。
これから数回にわたって、みなさんと、葬儀お墓・仏壇・保険等、一緒に考えて行きたいと思います。