塗りは江口漆工房の作。
タテガミ取り付け前の獅子の写真は貴重
漆の硬化は一定の温度と湿度が必要で、今の様な厳冬期にはその調整が難しいと聞く。
漆は完全に硬化するまで時間がかかる事が分かるのは、私の両手に現れる肘にかけての漆マケ
が物語る。命に関わるアレルギーでは無さそうなので2週間の我慢である。
これは歌丸の獅子の漆マケではなく長野の三獅子の加工の際のものだろう。
漆が塗り上がり金箔を押し、少し養生してから塗師から彫師へ引き渡される。
白馬毛のタテガミを植える前に、獅子の金箔部にウレタンの保護剤を塗布しなければならない。
硬化間も無い塗面や金箔は、ちょっとした摩擦で傷が現れるのだ。
透明な保護剤は気をつけないと垂れたり塗り残しがで台無しになるので照明を増やすが、黒と金
の強いコントラストで判別が難しい。
保護剤が硬化すると獅子の毛穴に束にし整えた白馬毛を植える。
60本ほどの毛穴は黒獅子系としては少ない方で、成田や五十川型の黒獅子はその倍の束を必要とする。
毛量は植え過ぎも節約するのも良くなく、やはり程々が最適。それも経験で会得するしかない。
またモデルにした獅子頭の毛穴を見れば分かる事である。

最近、ヘアーアイロンを使って白馬毛の癖を調整する事を覚えた。前後するが毛穴の植え方、固定の仕
方にもコツがあり、毛量の見栄えを左右する。
歌丸の獅子の軸棒は、成田五十川型や白鷹鮎貝系の様に横ずれ防止になるコブがなく棒状で、栓で固定
しないと口の開閉などで横ズレし、頭部と顎が外れてしまう事態となる。
軸棒に穴を開け、細い竹で栓になるピンを挿し横ずれ防止とするが時に栓は抜け落ちるトラブルが多く、
今回は穴を開け細いが丈夫な紐を堅く巻いて横ズレ止めとした。
完成した獅子頭を机に乗せ眺める。
角度や高さを変えたり、違った位置から照明を当てて凝視する。
すると獅子が、ポツリポツリと批評を語りはじめる。
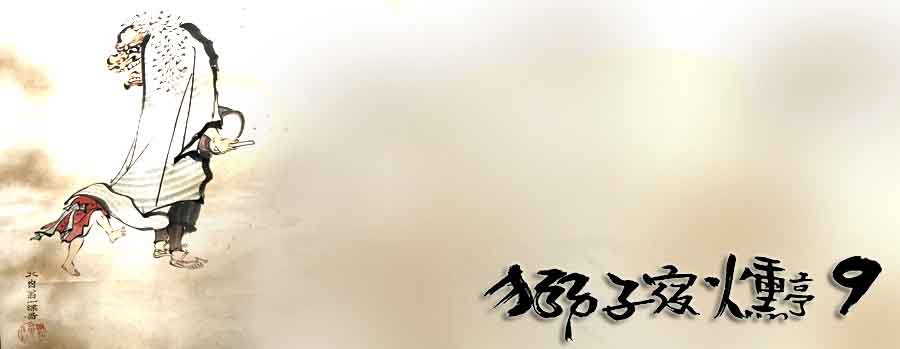


この記事へのコメントはこちら