張子の獅子頭は現在、漆塗りの仕上げ上塗りのクライマックス。
木地の下地とは違い、和紙を獅子の木型に何枚も貼り付け乾燥させで型から抜き、組み立て
て成形する。今度はその張子に漆を塗り研ぎを繰り返し強度を持たせて成形していくのであ
る。
面四体は桐の木地で漆仕上げし、藍二体と赤い髪一体の毛を取り付けている。
幸い長井市は江戸時代以前より青苧の生産や絹織物の生産が盛んだったので織物の工房が現
存していて青苧の繊維の染を依頼する事が出来た。
意外にも獅子幕を染めるような染め屋さんには出来ない分野だった。
また織物の原料となる青苧と関わる事はなかったので、入手した植物繊維が青苧か麻か何な
のか判別出来ない。ようやく見慣れてきたが、織物に使う繊維は様々あり青苧の他、葛
(くず)やシナの皮、和紙の原料コウゾなども知人のコレクターから入手した。

染め上がり水気を切る

織物工房で青苧を染める工程も見学できた。藍の緑色の染料に繊維を浸し、持ち上げて空気に
晒すと徐々に緑から青に変化してくる様子は新鮮だった。
いよいよ取り付けの準備に入り、染められた青苧の繊維を自然乾燥させるとゴワゴワの繊維の
状態なので、一握りの束に裂いて髪の毛をすくように繊維をほぐす。人が使うクシでは抵抗が
あり過ぎるので布に穴を目貫を使い根気良く、梳く(スク)と1.5倍に膨らみ濃い藍色が薄らい
でいく。五体分をスクのは、かなり時間が掛かりそうだ。
一握りの繊維をスク
濃紺の獅子幕をミシンで縫製すると
手が青くなる事があるが、青苧はしっかり染料が定着しているのか色移る事は無いようだ。
見本の現物の繊維を見ると、黒や茶褐、色褪色した藍色などあり年月を経た複雑な色合いである。
茶褐色は青苧の茎の表皮の部分では無いだろうか。
昭和村から仕入れた青苧は等級があり特上・上・並と分けられ特上は薄っすら緑掛かって白っぽく
茶褐色の部分は綺麗に取り除かれている。今回分けてもらった並にはほんの少し残っている。
青苧は2m程に成長し、収穫して清水に浸け茎から表皮をはぎ取る。それを剃刀で表皮をむいて繊維
にするのだそうだ。毎年、獅子宿の周辺の草刈りをすると見かけるが成長すると厄介なので短いうち
に刈り捨てていた。今回の制作で青苧の見方がだいぶ違ってきた。
昨日一昨日のドカ雪の除雪で大騒ぎしたが、本日は自宅に籠もってぬくぬくと地道な手仕事になりそ
うだ。窓から積み上げられた廃雪の雪山がそびえている。
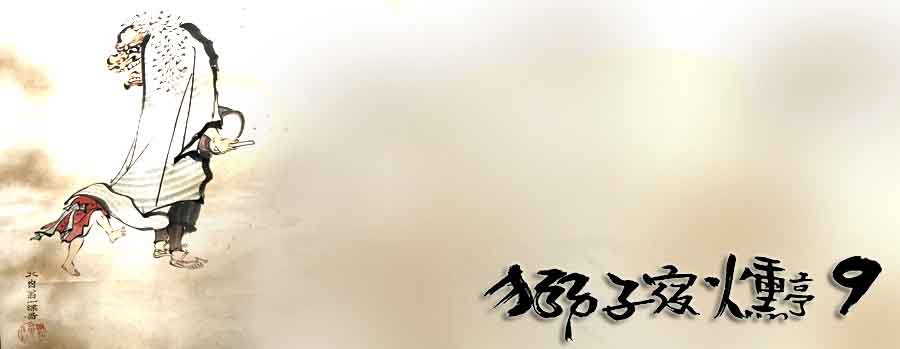


この記事へのコメントはこちら